◆②社会保険料支払いが必要となる130万円の壁
二つ目は「②社会保険料支払いが必要となる130万円の壁」である。
妻が夫に扶養されている場合、妻は自身の社会保険料の支払いは不要である。しかし、妻年収130万円を超えると妻は夫の扶養から外れ(*11)、妻自身で社会保険料(健康・介護保険料、厚生年金保険料等)の支払い義務が生じる(*12)。これにより、妻年収が130万円を超えると妻の可処分所得は大幅に減少することから130万円の壁と言われている。
夫年収550万円の場合で試算してみると、130万円の壁は大きく世帯収入の壁として存在していることが確認できる(図表7)。
妻の年収に対する世帯の可処分所得の変化は、妻年収が129万円では可処分所得は549.6万円となるが、130万円では532.7万円まで減少し、約16.9万円の可処分所得の逆転現象が生じていることになる。さらに妻年収129万円時の可処分所得を越えるには、年収157万円となるまでかなり働く量を増やさねばならない。可処分所得の観点からは、103万円の壁よりも社会保険料の130万円の壁の方が影響は大きい(*13)。
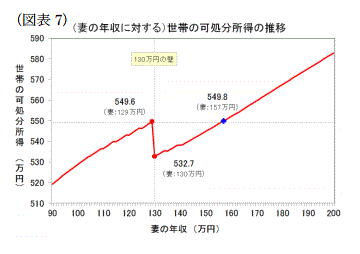
◆③企業の配偶者手当=103万円の壁
103万円の壁は税制上の問題だけではない。企業も従業員に福利厚生の一環として家族に対して手当を支給する場合がある。それら手当は、従業員に扶養している家族がいる場合、その従業員に毎月1万円支給するなどといったものである。
家族に対する手当を支給する民間企業の割合は76.5%で、このうち90.3%が配偶者手当を支給している。そのうち68.8%が配偶者の支給基準を妻年収103万円、25.8%が130万円としている(*14)。企業が配偶者手当をする支給要件は企業ごとに様々であるが、国の配偶者控除と連動して103万円前後を基準に支給しているケースが多い。
ⅰ)企業から配偶者手当が毎月2万円支給される場合
企業の配偶者手当を加味して世帯の可処分所得がどのように変化するか確認してみよう。妻年収が103万円未満の場合、毎月に配偶者手当2万円(*15)を支給している企業に夫が勤めていると仮定し、夫年収550万円ケースで試算すると(図表8)のようになる。
妻の年収支給要件103万円を境に所得の逆転現象が起きることが分かる。本試算では103万円以下を支給要件と想定しているため、妻年収が102万円で世帯の可処分所得は554.6万円となるが、103万円では531.5万円と約23万円も大幅に減少する。
また、130万円の壁も存在するため妻年収102万円の時以上の世帯可処分所得を得るには、妻年収は164万円まで働く量を増やす必要がでてくる。妻年収が164万円を超えて働けない場合、妻は可処分所得が最大となる102万円超えて働かない方が合理的となる。
企業の配偶者手当によって生じる103万円の壁は、130万円の壁と相まって大きな壁となって女性の働く時間を抑制する要因となっている。
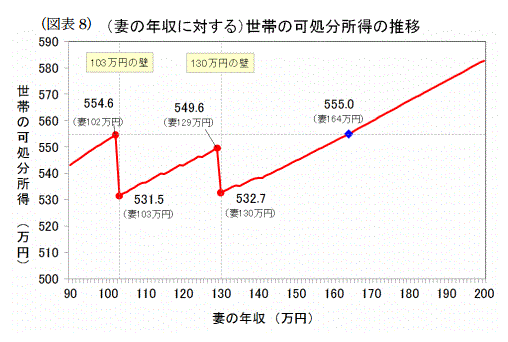
◆まとめ
既婚女性の就労調整を促すと指摘されている3つの壁について、可処分所得の損得で考えると、「①税制上の配偶者控除による103万円の壁」については、夫の可処分所得だけで「逆転現象」が生じているため、心理的な壁として意識される可能性は残っているものの、世帯の可処分所得で見れば配偶者特別控除の導入により既に壁はなくなっている。納税者に正しい認識を徹底するだけでも一定の解決が望める可能性があり、就労調整の壁となっているという指摘は正しくない。
「②社会保険料支払いが必要となる130万円の壁」と「③企業の配偶者手当=103万円の壁」については、可処分所得の損得で考えると、逆転現象が明確に生じており、制度の見直しを検討する必要がある。可処分所得の観点から、女性の就労調整を促す要因となっているのは、この2つである。
そうはいっても配偶者控除の見直しも進めるべきだろう。企業における配偶者手当の支給基準は配偶者控除と連動していることから、税制上の配偶者控除を見直すことで、自発的に企業も配偶者手当の見直しに動く可能性がある。国が税制上の配偶者控除を見直し、あわせて公務員の扶養手当(*16)も見直す。
その後で国から企業へも配偶者手当の見直しを働きかける形で企業の配偶者手当を見直し促す必要があると思われる。同時に「130万円の壁」についても検討が必要だが、まずは税制上の配偶者控除を見直すことで、社会全体の考え方を変化させる後押しともなり、企業の配偶者手当の見直しにつながれば、その影響は大きい。