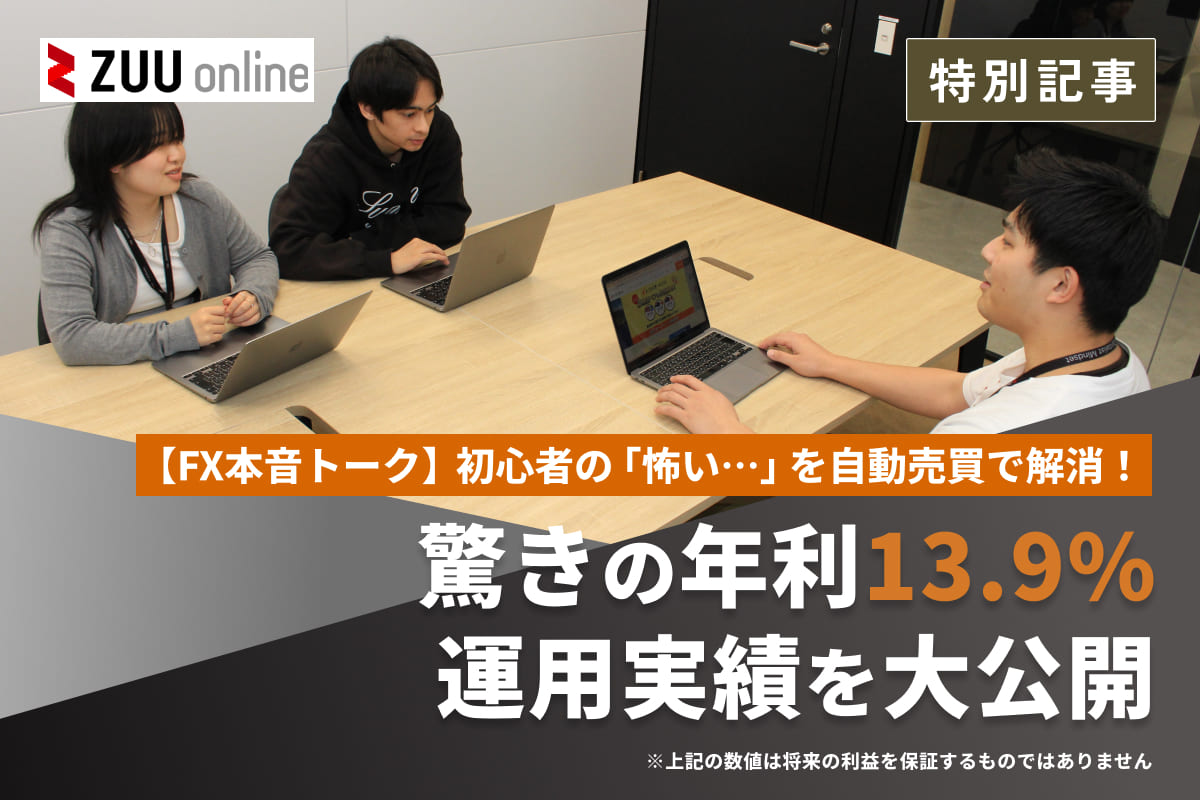後継者不足に悩む中小企業が増え、日本経済全体の大きな課題となっている事業承継に対し、「自己勘定投資」というアプローチで挑むのが、株式会社NYCだ。同社は短期的な利益追求ではなく、長期的な視点で中小企業の成長に寄り添う。創業からわずか3年半で投資先は18社、グループ売上は72億円に成長。その裏にある独自のビジネスモデル、事業再生の哲学、そして日本の中小企業全体を見据えた壮大な未来構想とは──。
目次
◼︎投資ファンドでの経験と自己勘定投資への道
── もともとはソフトバンクでベンチャー投資を手がけていらっしゃったそうですね。
中塚 はい、新卒でソフトバンクに入社し、国内外のスタートアップへの投資を担当していました。非常に夢のある仕事でしたが、一方で、実態が伴わないまま評価額だけが上がっていくような案件も目の当たりにし、「これは本当に地に足がついているのだろうか」と疑問を感じることもありました。
父が中小企業を経営していたのもあってか、もっと地に足のついた、リアルな手触りのあるビジネスに関わりたいという思いが強くなっていきました。そこで、スタートアップ投資とはある意味で正反対の世界である、中小企業のM&Aや事業再生の分野へキャリアチェンジしました。その後、コンサルティングファームやPEファンドを経て、NYCの創業に至りました。
ソフトバンク時代に培った「新しいことへ挑戦するマインド」と、PEファンドで学んだ「地に足のついた経営」を融合させることが、今のNYCのスタイルにつながっているのかもしれません。
── NYCを創業されるまでの経緯についてお聞かせください。
中塚 もともと私は、事業承継問題を扱う投資ファンドで働いていました。後継者不足で困っている中小企業を譲り受け、経営支援をして売却するというビジネスです。ただ、ファンドはどうしても外部の投資家の意向を受けるため、1〜2年という短期間で売買することが多かったのです。
中小企業の経営に関わるからには、もっと腰を据えて、最低でも5年といった長いスパンでじっくりと取り組みたい。そう考えたとき、外部の投資家がいない「自己勘定投資」、つまり自分たちのお金で投資を行うスタイルしかないと思い至りました。この想いを実現するために、3年半前に立ち上げたのがNYCです。
── 自己勘定で投資を行うことの強みはどこにあるのでしょうか。
中塚 最大の強みは、外部からの圧力がないため、経営支援の期間を長く取れることです。投資ファンドの場合、投資家へのリターンを最大化するために短期的な成果が求められがちですが、私たちはそうした制約がありません。だからこそ、企業のオーナー社長にじっくりと寄り添い、本質的な課題解決に取り組むことができます。このスタンスが、多くのオーナー社長から信頼をいただくことにつながっていると感じます。
また、情報発信の自由度が高いことも強みです。私たちは投資会社としては珍しく、YouTubeチャンネルを運営しています。ノウハウの流出を懸念して多くの同業他社がやらないことですが、私たちはあえて情報をオープンにすることで、私たちの考え方や人柄を知ってもらう。
今の時代のオーナー社長はYouTubeもご覧になりますから、親しみやすさを感じていただき、結果として「この会社なら任せられる」と思っていただけるケースも増えています。自己勘定ならではの「自由さ」を最大限に活かした戦略です。
◼︎創業から3年半でグループ売上72億円。急成長を支える独自のビジネスモデル
── 創業から3年半で、投資先は18社、グループ全体の売上は72億円に達したとうかがいました。この急成長を支えるビジネスモデルについて、もう少し詳しく教えてください。
中塚 私たちの投資対象は、後継者がいないだけで、事業自体は安定している優良な中小企業です。歴史があり、地域に根差し、長年付き合いのある金融機関からも高く評価されている。しかし、後継者がいないために未来が描けない、という会社です。
私たちは、そうした会社の事業承継を手がけるわけですが、買収資金は毎回、金融機関からの融資で調達しています。創業して間もない私たちに、なぜ金融機関が融資してくれるのか。それは、私たちが買収しようとしている会社そのものが、いわば「担保」になるからです。
金融機関からすれば、融資先は「歴史も業績も安定している優良企業」です。ただ、後継者不在という課題を抱えている。そこへ私たちが現れ、「私たちがこの会社を事業承継し、経営を引き継ぎます。融資の返済も、この会社の事業からきちんと行います」と提案する。これを「LBO(レバレッジド・バイアウト)」と呼びますが、買収先の企業の信用力を活用することで、資金調達を可能にしているのです。
── 経営の引き継ぎは、具体的にどのように進めるのでしょうか。
中塚 事業承継には、「株式(資本)」の問題と「経営(後継者)」の問題という二つの側面があります。私たちは株式を譲り受けるとともに、その会社に最適な新しい経営者を外部から見つけてきます。
NYCのメンバーが役員として入ることもありますが、基本的には「社長候補」を求人などで探し、新しい社長として会社に入ってもらう形です。世の中には、「社長をやってみたい」という意欲と能力のある方がたくさんいます。私たちは、そうした方々を発掘し、活躍の場を提供する役割も担っているのです。
◼︎成功のカギは「経営者のキャスティング」 映画でいえば社長が監督、自分たちはプロデューサー
── 事業を引き継いだ後、経営を立て直すうえで最も重要視しているポイントは何ですか?
中塚 一番の肝は、先ほど申し上げた「社長選び」です。私たちは、自分たちのことを「映画のプロデューサー」のような存在だと考えています。どんな作品(会社)にしていくかという大枠の方向性を描き、その作品を最高のものにしてくれる「監督(社長)」をキャスティングする。これが私たちの仕事です。
事業承継後、まず私たちと従業員の皆さんで、「この会社をどういう方向性で伸ばしていくか」を徹底的に議論します。たとえば製造業なら、品質をさらに高める方向性もあれば、営業力を強化する方向性、あるいはまったく新しい商品を開発する道もあるでしょう。
その方向性が決まったら、それに最適な経験やスキルを持った社長を探します。品質管理のプロが必要なのか、それとも営業のトップランナーがふさわしいのか。ここの見極めを誤ると、すべてがうまくいきません。適切な監督をキャスティングすることこそが、事業再生の成否を分けるのです。
── 事業承継後、業績はすぐに上向くものなのでしょうか。
中塚 正直にお話しすると、事業承継案件では、6〜7割の確率で一度業績が下がります。というのも、オーナー社長は「今年が業績のピークだろう」と分かったタイミングで会社を売却するケースが多いからです。「来年も業績が上がるなら、今年売る必要はない」と考えるのが自然ですよね。
ですから、私たちはまず業績が下がることを前提に、そこからどう立て直していくか、というプロセスをたどります。もちろん、すべての会社がうまくいくわけではありませんが、新しい社長とともに粘り強く改革を進めていくことが重要です。
◼︎足元の目標は100社への投資 その先の「エコシステム」は?
── 今後のNYCの展望について、どのような未来を描いていらっしゃいますか。
中塚 まず足元の目標として、「100社への投資」を掲げています。投資先の数が増えれば、グループ企業間のシナジーも生まれますし、会社としての規模も大きくなる。そうやって、事業承継マーケットにおける存在感をいっそう高めていきたいと考えています。
最近では、事業承継で得た知見を活かし、ベンチャー投資も始めています。たとえば、私たちの投資先に40年の歴史を持つ学習塾があるのですが、その塾に対して、問題作成などをサポートするITサービスを開発するシード期のスタートアップに投資しました。スタートアップは私たちの塾を実証実験の場として活用し、プロダクトを磨き上げることができる。このように、歴史ある中小企業と、新しい技術を持つスタートアップを掛け合わせることで、新たな価値を生み出す取り組みも進めています。
将来的には、特定の業界に特化して買収を進め、業界再編を主導していくようなことも視野に入れています。
── 100社という目標を達成した先には何を見据えていますか?
中塚 日本には300万社以上の中小企業があると言われており、私たちが100社を支援したとしても、事業承継問題全体から見れば、まだまだ微々たるものです。私たちだけの力では限界があります。
そこで、将来的には、私たちと同じように「中小企業の社長になりたい」「自分の力で会社を買って経営したい」と考える、意欲ある若者たちをサポートする側に回りたいと考えています。
彼らにお金や案件探しのノウハウを提供したり、共同で投資を行ったりする。NYCを中心としたコミュニティ、いわば「エコシステム」のようなものを構築することで、レバレッジを効かせ、日本全体の事業承継問題を解決する大きなうねりを起こしていきたい。それが私の描く未来像です。
── 近年、事業承継を考えるオーナー社長の意識に変化は感じますか?
中塚 とても感じますね。数年前までは、病気など、やむにやまれぬ事情で売却を決意する方が多かったのですが、最近はコロナ禍やAIの台頭といった世の中の大きな変化を受けて、「このまま自分一人で経営を続けるのは不安だ」「時代の変化に対応できる若い世代に任せたい」と考えるオーナー社長が明らかに増えています。
以前は、私たちのような若い会社が事業承継をしようとすると、「スーツをカチッと着て、いかにも金融マンらしい振る舞いをしないと相手にされない」という風潮がありました。
しかし今は逆で、私たちのラフなスタイルや、YouTubeでの発信も含めて、「荒削りだけど勢いがある」「AIなど新しいことにも詳しそうだ」と評価していただき、大企業とのコンペで私たちを選んでくださるケースも出てきています。これは非常にありがたい変化です。
── 読者の中にも事業承継で悩んでいる社長は多いと思います。
中塚 私たちは、単なる投資ファンドではありません。長期的な視点に立ち、新しい風を吹き込むことで、会社の未来を一緒に創っていくパートナーです。もし、ご自身の会社の将来について、事業の頭打ちや後継者不在といったことで悩んでいるオーナー社長がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、私たちにご相談いただければと思います。
また、私たちの取り組みに共感し、「後継者として中小企業の経営に挑戦したい」という方や、「NYCの活動を支援したい」という方も大歓迎です。一緒に、日本の未来を支える中小企業を元気にしていきましょう。
- 氏名
- 中塚 庸仁(なかつか のぶひと)
- 社名
- NYC株式会社
- 役職
- 代表取締役社長