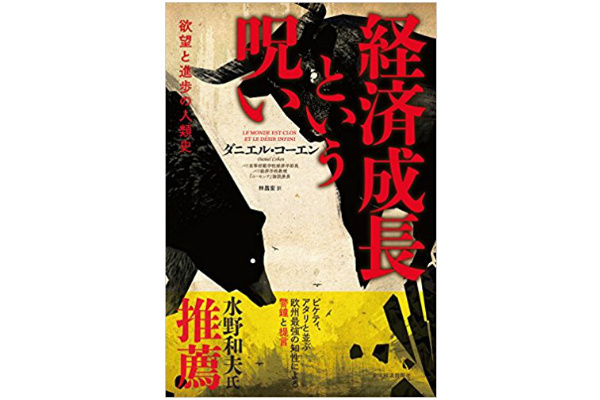「現代の宗教ともいえる経済成長は、人々の衝突を和らげ、無限の進歩を約束する妙薬」のはずだった。ところが今、先進国の経済成長率は伸び悩んでいる。それに起因するとみられる対立や衝突も生じている。
デジタル技術が急速に普及する一方、経済成長率は低迷を続けている。現代社会は成長を必要としているのか? われわれの最終目的は、富か、それとも成長か? あるべき経済成長の姿とは何か?――これらが本書の主な問いである。
著者ダニエル・コーエンは、パリ高等師範学校(エコール・ノルマル・シュペリウール)の経済学部長、『ル・モンド』の論説委員などを務めるフランスの著名な経済学者であり、思想家である。
本書は、人類史を通じて文明化の過程を辿るとともに、有限な「閉じた世界」に住まう現代人が、なお経済成長への「無限の欲望」を追い求めることの問題点と将来性について、深く人間心理にまで分け入って考察した好著である。
『経済成長という呪い――欲望と進歩の人類史』 著者:ダニエル・コーエン 訳者:林昌宏 出版社:東洋経済新報社 発売日:2017年9月7日
「絶えざる経済成長」という概念の誕生
本書の原題はLe monde est clos et le désir infini(閉じた世界と無限大の欲望)、英訳版はThe Infinite Desire for Growth(成長への無限の欲望)である。
エミール・デュルケームのいった「無限(アンフィニ)という病」を思わず連想したが、実は本書の題名は、ロシア出身の科学史家アレクサンドル・コイレの著書From the Closed World to the Infinite Universe(閉じた世界から無限の宇宙へ)からヒントを得たらしい。
コイレによると、17世紀の科学革命は、宇宙が無限かつ真空であり、神が存在しないことをヨーロッパの人びとに強く意識させたという。また18世紀の啓蒙思想は、神の座に理性を据えるとともに、神による救済の約束が確実に果たされるという希望(espoir)=望徳(ぼうとく)を失った人びとの意識に「進歩」という新たな信条を吹き込んだ。
ただし当時の「進歩」は、道徳的な意味、あるいは旧体制を否定する政治的な意味であって、経済、特に物質的な豊かさ(金儲け)と結びつけて考えられていたわけではなかった。それが結びつくのは19世紀の産業革命によってであり、そのときまで「絶えざる経済成長」という概念は存在しなかった。
20世紀になると、フォーディズムに代表される大量生産と大量消費による経済成長が続く。ところが今日、21世紀のポスト工業社会を生きるわれわれは、テクノロジーの躍進によるデジタル革命を経験しながらも、それが経済成長に結びつかない状況に直面している。