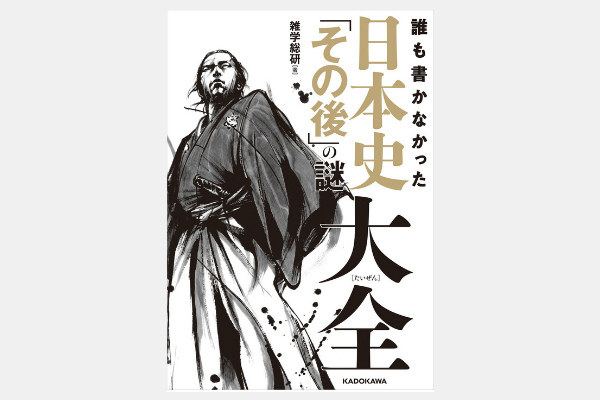日本史にはさまざまな謎が存在する。その中でも大実業家と言われた渋沢栄一や財政家の高橋是清、1万円札の顔である福沢諭吉はどのような素顔だったのだろうか。『誰も書かなかった 日本史「その後」の謎大全』から一部取り上げてご紹介しよう。
(本記事は、雑学総研の著書『誰も書かなかった 日本史「その後」の謎大全』=KADOKAWA、2018年2月1日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)
【関連記事 『誰も書かなかった 日本史「その後」の謎大全』より】
・(1)引退後に渋沢栄一がしたこと、高橋是清や福沢諭吉の信念とは-日本史に残る「お金」に関する謎
・(2)日本の通貨が両から円になった背景、秀吉の財産、シーボルトの持ち出し品の行方は?
いまだ謎に包まれたまま! 西郷隆盛の本当の顔はどれなのか?
2018(平成30)年は、明治維新から150年という節目にあたる。
明治維新とは、簡単にいえば「日本を近代国家にするために、明治時代のはじめに行なわれた一連のさまざまな改革」のこと。そして明治維新は、1877(明治10)年の西南戦争の平定によっていちおうの完成を見たとされる。
西南戦争において、鹿児島の不平士族らが盛り立てたのが西郷隆盛である。すぐれた指導力で明治維新を成功させた人物がこの「西郷どん」であるが、その一方で明治維新を「終わらせた人物」もまた彼であったといえる。
さて、西郷隆盛といえば、いまだに謎なのが「顔」である。肖像画や写真を後世に遺すことを好まなかった西郷だったから、彼の実際の容貌がどのようなものだったのか、いまだにわからずじまいなのである。
そこで、西郷が本当はどんな顔だったのかというミステリーがいまだに流布しているわけだが、実はいまもなお新たな肖像画が発掘され続けているのだ。
近年においては、2003(平成15)年に大分県日田市で発見された肖像画がある。これは、幕末・明治期に同市で活躍した文人画家・平野五岳が掛け軸に描いたもので、水墨淡水画となっている。この肖像画に描かれた西郷は、これまで私たちが見てきた軍人のかっぷくような恰幅のよい容姿ではなく、優しくて気立てのよい老人のような西郷だ。福耳で、柔和な顔立ちなのも、ほかの肖像画とは一線を画している。
描かれた人物が本当に西郷であるかどうかについては、平野が西郷に面会を申し込むときに書かれたものとされる漢詩が遺っており、また、この肖像画の人物が着ている羽織が西郷南洲顕彰館に遺されているものと同一であることから確認できる。
ただし、これが西郷の肖像画の決定版かというとそうではないようで、2017(平成29)年には鹿児島市在住の古美術収集家が所蔵していた、それまで未公開の肖像画の所在も明らかとなった。やわらかい表情の描き方は、日本画家・服部英龍のタッチに似ているが、画中の印から英龍の弟子・雲龍のものとされている。
西郷隆盛の肖像画に関しては、イタリア人の銅版画家エドアルド・キヨソネの手による肖像画(顔の上半分を弟・西郷従道、下半分を従兄弟・大山巌の写真をもとに描いた絵)や、上野の西郷像のモデルになった服部英龍の描いた肖像画(着流しで洋犬を連れている絵)、庄内藩の士族・石川静正による穏やかで慈悲深い表情の肖像画、西郷の膝の上で遊んでいたという薩摩藩出身の画家・肥後直熊の肖像画など、さまざまあるが、どの絵も微妙に表情は異なる。
西郷隆盛の本当の顔をめぐる謎は、実はいまも現在進行形なのである。
坂本龍馬暗殺後、海援隊はどうなった?
「日本初の株式会社」と称される亀山社中を前身に持つ「海援隊」。
幕末の混沌とした時代に結成された団体(新選組、奇兵隊など)と比べて亀山社中がユニークだったのはその利益の上げ方で、薩摩藩から資金提供を受けた上で経営を亀山社中が行なうという、現在の株式会社のようなシステムは、幕末の日本においては画期的なことだった。
亀山社中が日本初の株式会社といわれるのはこのことによるもので、「株主」を薩摩藩から土佐藩に変えて生まれたのが海援隊というわけである。
だが、不幸なことに、本格的な経済活動を行なう前に坂本龍馬は暗殺されてしまう。
龍馬の指揮のもとに海援隊が活動できたのは、わずか半年にすぎなかった。
では、1867(慶応3)年11月に京都の近江屋で龍馬が殺されたあと、当の海援隊はどうなったのだろうか。
このとき、海援隊の所属隊士は京都と長崎にわかれて活動していたが、とりあえず存続はしていた。
龍馬の秘書室長だった長岡謙吉は1868(慶応4)年1月、官軍の一員として海援隊の同志たちと瀬戸内海に浮かぶ塩飽諸島を訪れ、一帯を鎮めることに尽力し、高松藩の居城である高松城(香川県高松市)の接収なども行なっている。
これらの統率により、同年四月には長岡が海援隊の二代目隊長に就任するが、新宮馬之助や睦奥陽之助(宗光)、佐藤与之助、伊東祐亨など、隊士たちが新政府に出仕していったため、同年閏4月、株主である土佐藩からの通告によって海援隊は消滅したのだった。
なお、龍馬と仲のよかった岩崎弥太郎は海援隊から船や水夫などを譲り受け、三菱財閥の初期の基盤であった海運業を成功させる。つまり、三菱を大財閥に成長させたのは、海援隊の解散ともいえるのだ。
その後、弥太郎の築いた三菱の海運会社は日本郵船と合併するが、日本郵船の社旗こそ、白地に赤二本線を配した海援隊の旗と同じであった。海援隊、引いては龍馬の遺志は、弥太郎に引き継がれたともいえる。
「命のビザ」を発給し続けた杉原千畝の不遇なその後
1949(昭和15)年7月29日、早朝。リトアニアの当時の首都・カウナスにある日本領事館の扉が開かれ、難民となったユダヤ人が日本を通過できるためのビザの発給作業が開始された。いわゆる「命のビザ」の発行がはじまったのだ。
この、ユダヤ人のためのビザを発給した人物が外交官・杉原千畝だった。当時、ビザはまだ手書きで、食事をする時間を惜しんで杉原は一晩中ビザを書き続けた。
それは同年9月5日に杉原一家がカウナスを発つまで続けられ、彼は駅のホームでもベンチに座りながらビザをひたすら書いた。結果、杉原が発給したビザの総数は2139枚に達し、6000人ものユダヤ人が命を長らえることができたと伝わる。
しかし、戦後、ルーマニアのブカレスト郊外の捕虜収容所に連行されて、終戦の翌年4月にようやく故郷の土を踏むことができた杉原に、日本での居場所はなかった。その原因は明らかにユダヤ人に出したビザの件であり、外務省としてもかばい切れないという旨の通告とともに同省を解雇されたのだった。
いくら所属先の命令に反してビザを出したとはいえ、6000人の命を救った事実は揺らぐことはない。この外務省による「仕打ち」がよほど悔しかったのか、杉原は以降、同省の関係者とはいっさい連絡を取らなかったという。
その後、貿易会社や翻訳、語学指導などのかて仕事に就いて生活の糧にしていた杉原だったが、1968(昭和43)年8月、イスラエル大使館から電話があり、大使館へ赴いてみると、そこには彼が発給したビザによって助けられた人物がいた。彼をはじめとする人びとは、長いあいだ杉原の行方を探し続けていたのだという。杉原の行ないは、戦後23年ののち、ようやく報われたのだった。
現在、杉原がビザを発給した地であるリトアニアには「スギハラストリート」という、彼の栄誉を讃える通りが存在し、また、同国の歴史の教科書などには彼の行ないが語られている。
なお、死の前年の1985(昭和60)年1月には「諸国民の中の正義の人賞」を意味するヤド・バシェム賞を受賞。ユダヤ人を救った人物として、スギハラはいまでもなお人びとの心の中に生き続けている。
アメリカへ戻ったマッカーサーはその後どうなった?
第二次世界大戦における日本の無条件降伏後の1945(昭和20)年8月30日午後2時5分、ダグラス・マッカーサーは連合国軍最高司令官として厚木飛行場に降り立った。開襟シャツにレイバンのサングラス、そして口にはコーンパイプ。その姿はまさに、「先進国」アメリカを象徴するものであった。
さて、日本の民主化と非軍事化を実現していったマッカーサーだが、「アメリカ政府や国連の公務に対して心から支持していない」という理由でトルーマン大統領から解任され、1951(昭和26)年4月16日に羽田飛行場から帰国したあと、どのような人生を送ったのだろうか。
全米各地で熱狂的な歓迎を受け、議会で「老兵は死なず、ただ消えゆくのみ」というあまりにも有名すぎる演説をした彼だったが、「消えゆく」思いは微塵も持ち合わせておらず、実は対日政策の成果をひっさげて、帰国の翌年に行なわれる大統領選に打って出ようとしていたのだ。
マッカーサーの解任当時、アメリカ国民は英雄である彼の職を解いたトルーマン大統領に対して非難の目を向けており、マッカーサーもその世論を基盤にしていたが、「マッカーサー・ブーム」も長くは続かなかった。同年の共和党大会において、彼が大統領候補に推されることもなかった。
1952(昭和27)年7月には民間企業のレミントンランド社の取締役会長に就いたが、これは名誉職ともいえるもので、政治・軍事の世界でなおも活躍しようと考えていた彼にとっては何も得るものはなかったといってよい。
1962(昭和37)年、陸軍士官学校において陸軍大学の最高勲章であるシルバナス・セイヤー・メダルを贈られたが、ほどなく胆のうを患い、2年後には入院を余儀なくされ、同年4月5日、ワシントンのウォルターリード陸軍病院にて亡くなった(享年84)。
慈善事業を「道楽」と呼んで楽しんだ実業家・渋沢栄一
官による主導ではなく、民間からの殖産興業(明治初期、近代産業技術を輸入して資本主義的生産方法を保護・育成しようとした政策)によって、明治の日本に貢献した実業家・渋沢栄一。
渋沢はいわば「大実業家」と讃えられるほど、手広く事業を展開し、その指導的立場にあった。第一国立銀行を設立して頭取に就いたのをはじめ、日本郵船会社、帝国ホテル、札幌麦酒、東京電力、東京瓦斯など、およそ500の企業の創立に携わったとされる。
1840(天保11)年、豪農の家に生まれた渋沢は、若い頃には尊攘運動に身を投じるが、その後、御三卿の一つである一橋家に仕え、慶喜の弟・昭武に随行してパリで開かれた万国博覧会を見学。このことが渋沢をいざな実業界へと誘う契機の一つとなった。
帰国後、日本初となる株式会社(当時の名称は合本組織)とされる商法会所を設立。のち、大蔵官僚を経て、先述の大実業家の道を歩むこととなるのである。
さて、そんな渋沢は、1916(大正5)年、77歳のときに第一銀行(1896年に改称)の頭取を辞したが、その後はいったいどんな人生を送ったのだろうか。
渋沢が以降に行なったのは、社会公共事業に専念することであった。
彼は30代の頃より、東京市養育院などを設立して身寄りのない子どもや老人のために尽くしていたが、そのような活動を余生でも続けようとしたのである。
渋沢は自ら資金を提供するのはもちろんだが、実は自分以外の企業人などに金を出させることもまた得意であった。渋沢はこのことについて、以下のように語っている。
「私には、事業を楽しむ癖がある。これまで種々の社会事業に奔走し、寄付金集めをやってきたが、また渋沢の寄付金取りかと、しかめっ面をする金持ちもいたらしい。こう思われてもあまり良い気分ではないが、私はちっとも苦痛とは思わない。これは私が社会事業のために尽力するのを無上の楽しみにしているからである。もし、これを楽しみにしてかからなければ、とても寄付金集めで駆け回れるものではない」
渋沢が晩年になってもこのような純粋な気持ちを持ち続けることができたのは、七歳の頃に読んだ『論語』をはじめとする四書五経といった中国の古典や、母・えいの教えが影響していたようだ。「三つ子の魂百まで」といったところだろうか。
そして、渋沢はその信念を以下のような言葉で述べている。
「不肖ながら私は論語を以て事業を経営して見よう。従来論語を講ずる学者が仁義道徳と生産殖利とを別物にしたのは誤謬である。必ず一緒になし得られるものである」
1931(昭和6)年11月、渋沢は腸閉塞の悪化などにより92歳でこの世を去った。彼が死去したとき、看病していた皆が号泣したと伝わる。渋沢がどれほど慕われていたかがわかるエピソードといえよう。
大津事件を裁いた児島惟謙は賭博スキャンダルで失脚した
1891(明治24)年5月11日、当時の日本を震撼させる事件が勃発する。
ウラジオストックにて催されるシベリア鉄道の起工式に出席する際、日本に立ち寄ったロシア皇太子・ニコライ(のちのニコライ二世)が大津町(現・滋賀県大津市)で警衛中の滋賀県巡査・津田三蔵に頭部を斬りつけられ、負傷したのだ。
津田はロシア皇太子の来日を、ロシアによる日本征服の端緒であると捉え、事件を起こしたのだった。この事件は「大津事件」(南事件とも)と呼ばれ、明治中期の日本を襲った大事件として記憶されている。
この大津事件を処理したのが、大審院院長・児島惟謙だ。大審院はいまでいう最高裁判所のことだが、事態の大きさから日本の皇室に対する罪として捉えて「津田を極刑(死刑)にすべし」という松方正義内閣の要請を、「外国の皇族なので、一般の殺人罪しか適用すべきでない」と児島は突っぱね、結局津田を無期懲役の刑に処した。
このことにより、児島は法を遵守したということから「護法の神」として讃えられることになったのだった。 ところがこのあと、児島にスキャンダルが持ち上がる。児島をはじめとする七人の大審院判事が花札賭博をしていたというのだ。
確かに児島らは花合わせをしたことは認めたが、金銭を掛けた事実はなかった。つまり児島は、大津事件の判決に対する意趣返しで、反児島派からハメられたのである。
1892(明治25)年7月、児島は懲戒裁判のすえ無罪となったが、事件の責任を問われて辞任。児島が大審院院長に就いていたのは、わずか1年3か月であった。その後、児島は貴族院議員、衆議院議員など、十一年以上にわたり帝国議会議員を務めるが、あまり活発に政治活動を行なっていなかったようで、政治家としての児島の評価はそれほど高くはない。
なお、冒頭に述べた「護法の神」としての児島の評価だが、事件に際し、自身は事件を担当していないにもかかわらず、担当判事を個別に呼び、自分の説に賛成するように迫ったといわれる。こうなると、児島は「裁判所の独立」を自ら犯したことになり、「護法の神」とはいえないのではないか、と考える識者もいる。
「何も遺さず死ぬ」との信念を貫いた政治家・高橋是清
明治から昭和にかけて活躍した政治家・財政家の高橋是清ほど、波瀾万丈な人生を送った男はいない。
幕府の御用絵師・川村庄右衛門の庶子(正妻でない女性の産んだ子)として江戸に生まれ、仙台藩の足軽・高橋是忠の養子となった是清(幼名は和喜次)は、1867(慶応3)年に仙台藩の留学生として渡米するが、留学中に手違いで奴隷として売られた。
帰国後は農商務省の官吏となって特許局昇進するも、その職を辞して南米へ渡り、ペルーで銀山開発に取り組むが失敗、無一文で帰国している。
是清の人生の変遷はまだ続く。第三代日本銀行総裁・川田小一郎に誘われて、建築中の日本銀行本館の建築事務主任に抜擢されると、その後、九州全域を管轄する西部支店の初代支店長に就任し、副総裁を経て、1911(明治44)年には総裁にまで登り詰めた。
以降、政界に進出した是清は、首相を1回、そして大蔵大臣をなんと7回(うち1回は首相との兼任)も経験している。
日本が経済的に危機を迎えたとき、政治家から請われて登用されたのが是清で、1925(大正14)年4月にいったん政界を引退し、東京都港区赤坂にあった自邸で仏像鑑賞や盆栽を楽しんでいた彼は、その後だけでも三度も大蔵大臣に就いている。
もしも是清が1925年に引退してから再び政界へ戻ることがなかったならば、1936(昭和11)年の2・26事件で陸軍青年将校の凶弾にたおれることもなかっただろう(享年81)。
それまで何度も日本の経済危機を救ってきた是清だったから、満洲事変の勃発以降に急激に増加した戦費を抑えるために、軍部の軍事費拡大の要求をのむことはできなかった。ここに是清の不運があった。
さて、このような激動の人生を送ってきた是清だったから、自身が無一文になることをまったく恐れず、こんな考えをもっていたという。
「子が相当の年齢に達した以上は、まったくの独立独歩、一厘半銭も親の厄介にはならず、自分の奮闘によって、自分の運命を開拓して行く」(「是清翁遺訓」)
留学中に奴隷となり、ペルーの銀山開発ですっからかんになり、何度も重職を歴任した是清だからこそたどり着いた思想は、無から有を生み出すことができる強さを求めたものといえるし、逆にいえば、死ぬ間際に金に執着することを認めないものでもあっただろう。
事実、是清は財産と呼べるようなものを遺さなかったとされ、また、彼がずっと胸に抱いてきた信念にその真意を読み取ることもできる。
彼は、こんな信念を持っていたと伝わる。
「自分の始末は自分一個の腕でやれ」
死ぬ間際まで他人に媚びることのなかった福沢諭吉
「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らずと言えり」
明治時代の啓蒙思想家・福沢諭吉は自著『学問のすゝめ』(1872年)の中でこのように述べ、人間の自由、平等、そして権利の尊さを説いた。
一方、諭吉は以前より築地・鉄砲洲に建っていた奥平藩の屋敷にて洋学塾を開いていたが、それを芝・新銭座へ移した。この塾こそ「慶應義塾」で、現在の慶應義塾大学の前身である。慶應義塾が現在の三田の地に移ったのは、1871(明治4)年のことであった。
このように、諭吉はそれまでに自身が体験して得た外国事情(1860年、日米修好通商条約の批准のために渡米する木村喜毅の従者として同行、1862年には遣欧使節の通訳としてヨーロッパ、ロシアへ同行)を日本へ持ち帰り、新生日本を担う若者たちにそれらを伝えたのだ。
では、諭吉はその後、どのような人生を送ったのだろうか。
諭吉の著作の中でもっとも有名なものの一つが『福翁自伝』であるが、同書が刊行されたのは1899(明治32)年のことである。
海外経験が豊富で、つねに人びとの先頭に立ってきた諭吉の生涯を知りたいと願う人は少なくなかったが、諭吉が多忙のため実現できずにいた。
だが、ある外国人にそれまでの生涯を語ったところ、自身の思うように伝えることができたのだろう、自身の経てきた道を後世に伝える気持ちが募り、1897(明治30)年11月より口述による原稿制作が開始される。
口述自体は翌年5月までに終えることができた。
その後、諭吉が原稿を校正し、同年7月より「時事新報」(諭吉が主宰する新聞)紙上にて連載することとなった。
だが、諭吉にそれほど生きる時間は許されていなかった。連載開始から2ヵ月後の9月26日、諭吉は脳出血で倒れ、言葉も発することができない状態となった。その報が皇居へ伝わると、天皇、皇后、皇太子から見舞いの品が届けられ、加えて、政府からは諭吉に爵位を授与しようという動きが見られるようになる。
だが、諭吉は爵位の授与を断った。このとき、彼の意識は混濁状態にあったので、正確には諭吉の家族が判断したことではあったが、意識を失う前の諭吉の意思が反映されたものだった。
実は、諭吉にはそれ以前にも、在野の思想家であり続けたいと願うことを象徴する出来事があった。
1891(明治24)年、国語学者・大槻文彦が国語辞典『言海』を完成させた記念として祝賀会が開かれることとなり、諭吉もそれに呼ばれたことがある。
ところが、同会で諭吉に用意されていたスピーチの順番が伊藤博文のあとであったことから、「老生は伊藤伯に尾して賤名を記すを好まず」と、自分の名前が伊藤の後ろに連なることを拒否したのだった。
この行為には、在野の思想家として「官」に対する毅然とした態度を貫きたいという諭吉の思いが込められているのではないだろうか。1901(明治34)年1月25日、諭吉は再度脳出血で倒れ、翌月3日、この世を去った(享年68)。東京麻布・善福寺で催された葬儀には、1万5000人以上の参列者が訪れたと伝わる。
孫に「アンポ、ハンターイ!」と叫ばれて困惑した岸信介
戦前は革新官僚のトップとして満洲の経営に従事し、戦後はA級戦犯容疑で巣鴨プリズンでの獄中生活を3年3ヵ月送るものの、その後首相の座に就いた政治家・岸信介。彼につけられたあだ名は「昭和の妖怪」「巨魁」「不死鳥」「怪物」と数多いが、その理由は前述のような、逆境から何度も立ち上がってきた経歴によるものである。
1957(昭和32)年に首相になった岸は、3年後の1960(昭和35)年5月に新安保条約を強行採決すると、6月には全国的な運動に発展。デモ隊が国会構内に突入して警官隊と衝突し、7月、条約の自然承認後に退陣する。このとき岸は64歳だった。
では、岸はその後どのような人生を送ったのだろうか。
晩年の彼は、趣味の盆栽とゴルフに明け暮れていたようだ。
岸の盆栽好きは政界でもかなり有名だった。政界には岸のほかに、弟の佐藤栄作や鳩山一郎、石橋湛山、河野一郎などの盆栽愛好家がいたが、彼らを盆栽の世界に導いたのが岸であったといわれる。岸はそれほどの盆栽好きであったから、政界引退後、御殿場にあった私邸では、鋏を手に盆栽を楽しんでいたという。
岸の趣味にはゴルフも欠かせなかった。
岸がゴルフにはまったのは商工省の参事官として働いていた1926(大正15)年のことで、渡航先のアメリカではじめたことがきっかけだったという。岸の言い分によれば、ゴルフやダンス、自動車の運転を理解できなければアメリカ人の思考は理解できない、ということだったらしい。岸が人の懐に深く入ることができる術を若いときから持っていたことが、このエピソードからも読み取れる。
一方、岸信介といえば、第90・96・97・98代首相・安倍晋三の祖父でもあるが、ちょうど退陣を余儀なくされようとしていたときの逸話が興味深い。
当時、岸の私邸は東京都渋谷区南平台にあったのだが、先述の新安保条約の強行採決時、大学生を主体とするデモ隊は首相官邸のみならず、渋谷の岸の私邸をも取り囲む行動に出る。
そのとき、私邸で遊んでいた晋三は、デモ隊のシュプレヒコールを真似て「アンポ、ハンターイ!」と足踏みした。晋三の父である安倍晋太郎は息子のそのような行動を見かねて「『アンポ、サンセイ』といいなさい」と咎めたが、岸は孫を叱ることもせず、ニコニコと笑っていたという(安倍晋三『この国を守る決意』扶桑社)。
1987(昭和62)年八月、岸は90歳の生涯を閉じた。政治家としての念願であった小選挙区制の導入は実現したが、二大政党制はまだはっきりとした形では実現していない。「昭和の妖怪」の頭の中にあった理想は平成になってから花開いたが、彼が政界に遺した影響力がいかに大きかったかを物語るものといえよう。
雑学総研
珍談奇談の類から、学術的に検証された知識まで、種々雑多な話題をわかりやすい形で世に発表する集団。江戸時代に編まれた『耳袋』のごとく、はたまた松浦静山の『甲子夜話』のごとく、あらゆるジャンルを網羅すべく、日々情報収集に取り組んでいる。