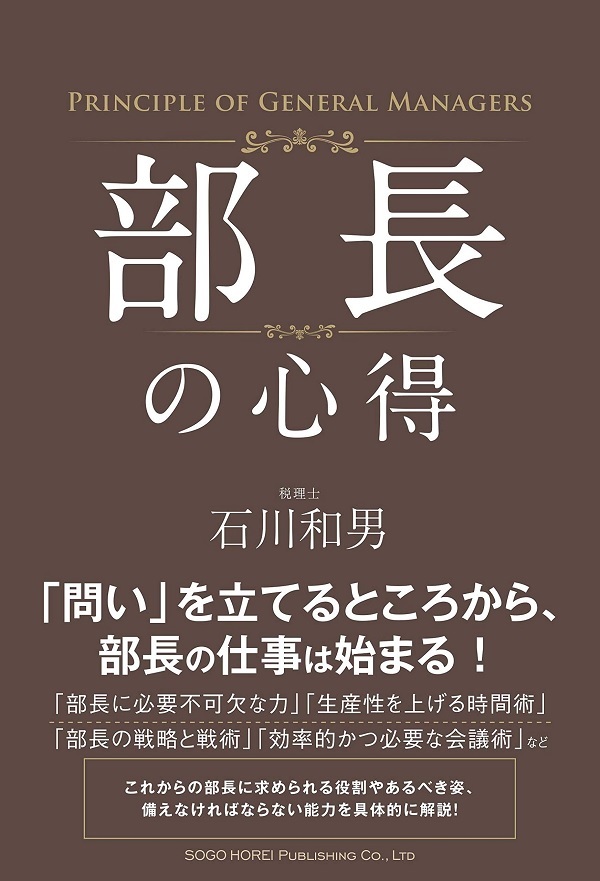(本記事は、石川和男氏の著書『部長の心得』総合法令出版の心得の中から一部を抜粋・編集しています)
部長に必須の「マネジメント力」
「虫の目」「鳥の目」「魚の目」とは
ビジネスにとどまらず、生きる上で必要な三つの視点を表したのが、「虫の目」「鳥の目」「魚の目」です。
まずは「虫の目」。虫はその小さな目で、非常に細かな世界を見据えています。人間の目では見えない世界も、虫にはしっかりと見えている。
そんなミクロの視点を表しているのが「虫の目」です。
続いて「鳥の目」。上空から斜めに見下ろしたような形式の地図を鳥瞰図(ふちょうかんず)と言いますが、この言葉が象徴するように、高い視点で物事を眺める資質を意味しています。高所から眺めれば、広い範囲を見て取れる。よく経営者が「大所高所から」と言いますが、これは「鳥の目」で俯瞰(ふかん)することを意味しています。「虫の目」のミクロな視点に対して、「鳥の目」はマクロな視点です。
最後に「魚の目」。話の流れから「魚(さかな)の目」だとわかりますが、単体だと足の裏にできる「魚(うお)の目」を連想しますね。もちろん、まったく異なります。
海を泳ぐ魚は潮の流れに敏感です。そんな魚のように時代の変化や潮流をしっかりと見定めること。魚の目は、時間の流れを意味しています。
部長には「鳥の目」が必要
三つの「目」の中で、どれが部長に必要とされる目でしょうか?
答えは、マクロな視点としての「鳥の目」です。
木の上に登って遠くを見渡す力。上空から地上を見渡し、どちらの方向を目指して進むべきかを示唆する力。
大胆に見える改革でも、実際には未来を見通し、たしかな勝算と共に提案する力。
そのような力を生み出すものこそ、「鳥の目」だと言うことができます。
もちろん、ほかの二つの目がいらないわけではありません。
細部に意識が向かない人や、時流を的確に読み取れない人は、消費者のニーズを見つけられず、説得力のある提案も難しくなります。
虫や魚の目がないと、部下の気持ちも理解できません。感情に訴えるプレゼンを実施することができません。
それでも、最後にすべてをまとめ上げるためには、やはり「鳥の目」が必要になります。
飛行機の窓から地上を見下ろすと、道路の構造が非常によくわかるように、「鳥の目」で組織の枠組みを正しく理解することができます。
また、「鳥の目」は失敗を回避することにも役立ちます。
悪い兆候を察するのは「鳥の目」の役目です。同じ地上に立っていては、方向性の誤りに気づきません。「大所高所」が大切だと言うのも、こうした視点に基づいています。
「鳥の目」を活かした「多角的視点力」
「鳥の目」を武器として、部長は様々な困難と向き合います。
そのための力を、「多角的視点力」と呼びます。
「多角的」とは「様々な角度から」という意味です。
部長は独自の視点で物事を判断しなくてはならないわけですが、自分の視点が常に正しいと思っていては、やがて判断を誤ってしまうことになります。
自らの視点を、自分自身で疑ってみるという資質。
それこそが、多角的視点力の本質です。
この力を発揮するためには、他者の視点が必要です。私はもう一人の自分と対話をして一人会議を行っています。もう一人の自分となので二人会議になるかもしれませんが、部長と課長、賛成意見と反対意見、ときには社長と部長になって、自らの頭で問いを立て、紙に書き出してそれに対する答えを模索します。すると、様々な角度から新しい発想が生まれてくるのです。