

不動産投資に取り組む中で、規模が拡大してくると意識したいのが「事業的規模」という区分です。この区分は税制や会計処理において大きな影響を及ぼします。
本記事では、不動産投資における事業的規模の基本から、「5棟10室ルール」と呼ばれる判断基準の具体的な内容、そして実際に事業的規模を目指す際に理解しておきたい戦略を解説します。
目次
1.不動産投資における事業的規模とは?

不動産投資における事業的規模とは、税務上、不動産所得が事業として認められるかどうかの目安となる区分です。
事業的規模であるかどうかは、税務的にどう取り扱われるかを左右する重要なポイントです。たとえば、事業的規模と認められると、不動産所得に対して青色申告特別控除(最大65万円)が適用可能になり、さらに家族に支払った給与を必要経費として計上できる「青色事業専従者給与」も利用できるようになります。また、損益通算の幅も広がるため、所得税や住民税の節税効果も期待できます。
一方、事業的規模に該当しない場合は、これらの優遇措置が使えなかったり、控除額が制限されたりするため、運用効率や節税の観点で差が出てくることになります。
2.事業的規模の判断基準となる「5棟10室ルール」

不動産投資が税務上の事業として認められるかを判断する際、よく使われるのが5棟10室ルールです。これは、一棟貸しの物件であれば5棟以上、部屋ごとの貸し出しであれば10室以上を所有していれば、原則として事業的規模とみなされるという基準です。
この5棟10室ルールは、かつての国税庁通達などに基づいており、明文化された法律ではないものの、長年にわたり税務上の実務で広く使われている判断基準です。
参考:No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分(国税庁)
2-1.駐車場や貸地の場合の判断基準
駐車場経営の場合は以下のように換算されることが一般的です。
・未舗装の青空駐車場やコインパーキングを委託運営→事業性が乏しいとされ、事業的規模と認められにくい傾向あり
このように、物件の種類によっては、規模だけでなく運営実態も重要な判断材料となります。
2-2.共有名義の物件の場合の判断基準
10室のアパートを夫婦で50%ずつ所有している場合、自分の持ち分は5室分になりますが、事業的規模の判断においては「物件全体で10室あるかどうか」が基準となります。つまり、共有名義であっても、共同で事業を運営しているとみなされ、原則として事業的規模に該当すると考えられています。
2-3.「5棟10室」だけが絶対条件ではない
5棟10室はあくまで一般的な目安であり、これに満たなくても、管理業務を自ら行っている、物件の稼働率が高いなどの要素があれば、事業的規模と判断される可能性はゼロではありません。逆に5棟10室を満たしていても、運営実態が乏しいと判断されれば、税務署から否認されるケースもあります。
5棟10室は大切な指標でありながらも、実際の判定には実態が問われることを理解しておきましょう。
3.不動産投資が事業的規模に達することで得られる3つのメリット

不動産投資を行う上で重要な判断基準となる「事業的規模」。この基準を満たすことで、税制面で大きなアドバンテージが得られます。ここでは、不動産投資が「事業的規模」に達することで得られる代表的な3つのメリットについて解説します。
3-1.青色申告特別控除を活用できる
個人で不動産所得がある場合、青色申告を選択すれば最大10万円の控除が受けられますが、事業的規模に該当すれば、この控除額が最大65万円に拡大します。これは帳簿を複式簿記で記帳し、一定の届出を行っていることが前提となりますが、節税効果は大きくなります。
例えば、年間の不動産所得が300万円の場合、通常の青色申告なら10万円の控除で課税所得は290万円ですが、事業的規模として65万円の控除が適用されれば課税所得は235万円となり、所得税率20%と仮定すると、11万円(=(290万円-235万円)×20%)の節税になります。
参考:No.2070 青色申告制度(国税庁)
3-2.家族に給与を支払える「青色事業専従者給与」が認められる
事業的規模と判断されると、家族を従業員として登録し、給与を必要経費として計上する「青色事業専従者給与」が認められるようになります。これにより不動産投資家本人の課税所得を圧縮でき、所得税や住民税の節税につながります。
なお、支払った給与は専従者側の所得としても課税対象になりますが、高い税率が適用される本人から、税率の低い家族へと所得を分散でき、トータルの税負担を抑える効果が期待できます。ただし、専従者は配偶者控除や扶養控除の対象外となる点に注意が必要です。
税務署は「実態を伴わない家族への給与支払い」については厳しく見ています。家族が実際に業務(物件の管理や事務作業など)に従事していること、また支払う給与額が妥当であることを示す証拠(業務記録や市場相場との比較資料など)を残しておくことが重要です。
3-3.損益通算の幅が広がる
不動産所得が赤字になった場合、原則として給与所得など他の所得と損益通算できます。ただし、事業的規模でない場合は、赤字の理由によっては通算が制限されることがあります。代表的なもので、減価償却(建物などの資産価値の減少分を費用計上する仕組み)や金利による赤字などが挙げられます。
一方、事業的規模であれば、減価償却や金利による赤字も正当な事業運営の一環と見なされ、損益通算が認められる可能性が高くなります。
4.不動産投資の事業的規模がもたらすの3つデメリットとその対策
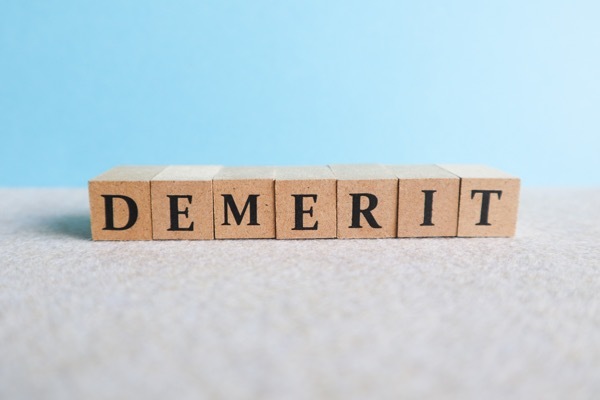
事業的規模に達することで多くの税務上のメリットを享受できます。しかし、その一方で規模が大きくなるからこそ生じる負担やリスクも存在します。ここでは、見落としがちなデメリットや注意点について整理しておきましょう。
4-1.事業税の対象になる可能性がある
不動産所得が事業的規模に該当し、かつ年間の所得が一定以上になると、「個人事業税(事業税)」の課税対象になる場合があります。東京都の場合、不動産貸付業で年間の事業所得が290万円を超えると、5%の事業税が課される可能性があります。なお、事業税の課税基準や税率は都道府県によって異なるため、物件所在地の自治体ホームページで確認することをおすすめします。
参考:あなたと都税2024(令和6)年8月号(東京都主税局)、貴重や帳簿等保存・青色申告(国税庁)
事業税は必要経費として計上できるものの、実際の影響は大きいです。例えば、不動産所得が500万円の場合、青色申告の特別控除65万円で所得税・住民税を節税できたとしても、事業税として約25万円(500万円×5%)が別途課税されます。「せっかく節税したのに、別の税金で持っていかれた」という声も少なくありません。事前に税負担を総合的に試算しておくことが大切です。
4-2.帳簿作成や確定申告の手間が大きくなる
事業的規模に該当して青色申告を行う際には複式簿記での帳簿作成が必要になります。そのため、仕訳帳や総勘定元帳の作成・保管に加えて、日々の記帳作業の正確さが求められます。また、確定申告の際には不動産所得に関する明細や、帳簿書類を提示する必要があるため、手間やミスのリスクが増える可能性があります。
こうした会計処理や申告業務については、税理士などの専門家に依頼することも可能です。費用はかかるものの、ミスを防ぎつつ本業や資産運用に集中できるメリットもあるため、自分で全部こなすのは不安という方は、専門家の力を借りる選択肢も前向きに検討すると良いでしょう。
4-3.副業制限がある職業では注意が必要
会社員として勤務しながら不動産投資を行っている方の場合、勤務先の副業規定にも留意する必要があります。事業的規模に該当すると、不動産所得が「事業的な収入」として扱われ、場合によっては副業に該当すると見なされるリスクがあります。
特に公務員や金融機関勤務の方など、職業によっては副業禁止規定が厳格なケースもあります。あらかじめ社内規定を確認しておくとともに、税務申告の際の「事業的規模」と、雇用契約上の「副業」の定義は別物であることを理解しておくことが重要です。
5.事業的規模に到達するためのステップと戦略

事業的規模の達成はひとつの目安になりますが、やみくもに物件数を増やせばよいわけではなく、資金や管理のバランスを見ながら、戦略的に進めることが大切です。
ここでは、事業的規模に到達するための現実的なステップと考え方を紹介します。
5-1.まずはどちらのルートで事業的規模を目指すかを決める
事業的規模の判断基準は、「5棟」または「10室」でした。そのため、目指すルートとしては「一棟アパート・戸建て中心で5棟以上」もしくは「区分マンションなどの部屋数で10室以上」の大きく2パターンがあります。
少額からスタートして区分マンションを買い増すスタイルであれば「10室ルート」が現実的ですが、融資を活用しながら一棟アパートを段階的に取得するなら「5棟ルート」が近道となることもあります。
5-2.目標までの逆算をする
事業的規模を目指すルートが決まれば、あと何室・何棟必要か明確になります。もし区分マンションを4室保有している場合、あと6室取得すれば10室ラインに達します。
その上で、ターゲットとする物件や必要な自己資金、金融機関からの融資の目処といった現実的な条件を整理し、取得ペースや優先順位を設定していくことが大切です。
5-3.購入戦略の選択がカギを握る
事業的規模を効率的に目指す上で、どのような物件を選ぶかも重要です。次に記載されている物件の特徴は、最低限理解しておきましょう。
・都市部の区分マンション:流動性が高く、管理の手間も少ないが、戸数の確保には時間がかかる
・地方の高利回りエリア:取得費用は安いが、空室リスクが大きい
自身の資金力や不動産投資に割ける時間や労力と照らし合わせて、無理のないスタイルでスケールアップを図ることが成功のポイントになります。
6.事業的規模と法人化の関係

不動産投資で事業的規模に達すると、「そろそろ法人化を考えるべき?」という悩みを抱く方も多くなります。実際、物件数が増え、収益が安定してくると法人化の選択肢が視野に入ってくるのは自然な流れです。ただし、事業的規模と法人化は別の軸で考える必要があることを理解しておきましょう。
関連記事:不動産投資で法人化すべき?メリット・デメリットやタイミング、会社設立の流れ
6-1.不動産投資の事業的規模と法人化の違い
まず押さえておきたいのは、事業的規模=法人化しなければならない、というわけではないということです。個人のままでも5棟10室を超えて事業的規模に該当することはできますし、青色申告や専従者給与といったメリットも活用できます。
一方で、法人化は税率のコントロールや資産管理の分離など、別の視点から検討されるべきものです。
6-2.法人化の主なメリット
法人化は、所得税率、経費計上、相続などでメリットを享受することができます。
6-2-1.所得が高額になるほど法人の方が税率を抑えやすい
個人の場合、所得が増えるほど所得税の税率も上がっていき、最高税率は45%にも達します(住民税を含めると最大55%)。一方、法人税は利益の額に応じて段階的な税率が適用されますが、一定の利益までは中小企業の軽減税率(15〜23.2%程度)が適用され、高所得者ほど法人の方が有利になる傾向があります。
一般的には、課税される不動産所得が年間800〜1,000万円を超えるあたりから、法人化による節税メリットが出てきやすいとされています。ただし、この判断はあくまで目安であり、所得構成や他の収入とのバランス、将来の投資方針によって適切なタイミングは異なります。
参考:No.2260 所得税の税率(国税庁)、法人税率の軽減(中小企業庁)
6-2-2.経費計上の幅を広げやすくなる
個人の青色申告でも一定の経費は計上できますが、法人ではより柔軟な経費処理が可能になります。たとえば、法人契約での車両購入や通信費、出張費支払いなどは事業に関連していれば経費としやすく、節税の選択肢が大きく広がります。
6-2-3.相続・事業承継の柔軟性が高まる
法人化は、将来的な資産の承継や相続対策としても有効です。不動産を個人で所有していると、相続時にその評価額が相続税の対象となりますが、法人所有であれば、株式の形で資産を引き継ぐことが可能です。これにより相続評価額を抑えたり、事前に贈与計画を立てたりといった柔軟な資産管理ができるようになります。将来的に子どもや家族に不動産事業を引き継がせたいと考えている場合には、大きなメリットになるでしょう。
6-3.法人化の注意点
法人化すると、いくつかの追加負担も発生します。
まず、法人を設立するには登記費用や定款の作成、各種届出といった初期費用がかかり、設立後も毎年の決算申告や税務申告のために、税理士などの専門家に依頼するケースが一般的です。その分、運営コストは個人よりも高くなりがちです。
また、法人が一定の要件を満たすと、社会保険への加入が必要となる場合があります。たとえば、代表取締役1人だけの小規模法人であっても、強制的に厚生年金・健康保険に加入することになり、これも見落とされがちな負担のひとつです。
さらに、法人と個人はお金の出し入れや資金繰りを明確に分ける必要があります。収益を個人で使いたい場合は、法人からの役員報酬や配当という形にしなければなりません。そのため、資金管理の難易度が上がる点は留意する必要があります。
単純に「節税になりそうだから法人化しよう」と飛びつくのではなく、中長期的な収支やライフプランに基づいて検討することが重要です。
7.事業的規模は不動産投資家としての分岐点

不動産投資における「事業的規模」は、単に物件数が増えたというだけでなく、税務上の扱いや経営スタンスにおいて、大きな転換点となる概念です。特に事業的規模によって開かれる節税メリットは、資産形成の加速にも直結します。
一方で、帳簿作成や申告の複雑化、事業税の発生といった実務上の負担も伴うため、「ただ戸数を増やせばいい」という短絡的な発想では後悔することもあり、自身のライフスタイルや長期的な投資ビジョンに照らした慎重な判断が求められます。
まずは自分が今どの地点にいて、どんなスタイルを目指したいのかを整理しながら、無理のない範囲でスケールアップを検討することが重要です。
制度を正しく理解し、自分に合った最適な不動産投資のかたちを見つけていきましょう。
(提供:Dear Reicious Online)
【オススメ記事 Dear Reicious Online】
・40代からの将来設計。早いほどおトクなマンション経営
・マンション経営の物件選び!初心者がまず知っておきたい必須のポイント
・少子高齢化社会が不動産の可能性に与える影響
・「働く」だけが収入源じゃない 欧米では当たり前の考え方とは
・実は相性がいい!?不動産×ドローンの可能性
