本記事は、枡野 俊明氏の著書『気にしないコツ』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

イヤな相手に支配されない技術
平常心是道 - 極める先に道があるのではない。日常の暮らしそのものが道である。修行の末に悟りに至るのではない。平常の心こそ悟りなのだ。それに気づくことが何より大切である。
自宅に戻ってから、昼間に誰かから言われた言葉をふと思い出し、無性に腹が立ってきたり、仕事相手の振る舞いが頭をよぎり、許せない気持ちが再び込み上げてきたりする、こんな経験はありませんか?
そのときはうまくやり過ごしたつもりだったのに、時間が経つにつれて、段々と怒りが湧き上がってくる。相手が、目の前にいないのに、あとからイライラにとらわれてしまう。特に夜は、感情が高ぶりやすいため、心が怒りに支配されて眠れないこともあるでしょう。
怒りに心が支配されているのは、平常心を失っている状態です。ですが、心はいったん怒りの方向に振れても、すぐに元の状態に戻ります。竹を思い浮かべてみてください。風が吹けば竹はその方向にしなりますが、風がやむと、竹はしなやかに元の位置に戻ります。心も同じで、元の平常心に戻る力が備わっています。
では、どうすれば素早く平常心に戻れるのでしょうか?
特別なことをする必要はありません。普段の日常的な行動をいつも以上に丁寧に、いっそう心を込めて行うのがポイントです。
たとえば、お茶を飲む動作。お湯を沸かし、急須にお茶の葉を入れ、適量のお湯を注ぐ。そのような1つひとつの動作を丁寧に行うのです。葉の香りと味が溶け出す頃合いを見て茶碗に静かに注ぎ、ゆったりと味わう。
「
この禅語は、心と身体が密接に結びついていることを意味しています。日常的なシンプルな行動を丁寧に行うことによって、心も身体も調和し、自然と心が落ち着いていく。すなわち、平常心に戻っていくのです。
お茶を味わっている間、心に広がるのは「おいしい」の言葉だけのはず。そのときは、目の前のお茶と一つになっている。そこに余計な考えや感情が入り込む余地はありません。もちろん、怒りは綺麗さっぱり消え去っているでしょう。
「
この禅語は、外側の動き(姿勢・動作)を整えると、内側の心も併せて整えられることを表しています。心を込めて丁寧に行動することが、威儀を正し、仏法を叶えるのです。
腹が立ったときばかりでなく、不安や悩みが心を覆ってしまって寝つけない、といったときなども、すべての行動を丁寧に、心を込めて行い、頭の中にイヤな出来事を住みつかせないようにしましょう。感情に振りまわされることなく、平常心を保つ力は、日常の中の当たり前にあるのです。
身近な行動の中に、怒りを消すヒントがある
ムダな感情に振りまわされない「本質を見極める力」
忘筌 - 「
筌 」とは竹を細く割いてつくった、魚を取る道具。目的は魚を取ることにあり、魚が取れたら筌はもはや必要ない。目的と道具をはっきり見分け、道具にとらわれるな。
「忘筌」の概念は、目的と手段を見極めることにあります。たとえば、地図は目的地にたどり着くための道具にすぎません。地図ばかりを眺めて歩みを止めてしまえば、目的地には到達できないでしょう。手段と目的を混同することなく、手段にとらわれず、目的を正しく見据えることです。
一般の生活にも、このような取り違えはあります。仕事や人間関係の中で、表面的な言葉や感情に振りまわされ、本質を見失うことはないでしょうか。物事の本質を見極めることが大切であるのに、些細な出来事に気を取られたり、言葉尻にこだわりすぎたりして、大事な目的が後回しになってしまう。そのような経験は誰にでもあるはずです。
仕事でミスをして、上司から
「ミーティングの前日になったら、先方にアポイントの確認をするのは、常識中の常識だろう! いったい何年この仕事をやってるんだ。まったく、使えないな!」
いってみれば、“罵倒派(パワハラ?)”上司というところですが、みなさんがこのように言われた部下だったら、どんな気持ちになるでしょうか?
たしかに、アポイントの確認を怠ったのは自分のミスかもしれません。しかし、その指摘の仕方に腹が立つ、悔しさが込み上げる、しばらく上司の顔も見たくない……。
そんな感情を抱くのも当然でしょう。
さて、ここで少し視点を変えて、考えてください。もし、この上司がもっと穏やかに「アポイントの確認は忘れないように」とだけ伝えたら、どう感じるでしょうか?
余計な怒りを感じることもなく、素直に「次から気をつけよう」と思えるはずです。
つまり、私たちが怒りを感じるのは、本質ではなく、その周囲の「余計な言葉」にとらわれているからなのです。上司の厳しい言葉の中にある本質は、「アポイントを確認しなかった」事実だけです。それ以外の「常識中の常識だ」「使えないな」といった言葉は、上司の個人的な感情や価値観が乗っかった「装飾」にすぎません。
もし、私たちがこうした「装飾」にとらわれず、ただ「本質」だけを受け取るようにしたらどうでしょう。ミスをした事実を冷静に受け止め、無駄な怒りやストレスを抱えなくて済むはずです。
これは、単に「怒るな」と言っているわけではありません。感情が湧き上がるのは自然なことですが、それを長く引きずるかどうかは、自分でコントロールできる部分でもあります。本質を見極め、不要な部分を手放すのです。
本質だけを見て、事実だけ受け止めていくようにしたら、さまざまなストレスも、大幅に減っていきます。この方式、採用しませんか?
本質に集中し、余計なものを手放す
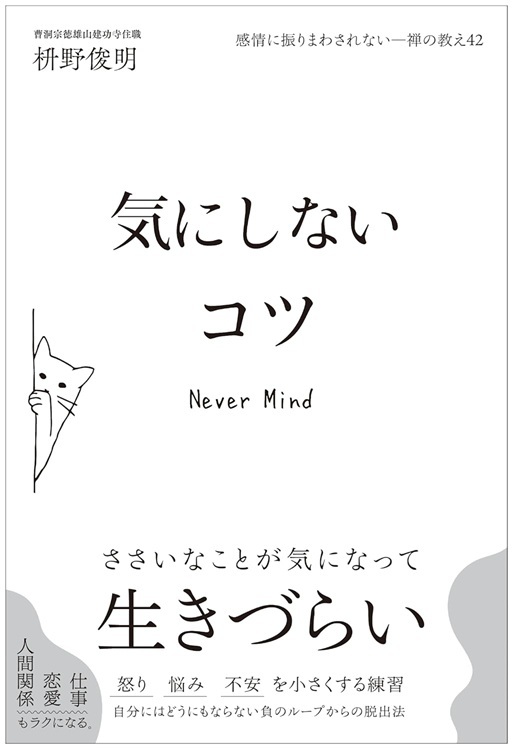
禅僧、庭園デザイナー、教育者、文筆家。曹洞宗徳雄山建功寺住職。多摩美術大学名誉教授。
大学卒業後、大本山總持寺にて修行。以降、禅の教えと日本の伝統文化を融合させた「禅の庭」の創作を続け、カナダ大使館庭園やセルリアンタワー東急ホテルの日本庭園など、国内外で数多くの作品を手がけている。
芸術選奨文部大臣賞(1998年度)を庭園デザイナーとして初受賞。カナダ総督褒章(2005年)、ドイツ連邦共和国功労勲章功労十字小綬章(2006年)なども受賞している。
2006年、『ニューズウィーク(日本版)』にて「世界が尊敬する日本人100人」に選出。主な作品はカナダ大使館庭園、セルリアンタワー東急ホテル庭園「閑坐庭」、ベルリン日本庭園「融水苑」など多数。2024年には最新作品集『禅の庭Ⅳ 枡野俊明作品集2018~2023』(毎日新聞出版)を刊行。
禅の精神と現代人の悩みをつなぐ語り口に、世代を問わず共感の声が寄せられている。教育の現場では、長年にわたり多摩美術大学で後進の指導にあたり、2023年、名誉教授の称号を受ける。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
