本記事は、枡野 俊明氏の著書『気にしないコツ』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

過去を断ち切る方法
前後際断 - 過去、現在、未来 …… と時間はつながっているが、大切なのは現在、その瞬間である。過去(前)を引きずることなく、未来(後)を
慮 ることもなく、今を生き切ればいい。
これは曹洞宗の開祖である
薪は燃え尽きて灰になる。そのため、両者はつながっているかに見えますが、薪は薪の姿で完結していて、灰は灰の姿で完結している。それぞれが絶対の姿であり、薪(前)と灰(後)の間は断たれている。同じ物質から派生したものが、別々のものとして存在しているとする考え方です。
生も死もそれぞれが独立した絶対のもので、生は生、死は死。生を「生き切り」、死を「死に切る」。命があるどの瞬間も
過ぎ去った時間や過去の出来事に縛られていては、今の自分を見失ってしまいます。
悔いが残っても、時間を戻してやり直すことはできません。いつまでも引きずっていれば、今を
信じていた人に裏切られた経験があると、その出来事が心に深く刻まれ、怒りが込み上げてくることもあるでしょう。しかし、怒りに支配され続けるとは、相手を意識し続けることでもあります。
つまり、自分が「裏切られた人間」として生きていることになるのです。
多少は尾を引くことがあっても、できる限り早急に、その感情や過去は断ち切ってしまいましょう。相手を意識の外に追い出すのです。過去に縛られた感情によって、目の前にある時間を費やすのはもったいない。変えられない過去に心を奪われ続けるのは、時間の浪費にほかなりません。
「そんな出来事もあったが、今の自分はそれにとらわれず生きている」。そうやって過去に引導を渡すことが、「今を生きる」姿勢につながります。
では、「今を生きる」とはどういうことか。それは、未来への不安や過去の後悔にとらわれず、目の前に意識を向けることです。
「喫茶去」の節でも触れましたが、どんな状況でも一度落ち着いて、今この瞬間に意識を向ける。たとえば、仕事中は仕事に没頭し、食事中は味わいながら食べ、誰かと話すときはその人の言葉にしっかり耳を傾ける。そのような丁寧な生き方が、人生の質を高めてくれるのです。
また、「今を生きる」とは、自分の感情と丁寧に向き合うことでもあります。過去の痛みを無理に忘れるのではなく、今の自分にとって必要なものだけを選び取る。そうして選び取った経験は、やがて苦しみを成長の糧へと変えてくれるのです。
1つひとつの時間を誠実に生きよう
未来は「今」の積み重ねで、できている
而今 - 絶対の命の真実は「今」にしかない。その今を大切に生きる。そのことのほかに、できることはない、やるべきことはないのである。
この禅語もそうですが、禅では繰り返し「今」が大切だと説いています。目の前の瞬間に心を注ぎ、全身で打ち込めば、おのずと心が落ち着き、安心を得られます。
しかし、実際にそれを実践するのは簡単ではありません。「言うは易く、行うは難し」です。不安が一杯で心が塞がり、仕事が手につかない、食事も喉を通らない、夜も眠れないといった経験は、誰にでもあるでしょう。
さて、その不安について、禅ではこう捉えます。禅宗の始祖・達
「私(慧可)はいまだ不安から脱することができません。お師匠さま(達磨大師)、どうか私の心を安らかにしてください」
「わかった。ならば、その不安な心とやらをここに持っておいで。そうしたら、安心させてやろう」
慧可は必死になって不安な心を探します。だけど、どうしても探しあてることができません。そこで、そのことを師に伝えます。
「いくら探しても、不安な心が見つかりません」
ここで、達磨大師は言います。
「ほら、もう、おまえの心を安心させてあげたではないか」
これは「
目の前に仕事があるなら、それに集中する。食事をするのであれば、それに心を注ぐ。それが「而今」に徹すること。仕事が手につかず、食事が喉を通らないのは、不安という幻に心を奪われているからです。
坐禅の修行でも、初めは集中できず、雑念が浮かぶものですが、続けていくことで自然と坐禅そのものに意識を向けられるようになります。日常生活でも同じです。「而今に徹しよう」と意識すると、徐々に集中力が養われ、余計な不安に振りまわされなくなるのです。
不安や悩みが生じたときこそ、「今」に立ち返る。やるべき1つのことに集中する。
その姿勢こそが、心の安心につながるのです。不安は、私たちを磨く機会ともいえるでしょう。感情に流されるのではなく、成長の糧として活かしていくことが、真の安心への道なのです。
今やるべき1つのことに意識を向かわせる
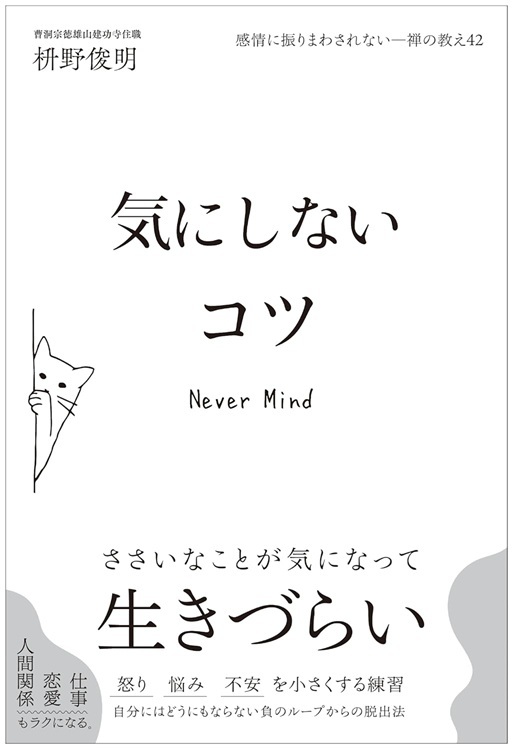
禅僧、庭園デザイナー、教育者、文筆家。曹洞宗徳雄山建功寺住職。多摩美術大学名誉教授。
大学卒業後、大本山總持寺にて修行。以降、禅の教えと日本の伝統文化を融合させた「禅の庭」の創作を続け、カナダ大使館庭園やセルリアンタワー東急ホテルの日本庭園など、国内外で数多くの作品を手がけている。
芸術選奨文部大臣賞(1998年度)を庭園デザイナーとして初受賞。カナダ総督褒章(2005年)、ドイツ連邦共和国功労勲章功労十字小綬章(2006年)なども受賞している。
2006年、『ニューズウィーク(日本版)』にて「世界が尊敬する日本人100人」に選出。主な作品はカナダ大使館庭園、セルリアンタワー東急ホテル庭園「閑坐庭」、ベルリン日本庭園「融水苑」など多数。2024年には最新作品集『禅の庭Ⅳ 枡野俊明作品集2018~2023』(毎日新聞出版)を刊行。
禅の精神と現代人の悩みをつなぐ語り口に、世代を問わず共感の声が寄せられている。教育の現場では、長年にわたり多摩美術大学で後進の指導にあたり、2023年、名誉教授の称号を受ける。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
