本記事は、枡野 俊明氏の著書『気にしないコツ』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

自分の中にある「はからい」から離れる
露堂々 - 真理を求めて
躍起 になることなどない。真理はそこらじゅうに堂々と現れている。露 わになっているのである。
禅では、真理は遠くにあるものではなく、日常の中に自然と存在すると考えます。
たとえば、道端に咲く一輪の花。人が「綺麗だ」「すごい」と感じたとしても、花は誰かに見てもらうために咲いているのではありません。
ただ、咲いているだけ。花としての本分をまっとうしているのです。「〜してもらおう」「〜させよう」といった思惑や企みは、
時が過ぎれば、やがて枯れます。枯れることもまた、花の本分です。咲くことだけが花ではなく、枯れることもしおれることも、すべて花。どんなときも、花なのです。
しかし、私たちは、「なんだ、枯れてしまったのか。つまらない」などと、勝手に評価してしまう。けれど、「綺麗」「すごい」「つまらない」の言葉は、すべて私たちの勝手なはからいにすぎません。
大切なのは、この「はからい」から離れることです。私たちは、うまくいっているときは「成功だ」と喜び、失敗すると「価値がない」と落ち込んでしまいます。ですが、花が咲くのも枯れるのも自然な流れであるように、人生にも流れがあります。
私たちも結果だけにとらわれずに、「今の自分にできることを精一杯やっているだろうか?」と自分に問いかけてみましょう。今あることに向き合えたとき、真理は決して遠くではなく、すぐそばにあるのだと感じられるはずです。
この考え方を、日常生活にあてはめてみましょう。誰かの言動に腹を立てている自分を思い浮かべてください。
「あんな言い方をされたら、怒って当たり前じゃないか!」
「絶対に人を怒らせる態度だった!」
「こんなひどいことを言われたら、誰だって傷つくに決まっている!」
このような感情を抱くことはよくあると思いますが、いずれも、自分のはからいではありませんか?
「こうあるべき」「こうでなければならない」といった自分の思い込みが根っこにあるのではないでしょうか。
「私のはからいではないか?」と自分に問いかけてみると、「そういう人もいるんだな」「相手に悪意はなかったかも」と思えるかもしれません。少しずつ、そのはからいを手放していきましょう。
もちろん、人はそう簡単に、はからいから離れることはできません。ですが、そのための努力はできます。道端の花をはじめ、あらゆる自然のものに対して「それぞれが本分をまっとうしている姿なのだ」と意識して、向き合うのです。そうした小さな積み重ねにより、むやみに感情に振りまわされない新しい自分に近づけるはずです。
決めつけを剥がし、新しい自分をつくっていく
「都合」を引っ込めると自分の可能性が広がる
無心風来吹 - 暑いさなかに吹いてくる風は涼をもたらす。しかし、風は人を涼しくしようとして吹いているのではない。無心に吹いているだけである。
花の話をしましたが、風も同じです。「涼しさを届けよう」「心地よさを与えよう」と考えて風が吹いているわけではありません。ただ吹いているだけ。その風をどう感じるかは、受け取る側の都合次第です。
小鳥のさえずりや川のせせらぎも同じです。「癒される」と感じることもあれば、「うるさい」と思うこともある。自然はただ本分をまっとうしているだけで、聞く側の“都合”によって感じ方が変わるのです。
こうした“都合”は、私たちの日常にも多く見られます。たとえば、喫煙を巡る議論。禁煙を歓迎する人もいれば、吸える場所が減ることに怒る人もいる。どちらも、自分にとっての快適さを主張している点では同じです。
年末の除夜の鐘も同様。「風情がある」と感じる人と「うるさい」と感じる人。どちらも“都合〟からの意見にすぎません。
これらはすべて、“都合のぶつかり合い”です。
私たちが抱く怒りや不満も、多くは自分の都合が通らないことが原因です。そんなとき、「この怒りは、自分の都合から生じていないか?」と自問してみましょう。
そう問いかけることで、少し冷静になり、「あぁ、今の自分は自分の都合ばかりを考えていたかもしれないな」と気づければ、凝り固まった考えや怒りはスッと軽くなるはずです。
もちろん、すべての負の感情を無理に抑える必要はありません。しかし、もし「まぁ、いいか」と思える余地があるのなら、その感情やこだわりは手放してしまったほうがラクになれます。
「こんなことで怒るの、ちょっと損してるかもな」
「まぁ、気にしすぎても仕方ないか。流しておこう」
「これくらいでイライラしても、時間がもったいないな」
このように一歩引いてみると、怒りや自分都合のこだわりは、自然としぼんでいきます。結局、自分をコントロールするカギは、「都合を引っ込められるかどうか」にかかっているのです。
心を穏やかに保つためには、周囲で起きる出来事や人の言動に過剰に反応せず、まずは自分の思い込みや期待を手放すことです。日々の暮らしの中で、ふとした瞬間に感情が湧き上がるのは自然なことですが、そんなときこそ「まぁ、いいか」と受け流す。
都合にとらわれすぎないことで、変化を受け入れる余地が生まれます。それは新たなチャンスや可能性にもつながります。自分の感情や都合を一歩引いて眺める。それが、自由で平和な心を育てる一歩となるのです。
縛られず、「まぁ、いいか」と受け流す
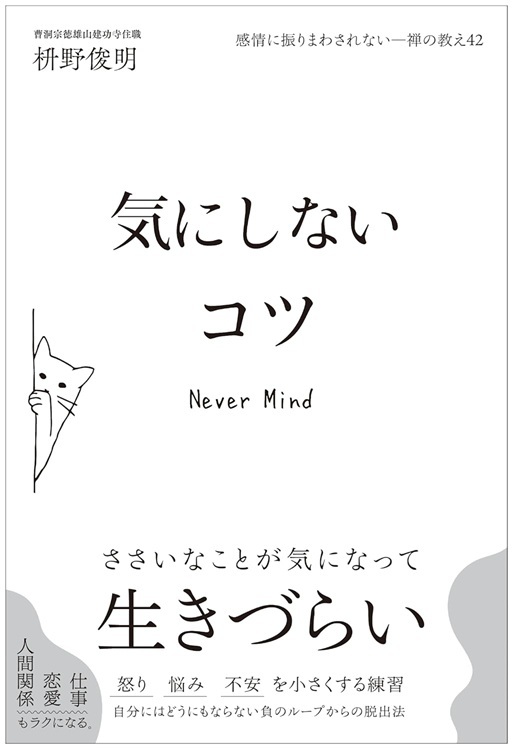
禅僧、庭園デザイナー、教育者、文筆家。曹洞宗徳雄山建功寺住職。多摩美術大学名誉教授。
大学卒業後、大本山總持寺にて修行。以降、禅の教えと日本の伝統文化を融合させた「禅の庭」の創作を続け、カナダ大使館庭園やセルリアンタワー東急ホテルの日本庭園など、国内外で数多くの作品を手がけている。
芸術選奨文部大臣賞(1998年度)を庭園デザイナーとして初受賞。カナダ総督褒章(2005年)、ドイツ連邦共和国功労勲章功労十字小綬章(2006年)なども受賞している。
2006年、『ニューズウィーク(日本版)』にて「世界が尊敬する日本人100人」に選出。主な作品はカナダ大使館庭園、セルリアンタワー東急ホテル庭園「閑坐庭」、ベルリン日本庭園「融水苑」など多数。2024年には最新作品集『禅の庭Ⅳ 枡野俊明作品集2018~2023』(毎日新聞出版)を刊行。
禅の精神と現代人の悩みをつなぐ語り口に、世代を問わず共感の声が寄せられている。教育の現場では、長年にわたり多摩美術大学で後進の指導にあたり、2023年、名誉教授の称号を受ける。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
