本記事は、伊藤 勝彦氏の著書『モメない相続でお金も心もすっきり! 親子終活』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

相続と遺言書の基本と役割を理解する
相続とは何か?
身の回りの思い出の品を整理したら、いよいよ相続について考えていきましょう。家族の絆を守り、将来のトラブルを防ぐために欠かせない工程です。
そもそも相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利義務を、法律に定められた相続人が引き継ぐことです。
被相続人から相続する代表的な資産や権利は、次のようにプラスの財産とマイナスの財産に分けられます。
- プラスの財産(=受け取る資産)
金銭、金融資産
- 預貯金(銀行・ゆうちょなど)
- 現金
- 株式・投資信託・国債などの有価証券
- 保険金(死亡保険金は受取人が指定されている場合は、受取人固有の財産となり、相続財産から除外されるのが原則)
不動産
- 自宅や別荘などの土地・建物
- 借家・賃貸マンション・収益物件
- 農地や山林
動産
- 車・バイク
- 家具・貴金属・骨董品
- 美術品・時計・ブランド品
その他の権利
- 貸付金・売掛金(人にお金を貸していた場合)
- 特許権・著作権・商標権など
- マイナスの財産(=引き継ぐ負債)
借入金・ローン
- 銀行や消費者金融からの借入金
- 住宅ローン(残っている場合)
- クレジットカードの未払い分
未払いの負債
- 税金・保険料・公共料金の未納分
- 病院や施設の入院費・介護費の未払い分
- 保証人としての債務
これらの財産を正しく把握し、どのように引き継ぐかを考えることが、相続の基本です。特にマイナスの財産も相続の対象になることを理解し、家族に過度な負担を残さないように備えることが大切です。
法定相続人の確認方法
それでは、こうした財産や権利について誰が相続人になるのでしょうか。亡くなった方(=被相続人)の財産は、原則として民法のルールに従って、一定の範囲の親族が引き継ぐこと(=法定相続人)が決まっています。
法律で定められた相続人には順位があり、次のように分類されます。
- 第1順位:配偶者と子(子がいない場合は孫)
- 第2順位:配偶者と直系尊属(親・祖父母)
- 第3順位:配偶者ときょうだい(甥・姪を含む)
配偶者は常に相続人であり、他の相続人は状況によって変わります。認知していない子どもや養子も相続権を持ちます。
そのため、法定相続人の確認では戸籍謄本を取得するのが確実です。自分が生まれてから現在までの全ての戸籍を集めると、法律上のつながりがある親族が誰なのか分かります。
養子や婚外子(非嫡出子)がいらっしゃる場合、法律上は実子と同様に相続権を持ちます。結婚、離婚、出産、死亡などの生活の変化によって相続人は変わることがあるので、必要に応じて確認し直しましょう。
ただし、家族関係が複雑な場合には、相続人同士の話し合いが難航する可能性もあります。こうした状況では、遺言書によって分割方法を指定しておくことがとても有効です。
遺言書があることの家族へのメリット
相続というと遺言書とセットでイメージされる方も多いことでしょう。なぜ遺言書が重要な役割を果たすのか、皆さんはご存じでしょうか。相続が発生すると、相続人同士で財産の分け方について決める「遺産分割協議」が必要になります。
もし協議で意見が対立すれば、話がまとまるまでに時間がかかったり、合意できなければ調停・審判に発展したりすることもあるシビアな問題です。
一方、事前に遺言書を作成しておけば、相続人同士のこうした話し合い(遺産分割協議)を不要にしたり、あるいは簡略化したりすることができます。
特に以下のようなケースで効果を発揮します。
・特定の財産に思い入れがある
「この家は長男に」「祖母の形見の指輪は長女に」など、特定の財産を特定の人に引き継いでほしい希望がある場合、遺言書でその旨を指定できます。
・複雑な家族関係
再婚家庭で前妻の子と後妻(またはその子)の間で分割協議がスムーズに進まない可能性がある場合、遺言書によって分割方法を指定しておけば、直接の話し合いを避けられます。
・相続人以外に財産を渡したい
法定相続人以外の人(内縁の妻や夫、子どもの配偶者、お世話になった人や慈善団体など)に財産を渡したい場合、遺言書がなければ実現できません。
・事業承継が必要
家業や会社を特定の相続人に引き継がせたい場合、遺言書で事業用財産や株式の承継先を指定できます。事業用財産を分散させずに集中させることで、事業の継続性を確保できます。
私はこれまで、遺言書があったことで家族の絆が保たれたケースをたくさん見てきました。
例えば、ある方は、長年営んできた事業を長男に引き継ぐ内容の遺言書を作成していました。他のきょうだいは、「父の意思だから」と受け入れ、言い争いには発展しませんでした。
別のケースでは、後妻と先妻の子どもの相続において、遺言書の存在によって複雑な話し合いを避け、円滑に相続手続きを進めることができました。
遺言書があれば、相続手続きの負担も軽減されます。金融機関や不動産の名義変更など、各種手続きがスムーズに進むからです。特に遺言執行者が指定されていれば、その人が中心となって手続きを進めることができます。
いわば、遺言書の存在は、故人の「最期の思いやり」とも言えるでしょう。生前に自分の意思をしっかりと示しておくことで、残された家族の負担を減らし、故人を
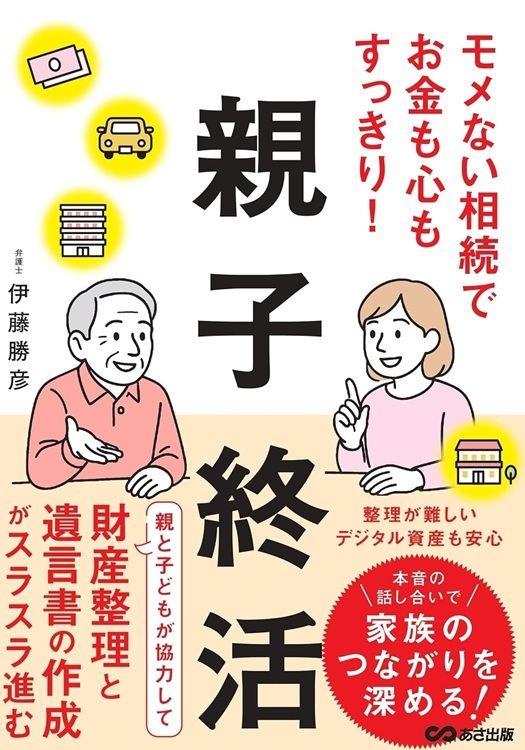
1973年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業の年に司法試験合格。
弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士など多方面のプロフェッショナルを擁する総合法律事務所の代表を務める。弁護士活動の初期から「終活」関連分野に注力。遺産分割や遺留分侵害額請求に関する調停・訴訟に多数関与し、依頼者の代理人として相続人全員が納得できる解決に導いてきた。その経験から、遺言や相続に関わる社会的関心の高い事件について、テレビ局のニュース番組で解説なども行う。
信条は日々相談者の困難や不安に寄り添い、頼れる存在であり続けること。
著書(共著)に『サービス残業という地雷』(幻冬舎)がある。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
