本記事は、伊藤 勝彦氏の著書『モメない相続でお金も心もすっきり! 親子終活』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

誰にも知られたくない秘密は専門家の力を借りる
「墓場まで持っていきたい秘密」への対応
人生には、誰にも知られたくない秘密を抱えることがあります。いわゆる「墓場まで持っていきたい秘密」です。
しかし、その秘密が相続や家族の将来に影響を与える可能性がある場合、どのように対処すべきでしょうか。
まず考えるべきは、その秘密が本当に最後まで隠し通しておくべきか、それとも誰かに伝えておくべきかという判断です。
例えば、隠し子の存在や愛人関係などは、死後に明らかになると相続に大きな影響を与える可能性があります。隠し財産や借金の存在なども、残された家族を混乱させる原因となります。
秘密を誰かに打ち明ける場合、最も安全なのは守秘義務のある専門家に相談することです。弁護士や税理士、公認会計士などは、依頼者から打ち明けられた秘密を守る法的義務があります。特に弁護士との間では、依頼者と弁護士の間の会話について証言を拒否できる権利や資料の押収を拒否できる権利が認められており、高いレベルでの秘密保持が法的に守られています。
弁護士に秘密を打ち明けるときには、その秘密をどのように扱ってほしいのかを明確にしておくことが重要です。
「自分の死後、家族にこの事実を伝えてほしい」「死後もずっと秘密にしておいてほしい」「特定の条件が満たされた場合にのみ開示してほしい」など、具体的な指示を与えておくことで、自分の意思に沿った対応がされやすくなります。
秘密の種類によっては、専門的な対応が必要なケースもあります。例えば、隠し財産がある場合は、その財産の取り扱いについて税理士や弁護士に相談します。次のような対応策とともに検討してくれるでしょう。
・正規化(財産の表面化)
隠し財産を正式に申告し、必要な税金を納付して合法的な資産として位置づける方法です。過去の申告漏れには加算税などのペナルティが発生する可能性がありますが、相続時の混乱を防ぎ、法的リスクを解消できます。
・修正申告
過去の所得税申告に漏れがある場合、修正申告を行い、適正な税額を納付します。自主的な修正申告は強制調査よりもペナルティが軽減される場合があります。
・国外財産の正規化
海外に隠し財産がある場合、国外財産調書の提出や国際的な銀行情報の「自動交換制度(CRS)」に対応した適切な申告を行います。
・遺言書での明確化
隠し財産の存在と分配方法を遺言書に明記し、相続人間のトラブルを防止します。
・生前贈与の検討
生前に財産を少しずつ贈与することで、相続時の問題を軽減できる場合もあります。ただし、贈与税の適正な申告が必要です。
家族へ内緒にしていた財産というだけならよいのですが、違法な資産隠しであったなら、発覚時には重いペナルティや家族への大きな負担につながる可能性があることを理解しましょう。
また、法律や倫理に反する行為(脱税や犯罪行為など)には、専門家も協力できません。例えば、犯罪によって得た財産を隠すような指示には、応じられません。
時として、秘密を打ち明けることで心の負担が軽くなることもあります。長年抱えてきた秘密を誰かに話すことで、精神的に楽になることもあります。
一方で、秘密を墓場まで持っていくという選択も、尊重されるべきです。すべての秘密を明かす必要はなく、自分の尊厳や家族の平和を守るために秘密にしておくことが最善と判断するなら、それも1つの選択肢だと言えるでしょう。ただし、その場合でも、秘密が後々明らかになる可能性や、それによる影響についても考えておくことが大切です。
相続開始から3カ月以内であれば相続放棄ができます。相続放棄すればはじめから相続人でなかったことになり、問題を相続人に引き継がれません。適切な時期に守秘義務を解除して遺族が困らないようにしましょう。
【コラム】
弁護士など専門家への相談方法
終活や相続に関する問題は、法律・税金・登記などさまざまな分野が絡むため、自分だけで解決しようとすると混乱しがちです。そんなとき、専門家のアドバイスは非常に心強い味方になります。
ただし、相談するには「誰に、何を相談するのか」をしっかり見極めることが大切です。
相続に関する問題では、主に弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家が関わります。その役割は以下の通りです。
-
弁護士
相続トラブルの解決、遺言書の作成、成年後見制度の活用など、法律全般の対応に強い。
税理士
相続税の申告や節税対策、確定申告など税務関連のアドバイスを行う。
司法書士
不動産の名義変更や相続登記など、登記手続きを専門に行う。
行政書士
遺言書の文案作成や行政手続きに関する書類作成のサポートを得意とする。
専門家を選ぶときのポイントは、その得意分野を把握することです。例えば、弁護士のなかでも、相続や家族法を専門としている人を選ぶとよいでしょう。
次に、信頼性の確認が大切です。知人からの紹介や専門家団体の相談窓口を利用したり、インターネットでの評判を調べたりする方法があります。また、相性も重要です。話しやすく、自分の考えや状況を理解してくれる専門家を選びましょう。
相談をスムーズに進めるために、事前の準備を念入りに行います。財産や家族関係の概要、今直面している問題、将来心配していることなどをメモしておくと、相談時にスムーズに説明できます。関連する書類(戸籍謄本、不動産登記簿謄本、預金通帳のコピーなど)も可能な限り用意しておくと、より具体的なアドバイスを受けられます。
相談するときには、正直に話しましょう。専門家には守秘義務があり、話した内容が外に漏れることはありません。隠し事をすると適切なアドバイスが受けられなくなるため、少し話しにくい内容であっても、包み隠さず話すことが大切です。
専門的な言葉や説明で分からないことがあれば、その場で確認します。複数の選択肢がある場合は、それぞれの良い点と悪い点をしっかり聞いておくことが大切です。
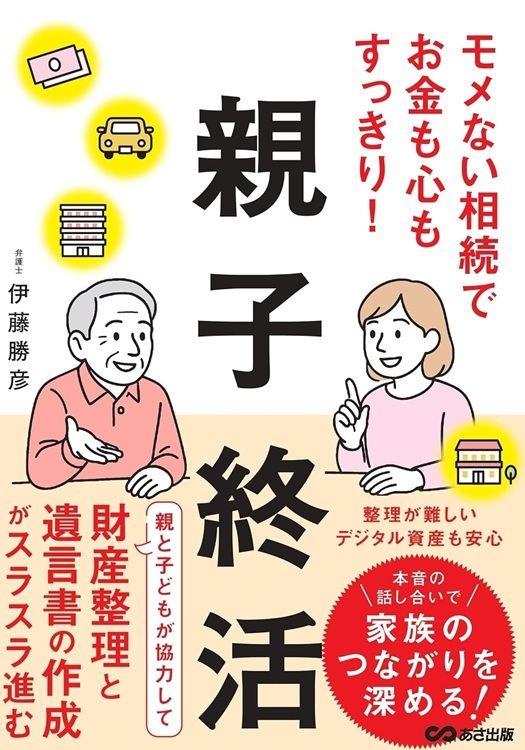
1973年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業の年に司法試験合格。
弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士など多方面のプロフェッショナルを擁する総合法律事務所の代表を務める。弁護士活動の初期から「終活」関連分野に注力。遺産分割や遺留分侵害額請求に関する調停・訴訟に多数関与し、依頼者の代理人として相続人全員が納得できる解決に導いてきた。その経験から、遺言や相続に関わる社会的関心の高い事件について、テレビ局のニュース番組で解説なども行う。
信条は日々相談者の困難や不安に寄り添い、頼れる存在であり続けること。
著書(共著)に『サービス残業という地雷』(幻冬舎)がある。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
