本記事は、吉武 麻子氏の著書『無駄をスッキリさせて、人生の質を高める 時間デトックス』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

無駄な時間を手放すことで得られるもの
手放すものは大きく3つ
不要な時間を手放すには、時間がかかります。1日ですべてを手放せるものばかりではないからです。手放すものは大きく分けて3つあります。
1つ目が、「今すぐ手放せること」です。たとえば、ていねいな掃除やメール返信など、具体的な細かいタスクは「捨てる・任せる・ゆるめる」を活用すると、すぐに手放せます。
麦茶づくりを例にとると、「麦茶づくりをやめて購入するようにした」「麦茶づくりを家族に任せた」「麦茶を『必要な時しかつくらない』とゆるめた」という人がいました。同じ麦茶づくりでも、三者三様の手放し方です。
2つ目が、「これから勇気をもって手放すこと」です。これまで、時間もお金もかけてやってきたことは、「もったいない」気持ちが先行して、手放すことに勇気がいります。この状況は、サンクコストにとらわれているといえます。
「サンクコスト」とは、もう取り戻せない時間や労力、お金などのことです。
サンクコストは、意思決定において無視すべきものですが、実際には多くの人がこれに影響され、合理的ではない判断をしてしまいます。キャリアや資格取得など長年投資してきたことが、本当に求めていることではないと気づいた時に、「今までの努力や投資が無駄になる」と、やめられないことがサンクコストの典型例です。
手放したら自分らしくいられないのではないか、特にうまくいっているものを手放したら自分の価値がなくなるのではないかなど、不安になることもあるでしょう。
これらは今すぐには手放せなくても、将来の価値に基づいて意思決定していくことが重要です。あなたの貴重な時間やエネルギーを何に投資すれば最も価値があるのかを考え、いつかは勇気をもって手放しましょう。
3つ目は、「思い込み」です。完璧主義な自分や、「べき」「ねば」という思考、人には聞けない、頼れないといった思い込みなどです。これらは具体的なタスクではないうえに、幼少期からの教えや環境で形成された思考であるため、手放すも何も、そもそも自分がその思考に気づいていない場合もあります。
時間の使い方には、その人の価値観が反映されます。「時間がない」「やりたくない」などと感じる時は、その状況が起きている背景を探ってみてください。そうすると、自分が気づいていない思考グセが見えてきます。
手放すことで得られるもの
手放すことで、時間、精神的余裕、成果を得られます。
1日24時間は変わりませんが、やることを手放せたら、やりたいことをやる「時間」を新たに生み出すことができます。
自分の心地よさを軸に無駄な時間を手放していけば、心地よくないことが減っていき、心理的負担もなくなっていきます。「精神的余裕」も生まれます。
また、精神的余裕が生まれると、同じ1時間でも、「成果」に大きな差が出ます。
時間的にも精神的にも追われて疲弊した状態や、疲弊を超えて無気力な状態で行うパフォーマンスと、心も体も安定した状態で行うパフォーマンスでは、成果に雲泥の差が出ることは容易に想像できます。
時短、効率化や習慣化などに取り組む前に、まずは日々の心地よくないことを手放すことに意識を向けてください。心地よく時間を使うことの大切さを、じわりじわりと感じていただけるはずです。
時間デトックスは、自分を追い込むのではなく、自分の心身の状態を安定させてくれます。その結果、やりたいことに打ち込むことができるのです。
手放すことはわがまま? 気持ちよく手放すには
手放すことに対して「自分の嫌なことを誰かに押しつけているようで気が引ける」「やりたくないから捨てるみたいで嫌だ」と、罪悪感を抱く人もいるかもしれません。実際に、手放すことが苦手な人は多いです。
手放すためには、まずは「気づく」ことからスタートしましょう。そして、「心地よくない」気持ちがあると認め、それを手放していきます。
「心地よくない」気持ちを無視しない
人は「心地よくない」「やりたくはない」と気づいても、そのことを保留しようとします。
「今だけ乗り越えれば、何とかなるはず」「私がガマンすればいい」「モヤモヤするのは気のせいかも」「手放すにも、エネルギーも時間も必要」「お世話になっている人の頼みだから」など、理由はいくらでも出てきます。そのため、気づいた後の行動が、無駄な時間を手放せるかどうかの分かれ道となります。
「気づく」ことができたなら、気づいた自分の気持ちを無視しないことが大切です。
そして、何に対して「心地よくない」と感じたのか、細かく分解してみてください。
極端な例ですが、「家事全般すべてが嫌だ」と気づいたとします。そこでいきなり「家事は嫌だと気づいたから、今日から全部私はやりません!」と宣言するのは、単なるわがままです。また、たとえそのように宣言したとしても、家族が「いいよ。全部、僕(私)がやるよ!」と言うと考えるのは、あまりにも非現実的です。
かといって、「どうせ自分がやるしかない」「言っても無駄」「私がやったほうが早い」と最初から諦めて、自分の気持ちを飲み込むこともやめましょう。いつまでも時間に追われ、心地よい時間の追求どころか、イライラがつのるのは目に見えています。
一方的な気持ちをそのまま伝えたらわがままになりますが、気持ちを飲み込むことも実は、自分の人生に対する責任放棄です。
すべての家事が嫌だと気づいたら、その気持ちをまずは一緒に暮らす人に伝えたうえで、交渉・解決策を提示していくのが「手放し」です。
手放さない危険もある
また、手放さずに抱え込んでおくことが、結果的に周りの皆を不幸にする可能性もあります。自分以外の人の成長と活躍の機会を奪うことになるからです。
たとえば、家庭において子どもに家族の一員として家事などを任せていくことは、子どもの自立にもつながります。
仕事においては、部下の育成の重要性を認識しつつも、「自分がやったほうが早いし、クオリティを保てる」「まだ任せられる人材がいない」など、任せられずに時間に追われているリーダー層も少なくありません。これは長い目で見ると、生産性向上につながらないため、リーダーの役割を果たしていないともいえます。
特定の人が担当していることが、当人以外にはわからなくなってしまう「属人化」の状態になる危険性もあります。
意図をもって手放していくことは、決してわがままではありません。
手放すコツ― グラデーションで手放す
無駄な時間を手放すことがうまくいかない人は、手放すか手放さないかの「0か100か」で考えているケースが多いです。「やるか、やらないか」の究極な選択にするから、いざ手放そうとすると勇気が必要で、うまく手放せなくなります。
しかも、多くの人が、「仕事」「家事」「ダラダラする時間」など、無駄な時間を大きな塊のまま考えています。無駄な時間を手放す時のポイントは、タスクをできるだけ細かく、具体的に書き出し、グラデーションで考えていくことです。手放せることから手放して、その領域を広げていけばいいだけです。
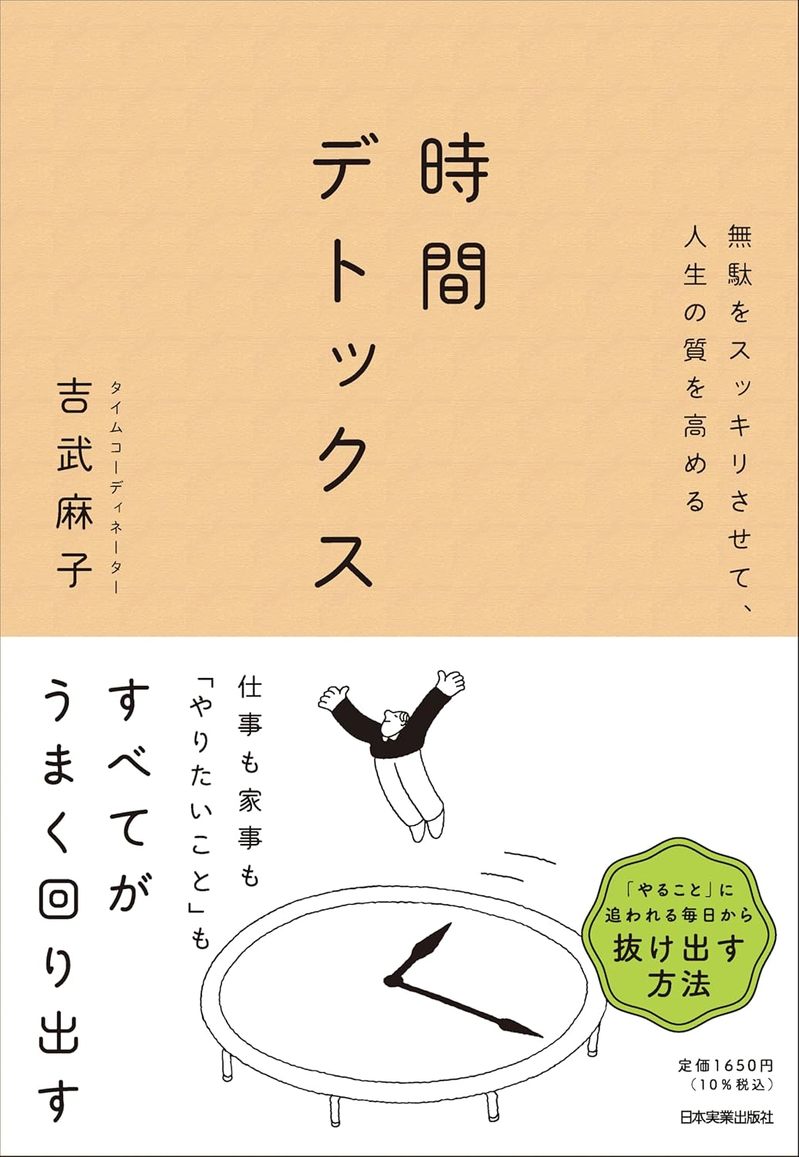
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
