本記事は、吉武 麻子氏の著書『無駄をスッキリさせて、人生の質を高める 時間デトックス』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

「得意な人」に任せる
仕事においても、家庭においても、人に「任せる」時に、自分が楽になることだけを考えると、結果的にうまくいきません。任せる人、任せられる人、どちらにとってもプラスになるような任せ方が重要になります。
任せる人(あなた)にとってのプラスとは、時間の創出、負担削減、新たな仕事やチャレンジに着手できることなどです。
任せられる人にとってのプラスとは、収入のアップや経験値の向上、能力開発や主体性が育まれることなど、成長できることです。
そして任せる人、任せられる人を含めた組織・家族というチームでは、組織力や生産性が上がり、脱「属人化」も進み、コミュニケーションが活性化します。
任せる際に大事な視点が、「任せる人」「任せられる人」「チーム」三者にとって三方よしになれるかどうかです。仕事においては、この三者に加え、「顧客」も含んだ四者にとって四方よしになるかどうか。この成果がもたらされるかどうかの視点で、任せることを検討していきます。
「任せ上手」は相手想い
任せることは、「任せる人」がその必要性を感じた時に発生します。たとえば、やることが山積みで、猫の手も借りたいくらい時間がない時、苦手なことを手放して心理的な負担を減らし、得意なことで生産性を上げたい時、自分がやるべきことや新しいチャレンジに集中するため、今まで担当していたことを引き継ぎたい時などがあげられます。
このように、「任せる」の起点は利己的であることがほとんどです。そして、多くの人がこのことに罪悪感を覚えるために、「任せる」がうまく進まないのです。
しかし、ここに罪悪感を覚える必要はありません。任せることが上手な人は、起点は利己的であっても、相手にとってのメリットも同時に考えています。つまり、利他的な任せ方ができないかと、意図的に転換しているのです。
任せることがうまい人は、自分の時間を生み出したいために、誰でもいいから任せるのではなく、任せる「相手」や「タイミング」を見計らっています。メンバーや家族が興味を持つこと、得意なこと、意欲を持っていることを、日頃から観察していないと、任せる相手やタイミングは判断できません。
複合的な視点で観察し、「この人だ」「今のタイミングだ」と見極め、任せたら、あとは信じて見守ります。自分の判断で「任せる」を決めているからこそ、中途半端な任せ方はしません。口を挟んだり、聞かれる前にあれこれアドバイスをしたりしないのです。山本渉氏の『任せるコツ』(すばる舎)にも、「『中途半端な丸投げ』はやる気を削ぐ、一番やってはいけないこと」と書かれています。
ただし、取り返しのつかないミスにつながらないよう、陰でしっかり見守っています。だから「任せられる人」も安心して取り組むことができるのです。
任せっぱなしは無責任
ここに正しい任せ方のポイントがもう一つあります。それは、任せた後すぐに、自分にタスクを詰め込まないことです。任せた後は、見守る時間が必要になるからです。
「任せて時間ができた!」と解放された気分になり、新たな仕事や溜まっていたタスクをスケジュールに詰め込んだせいで、任せたことをフォローできなかったら、それは無責任な任せ方です。
任せる前は、観察やヒアリングをする時間の余裕が必要となり、任せた後も、見守る時間の余裕が必要となります。任せる時は、いきなり実現するわけではないことを前提として、取り組んでいきましょう。
「同僚・部下・上司」に任せる
仕事において、任せることは、リーダー層の重要な役割・業務です。「任せる」がうまくいかないと、いつまで経っても属人化から抜け出せず、組織力が向上しません。
それゆえ、生産性も上げることができず、組織にとっては現状維持どころか、衰退の一途となるでしょう。
「任せ上手」の上司がしていること
では、どのように同僚や部下に任せていけばいいのでしょうか?
リーダーに必要なのは「虫の目」と「鳥の目」です。「部内・チーム内」と「組織全体」、「今(短期的視点)」と「未来(長期的視点)」、「一人ひとりの能力」と「チームとしての能力」など、虫の目と鳥の目を行ったり来たりしながら、複合的に任せることを判断していきます。
まずは、部署・チーム一人ひとりの「やりたいこと」と「強み」を明確にしていきます。具体的な「やりたいこと」を本人が自覚していなくても、興味・関心のあることや、これまでやる気を出していた業務など、本人にヒアリングしながら、上司から見た「やりたいこと」を書き並べていきます。
同じように、一人ひとりの強みも書き出していきます。「本人が自覚している得意なこと」よりは、「本人は気づいていなくても、知らぬ間にさらっとできていること」や「他のメンバーがその人に対して感謝していること」などを集めていくといいでしょう。
ただし、任せる相手を検討する際、相手の「やりたいこと」と「強み」、どちらか一方だけで判断するのは選択肢として危険です。その人の適性ではないことを任せてしまう可能性もあります。組織での任せ方は、組織力・生産性向上につながるかどうかの判断が必要です。
また、相手の「得意(強みがある)」なことを任せれば、組織力や生産性向上に直結する可能性は高いです。しかし、長期的視点で見ると、任せる相手に意欲がない(「やりたいこと」ではない状態)と、心をすり減らせてしまいます。任せる相手自身が「自分ががんばればいい」とがんばるようでは、心身を壊してしまったり、組織を抜けたりすることも起こり得ます。そうなると、結果的に組織力が落ちかねません。「得意だから」という理由だけで、その人に頼るのは注意が必要です。
そして、組織全体を見ながら部署を超えて、他部署に任せることはできないか、または、共同で取り組んでいけないか、「鳥の目」で働きかけることもリーダーの役割です。他部署で引き取ってもらったほうが効率のいい業務も、中にはあります。
ここでも三方よしの視点です。部署内の負担が減り、他部署にとっての成長機会につながり、組織全体の生産性向上につながるかどうか。逆に、他部署よりも自分の部署が引き取ったほうが効率の上がる業務があれば引き取りましょう。
上司は部下の育成、チームや部署の組織力向上、生産性向上の責任者です。プレイヤーのままでは、いくら時間があっても足りません。
同僚や部下に任せることで、上司は時間を創出できます。そして、本来やるべき業務に時間を使うことができます。その結果、個人やチームの生産性が最大化し、持続可能なワークライフバランスまでもが実現可能になってくるのです。
「任せる」は上司ではなくても活用できるスキル
また、「任せる」は上司やリーダー層だけが身につけるべきスキルではありません。
他の社員に仕事をお願いする場面や、部下が上司に相談する場面でも活用できます。
たとえば、非効率的な業務について上司に相談するとします。この時に大事なことは、不満ベースで話をしないことです。不満や不便さだけを訴えても「そうなんだ」と共感されて終わります。しまいには「何とかがんばってよ」と言われかねません。
組織の中で何かを変えようとする場合、上司の承認が必要な組織も多いです。この場合、「上司に相談する」と考えるのではなく「解決を上司に任せる」ととらえましょう。つまり、上司に動いてもらうためにはどうすればいいかを提案します。不満ベースではなく、提案ベースで話をするのです。
現状の悩み、現状が続くデメリット、解決するメリット、そして解決するためのステップを提案する。さらに、上司が動くことで得られる上司のメリットもプラスすると、上司は解決のために動いてくれる可能性が高まります。
上司であれ、部下であれ、どの立場であっても、任せることによって、それぞれの時間の価値は上がり、その結果、生産性も上がります。反対に、生産性を上げるためにも、正しい任せ方をして時間を生み出していきましょう。
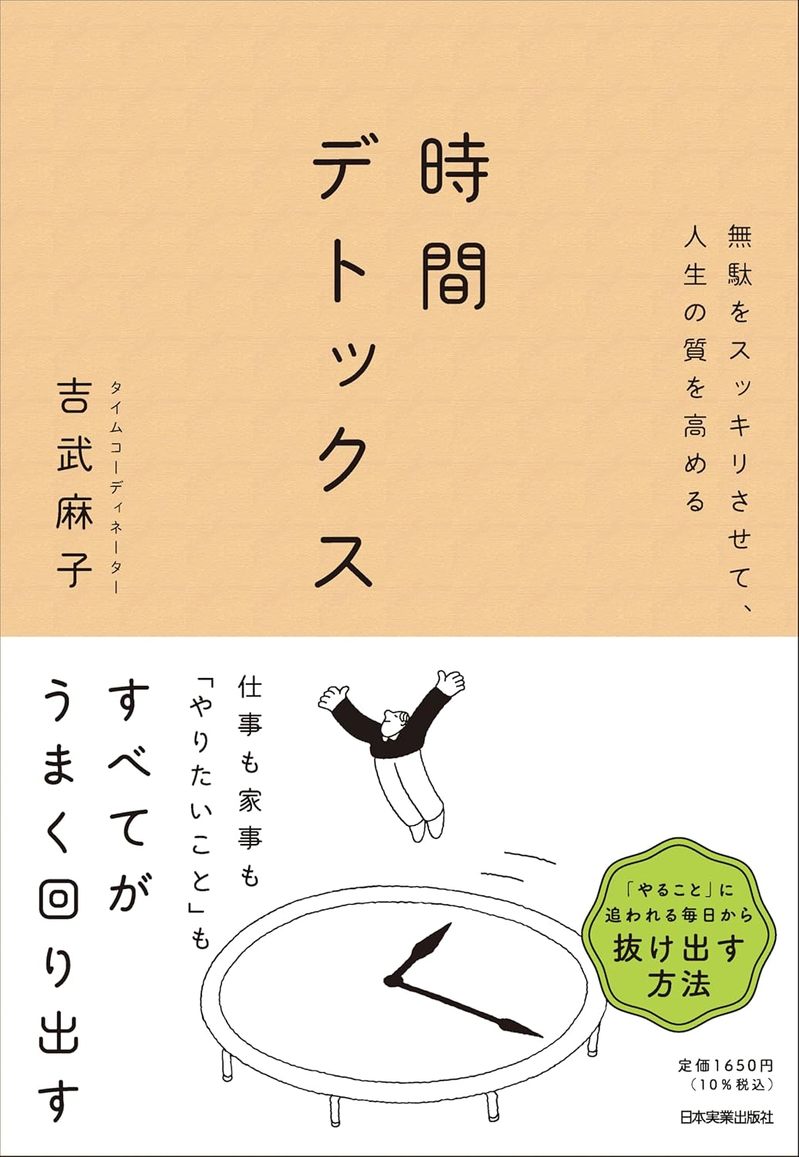
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
