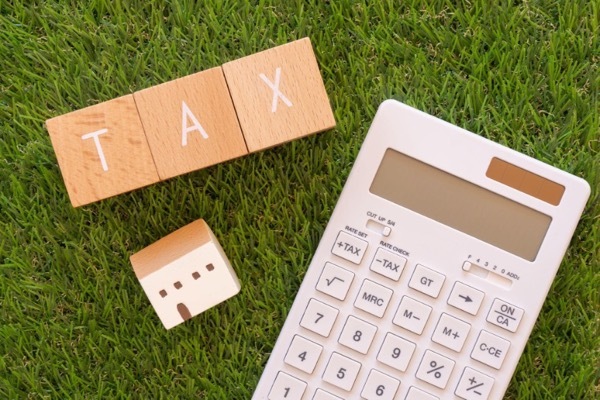
「親からまとまった資金援助を受けた」「祖父母が孫の自分のために教育資金をくれた」など、個人から財産をもらう機会は意外と身近にあるものです。
このような個人間の財産のやり取りは「贈与」と呼ばれ、受け取った金額によっては「贈与税」という税金がかかる可能性があります。
贈与税の計算は少し複雑に感じるかもしれませんが、ポイントは「誰から、誰へ」財産が渡されたかという点です。実は、この関係性によって適用される税率が変わり、最終的な納税額に大きく影響します。
この記事では、贈与税の基本的な仕組みから、2種類の税率の違い、具体的な計算方法までを、初めての方でも理解できるよう丁寧に解説します。最後まで読めば、ご自身のケースで贈与税がいくらかかるのか、ご自身で計算できるようになるはずです。
- 贈与は個人間で財産をもらうこと、金額次第で贈与税がかかる。
- 年間110万円までは非課税(基礎控除)。
- 税率は「直系尊属からの贈与は特例税率」「それ以外は一般税率」。
- 高額贈与は申告と納付が必要。
目次
贈与税の計算方法|カギは「基礎控除110万円」
贈与税の計算は、以下の計算式が基本となります。
(1年間にもらった財産の合計額 - 基礎控除額110万円)× 税率 - 控除額 = 贈与税額
この計算式で最も重要なのが「基礎控除額110万円」です。これは、贈与税の課税方法である「暦年課税」において、財産をもらった一人ひとりに対して認められている非課税枠です。つまり、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。
一つ注意点として、この110万円は「もらった人」基準で計算します。例えば、同じ年に父から100万円、母から100万円をもらった場合、合計で200万円の贈与を受けたと見なされ、110万円を超えた部分の90万円が課税対象となります。
【重要】贈与税の税率は2種類!「特例税率」と「一般税率」
基礎控除額を超えた部分にかかる税率は、実は一律ではありません。「誰から贈与を受けたか」によって「特例税率」と「一般税率」という2つの異なる税率が適用されます。この違いが納税額に大きく関わるため、しっかりと理解しておきましょう。
特例税率とは?
「特例税率」は、特定の親族間の贈与に適用される、税負担が少し軽くなる税率です。
・適用されるケース
直系尊属(父母や祖父母など)から、その年の1月1日時点で18歳以上の子や孫などへの贈与
・目的
親世代や祖父母世代が持つ資産を、より若い世代へ早期に移転しやすくすることを目的としています。
一般税率とは?
「一般税率」は、特例税率が適用されない、それ以外のすべての贈与に適用されます。
・適用されるケース(具体例)
兄弟姉妹からの贈与
夫婦間の贈与
親から未成年の子(18歳未満)への贈与
親族ではない他人からの贈与
贈与税の速算表(税率表)
それでは、実際の計算で使用する2種類の税率表(速算表)を見てみましょう。自分のケースがどちらに当てはまるかを確認し、基礎控除(110万円)を差し引いた後の金額を当てはめて計算します。
【特例贈与財産用】の税率(特例税率)
(直系尊属から18歳以上の子・孫などへの贈与)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
【一般贈与財産用】の税率(一般税率)
(特例贈与以外の場合)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【計算シミュレーション】ケース別で見る贈与税の計算例
速算表を使って、具体的なケースで贈与税額を計算してみましょう。
ケース1:父から20歳の大学⽣の子へ500万円を贈与した場合
このケースは「直系尊属から18歳以上の子への贈与」なので、特例税率が適用されます。
・課税価格を計算する
→500万円(贈与額) - 110万円(基礎控除) = 390万円
・速算表で税率と控除額を確認する
→課税価格390万円は、特例税率の表の「400万円以下」の区分に該当します。 よって、税率は15%、控除額は10万円
・贈与税額を計算する
→390万円(課税価格) × 15%(税率) - 10万円(控除額) = 48万5,000円
贈与税額は、48万5,000円となります。
ケース2:兄から弟へ開業資金として500万円を贈与した場合
兄弟間の贈与なので、一般税率が適用されます。贈与額はケース1と同じですが、税額がどう変わるか見てみましょう。
・課税価格を計算する
→500万円(贈与額) - 110万円(基礎控除) = 390万円
・速算表で税率と控除額を確認する
→課税価格390万円は、一般税率の表の「400万円以下」の区分に該当します。 よって、税率は20%、控除額は25万円
・贈与税額を計算する
→390万円(課税価格) × 20%(税率) - 25万円(控除額) = 53万円
贈与税額は、53万円となります。
このように、同じ500万円の贈与でも、誰からの贈与かによって納税額に4万5,000円の差が出ることがわかります。
贈与税の申告と納付を忘れずに
1年間にもらった財産の合計額が110万円を超え、贈与税が発生する場合には、必ず申告と納付の手続きが必要です。
・申告・納付の期間:財産をもらった年の翌年2月1日~3月15日
・申告する人:財産をもらった人(受贈者)
・申告先:受贈者の住所地を管轄する税務署
期限内に手続きをしないと、ペナルティとして延滞税などが課される場合があるので注意しましょう。
まとめ
贈与は、家族や大切な人をサポートするための素晴らしい行為です。しかし、高額になると税金の問題が関わってきます。もし贈与額が大きい場合や、ご自身のケースでの判断に迷うことがあれば、専門家に相談することをおすすめします。
(提供:ACNコラム)