本記事は、宇根 尚秀氏の著書『最後に勝つ投資術』(ダイヤモンド社)の中から一部を抜粋・編集しています。

株と債券はどう違うのか?
オルカンの先を見にいくという主題を進める前に、まずは金融商品の基本である株と債券の本質的な違いについて説明したいと思います。これは、私が東大生などに向けた金融教育の授業をするときに、いつも話していることです。
昨今の起業ブームの波に乗って、私が「宇根自動車」という自動車メーカーを起業するとします。
事業を開始するには、自動車の設計について研究して商品を開発しなくてはなりませんし、資材を調達する必要もあります。さらには人材を採用したり、製造のための機械・設備を買ったりするためにお金がかかります。
かなり大がかりな資金が必要ですから、自己資金ではまったく足りません。でも、どこからか資金を調達することができれば、事業を始められます。
そこで私は、まず銀行に融資の相談をすることにしました。銀行からお金を借りられれば、資金不足を解決できそうです。
ところが、私が相談をした銀行員は、私の相談を聞くや否や眉間にしわを寄せました。そして、「宇根さんのやる気はわかりますが、自動車製造の実績がないですよね」「お金を貸しても、期日までに返してもらえるかわからないですし、担保がないならお金は貸せません」と、けんもほろろに断られてしまいました。
たしかに自動車製造に対する私の挑戦がうまくいくかは、まったくの未知数ですから、銀行としてはお金を貸すのはリスクが高すぎると判断したのでしょう。残念ですが、現実を受け入れるほかありません。
それでも、どうしても起業を諦められない私は、他の方法を探ることにしました。
お金を借りずに事業を始めるのはどうでしょうか? まずは少人数でコストをかけずに事業を始め、黒字経営で資金を少しずつ貯めていく方法であれば、「銀行にお金を返さなければいけない」と精神的プレッシャーを抱えることもありません。
でも、この選択にも問題があります。自己資金でできる事業にはどうしても限界があるので、成長が遅くなってしまいます。ましてや自動車製造はお金がかかるので、それなりの形にするだけで何十年もかかってしまうかもしれません。
人生は長いようで短い。そしてビジネスの展開は速いです。そんなにのんびりしていたら、いつまでたっても自動車メーカーとして世界に打って出られないでしょう。
やはり、自分が思い描いた事業プランを実現するには、どこかからお金を調達しなくてはならないようです。また振り出しに戻ってしまいました。
銀行は、「必ず返せる見込みがない」といってお金を貸してくれませんでしたし、借りる立場の私としても、返済を求められるのは不安です。
私は、「できれば、たくさんのお金を出してくれて、返済を求めてこない人がいたらいいのに……」と考えますが、そんな都合のいい話があるのでしょうか?
それがあるのです。ここで登場するのが「株式」です。
銀行ではお金を借りられないとしても、ここで起業を諦めるのは早すぎます。なぜなら、起業家のビジネスプランがしっかりしたものであれば、株式を発行することで資金を得られるからです。
株式は会社の「所有権証書」であり、株式を買うことで、会社が利益を生めるようになったら、その利益のなかから「配当金」を受け取れる可能性が出てきます。
ただし、すでに実績のある会社の株式とは違い、起業した時点のスタートアップは失敗するリスクのほうが高いです。もし会社がつぶれたり、利益を上げられなかったりすれば、株主が出資したお金は“丸損”になってしまいます。
それでもスタートアップが出資を受けられるのは、その事業プランの可能性に期待があるからです。
「時間を買う」という意味で、起業した時点から人材・設備に投資をしてほしい。株式を発行して出資を受け入れ、事業成長を加速させることができれば、やがて利益を生み、出資してくれた株主に配当金としてリターンを返せる。
だから私の会社に出資していただきたい―。
このように起業家は、自分の事業プランを示し、株式による資金調達に取り組むことで、資金不足の問題を解決できるのです。
もしも起業家の事業プランに賛同してくれる出資者が現れたら、会社は出資の対価として株式を発行するわけですが、起業家にとって、これから心血を注いで大きくしようとする会社の所有権を引きわたすのは重大なことです。
たとえ一部であっても、会社の所有権を譲るのは、自分の血を分けるような行為ともいえます。
こうした関係にあるため、スタートアップの起業家と投資家は、会社が大きくなる夢を共有する運命共同体です。ビジネスが成功して利益を出せるようになった暁には、起業家と投資家はともに大きな経済的便益を享受することになりますが、逆に失敗すればともに損害を受けることになります。
株と債券は企業などが資金調達をするための手段ですが、「株は所有権を、債券は借り入れを、それぞれ金融商品化したもの」であることに、本質的な違いがあると理解しておきましょう。
ひと口に債券といっても、さまざまな種類がありますが、企業は投資家から資金を集めるために「社債(会社が発行する借金の証書)」を発行します。企業は投資家に利息を支払い、満期になると元本を返済します。
銀行融資よりも低金利で多額の資金を調達しやすいのがメリットですが、信用力が低い企業は発行が難しい面があります。
投資家の立場から見ると、株は金融商品として投資した金額が返ってこないリスクが相応に高く、その分、大きなリターンを期待できます。その一方、債券(社債)は投資した金額が返ってくる可能性が相応に高く、その分、期待できるリターンは限られます。
これで、株と債券の本質的な違いを理解できたでしょう。さて、準備が整いました。
「オルカン50%+日本円(現金)50%」が基本形
手間いらずのオルカン投資が、個人投資家の王道といいましたが、ここで“オルカンの先”を見ていくことにしましょう。
これまでに伝えたようにオルカン投資というのは株式投資なので、すべての資金をつぎ込むのはリスクをともないます。他の資産クラスを交ぜてアセットアロケーション(資産配分)をする必要があります。
オルカンをベースとするおすすめの資産配分は、金融資産を「オルカン50%+日本円(現金)50%」で持つという基本形です。これが、もっともシンプルかつ合理的な方法になります。
お伝えしてきた通り、あなたが世界経済の成長を信じるのであれば、その成長の恩恵を受けられるオルカンをこのように活用するだけで十分です。後の追加的な勉強は必要なく、これだけでよいのです。
ところが、他の投資に挑戦したくなる、つまりオルカンの先を見ようと思った途端、知っておくべきことは増えていきます。
お手本であるGPIFの日本・外国の株式、債券に4等分(25%)ずつ分散投資する「4資産均等型」の投資法(48ページ参照)に倣って、より厳密に運用したいのであれば、丸ごと「4資産均等型の投資信託を買う」とか「オルカン、MMF(マネー・マーケット・ファンド)、外債(外国債券)投資などを組み合わせて、疑似的にGPIFポートフォリオを自分で組み立てて買う」といったこともできます。
この場合、オルカン以外の新たな投資信託やETFを取り入れれば、比較的簡単に実現できます。
さらにリスクをとれるのであれば、株式の配分をお手本の50%ではなく、例えば80%にしてもいいかもしれません。
このようなアレンジを加えるとき、次の2つの質問を自分に投げかけてみましょう。
| 自分への問いかけ① リスクの把握 年間でどれくらい収益(アップケース)や損失(ダウンケース)があり得るのか? |
|---|
| 自分への問いかけ② ストレステスト 株価暴落が起きた場合、自分はどれくらい損失を抱える可能性があるのか? |
|---|
ひと言で投資といっても、オルカンのような「グローバル分散・パッシブ投資」だけでなく、市場平均超えを目指すアクティブファンド投資、個別株投資、オルタナティブ(代替金融商品)投資、事業投資などさまざまあります。
これらは扱う難易度も必要な知識も労力もさまざまで、手を出すならば勉強すべきことは多いです。ある意味で大変なのですが、社会人として、経営者として、消費者として投資から学べることは少なくありません。
そこでこのPARTでは投資の目的を整理し、それに適した投資法の選択肢を整理しつつ、その背景にある思考法にも触れていきます。
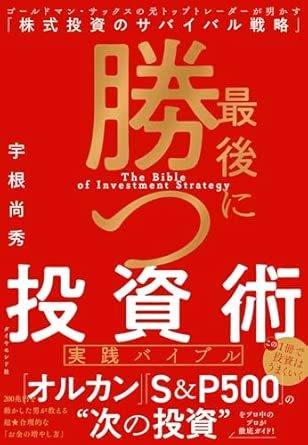
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
- 金融のプロが教える! 素人でも勝てるグローバル分散投資の王道
- 儲かる投資法を見定める2つの視点とは
- オルカンだけでは不十分? 富裕層が実践する資産配分の基本
- 株式比率は「100−年齢」で決める:長期で勝つ資産配分の黄金律
