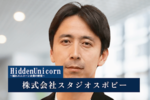BizteXは2015年の創業以来、クラウドRPA「BizteX cobit」やiPaaS「BizteX Connect」で企業の業務自動化を推進してきた。労働人口減少やDX格差といった社会課題に対し、生成AIやRPA、iPaaSの技術と自社のノウハウを組み合わせた「インテリジェント フロー」や新たなAIエージェントを開発。高いITリテラシーを持たない企業にも寄り添い、伴走型の支援で「AI Automation Company」への進化を目指し、全企業が自動化の恩恵を受けられる社会の実現に貢献する。
目次
BizteXの歩み──クラウドRPAからiPaaSへ
── RPA(Robotic Process Automation、ロボティック・プロセス・オートメーション)のシステムが主力製品とうかがいました。
嶋田氏(以下、敬称略) 当社は2015年に創業し、今年で10年目を迎えます。創業当初は2017年にリリースしたクラウドRPA「BizteX cobit」が主力プロダクトでした。これは、人がパソコンで行うさまざまなシステムへの入力や出力作業を自動化するサービスです。
RPAは2018年頃からブームとなり、「働き方改革」や「労働人口不足」といった課題に対し、デジタルロボットが人の代わりに働く領域として注目されました。
当社のクラウドRPAは、複数のロボットが同時に50個、100個、あるいは1000個と稼働できる特徴を持ち、国内では初となる形で提供を開始しました。お客様は広告代理店や大手企業、人材紹介会社が多く、定型業務の自動化に活用いただいています。
次に、iPaaS(Integration Platform as a Service)という事業領域があります。「BizteX Connect」というプロダクトで、さまざまなSaaSが持つAPI(データの入り口・出口)を事前に設定・連携しておくことで、SaaS間の連携をノーコードで実現できます。
たとえば、Zoomでのオンラインミーティング終了後、録画データを自動的にGoogleドライブに保存し、保存完了をSlackに通知するといった連携ができます。Zoom、Googleドライブ、Slackといった複数のSaaSを横断してデータ連携ができるのが特徴です。
活用事例として多いのは、顧客データベースとして利用されているkintoneとの連携が挙げられます。商談情報をスプレッドシートに毎日出力したり、HubSpotに入力された顧客データをkintoneに登録したりするケースがあります。
また、Google WorkspaceやMicrosoft Teamsといったグループウェアとの連携も多く、kintoneに商談情報が入力されると、Googleカレンダーに自動登録されるといった使い方もされています。
AIシフトと創業者の思い:DX格差を乗り越える伴走型支援
── この分野ではAIの台頭は見逃せない波なのではないでしょうか。
嶋田 当社も生成AIへのシフトを進めています。既存のRPAやiPaaSの価値をさらに高めるため、生成AIを組み合わせた「インテリジェント フロー」を今年5月にリリースしました。
RPAやiPaaSは定型業務の自動化を得意とする一方、AIは自然言語での判断や非定型業務への対応も可能です。お客様の業務は定型と非定型が混在していることが多いため、RPA、iPaaS、AI、そして人の力を組み合わせることで、業務ワークフロー全体の自動化と価値の最大化を目指しています。
さらに、バックオフィス向けのAIエージェントも開発中です。ベータ版を経て、10月に正式リリースさせていただきました。当社は「AI Automation Company」となるべく、既存事業のAI化と新たなAI事業の創出に注力しています。
── 専門性の高い分野だと思いますが、会社を立ち上げられたきっかけは?
嶋田 私の課題感は、ITやインターネットを使って人・モノ・情報をより循環させ、人々が本当にやりたいことに時間を使える世界を創りたいというものです。
これは、私が香川県の田舎で生まれ育ち、小さい頃に「やりたいことができない」と感じることが多かった経験に由来します。社会人になり東京に出てきて、人・モノ・情報が溢れている状況を目の当たりにしました。
当時勤めていたソフトバンクでは、ITやインターネットを活用して制限のない働き方を提供することに従事しており、私自身の過去の課題感から、このような世界を自分で創ってみたいという思いで40歳のときに起業しました。
DXからAXへ:進化する自動化サービスと未来戦略
── 事業を拡大できた理由をどう分析されますか?また大きな転機となった出来事はありますか?
嶋田 一つは、初期のクラウドRPAプロダクトが、広告代理店や人材紹介会社といったマーケットに非常にフィットしたことです。
当社のプロダクトの特徴は、複数のロボットが同時に立ち上がり、大量の業務を代替できること。お客様は人手(ひとで)を使って同じ作業を大量に同時刻に行わなければいけない課題を抱えていること。この課題感とプロダクトの価値が合致したことが大きな要因です。私自身が初期のお客様ヒアリングや営業活動を通じて、この業界の課題に出会えたことが大きかったと思います。
もう一つは、DX(デジタルトランスフォーメーション)の格差に気づいたことです。2000年頃からDXという言葉が認知され始めましたが、RPAのようなITは専門性が高く、難しく感じられることがあります。日本企業の約8割を占める製造業などでは、歴史が長く中小企業も多いため、ITリテラシーが高い人材が少ないのが実情です。
一方で、SaaSやIT企業は増加し、ITリテラシーの高い大企業やアーリーアダプターの企業はDXを先行して進めていきました。この結果、DXの格差が広がっていると感じました。
当社の強みは、営業やカスタマーサクセスがお客様に「伴走」し、使えるようになるまで徹底的にサポートする点にあります。事例として、長野県で150名の従業員を抱える製造業の株式会社カクイチ様があります。
平均年齢48歳で、農家向けの倉庫や農業用ホースなどを製造されています。同社はDX推進に意欲的でしたが、他社のRPAではサポート不足でうまく活用できていませんでした。
そこで当社のサービスを導入いただき、ノーコードで使いやすい点と手厚いサポートを高く評価していただきました。これをきっかけに、当社のサポート力が他社との差別化要因であると再認識しました。
パートナーシップとZUU online読者へのメッセージ
── 大きな気づきだったわけですね。
嶋田 この気づきから、私たちは新しいサービス「インテリジェント フロー」の提供方法も進化させました。
これまではお客様にRPAやiPaaSを覚えていただき、その上でサポートするという形でしたが、それでもDXがうまくいかない企業もあります。多くの場合、最初に頑張ってくれた担当者が異動したり退職したりすると、サービスが使われなくなってしまうためです。
そこで「インテリジェント フロー」では、DXに課題を抱える企業に対し、当社がRPAロボットや自動化フローを構築して提供する形へと変更しました。これにより、お客様社内に高いITリテラシーを持つ人材がいなくても、自動化の恩恵を受けられるようになりました。日本の多くの企業が抱える課題を解決するため、サービス提供のあり方を進化させています。
現在、お客様は中小企業が増えていますが、大手銀行や自動車会社にも導入いただいており、ご利用いただく業界や企業規模は大手から中小まで幅広く広げています。
──ファイナンス戦略、たとえばIPOやM&Aの構想についてはいかがでしょうか。
嶋田 当社はBtoB領域で、お客様に深く入り込むサービスを提供しているため、独立系VCに加え、BtoBのお客様を多く持つKDDI様やサイボウズ様といった事業会社からもご支援をいただき、協業を進めています。
先日、サイボウズ様には当社のiPaaS「BizteX Connect」をOEM提供し、kintoneのデータ連携オプションとしてリリースしました。この1週間で約300社からお申し込みをいただくなど、大変良い反響をいただいています。
また、先ほどご紹介した株式会社カクイチ様も当社のファンとなってくださり、製造業のDXを共に広げたいという志でご出資いただいています。
現在、これらの株主のご支援をいただきながら、新たな資金調達ラウンドを計画しています。当社のAX事業にご興味をお持ちの企業や、協業・提携をご検討いただける企業と、ぜひご相談させていただきたいと考えております。
── 労働人口が減る今後、ますます重要なテーマ、事業分野になりそうですね。
嶋田 今後、どの企業においても労働人口の減少は避けられません。ITリテラシーの高い人材を育成するか、あるいはそうでない人材でもDX・AXを推進できる体制を構築するかは、経営における大きなテーマかと思います。
当社は、お客様の状況に応じてDX・AXをご支援できます。(顧客企業の)社内にITリテラシーの高い方がいらっしゃる場合は、その力を最大限に引き出すサービスを提供しますし、そういった方がいらっしゃらなくても、私たちが伴走してサポートし、自動化を構築・提供できます。そうしたお悩みがある企業には、是非ご検討いただければと思います。
- 氏名
- 嶋田 光敏(しまだ みつとし)
- 社名
- BizteX株式会社
- 役職
- 代表取締役社長