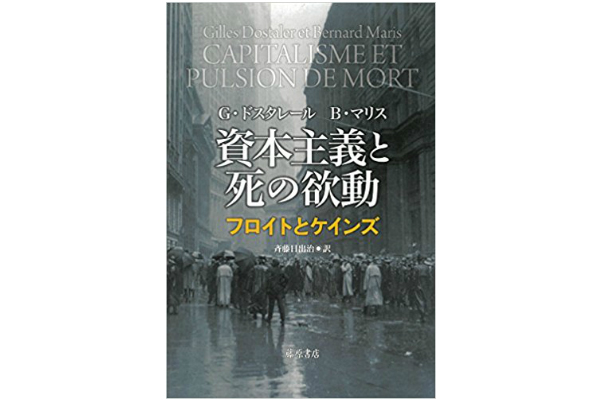古代ローマでは、これから闘いに臨む剣闘士(グラディアートル)が"morituri te salutant (those about to die salute you)"という言葉を発して皇帝(インペラートル)に挨拶したという。「死に赴かんとする者から皇帝閣下に敬礼」ということだが、「モリトゥリ」の「モリ」は"memento mori(死を想へ)"のmoriと同じ「死ぬこと」を意味する。
本書の序論には、この「モリトゥリ(死に赴かんとする者)」という題名が付されている。
世界金融危機直後の2009年にフランスで出版された本書は、著者たちが資本主義の「死」を強烈に意識したであろうことは論を俟たない(共著者のひとりは2015年1月7日のシャルリー・エブド襲撃事件で死亡)。本書、特に第3章で取り上げられているフロイトとケインズの著作『文化の中の居心地悪さ』と『わが孫たちの経済的可能性』もまた、世界恐慌発生直後の1930年に刊行されている。
『資本主義と死の欲動――フロイトとケインズ』
著者:G・ドスタレール&B・マリス
訳者:斉藤日出治
出版社:藤原書房
発売日:2017年12月10日
資本主義を揺さぶる「死の欲動」
本書の鍵となる概念である「死の欲動」は、原文のフランス語ではpulsion de mortとなっている。手元にある『小学館ロベール仏和大辞典』でpulsionを引くと、「欲動:衝動的、無意識的な力動の動因となる心迫の力。生物学的な本能instinctと区別して導入された」とあり、古典ラテン語のpellere(押し動かす、動揺させる)が語源であるとされている。
まさしく「死の欲動」が人びとの経済活動を押し動かし、現代の資本主義を動揺させていると唱えたのが、フロイトであり、ケインズである。すなわち、「フロイトが究明した死の欲動は、そしてケインズが描いた貨幣愛および資本蓄積と結びついた死の欲動は、資本主義の出現およびその発展において本質的な役割を果たした」と著者たちは述べる。
死の欲動という概念は、生の欲動とともに、『快原理の彼岸』(1920年刊)で導入された。フロイトは同書において、生きることすべてが死の意志を有しているという仮説を示し、「生を死に導こうと望む欲動と、たえず生の更新へと向かい生を吹き込もうとする性的欲動」との緊張関係を、エロスとタナトスの闘いとして論じている。
著者たちはいう。「資本主義の壮大な企みとは、消滅への諸力を、つまり死の欲動を成長へと誘導し、転移させることである。その意味で、エロス〔生の欲動〕がタナトス〔死の欲動〕を支配し、利用し、従属させる」と。だがそれは、タナトスを先送りすることでもある。
先送りされたタナトスは、自己増殖を繰り返し、破壊的な暴発力を高めていく。結果、エロスがタナトスを制御できなくなる。現代のわれわれは、金融バブルの発生と破裂、諸国民間や諸国民内部の著しい格差の拡大、自然環境破壊などのかたちで、その制御不能の事態を目の当たりにしているのではないか。
精神分析と経済学の相似変換
本書の魅力は、精神分析の祖フロイトと経済学の大家ケインズの見解の相似変換によって、現代資本主義が直面する危機的状況とその要因を人間精神と関連づけながら解き明かしている点である。
「経済学が合理性および供給と需要という言葉で語っていることを、精神分析は抑圧、および快原理と現実原理とのあいだの永続的運動という表現で語る」という。
フロイトのいう快原理とは「快を追求し不快を避ける」原理であり、現実原理とは「現実の状況の中で快の追求を一時断念し迂回させる原理」を意味する。死の欲動を(一時的に抑え込むも)将来的に昂らせることになる迂回のプロセスは、次の説明に見るとおりである。
「貯蓄することは消費を慎むこと、つまり欲求の充足を慎むことに等しい。そして投資することは、消費財を直接的に生産する労働を迂回させて資本を形成することを意味する。だから、欲求を抑圧し、欲求の直接的充足を拒否することによって、貯蓄し、生産を迂回させることが可能となり、エネルギーと労働を資本の形成に利用することによって、投資が可能となる。生産の迂回を、分業を、資本蓄積を、技術と生産の進歩を強化することによって、自然の破壊が強められることになる」
また、投機が投機を呼ぶ「金融バブルの雪だるま現象」を描いた次の説明も重要である。「ひとは投機に逆らって投機を行い(たとえば、リスクヘッジ市場で安定化を図ろうとする)、そしてそうすることで、さらに投機を増やす。マルクスが考えたように、資本の循環においては、貨幣はたえずより多くの貨幣を生む。個人はこのダイナミックな運動のなかに飲みこまれる」このダイナミックな運動が、今日のグローバリゼーションの姿である、と。
著者たちは、(世界を均質化する一方で、経済・社会格差の拡大をもたらす)グローバリゼーション、(金融派生商品など投機的金融取引の増大が招く)金融危機、(賃金と利潤を犠牲にする)レント〔不労所得〕階級の肥大化という三つの現象に、ふたりの見解の正しさを読み取っている。
フロイトとケインズの貨幣観
フロイトとケインズの貨幣観も、貨幣というものの本質を見事に捉えている。フロイトは、貨幣を糞便とみなし(もちろん、そうした見方は彼が初めてではなく、古来多くの寓話や説話で語られている)、所有の「本源的な形態」を肛門とみなし、性的抑圧とリビドーの昇華を嗅覚の抑圧と肛門性愛の昇華に結びつけて理解した。大人の貨幣欲望は、肛門期の幼児が排泄物に寄せる執着の昇華された姿である。
フロイトと同様、ケインズもまた、貨幣と汚物とのあいだに類似関係を見て、貨幣愛の根底に「死の欲動」があることを見抜いていた。ふたりがたびたび言及したミダスの神話には、「死の欲動と肛門性愛が住み着いている」という。「ミダスは、資本主義の小児的で自己消化的な性格を暴き出す。生産をむさぼり食う、という資本主義の性格が、それである」
著者たちのメッセージ
「呪うべき黄金欲」に取り憑かれた人類は、みずからの破滅(=死)を望んでいるのだろうか? どうもその気配が濃厚である。だが、もし仮に破滅を免れたいのであれば、次のことを忘れてはなるまい。
自分たちが日々いそしむ経済・金融活動が死を内包し、常に死の欲動と相克を演じているということを。その自覚こそが、辛うじて救いへの一縷の望みとなるかもしれない。かかる心得なき者は、危機に臨んで徒に周章狼狽するだけだろう。
われわれは、死の欲動を凝視し、人類あるいは文明の歴史における一種の臨死体験(恐慌や戦争等)を記憶に留め、絶えず想起すべきである。「メメント・モリ」――それが、本書に籠められた著者たちのメッセージにほかならない。(寺下滝郎 翻訳家)