本記事は、栗原毅氏の著書『 眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』(日本文芸社)の中から一部を抜粋・編集しています
健康診断での肝臓系数値の正しい見方

(画像=PIXTA)
●数値が悪化し始めたら要注意!
健康診断で肝臓の状態を把握する項目として「γ(ガンマ)ーGTP」が有名です。お酒の飲み過ぎによって数値が悪化しやすいため、健康診断の結果が届いたら真っ先にチェックするというお酒好きな方は多いのではないでしょうか?
なぜお酒を飲み過ぎるとγーGTPが多くなるのでしょうか?その仕組みを解説します。
お酒の飲み過ぎで肝臓の負担が大きくなると肝細胞は壊れてしまいます。通常は自然に再生していくのですが、負担が大きい状態が続くと、壊れたままの肝細胞が増えていきます。すると、肝細胞に含まれていたγ-GTPが血液中に漏れ出し、数値が悪化するのです。
逆に言えば、γーGTPの数値が悪化しない限り、お酒をいくら飲んでも問題ないのです。ただし、数値が少しでも悪化したら要注意!すぐにお酒を控えなければなりません。
また、「ALT」と「AST」というたんぱく質の代謝にかかわる酵素の値も、肝臓の健康状態を測るバロメーターとなります。肝臓に脂肪が溜まる脂肪肝の状態になると、肝細胞は炎症を起こして壊死していきます。そうなると、ALTとASTが血液中に漏れ出すのです。つまり、このふたつの数値が高い場合は、脂肪肝が原因で炎症が進行していると考えられますので、こちらの数値も必ずチェックしてください。

(画像=『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』より)

(画像=『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』より)

(画像=『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』より)
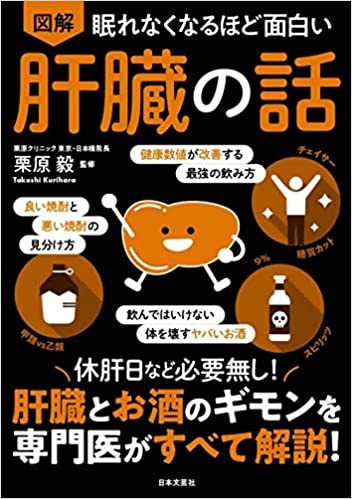
栗原毅(くりはら・たけし)
1951年新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。前東京女子医科大学教授、前慶應義塾大学特任教授。現在は栗原クリニック東京・日本橋院長を務める。肝臓の専門医としての日本の第一人者。脂肪肝の改善こそがメタボリックシンドロームの予防・改善に役立つと提唱。治療だけでなく予防医療にも力を入れている。血液サラサラの提唱者のひとりとして知られる。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます
※画像をクリックするとAmazonに飛びます
眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話
