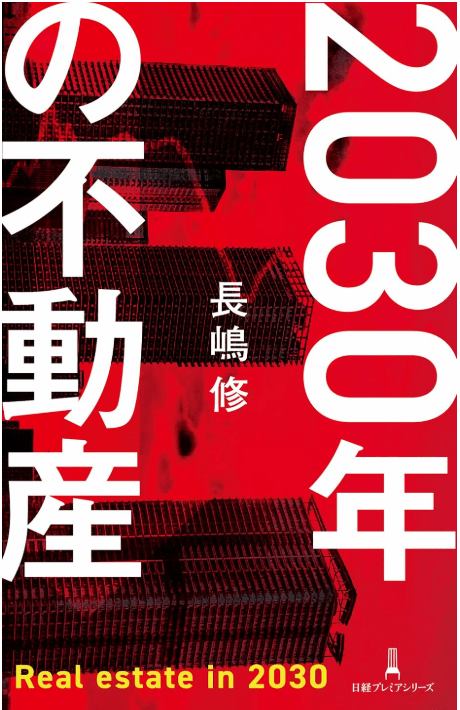本記事は、長嶋 修氏の著書『2030年の不動産』(日経BP 日本経済新聞出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

火災保険などの保険料は今後ますます上昇へ
ここでは、〝住宅コスト〞についてと、不動産投資についても軽く触れておきたいと思います。
不動産を購入する際には、物件の購入価格以外にもさまざまなコストが発生します。住宅ローンを組んで買うなら、金融機関に融資手数料を支払うことになります。返済が始まってからは、物件価格の返済分に加えてローン金利を負担しなければなりません。そのほか、ローン保証料に火災保険料、団体信用生命保険料、加入は任意ですが、地震保険料もかかります。不動産会社に支払う仲介手数料も必要。不動産エージェントやホームインスペクターに依頼した場合には、その分のコストもかかってきます。
2030年に向けては、こうした住宅コストの一部が上がっていくことが予想されます。
すでに値上がり傾向が顕著であり、今後も上がっていくと予想されているのが火災保険や地震保険、それにマンション総合保険の保険料です。これまでにもちょこちょこと値上げされてきた火災保険料は、2024年の秋に多くの保険会社で過去最大の上げ幅で引き上げられました。
地震保険は国と民間の保険会社が共同で運営していることから、どこの保険会社で加入しても保険料は同じですが、ここ数年でたびたび改定され、徐々に値上がりしています。南海トラフ地震や首都直下地震といった大規模な地震は、近い将来に高確率で発生することが予測されているため、これは仕方がないことかもしれません。
火災保険の保険料が引き上げられた背景には、近年顕著な災害の激甚化と、老朽化した建物の増加があります。ご存じのように、今やゲリラ豪雨はよくある出来事になり、台風は大型化して「100年に一度」という大仰な表現も頻繁に見聞きするようになりました。毎年のようにどこかで河川の氾濫や土砂崩れが起こり、水害の原因になる線状降水帯の発生も、もはや珍しいことではなくなっています。
自然災害の発生時に金銭面で住宅を守るベースとなるのは、火災保険です。火災保険は、失火やガス漏れなどによる火事の補償以外に、風災や雪災、雹災、落雷、水災、他住戸からの水漏れ、さらには盗難まで、幅広い事故による損害を補償するものです(商品によって、補償の範囲は特約をつけて加入者が決めます)。
災害が激甚化したことで、保険会社が負担する火災保険の保険金支払いは年々増加しており、このことが保険料の引き上げにつながりました。今後も、地球規模の環境変化を考えれば、災害の規模が小さくなることは考えづらいため、保険料は上がる一方でしょう。
2024年から特に大きく変わったのが、火災保険の水災補償です。水災補償の保険料率は、以前は全国一律でしたが、2024年からは地域ごとに変動する仕組みになりました。具体的には、水災のリスクが高い地域ほど保険料が高く、低い地域であれば保険料が安くなります。
リスクレベルは5段階で判断され、もっともリスクが低いと想定される地域が1等地、もっともリスクが高いと想定される地域が5等地とされます。河川の氾濫、いわゆる外水氾濫(洪水)だけでなく、排水能力を超えた豪雨が降ることにより下水道やマンホールなどから水が溢れ出す内水氾濫や、土砂崩れのリスクも含めて判断されるため、必ずしもハザードマップと合致するとは限りません。5等地の保険料は1等地の保険料の約1.2倍と、無視できない差があります。
自分が住んでいるエリア、あるいは家を買いたいと考えているエリアの水災等地は、インターネットで簡単に検索できるため、一度調べてみるといいでしょう。
マンション総合保険もさらなる値上がりの見通し
一般的にマンションの管理組合が契約者となり、共用部の損害に対する補償を目的に加入するのがマンション総合保険です。マンション総合保険は火災保険の一種で、自然災害や騒擾、集団による暴力行為などによってマンションの共用部に損害が生じた際、保険金を受け取ることができます。一般の火災保険が値上がりしていることを考えると、マンション総合保険の保険料も今後さらなる値上がりが予想されます。
現状、マンション総合保険の保険料率には築年数別料率が採用されていることが多いため、古いマンションほど保険料は高くなります。マンション総合保険の契約期間は最長5年ですが、更新後の保険料が高額で、管理組合が慌てふためくケースはよく見られます。
保険料率の仕組みが築年数別料率になっているのは、築浅物件に比べると築古物件のほうが、水漏れ事故などの不具合がはるかに起こりやすいからです。特に、築年数が20年を超えると、保険料は跳ね上がります。
マンションにおける水漏れは、住民の過失によって引き起こされることもありがちですが、大規模修繕工事が十全に行われていないマンションだと、外壁のひび割れや屋上の防水層の劣化が原因で雨漏りしたり、給排水管の経年劣化による破損で漏水したりすることもよくあります。
過去に水漏れ事故などを起こしているマンションは、保険料がさらに引き上げられるため、管理を徹底して建物や設備の補修・保全に努める必要があります。加えて、老朽化したマンションでは電気・ガスの設備も古くなり、火災のリスクが上昇することもまた、保険料の上昇要因の一つになっています。