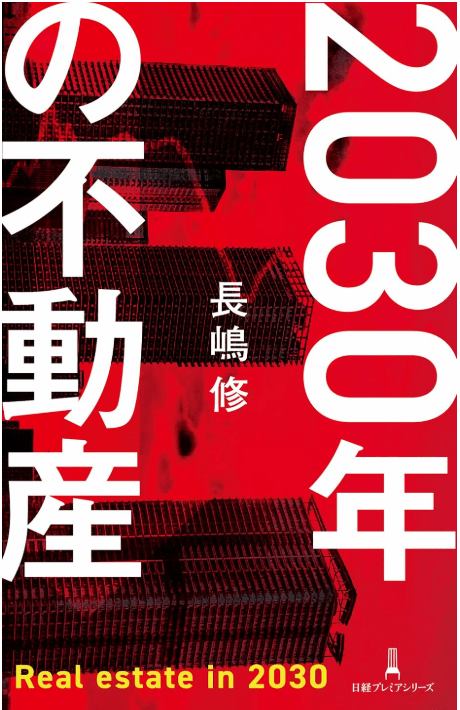本記事は、長嶋 修氏の著書『2030年の不動産』(日経BP 日本経済新聞出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

戸建住宅で生活するメリットとデメリット
必ずしもマンションのほうがいいとは限りません。マンションのメリット・デメリットと戸建のメリット・デメリットを比較のうえで、自分にとってどちらを選ぶのがベストかをよく考える必要があります。
戸建には、マンションにはないさまざまなメリットがあります。何でも住民同士で話し合って決めなければならないマンションと違い、我が家の管理や修繕の計画を自分だけで全部決められるのは、戸建のメリットと言っていいでしょう。
もちろん、相応の知識や計画性は求められますし、手間もかかります。それに、複数人で資産を共有しているマンションと違ってスケールメリットが働かないので、修繕のコスト負担も高くなりがちです。それでも、他人の意見に翻弄されて、ときに損する恐れすらあるマンションに比べると、自分の資産の問題を他人にゆだねることなく、自分で考えたい人にとっては戸建がベターです。
戸建は建物が独立しているため、周囲に音が響くことをそこまで気にする必要がなく、騒音トラブルに巻き込まれづらいのもメリット。駐車場代がかからないことや、外観・内装に好きなように手を加えやすいこと、ペットを飼いやすい点に魅力を感じる人も多いでしょう。庭付きの物件を買い、ガーデニングやバーベキューを楽しみたいという理由で戸建を選ぶ人もいます。
エリアによって一部例外はあるものの、基本的には戸建のほうがマンションより人付き合いの必然性が低いため、隣近所と密にコミュニケーションをとることなく、気楽に暮らしたい人にも向いています。
マンションは人間関係が希薄だと思われがちですが、分譲マンションでは管理組合の総会や防災訓練などで、住民同士が顔を合わせる機会が意外とあります。むしろ、住民同士のかかわりが深く、活気があるほうがいいマンションと言えるため、近所付き合いが皆無の場合、住民が管理に無関心な人ばかりの危険なマンションかもしれません。
前述のメリットの一方で、戸建には〝資産性が低下しやすい〟という決定的なデメリットがあります。
土地に関していうと、都心3区・5区などのごく限られたエリアを除き、戸建が立ち並ぶ駅から離れた住宅街は、今後地価が下がる可能性が濃厚です。
土地の問題に加えて、建物の劣化の問題もあります。鉄筋コンクリート造のマンションは堅牢な造りになっており、適切な修繕をしていれば長く住み続けられて、資産価値も低下しにくいもの。それどころか、新築分譲時よりも値上がりする物件も多くなっているというのは、先にも詳しく述べました。
これに対し、木造の戸建は鉄筋コンクリート造よりも耐用年数が短く、資産価値が低下するスピードも速いです。木造の建物の法定耐用年数は22年。マンションと同じく、法定耐用年数=建物の寿命ではないものの、適切な修繕をしていなければ30〜40年でボロボロになり、大規模なリフォームや建て替えを余儀なくされます。
これが鉄骨造や鉄筋コンクリート造の戸建であれば、耐用年数はもう少し長くなります。ただ、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物は手掛けている施工会社がそれほど多くはなく、コストが高くなる場合もあるため、いまだに戸建は木造が大半を占めます。
木造であろうと、適切なメンテナンスを施し続けることで寿命を延ばし、100年でも住み続けることはできます。しかし、屋根の点検・葺き替えや外壁塗装などを定期的に行い、建物の状態維持に気を配っている人は、そう多くありません。
そうしたこともあって、中古の戸建の販売価格が新築分譲時を上回ることはほぼありません。「新築の戸建は、人が住んだ瞬間から資産価値が3割下がる」と揶揄されるとおりで、マンションと比較するとコスパは悪いと言えます。
郊外では依然として戸建が強いが、立地の見極めが重要になる
マイカー保有率が低く、駅に近いマンションに住みたいというのはあくまで都心部のニーズであり、車が必須の郊外エリアでは、今でも戸建志向が強くなっています。地方都市にもタワマンが増えつつあるため、この価値観は徐々に塗り替えられていくかもしれませんが、当面はまだ戸建への引き合いも強いでしょう。
住宅メーカーも、郊外では新築の建売をローコストで建て、比較的手頃と言える価格で売るというおなじみの戦略を今も展開しています。手頃な価格に設定すれば、月々の住宅ローン返済額が近隣の賃貸マンションの家賃とそれほど変わらない、もしくはそれより安い金額に収まり、「それなら戸建を買ったほうがトク」という結論に落ち着きやすいからです。ただ、それでも売れ行きが絶好調というわけではなく、大幅に値引きしてやっと売り切っているパターンもよく見られます。
車で移動するのが前提とすると、予算に合わせて気に入った家を買えば、立地はそこまで重視しなくていいと思われるかもしれません。しかし、郊外であっても立地は非常に重要です。今後、郊外エリアでは立地適正化計画にのっとって、街のコンパクト化が進められていきます。駅やショッピングモールなどが集まる中心エリアから離れすぎると、居住誘導区域から外れる恐れがあります。
もし、買った土地が居住誘導区域外になってしまった場合、すぐさま何かが変わることはないとしても、徐々に行政サービスの提供が減り、最終的にゼロになります。ゆくゆくは行き交う人がいなくなり、治安が悪化するリスクも高いでしょう。そんなところに住み続けるわけにもいかず、家を売りたいと考えたとしても、居住誘導区域外の地価はほとんどゼロになるため、売るに売れません。
買い手からするとたまったものではありませんし、そんな土地に家を建てて売るなよ、と住宅メーカーに文句の一つも言いたくなるところですが、自治体と住宅メーカーはそもそも見ている方向が違います。後者は営利が目的であり、都市計画を第一に考えているわけではありません。貧乏くじを引かないようにするには、家を買う前に自分で自治体の都市計画について把握し、自衛するしかないのです。
居住誘導区域の地価は、誘導区域外からの移住者によるニーズもあるため、維持もしくは上昇する可能性があります。その中で戸建を買おうというとき、メインの選択肢は中古住宅になる見通しです。この先人口が減り、大手住宅メーカーは海外シフトの方針を明確に表し、住宅建設に携わる技術者も減り、資材価格が高騰するなか、新築戸建の供給は減っていくと見られるからです。すでに、新築住宅の着工戸数は毎年ゆるやかに減少し始めています。
マンションでは新築物件の販売価格が吊り上がり、富裕層でなければ手が出ない状況になりつつありますが、立地適正化計画が進んだ世の中では、新築の戸建もまた、資金力のある実需層のみが買えるものとなるかもしれません。