本記事は、下地 寛也氏の著書『結局、会社は思うように動かない。上手に働く人の社内コミュニケーション』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

仕事にコミュニケーションが必要な理由
仕事ができる人は、どのようなことを意識しながら働いていると思いますか?
私が優秀だなと思う人は、その組織における立ち振る舞いの勘どころを押さえながら行動しています。つまり、自分が「コントロールできるところ」と「できないところ」を明確に見極め、そのうえで行動を選択しているのです。
数学では、変えられないものを定数、変えられるものを変数といいますが、ビジネスでも同じことが言えます。仕事ができる人は定数に文句を言いません。そういう前提だと理解したうえで、どう変数を改善するかに注力します。自分が戦う土俵を理解しているわけです。これは要領のよさにもつながる話です。
その戦う土俵を理解するためのポイントは次の3つです。
- (1)会社のアルゴリズム
(2)相手の思考パターン
(3)仕事のツボ
コミュニケーションをするうえでは、もちろん「伝え方」や「説明する順番」などのテクニック面も大切でしょう。
しかしその前に、「自分たちが乗っている船がどのような仕組みで動いているのか」「船に乗っている人はどのような考えで働いているのか」「日々の航行をするためのやりとりにはどのようなものがあるのか」といった前提を押さえることが大切なのです。
これら3つの視点を意識しながら、自分の仕事に対するスタンスや1つ1つの言動を決めていくことで、社内コミュニケーションは格段に円滑になっていきます。
「会社のアルゴリズム」では、会社がどのような優先順位や判断基準で動いているのかという全体像を理解します。
仕事の意味や目的、組織内の力学、チームのあり方などを知ることで、会社という「船」がどのような仕組みで動いているのか把握できるようになります。
「相手の思考パターン」では、上司や同僚などの会社で働く人の価値観やモチベーション、そして「人と人」との関係性を理解します。
「なぜ相手はあのような言動をとったのだろうか?」を考え、次の動きを予測できれば、先回りして仕事ができるようになります。
「仕事のツボ」では、報連相、会議、依頼など業界や職種を問わず行われる仕事のやりとりにおいて「陥りやすいダメパターン」と「押さえておくべきポイント」を理解します。
これを押さえることができれば、1つ1つのコミュニケーションシーンにおける判断がストレスなくできるようになります。
コミュニケーションをするうえでは、もちろん「伝え方」や「説明する順番」などのテクニック面も大切でしょう。
しかしその前に、「自分たちが乗っている船がどのような仕組みで動いているのか」「船に乗っている人はどのような考えで働いているのか」「日々の航行をするためのやりとりにはどのようなものがあるのか」といった前提を押さえることが大切なのです。
これら3つの視点を意識しながら、自分の仕事に対するスタンスや1つ1つの言動を決めていくことで、社内コミュニケーションは格段に円滑になっていきます。
会社や相手、仕事という前提を理解できたら、最後に重要となるのは「自分自身のスタンス」です。
自分について意識するポイントは、「主体的に動く」という1点に集約されます。この主体性をリーダーシップと表現することもありますが、本質は同じことです。
主体的に動くとはどういうことなのかをここで簡単にお伝えしておくと、誰かに指示されたから動くのではなく、自分でどのように行動するか考えて決めることを意味します。
実は、主体性の有無がもっとも顕著に表れるのは「自分では決められない仕事」に直面したときです。
主体的な人は、たとえ決定権がなくても自分なりの意見やアイデアを持ち、「こうすればいいのではないか」と提案をします。
一方、受け身な人は、「私では決められないので指示をください」「どうすればいいのかわかりません」と早々に考えることを放棄します。
本人としてはそのつもりがなくても、経験がないから、あるいは答えを出せないからどのように動けばいいのかわからず、周囲からは思考停止しているように見えるのです。
こうした「自分では決められないこと」「誰が決定するのかわからないこと」について積極的に考えることこそ、主体性を育むためのカギとなります。
大丈夫です。初めから主体的な人なんてそうそういません。
多くの人は、会社に入社してから徐々に仕事を覚えていき、そのなかで判断に迷うことや誰が決めるのか曖昧なことに遭遇し、「自分だったらこうするはず」という考えを持つようになるものです。
やってはいけないのは、その貴重な考えを飲み屋の愚痴として浪費することです。
安全圏から「自分だったらこうするんだけどなー」「あの上司はわかってないわー」などと言っている間は受け身のままです。
そうではなく、そのような明確な答えがない状況に対して方向性を決定づけられるように、考えて、周りの人に働きかけてみてほしいのです。
最初のうちは少し勇気がいるかもしれません。しかし、そうした主体性を持つことで会社や仕事に対する見え方が大きく変わってくるようになります。
まずは小さなことからでいいのです。それこそ、挨拶を自分からする、落ちているゴミを拾う、誰も発言しない会議で呼び水となる意見を言ってみるなどで構いません。
役割としてのリーダーを任される前から周りに働きかけていく。そうした小さな行動の積み重ねが主体性を育てていくのです。
そのような主体的な行動を続けているうちに、必ず「主体的に動いたほうが楽だし、得だし、楽しい」と思う瞬間がやってきます。
それに、思うようにいかないときも「自分の伝え方が良くなかったのかもしれない」と健全に受け止められるようになります。そんな心持ちになれたらしめたものです。そこからは勝手に自分で成長できるようになっていきます。
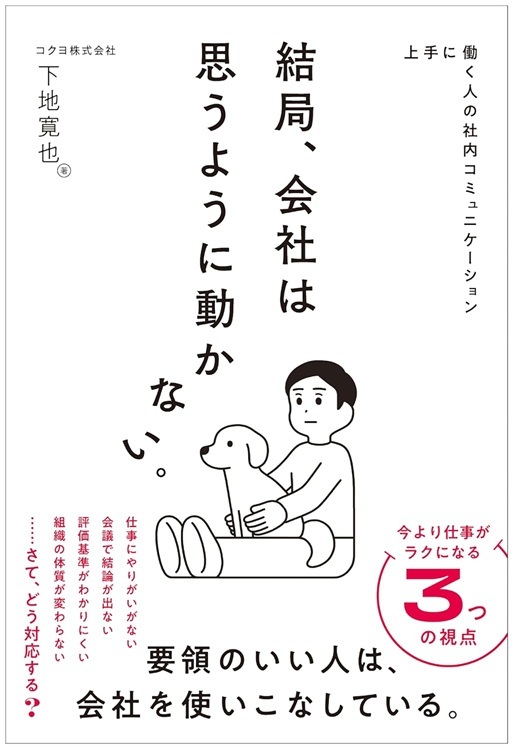
エスケイブレイン代表
1969年神戸市生まれ。
1992年文房具・オフィス家具メーカーのコクヨ株式会社に入社。
約20年間、顧客向けの営業および商品・サービス提案に従事し、現場目線でのコミュニケーションと課題解決に取り組む。その後、経営企画、業務改善、広報、社内風土改革など多岐にわたる社内業務を担当。現在は、コーポレートコミュニケーション室室長として、社内外の情報発信やブランド戦略、組織風土改革の推進をリードしている。
その実務経験を生かし、組織におけるコミュニケーションや働き方改革の理論と実践を独自に体系化。「組織のアルゴリズム」と「人の思考パターン」を軸にした社内コミュニケーション改善の手法は、多くの企業で注目を集めている。
同時に、新しい働き方を模索して複業ワーカー(エスケイブレイン代表)としてビジネススキルに関するセミナーや講演、YouTube動画配信などの活動も積極的に行っている。
主な著書に『考える人のメモの技術』(ダイヤモンド社)、『プレゼンの語彙力』(KADOKAWA)、『一発OKが出る資料簡単につくるコツ』(三笠書房)、『「しやすい」の作りかた』(サンマーク出版)などがある。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
