本記事は、下地 寛也氏の著書『結局、会社は思うように動かない。上手に働く人の社内コミュニケーション』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

主体的な思考はこうして生まれる
人間関係を築くうえでもっとも大切なのは信頼と言っても過言ではないでしょう。しかし、信頼は自分でコントロールできるものではありません。
「私たちはお客さまの信頼できるパートナーです」と企業がどれだけPRしたところで、実際に信頼するかどうかを決めるのはお客さまであるのと同じことです。
では、どうすれば信頼を得ることができるのでしょうか?
一番大切なのは約束を守ることです。約束を守れるかどうかは自分のコントロール下にあります。特に「小さな約束」を確実に守ることが大切です。
「なんだ、そんなことか」と思われるかもしれませんが、小さな約束を守ることができない人が多いからこそ、それらのことに誠実に向き合う人が信頼されるのです。
例えば、次のようなこともそうです。
- 上司から「お客さんにお礼のメールを送っといて」と言われたらすぐに実行する
- 「納期が間に合うか確認しておいて」と頼まれたら、すぐに確認して報告する
- ほかの人がどれだけ遅れようとも、自分は必ず会議の開始時間を守る
- 突発的なトラブルによって少しでも仕事に遅刻するときは、必ず電話で伝える
なにも大それた仕事を達成する必要はありません。ただ約束を守るだけでいいんです。
その小さな積み重ねが信頼へとつながります。
信頼を失うのはあっという間
「メールを打っておいて」と言われたのについ忘れてしまった。
「確認しておいて」と言われたのについ後回しにしてしまってできなかった。
その「失点1」を回復するのに守らなければいけない約束は1つではありません。
しかし、そのような簡単なことで信頼を失ってしまう人が大勢います。
周りにいる人が約束を守っていないからといって同じように行動してはいけません。そのようなときに約束を守れる人は一気に信頼ゲージが溜まります。逆に、みんなが当たり前に守るような約束では、それほど点数になりません。
コクヨには「信用のキップ」という言葉があります。
創業者の黒田善太郎はこう語っています。
信用は世間からもらったキップや。10枚あっても、1枚使えば9枚になり、また1枚使えば8枚、といった具合に減ってしまう。気を許すとあっという間に信用がなくなってしまう。(中略)信用は使ってはならない。使わなければどんどん増えていく。
人は信用されていると思った途端につい油断し、甘えが出てしまうものです。
そのような気持ちを戒めるいい表現だと思います。
仕事は常に想定外のことと隣り合わせのため、急な用事が入ったり、頼まれた作業を進めるのに思わぬ時間がかかったりすることもあります。
そんなときに必要なのは事前の報告です。相手に言われる前にこちらから言う。言い訳をしないでお詫びをする。
先に言えば説明、後から言えば言い訳です。
そのスタンスで仕事をしていたら、必ず頼りにされ、少しずつ大きな仕事を任されるようになります。
会社には地位や権限から生まれるポジションパワーと、実力や評判から生まれるパーソナルパワーがあります。
ポジションパワーが表れるのは、上司の言うことは聞いてもらえるのに自分が指示しても動いてもらえないときなどです。
では、どうすればポジションパワーを持たない自分の指示を聞いてもらえるのか?
タスクリーダーとして小さなチームを任されたとき、メンバーに動いてもらうため次のように指示を出すことは多いでしょう。
「この分析、明後日15時までにお願いします」
「ヒアリングはメンバー1人あたり最低5件しましょう」
短く、わかりやすい指示ですよね。ところが、この指示ではメンバーは思ったように動いてくれないことがあります。上司ののらりくらりとした指示より、よっぽど簡潔に伝えているはずです。にもかかわらず、なぜメンバーは動いてくれないのでしょうか。
まだ十分な権限がないから? あくまでその場かぎりのリーダーだから?
これらも1つの理由ではあります。人を動かすだけのポジションパワーがあれば、このような指示でも動いてくれるでしょう。しかし、まだ十分な権限がない段階では、明確な「つもり」の指示は嫌がられる可能性があることを覚えておいてください。
多くの場合、リーダーに選ばれるのは仕事ができる人です。リーダーは自分の仕事に自信を持っていることが多いため、「これくらい言えばわかるだろう」と上から目線になりがちです。しかし、そのような「自分が全部わかっているので指示を出します。皆さんはその通りに動いてくれればいいんです」という態度は相手に伝わってしまうものです。
そこでおすすめしたいのが、相手を動かす三視点トークという指示の出し方です。
この方法では、話を次の3つの視点で構成します。順番も次の通りに伝えます。
- (1)相手の視点に理解を示す
(2)会社の視点で全体の目的を伝える
(3)自分の(思いを含めた)視点で指示を出す
例えば、社内ヒアリングの依頼をする場合で考えてみましょう。
「加藤さんは毎日遅くまで残業をしているので、なかなかヒアリングの時間を捻出するのは難しいと思いますが
「このヒアリングは会社の業務上の課題を洗い出すための重要な取り組みだということはご存じだと思います
「私も今回は、このプロジェクトでなんとか非効率になっている業務プロセスを改善したいと思っていまして、ぜひともご協力いただけませんでしょうか?
このように多面的な視点を交じえて伝えることで、ただ指示を出すより相手も仕事を受け取りやすくなります。
権限がなくても、相手の負担に配慮して「一緒によりよくしていきたい」という姿勢を示すことで、好意的に協力してくれるようになるでしょう。
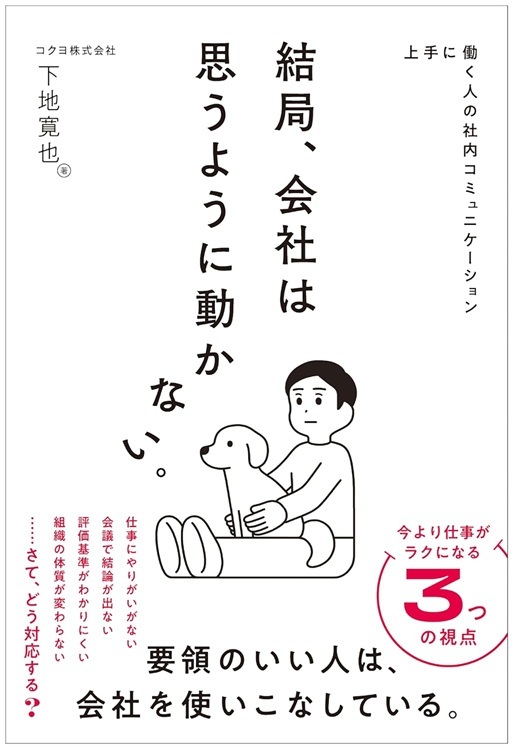
エスケイブレイン代表
1969年神戸市生まれ。
1992年文房具・オフィス家具メーカーのコクヨ株式会社に入社。
約20年間、顧客向けの営業および商品・サービス提案に従事し、現場目線でのコミュニケーションと課題解決に取り組む。その後、経営企画、業務改善、広報、社内風土改革など多岐にわたる社内業務を担当。現在は、コーポレートコミュニケーション室室長として、社内外の情報発信やブランド戦略、組織風土改革の推進をリードしている。
その実務経験を生かし、組織におけるコミュニケーションや働き方改革の理論と実践を独自に体系化。「組織のアルゴリズム」と「人の思考パターン」を軸にした社内コミュニケーション改善の手法は、多くの企業で注目を集めている。
同時に、新しい働き方を模索して複業ワーカー(エスケイブレイン代表)としてビジネススキルに関するセミナーや講演、YouTube動画配信などの活動も積極的に行っている。
主な著書に『考える人のメモの技術』(ダイヤモンド社)、『プレゼンの語彙力』(KADOKAWA)、『一発OKが出る資料簡単につくるコツ』(三笠書房)、『「しやすい」の作りかた』(サンマーク出版)などがある。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
