本記事は、下地 寛也氏の著書『結局、会社は思うように動かない。上手に働く人の社内コミュニケーション』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

仕事のツボを理解する
依頼がスムーズに進まない理由の多くは、目的がうまく伝わっていないことにあります。
覚えておいてください。目的は立場によって変わります。
先ほどの例でいうと、依頼者の目的、内容、方法は次のようになるでしょう。
- 目的 → 働く環境の課題を把握するため
- 内容 → 各自が部門内でヒアリングして内容を集約する
- 方法 → 添付のアンケート用紙に記載して、来週中に事務局にメールで返信
ところが、依頼を受けた側の人は次のように思うかもしれません。
「働く環境の課題を把握して何の役に立つんだろう。ピンとこないなあ」
「自分がわざわざメンバーにヒアリングして意見を集約しないといけないのか……」
「記載方法もよくわからないし、自分もメンバーも今月は忙しい時期なんだけどな……。ほかの部門はちゃんと提出するのかどうかちょっと様子を見てみよう」
依頼者としては目的を明確にしたつもりでも、相手にとっては全然ピンときてないし、そもそも何の意味があるのかも伝わっていません。そのうえ、内容も方法も面倒くさそうなので、全くやる気にならないわけです。
会社にとってどのような意味があるのか、自分の部門にどのような影響があるのかなど、「そもそもなんのため?」が伝わらなければ忙しい人に動いてもらうことはできません。
この場合であれば「半年後にオフィスをリニューアルするときの参考のため」と書けば、会社として取り組んでいることが伝わりますし、自分にとってもリニューアルしたときに環境を良くすることはメリットになるので協力しようと考えるでしょう。
ポイントは「目的が相手にとってメリットがあるように聞こえるか?」です。一見するとメリットっぽいことを書いていても、相手に響かなければ意味がありません。
どの部門の人も、自分の部門の目的や目標を達成するために活動しています。
他部門の依頼を全部受けていたら、いくら時間があっても足りません。
よって、依頼内容を取捨選択して協力するかどうかを選別しているわけです。
そうしたときに、よくわからない「目的らしきもの」が入っていても行動してくれないのは当たり前です。依頼文章を相手の気持ちで読み返してみて、自分が相手の立場でも依頼に答えたくなるようなメリットが入っているかを今一度確認してみてください。
仕事をしていると、「なんでこの人はこんな仕事のしかたをしているんだ?」と思う瞬間があるでしょう。
そのようなとき、見るに見かねてつい口を出してしまいたくなるものです。
ただしその言い方には注意が必要です。
以下は先輩と若手のよくあるやり取りです。
先輩「やっぱり、こまめにお客さんを訪問して関係性を維持することは大切だよね」
若手「でも、目標達成のために見込みの低い顧客には時間を使わず効率化すべきです」
先輩「う〜ん、そうなんだけどね……」
周りに流されず、自分の意見がしっかり言えるのは大切なことです。
しかし、そのことにより誰かの気分を害してしまっては建設的な議論にはなりません。
人は発言をするときに正しいか正しくないかで判断しがちです。
ところが、自分の考えをうまく伝えるためにはほかにも配慮する点があるわけです。
それは相手のメンツ、つまりプライドです。
「プライドやメンツを気にしていたら古い企業体質は変わらない」「もっと正面から切り込まないといけない」と思うかもしれません。しかし、健全な会社が何でもかんでも正しさを優先し、相手の感情に全く配慮していないかというとそうではありません。
反論する場合は相手のメンツを考え、慎重に言葉を選ぶものです。
特に、まだ経験が少ない人の「べき論」は聞いていて浅く感じてしまいます。
なぜかというと、べき論の後に具体的な代案がないからです。
先ほどの例では、そもそも先輩が提示したやり方と若手が提示したやり方では優先するポイントが異なります。先輩はお客さまとの関係性の維持を気にしています。一方で、若手は目標達成に意識が向いています。この場合、双方のポイントを押さえられる具体案を提示してほしいわけです。
この例で求められているのは「お客さまとの関係性を維持しつつ、目標達成に必要な効率化をどのように実現するか」です。べき論だけでは話が前に進みません。
そしてもう1つ配慮してほしいことがあります。
それは、相手のプライドを折らないマイルドな言い方です。
コツはクッションワードを使うことと、語尾を疑問形にすることです。
クッションワードとは「確かにそうですね。ただ……」「少し違う視点ですが……」「個人的な意見なのですが……」といった主張を和らげる前置きのことです。
語尾を疑問形にするときは、「〜すべきです」ではなく「〜してはどうでしょうか?」「〜する案ってどう思います?」と問いかける言い回しに変えます。
先ほどの例でいうと次のようになります。
先輩「やっぱり、こまめにお客さんを訪問して関係性を維持することは大切だよね」
若手「確かにそうですね。ただ、目標達成のために見込みの低い顧客には時間を使わず、効率化したほうがいいのではと思いますがどうでしょう?」
先輩「というと?」
若手「具体的には、見込みのある顧客にできるだけ時間を使って、見込みの低い顧客にはメールマガジンなどで関係性を維持する方法を考えるとかはどう思います?」
先輩「なるほど、それはありかもね」
こうして意見を尊重しつつ具体的な代案を示せば、建設的な議論ができます。
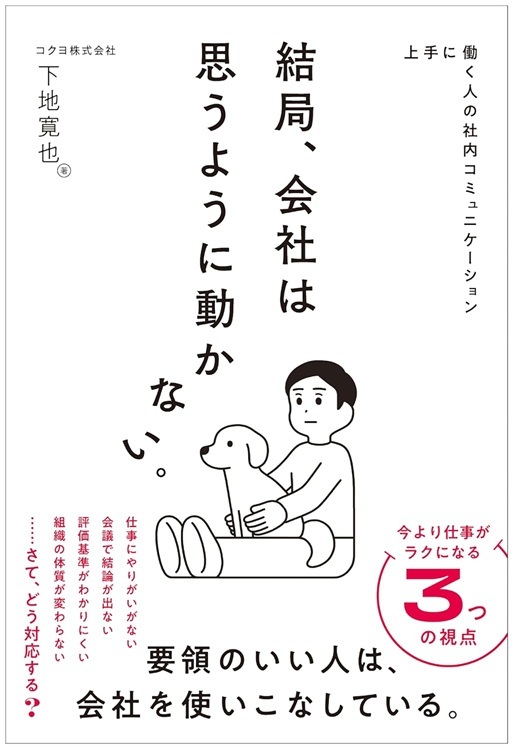
エスケイブレイン代表
1969年神戸市生まれ。
1992年文房具・オフィス家具メーカーのコクヨ株式会社に入社。
約20年間、顧客向けの営業および商品・サービス提案に従事し、現場目線でのコミュニケーションと課題解決に取り組む。その後、経営企画、業務改善、広報、社内風土改革など多岐にわたる社内業務を担当。現在は、コーポレートコミュニケーション室室長として、社内外の情報発信やブランド戦略、組織風土改革の推進をリードしている。
その実務経験を生かし、組織におけるコミュニケーションや働き方改革の理論と実践を独自に体系化。「組織のアルゴリズム」と「人の思考パターン」を軸にした社内コミュニケーション改善の手法は、多くの企業で注目を集めている。
同時に、新しい働き方を模索して複業ワーカー(エスケイブレイン代表)としてビジネススキルに関するセミナーや講演、YouTube動画配信などの活動も積極的に行っている。
主な著書に『考える人のメモの技術』(ダイヤモンド社)、『プレゼンの語彙力』(KADOKAWA)、『一発OKが出る資料簡単につくるコツ』(三笠書房)、『「しやすい」の作りかた』(サンマーク出版)などがある。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
