本記事は、田渕 直也氏の著書『金融と投資のための確率・統計の基本』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

ボラティリティとは
何かに投資するとき、期待リターンのみでは的確な投資判断はできません。期待リターンは必ず実現するリターンではなく、あくまでも長期平均的にみて実現するであろうリターンです。単年でみれば、実際に実現するリターンは期待リターンの上にも下にも振れるはずで、下手をすれば大きな損失を被って途中で投資からの撤退を余儀なくされるかもしれません。そうなれば、いくら期待リターンが高かろうとも、それは絵に描いた餅に過ぎなくなります。
期待リターンが年10%だとしても、うまくいけば30%のリターンが上がるかもしれないし、逆にマイナス10%になるかもしれないというようなことです。投資のリスクとは、このように、実現するリターンが期待リターンから乖離するときに、そのうちの下振れする可能性とその度合いを測るものといえます。
株式投資のリターンは株価の変動と配当の受取からなり、どちらも変動する可能性がありますが、リターンの振れ幅に与える影響でいうと価格変動の影響が圧倒的に大きいでしょう。そうであれば、株式投資の主要なリスクは株価変動によってもたらされると考えることができます。
株価は、大きく値上がりすることもあれば、大きく値下がりすることもあります。その振れ幅の大きさがリスクを生むのです。
株価に限りませんが、一般的に市場価格の変動率の振れ幅の大きさを示すのに使われる指標がボラティリティです。
気をつけて欲しい点は、ボラティリティには価格の上昇、下落といった方向性は加味されていないという点です。上昇方向であろうが下落方向であろうが、あくまでも価格変動率の振れ幅の大きさを示します。ですからボラティリティは、リスク、すなわちリターンの下振れの大きさを示すだけでなく、リターンの上振れの大きさも示します。つまり、ボラティリティが大きいということは「大きな利益を上げられるかもしれないし、大きな損失が発生するかもしれない」ことを意味し、ボラティリティが小さいということは「大きな利益は期待薄だが、大きな損失が発生する可能性も低い」ことを意味します。
このボラティリティは、資産運用やトレーディング業務、およびそのリスク管理において最も重要となる概念のひとつです。また、デリバティブの重要分野であるオプション※1の取引では、その価格を決定する最大のファクターとなります。
というよりも、オプションの市場は、実質的にはボラティリティを取引する市場そのものであり、その取引市場が巨大であることを見てもボラティリティの重要性をうかがい知ることができます。
※1 ここでは詳しく取り上げませんが、オプションは“権利の売買”の総称です。具体的には、特定の株式を将来の一定時点であらかじめ決められた価格で買うことができる権利、あるいは売ることができる権利といったものを売買します。
標準偏差を理解する
ボラティリティは、日本語では一般に「価格変動率」と訳されることが多いと思います。ただし、正確にいえば、「価格変動率の標準偏差」ということになります。では、標準偏差とは何でしょうか。
まずは言葉の意味からすると、標準的な偏差、ということになりますが、偏差はここでは期待値からのずれを意味するので、実現する値が標準的にみて期待値からどのくらいずれるかを測ったものといえます。なぜ“標準”というやや曖昧な言葉を使い、もっとわかりやすい“平均”と呼ばないかというと、それは「期待値からのずれの大きさの平均」ではないからです。
このことを理解するには、標準偏差の数学的な定義も知っておく必要があります。標準偏差は分散といわれるものの平方根として定義されます。では、分散は何かというと、「期待値からのずれ(偏差)の二乗の平均」です。
わかりやすいサイコロの事例で考えてみましょう。サイコロには1から6までの取り得る値があり、その期待値は3.5ということでした。1という目は、その期待値からは-2.5ずれています。同様に計算していくと、1から6までの各目の期待値からのずれは、-2.5、-1.5、-0.5、+0.5、+1.5、+2.5となります。
ここではこのずれの大きさを端的に表す値を知りたいわけですが、ではこれらの値の平均を取ってみればどうなるかというと、0になってしまいます。プラスの偏差とマイナスの偏差が打ち消し合ってしまうからです。そこで、プラスマイナスが打ち消し合わないようにしてなんとかずれの大きさを示す数字を算出することを考えるのですが、それにはいくつかのやり方があります。
最もわかりやすいのは、それぞれの目の偏差の絶対値2.5、1.5、0.5、0.5、1.5、2.5の平均を取るというものです。計算すると1.5になりますが、これを平均偏差(標準偏差ではなく)と呼びます。これなら、「期待値からのずれの平均的な大きさ」と理解することができますね。
別のやり方では、それぞれの目の期待値からのずれをいったん二乗にします。マイナスの値も二乗にするとプラスになるので、プラスマイナスが打ち消し合うことがなくなるのです。このずれの二乗を平均したものが分散です。ただし分散はあくまでも二乗された値なので、期待値からのずれの大きさを知るためにはそれを平方根にする必要があります。それが標準偏差です。
平均偏差に比べて少しややこしいと思いますが、期待値からのずれの大きさを扱うときに、そのずれの大きさを端的に表す値として、この標準偏差が一般的には使われています。
ちなみに期待値は、いわば確率変数全体をたった1つの数字で代表する値です。しかし、確率変数を代表する値にもいろいろな考え方のものがあり、たとえば、確率変数が取り得る値を上から(下からでも可)順に並べてちょうど真ん中にくる値を代表値として扱う考え方もあります。このときの値が中央値(メディアン)です。
あまり気にしなくてもいいのですが、確率変数を代表する値と、それぞれの値がそこからどれだけずれるかを表す偏差の計算方法は一応セットになっていて、メディアンからのずれを計算するときは先ほどでてきた平均偏差を、期待値からのずれを計算するときは標準偏差を使うことがよいとされています。
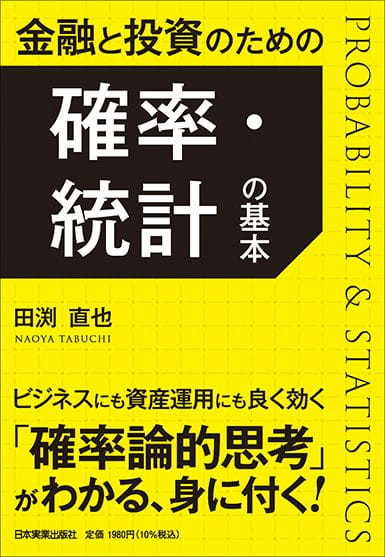
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
- 28.2%の幻想と10.4%の現実、株式投資における期待リターンの捉え方
- ボラティリティとは何か? 期待リターンの裏に潜むもう1つの真実
- なぜ確率は「山の形」になるのか? 正規分布と中心極限定理
- ひとつのかごに卵を入れない、分散投資の知恵
- 株価はなぜ動く? 市場モデルで解き明かす「リスク」の正体
- 「VaR」が金融を変えた! リスク管理の常識を覆した革命とは
- 「過去は未来を保証しない」ブラック・スワンに備える思考法
