本記事は、田渕 直也氏の著書『金融と投資のための確率・統計の基本』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

VaR革命
リスクは、一般に危険という意味で用いられる言葉ですが、一概に忌避されるべきものとは限りません。とくにビジネスや投資の意思決定においては、リスクは忌避すべきものではなく、選択すべきものとなります。
もちろんリスクをとらずに利益が得られるのであればそれがいちばん良いのですが、実際にはそのような機会に遭遇することはまれでしょう。仮に企業が「リスクはとらずに利益だけを得る」方針を決めたとしたら、おそらくビジネス機会はきわめて限られ、十分な利益を得られずに事業を継続できなくなる可能性が高くなります。結局、それが“リスクをとらないリスク”になるのです。
そう考えると、意思決定とは、どのようなリスクをどのくらいとるのかという判断をすることに他なりません。
そうであるならば、意思決定を下すためには、まず何かをやるときにどのようなリスクが付随するかを特定し、それぞれのリスクの大きさを可視化しなければなりません。リスクの特定と定量化こそが意思決定の前提になるということです。
1990年代前半にアメリカの大手金融機関JPモルガンのCEOを務めたデニス・ウエザーストーンは、「銀行業務の本質はリスク管理である」という発言を残しています。これは何も銀行業に限らず、すべてのビジネスに共通することだと思いますが、彼はその言葉を実践すべく、「明日、最悪の場合に自行にどのくらいの損失が発生しうるか」を毎日報告するようにスタッフに求めます。この要請に応えて開発されたのが、現在ではリスク量の定量化手法として幅広く用いられているバリュー・アット・リスク(VaR※1、Value at Risk)という指標です。
※1 分散を表すVar等と区別が紛らわしいですが、バリュー・アット・リスクの場合は真ん中のみ小文字でVaRと表すことが習わしとなっています。
ただし、“最悪の場合”といっても、何を最悪と考えるかはとてもむずかしい問題です。たとえば、将来様々に発生しうる損益の確率分布を、ここまで何度も登場させてきた正規分布で正確に表せるとしましょう。正規分布は左右対称の釣り鐘型確率分布で、平均から遠く外れる値の出現確率は非常に小さくなっていくとのことでした。ただし、その確率はどこまで行っても完全にはゼロにならないのです。したがって正規分布においては、どんな値よりもさらに悪い値となる確率が、たとえほんのわずかであっても残されていて、本当の意味での最悪の事態を特定することはできません。
そこでどうするかというと、99%とか、95%というような十分に大きな確率の範囲を設定し、そのなかで最大となる損失額を計算するのです。このときの99%とか95%という確率のことを、すでにでてきた言葉ですが、信頼水準もしくは信頼区間といいます。
現実に即して考えてみても、悪いシナリオはいくらでも考えることができます。たとえば、隕石が落ちて世界が壊滅的な打撃を受けるというような極端に悪いシナリオも、その発生確率は完全にはゼロでないでしょう。ですが、そんなことまで考えていてはビジネスなどできません。現実的な判断をするためには、確率が完全にはゼロでなくても、ゼロに近いとみなせるものは無視する必要があるのです。
それに、発生確率が非常に低い極端なシナリオを想定してしまうと、どんなことをやるにしてもすべてが損失になってしまうので、現実的な意味でのリスクの大きさの違いを把握することができなくなってしまいます。安全資産とされる国債でも、リスクの高い新興企業株の株式でも、世界が壊滅すればどちらも紙くずです。しかし、それではリスクの差がわからなくなって、リスク管理は意味を失います。だから、現実的な確率の範囲を決め、そのなかで想定される最大の損失額の大きさでリスクの大きさを表すのです。
では、信頼区間として何%の範囲で最大の損失額を計算すればいいかというと、その点についてはとくに正解があるわけではありません。
この問題は後でまた考えるとして、とりあえずは信頼区間を99%として話を進めます。その範囲で自社の最大の損失額を見積もったところ、その額がXになったとしましょう。
その場合、「99%の確率で損失額はXを超えない」と表現することが可能です。別の言い方をすれば、「Xを超える損失が発生する確率は1%である」と言うこともできます。
ここで、ちょうどXの損失をカバーできるだけの自己資本があるとしましょう。自己資本は、株式会社ならば株主資本と呼ばれ、本来は株主のお金です。ですが、借入のように返済義務を負ったものではないので、これを全部使い果たしてしまっても、株主は怒るでしょうが、それだけで会社が破綻することはありません。会社が破綻に追い込まれるのは、一般的には支払義務がある負債を支払えなくなったときです。
そうすると、99%の範囲で最大となる予想損失額を上回る自己資本を用意できていれば、「損失が自己資本を超えてしまって会社が破綻に追い込まれる確率は、1%未満に抑えられる」ということになります。
現実問題としては、破綻確率が1%もあるのはかなり問題ですが、この点にはあまりこだわっても仕方ありません。実際のリスク定量化の作業では、様々な仮定を置いて計算しなければいけないので、その正確性が厳密に担保されているものではないのです。だから、破綻確率を0.01%未満に抑えたいから信頼区間は99.99%で計算しなければいけないと考えても、その計算がそのとおりの正確なものになる保証はありません。
設定すべき信頼区間に正解はないというのはそういう意味です。そこで、実務上はとりあえず99%とか95%で計算します。でも、そうしていわば適当に計算した予想損失額を自己資本でカバーするだけだと、先ほどのとおり、会社の破綻確率は結構高めになってしまいます。そこでどうするかというと、たとえば99%信頼区間で計算した最大損失額の3倍分を自己資本でカバーする、というように何らかのバッファーを設けて管理していくのです※2。
※2 こうした計算は、バーゼル規制と呼ばれる国際的な銀行規制でも採用されているものです。
実際の業務では、大きなリスクをとったからそれに必要な自己資本をあわてて調達するというわけにもいかないでしょうから、既存の自己資本の一部を業務執行上で発生するリスクをカバーすることに計算上割り当て、実際のリスク量+バッファーがその範囲内に収まるように業務を運営していくことになります。
いずれにしても、せっかくきちんと定義をしてリスクを定量化するのに、最後はエイヤッというような部分が入ってきて、少しすっきりしないものを感じるかもしれませんが、現実のリスク管理には2つのステップがあるということです。
1つ目は、現実的な定義に従ってリスク量を測定するステップです。これができないと、どのようなリスクをどのくらいとっているかがわからないので、ここはきちんと定義し、きちんと計測しなければいけません。
次のステップは、そのリスク量に対して自己資本が十分に用意されていて、会社の破綻確率が僅少に抑えられているかどうかをチェックするステップです。この部分については、大きな損失を生むようなまれな事象の発生確率を事前に正確に見積もることが非常にむずかしいので、どうしてもある程度のエイヤッが必要となるのです。正確な見積もりがむずかしいなかで会社の破綻確率を僅少にするためには、いろいろとバッファーを設定して、保守的に計算していくことが現実的です。それが、先ほどの99%での最大損失額の3倍、というような計算です。
このように、信頼区間の水準と、会社の破綻確率を僅少にするためのバッファーは、組み合わせとして考えるべきものであって、信頼区間が大きければバッファーは少なくてもいいでしょうし、信頼区間が小さければより大きなバッファーが必要です。だから信頼区間の設定そのものには必ずしも正解はないということになります。
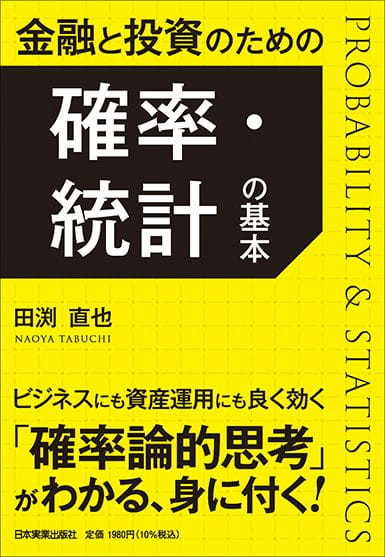
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
