本記事は、田渕 直也氏の著書『金融と投資のための確率・統計の基本』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

ポートフォリオの価値変動
昔からの投資格言に、「すべての卵を同じかごに入れてはいけない」というものがあります。そのかごを落としてしまったら、卵がすべて割れてしまうからです。卵を入れるかごをいくつかに分けておけば、そのうちの1つを落としてしまっても、壊滅的な被害を免れることができます。この格言は、大きな損失を避けるために投資対象を分散することが大切であることを説いたものです。
1952年、この分散投資の知恵を、シカゴ大学の大学院生であったハリー・マーコウィッツがエレガントな数学を使って見事に定式化しました。こうして確立されたのが現代ポートフォリオ理論、MPT(Modern Portfolio Theory)です。
ポートフォリオとは、投資運用資金の資産構成、あるいは銘柄構成のことです。要するに、投資運用資金をどのような対象に振り分けているかを示すものです。転じて、何らかの資産に投じられている投資運用資金自体を指す言葉としても使われます。金融業務においては、きわめて頻繁に使われる用語です。
ポートフォリオは基本的に複数の変動要因を含むものですから、ここで問題になってくるのは、確率変数を複数組み合わせたときに、その集合体がどのように振る舞うかということです。単純に構成要素を足し合わせたものと考えてよいのでしょうか。
まずは、ポートフォリオのリターン(収益率)について考えましょう。
単純なケースを想定して、トヨタ株とソニー株の二つの銘柄に50%/50%で投資することを考えます。トヨタの株価が10%上昇し、同時にソニーの株価が15%上昇したら、ポートフォリオの価値はどれだけ増加するでしょうか。
これは簡単ですね。トヨタ株に振り向けた50%部分で10%のリターンがあり、ソニー株に振り向けた残りの50%部分で15%のリターンがあるのですから、全体では12.5%(=50%×10%+50%×15%)のリターンになります。
もちろんこの関係は、将来の期待リターンについても成り立ちます。つまり、ポートフォリオのリターンは、実績リターンでも期待リターンでも、ポートフォリオの構成要素のリターンを投資比率に応じて加重平均したものになります。
別の言い方をすると、同じくらいの期待リターンを持つ銘柄に分散投資をしていった場合に、いくら分散投資をしてもポートフォリオの期待リターンは決して薄まったりしないということです。
ところが、リスクのほうはそうではありません。リスクは、リターンのバラツキであり、ボラティリティによってその大きさが決まるということでした。仮にトヨタ株のボラティリティが20%、ソニー株のボラティリティが30%だとして、両銘柄に50%/50%で投資したポートフォリオの価値変動のボラティリティは平均の25%になるかというと、そうはならないのです。
それは、トヨタ株とソニー株では価格の動き方が異なり、たとえば片方が値下がりしたときにもう片方が上昇して損失を穴埋めしてくれるようなことも生じうるからです。
つまり、異なる動きをする2つの確率変数には、それぞれの変動を打ち消し合う動き方をする可能性があり、そのため2つを組み合わせた集合体の標準偏差は、それぞれの標準偏差の平均値よりも小さくなるということです。先ほどのトヨタ50%/ソニー50%のポートフォリオの場合も、ポートフォリオとしてのボラティリティは25%よりも小さな値になります。ボラティリティはリスクの大きさを示す指標ですから、その分リスクが小さくなっているのです。このように分散投資によってリスクが小さくなるのが分散効果といわれるものです。
ここでは、構成要素が2つというきわめて単純なケースを考えていますが、一般的に構成要素が増えれば増えるほど、分散効果は大きくなります。
では、構成要素の数以外に、分散効果の大きさを決める要因は何でしょうか。
複数の確率変数がバラバラに動くことによってお互いの動きが打ち消されるのですから、そのバラバラに動く度合いが大きければ分散効果も大きくなると考えられます。
バラバラに動く度合いは、連動して動く度合いの裏返しです。つまり、連動して動く度合いが低いものを組み合わせれば、分散効果は大きくなります。ここで、2つの変数が連動して動く度合いを計算したものが相関係数といわれるものです。
相関係数は、-1から+1までの値を取ります。相関係数がプラスなら2つの変数は同じ方向に連動して動くことが多く、相関係数がマイナスなら逆方向に動くことが多いことを示します。そして、相関係数が+1というのは2つの変数が完全に連動して動くことを意味し、逆に相関係数が-1なら完全な逆連動です。相関係数がゼロだと、両者が同じ方向に動くことも逆方向に動くことも同じくらいに発生するイメージとなります。
株価の場合、2つの銘柄の価格が完全に連動したり逆連動したりすることは考えられないでしょうから、相関係数は-1と+1のあいだのどこかの値を取ります。この相関係数が低いほど、分散効果は大きくなるのです。一般に、逆連動しやすい銘柄を見つけることはそれほど簡単なことではないので、たとえば業種や業態が異なっていて、株価が概ね無関係に動いているように見えるもの、つまりは相関係数がゼロに近いものを組み合わせていくことで分散効果を大きくしていく、というのが現実的な考え方でしょう。
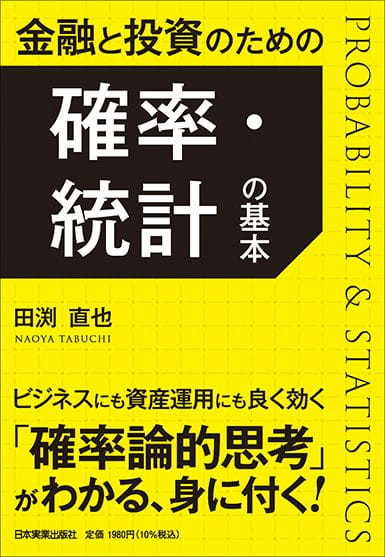
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
- 28.2%の幻想と10.4%の現実、株式投資における期待リターンの捉え方
- ボラティリティとは何か? 期待リターンの裏に潜むもう1つの真実
- なぜ確率は「山の形」になるのか? 正規分布と中心極限定理
- ひとつのかごに卵を入れない、分散投資の知恵
- 株価はなぜ動く? 市場モデルで解き明かす「リスク」の正体
- 「VaR」が金融を変えた! リスク管理の常識を覆した革命とは
- 「過去は未来を保証しない」ブラック・スワンに備える思考法
