本記事は、田渕 直也氏の著書『金融と投資のための確率・統計の基本』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

過去に生じなかった出来事にどう備えるのか
確率統計論は、過去の情報にもとづいて将来についての有益な情報を抽出することを基本にしています。そこには、将来は過去の延長線上にあること、過去に起きたのと同じようなことは将来にも起きうることが暗黙の前提として横たわっています。
このように、過去を振り返ることによって将来の予測をすることを“バックワード・ルッキング”な手法といいます。
実際に観測された過去のデータにもとづくので、P値ハッキングなどに気をつければ恣意性を排除でき、客観的な分析をすることができます。その一方で、こうした手法は過去のデータに依存するので、過去に生じていない出来事の影響を織り込むことはできません。
しかしながら、過去に生じなかった出来事が将来にも生じないという保証はありません。
かつてヨーロッパの人々は白い白鳥(スワン)しか見たことがありませんでした。だからスワンは白いものとばかり思っていたのですが、実際には黒いスワン(黒鳥)もいたのです。そのことから転じて、実際に生じる可能性があり、もし生じれば大きなインパクトをもたらすにもかかわらず、過去に経験したことがないことから予測できない出来事を“ブラック・スワン”と呼びます※1。ファットテールとよく似た概念ですが、こちらは「過去に例を見ない」という点にフォーカスが当たった言葉です。
過去データにもとづく統計学的アプローチには、常にこのブラック・スワン問題がつきまといます。
※1 トレーダー出身の経済学者、ナシーム・ニコラス・タレブの同名のベストセラーから広まった言い方です。ちなみに、タレブ著『ブラック・スワン』は、市場価格の変動が正規分布とは異なることを喝破したマンデルブロに捧げられる形で上梓されたものです。
では、過去データにとらわれずに、将来起きる可能性があることを想定するにはどうすればいいでしょうか。
このようなアプローチには、“フォワード・ルッキング”という名前が与えられており、リスク管理の世界では、バックワード・ルッキングな手法に加え、フォワード・ルッキングな視点も必要であるとされています。ところが、実際にどうすれば過去にない出来事を予想できるかということには必ずしも決め手がないのです。結局のところ、将来起きる出来事をその発生確率も含めて正確に予測することはできるはずもなく、確率統計論をもってしても、否それ以外のいかなるツールをもってしても、それは乗り越えることのできない大きな壁となります。
それでも、実務のうえではいくつかの手法が考えられています。最後に、そのいくつかを簡単に見ておきましょう。
・シナリオ分析
この手法は、“フォワード・ルッキング”という言葉に最もしっくりくるものではないかと思います。将来についての仮想的なシナリオをつくり、それにもとづいてリスクを計測していきます。ただし、過去に例を見ないようなシナリオをつくることはやはりむずかしく、仮にそのようなシナリオをつくったとしてもその発生確率を見積もることはさらにむずかしいでしょう。
そのため、よく用いられるものとしては、重大なリスクを引き起こすかもしれないイベントを想定し、そのリスクが顕在化したときに生じるリスクを測定するという方法です。たとえば「中東での紛争が激化し、原油価格が100ドルを超えたらどうなるか」といった分析をしていく、といったものです。
・仮想的なストレステスト
過去のデータや具体的なシナリオにかかわらず、たとえば「金利が1%上がったらどうなるか」といった仮想的な価格変動を想定して分析をします。もっとも、いくら仮想的といっても、あまりに現実離れした想定だと意味がないので、結局は過去の変動データを見て、現実的でかつインパクトが十分に大きい想定をする必要があります。
・過去データによるストレステスト
過去データのうち、現在のポートフォリオに最も重大な影響を与えるデータを使って分析します。過去データを使うという点では必ずしもフォワード・ルッキングではありませんが、そのなかでも最も保守的な計測を行なうことで将来に備えようとするもので、実務的には非常によく利用される手法です。
・リバース・ストレステスト
これ以上の損失が発生すると経営への影響が大きくなるというような損失額を特定し、どのような価格変動が起きればその損失額が発生するかを逆算します。つまり、特定の価格変動で生じる損失額を推定するという通常の計算を逆転させたもので、特定の損失額を生じさせる価格変動を計算しておくことで、実際に大きな価格変動が起きたときにどう対応すればよいかをあらかじめ想定することができます。
これらの手法は、どれか1つやっておけばOKというようなものではありません。結局は決め手がないというなかで、あれやこれやと考えられた手法なのです。したがって、目的に応じて適切な方法を選び、必要に応じてそれらを組み合わせていくことが肝心です。
過去に縛られたバックワード・ルッキングな手法も、このように必要に応じてフォワード・ルッキングな視点を組み合わせることで、より有効なものとなっていくはずです。
この点に限らず、確率統計論には当然のこととしていくつもの限界があります。実際に使用するデータの歪み、計算上の様々な仮定からくる現実との齟齬、そして何よりも将来のことは誰にも正確に予想できないという事実からくる大きな壁があります。ですが、そうした限界や制約を知ったうえで、目的に応じて様々な手段を組み合わせていくことで、確率統計論は真に強力なツールになるのだと思います。
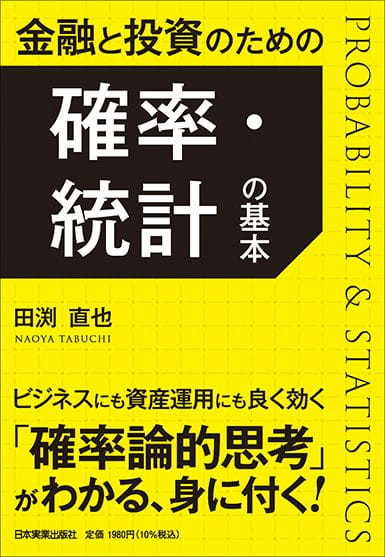
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
