本記事は、田渕 直也氏の著書『金融と投資のための確率・統計の基本』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

モデル、あるいはモデリングとは何か
金融業務では、モデル化(モデリング)という言葉がよくでてきます。モデルは数式で表されるものなので、モデルと聞いたとたんにむずかしくて理系の人向けの話という印象を持つ人も多いのですが、実際にはそれほどむずかしいものはまれです。
具体的には、市場価格の変動などリスクやリターンをもたらす様々な変動要素を単純化して、模式化したものがモデルです。模型、といってもいいでしょう。モデル化、モデリングというのは、この模型をつくる作業のことです。何のためにそんなことをするかというと、そうすることで市場価格の変動などをよりよく理解し、より簡単にコントロールできるようにするためです。
たとえば、ある銘柄の株価などの変動をただそのまま眺めていても、意味のある分析をすることはむずかしいでしょう。
ある日A銘柄は上がってB銘柄は下がった、次の日は両銘柄とも上がった、といった事実の羅列だけではたいした情報にならないのです。
でも、それら市場価格のあいだに何らかの相関関係があるとしたらどうでしょう。あるいは、それら市場価格の変動の背後には隠れた共通の変動要因があるとしたらどうでしょう。
そうしたことを知ることができれば、市場価格の変動によってもたらされるリスクの特性をよりよく理解できるはずですし、リスクをコントロールする手段もいろいろと考えられるようになるはずです。
模型は、あくまでも現実の動きを単純化したものです。ですから、思いっきり単純化してものすごく簡単なものをつくることもできれば、より精緻に現実の動きを再現することを目指して複雑なものをつくることもできます。
複雑であれば良いモデル、ということではありません。複雑なモデルは、きちんと作動するために様々な下準備をする必要があり、それがあやふやだとうまく機能しません。それに、モデルは何らかの目的を持ってつくるものですから、どのようなモデルを用いるべきかはすべて目的次第なのです。
モデルがどのようなもので、どのようにつくるかということを理解するために、最も簡単なモデルのひとつである市場モデルというものを取り上げていきます。これは、ある資産の価格変動を、その資産が属する市場全体の動きで説明しようとする非常に単純化されたモデルですが、これを使うことによって、その資産価格の変動リスクを市場全体の動きに連動する部分とそれ以外の部分に分解することができるようになります。
例として、ソニー株の変動をこの市場モデルによって表現することを考えていきます。
まず、ソニーの株価はどのような要因によって変動すると考えられるでしょうか。もちろん、これにはいくつもの切り口を考えることができるでしょう。たとえば為替相場の影響も受けるでしょうし、米国株の動向の影響もあるかもしれません。どのような切り口で分析をしたいかによってモデルのあり方も変わってくるのですが、ここではソニー株の変動が日本の株式市場全体の動きに影響を受けると考えてみます。
これは決して不自然な考え方ではないでしょうし、ソニーだけでなく様々な日本企業の株価にも広く影響を及ぼしそうな要因といえるのではないでしょうか。
ある企業の株価がその企業の業績見通しに大きく左右されることは当然ですが、それだけでなく、株式市場全体のムードが好転すれば、その企業の業績見通し自体に変化はなくても株価は上がりやすくなるはずです。加えて、多くの企業の業績は経済状況全般の影響を受けるはずですから、景気が良くなり、株式市場全体が上がっているときには、様々な企業の業績も良くなって、そのことを通じても各社の株価が上がる可能性は高まります。
つまり、市場全体の動きが個別企業の株価に、程度の差はあっても何らかの影響を与えていると考えられるわけです。
そこで、各銘柄の株価の動きは、全然バラバラに動いているわけではなく、その一部が市場全体の動きに連動していると考えます。市場全体の動きは、ここではTOPIXで表すことにしましょう。このTOPIXが与える影響度合いは、銘柄ごとにそれぞれ異なるでしょうが、すべての銘柄に共通する株価変動要因です。もちろん、それだけで各銘柄の株価変動を説明できるわけではないので、各銘柄の株価変動は、TOPIXから影響を受ける部分と、それ以外の銘柄固有の変動部分の合成として表現されます。こうして、すべての銘柄の株価変動は、同じモデルで記述できるようになります。
こうしてできあがったモデルが、市場モデルと呼ばれるものです。
どうでしょう。モデルをつくるといっても、かなりざっくりとした考え方にもとづいて、ずいぶんと単純化していることがおわかりでしょう。でもこれで、個々の銘柄の価格の動きを、同じ視点から捉えなおすことが可能になったのです。
あらためて整理すると、市場モデルでは各銘柄の期待リターンを、市場全体の変動に連動する部分から生まれる期待リターンとそれ以外の各銘柄固有の変動部分から生じる期待リターンの合計として捉えます。後者の各銘柄固有の変動部分から生じる期待リターンは、一般にα(アルファ)という記号で表します。一方、前者の市場全体の変動に連動する部分から生まれる期待リターンは、市場全体の期待リターンに、各銘柄が市場全体の変動にどのくらいの割合で連動するかという率を掛けたものになりますが、この市場全体への連動率を一般にβ(ベータ)という記号で表します。
個別銘柄の期待リターン=α+β×市場全体の期待リターン
ということですね。
これらαやβという記号は、株式運用の世界ではごく一般的な用語として使うことができます。たとえば、「アルファを狙え」といえば、市場全体の変動にかかわらずにリターンが上がるような銘柄を探せということになりますし、「ベータを高めよう」といえば市場全体の動きに対する連動度合いが大きい銘柄に投資していこうという意味になります。
モデルの上ではαやβの値は銘柄ごとに固有の定数として扱われますが、ではその値はいくらなのかというと、市場モデル自体はその答えを用意してくれないので、自分で値を求めなければいけません。こうしたαやβなどはモデルのパラメータと呼ばれるもので、したがってその値を特定する作業はパラメータ推定と呼ばれます。
つまりモデルづくりは、まずどのような切り口でモデルをつくるのか(各銘柄に共通する要因に何を選ぶのか)を考え、次にモデル式のなかのパラメータ(αやβなど)の値を推定していく、という手順を踏みます。ではパラメータ推定は具体的にどうするかというと、過去の値動きに当てはめて、最もしっくりくるような値を求めるのです。
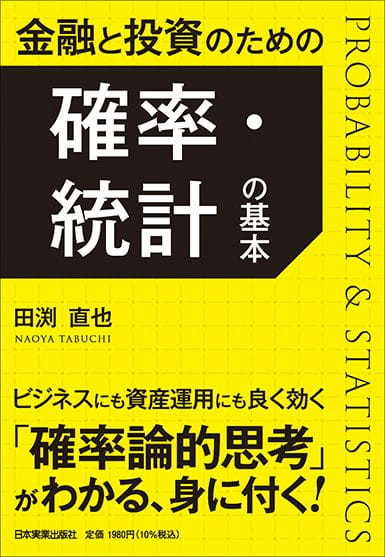
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
- 28.2%の幻想と10.4%の現実、株式投資における期待リターンの捉え方
- ボラティリティとは何か? 期待リターンの裏に潜むもう1つの真実
- なぜ確率は「山の形」になるのか? 正規分布と中心極限定理
- ひとつのかごに卵を入れない、分散投資の知恵
- 株価はなぜ動く? 市場モデルで解き明かす「リスク」の正体
- 「VaR」が金融を変えた! リスク管理の常識を覆した革命とは
- 「過去は未来を保証しない」ブラック・スワンに備える思考法
