本記事は、濱本 志帆氏の著書『リーダーの傾聴 なぜ、部下の不満に気づけないのか』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

不満を聞くときの5大NG行動
社員の話を聴く。それは意外と難しいことです。いわゆる傾聴の難しさは、聞き手が「聴く」だけに徹することができずに、つい、どうしても聞き手発信のアクションを起こしてしまうところにあるのかもしれません。
そこで本項では、ヒアリングの場面で社員に不満を話してもらうとき、多くの人が陥りがちな失敗をまとめました。なんとか社員に不満を話してもらおうとするヒアリングの場面において、やってはいけない5大NG行動をご紹介します。
NG行動① アドバイスをする
まずやってはいけないことは「アドバイス」です。社員からアドバイスを求められている場合は別として、まず聴く段階では、本当にただ聞くだけで十分です。
一度のヒアリングで、社員が本音まで話してくれるかは分かりません。まずは、何が起こっているのか知るところから始めます。
ところが、問題解決を焦るあまりか、あるいは何かうまいことを言っていいところを見せたいと思ったのか、つい求められてもいないアドバイスをすることがあります。
特に、何とかしてあげたいという思いの強い方は要注意です。よく言われる「良かれと思って」というやつです。相手のためにアドバイスをしたつもりのときほど危険です。
「良かれと思って」は、多くの場合は聞き手の思い込みのため、期待に応えたつもりのアドバイスをしても社員が感謝することはなかなかありません。それどころか、上司に忖度した社員に感謝のふりをさせることになったら目も当てられません。「これじゃ話しても分かってもらえない」と感じ、話すのをやめてしまいます。
この段階ではひたすら聴くことに徹して、アドバイスは、最終的にフィードバックをするときに伝えます。
NG行動② マウントを取る
マウントとは、自分のほうが優れていると誇示する態度を見せることです。
上司が「まだ若いから分からないだろうけど」と暗に社員の経験不足を指摘したり、「自分なんてもっと大変だった。でもこうやって乗り越えてきた」と語ったりする自慢話を挟まれると、自分の不満が軽視されているように感じ、何も話したくなくなります(ちなみに、上司本人は「参考になる経験談」のつもりで話していることがあります)。
自分自身に置き換えてみても、相談しているときに自慢話が返ってきたら、それ以上話す気持ちにはなりませんよね。
考えてみれば、部下を相手に優位に立とうとすること自体、無意味ではありませんか。初めから上司であるあなたのほうが優位にいるのですから。
NG行動③ 言質を取る
言質を取るとは、後で証拠として使えるような発言を言わせることです。
例えば、社員に辞めてもらいたいが解雇はリスクがあるため、自己都合退職を申し出るように仕向けることが一部の会社で行われています。このように、聞き手の側に話を聴く前から結論が決まっている場合、言質を取る行為が起こりやすいです。
しかし、聞き手が求めている答えを言わせる目的のヒアリングは、ヒアリングとは呼べません。聞き手のそういう意図は、相手に伝わってしまうものです。「こっちが何を言っても結論は決まっているのだろう」と思わせてしまいます。
あるいは、本人がそのときは気がつかなくても、後になってから「不利な内容に同意をさせられた」と言ってトラブルになることがあります。ヒアリングでは、先入観なくフラットな状態で相手の話を聴きます。
NG行動④ 論破する
論破、つまり相手を言い負かす行為もヒアリングの場においては無用です。
上司から見て、社員が抱える不満や問題がどれほど間違っていると思っても、「この人は、そう思っているのだな」といったん受け止めます。
間違いを正すのは、ヒアリングの場ではなく別の機会にフィードバックとして伝えます。不満を1つ聞くたびに間違いを正していたら、口を閉ざしてしまいます。
せっかくのヒアリングの機会。ほかに抱えていることはないかできるだけ聞いておきたいものです。相手にしゃべってもらってナンボのヒアリングです。
NG行動⑤ 恩着せがましい
なかなか話そうとしない社員に対して、「せっかく聞いてやろうとしているのに」と、ちょっとイラついた様子の先輩や上司がたまに見受けられます。口に出して言わないまでも、そうした態度を無意識のうちに見せてしまっていることもあります。
何のためのヒアリングなのか、目的を思い出してください。
社員が不満を溜めて問題社員に変わる前に、上司が不満を聞き出してフォローすることで、離職やトラブルを回避する。それは上司の評価にもつながり、会社への貢献となります。ということは、上司にとってもメリットがあるのです。
ここは、聞き手が謙虚であるべきです。ミッションは、不満を聞き出して承認欲求を満たすこと。これを恩着せがましい態度で遂行するのは不可能です。
ちなみに、最初のヒアリングで結論を出そうとする必要はありません。まずは情報を集めて、必要に応じて取るべき対応を協議して、対応が決まったらフィードバックします。
事案の軽重にもよりますが、一度のヒアリングで終わらせようと思わなければ、NG行動に気をつける余裕も生まれるというものです。
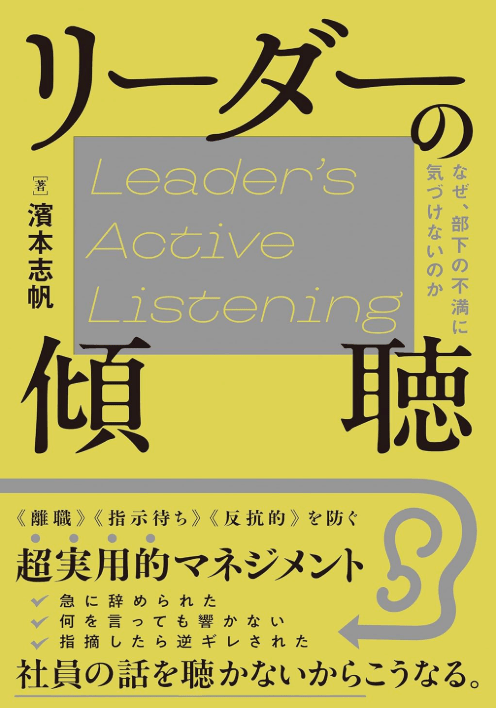
職場でのパワハラ・セクハラや月100時間以上のサービス残業、労災隠し、不当解雇を経験したことから、「会社が労働者を大切にできるための支援」を志し、社会保険労務士資格を取得。
顧問業務を行いながら、会社と労働者のトラブル解決に携わる過程で、本来的に職場トラブルを防ぐ方法を考えるようになる。
その後大学院に進学し、組織心理学とトラブル発生のメカニズムを研究。MBAを取得。大学院での研究と実務経験から、問題行動の背景には処遇に対する社員の不満があり、その8割は「不満を聴く」ことで解消していることに気づく。
これを紛争解決に取り入れたところ、多くの困難事例を早期解決できるように。
現在は特定社労士の試験でグループ研修のグループリーダーを7期務める。
裁判になる前に職場トラブルを早期解決する実務家として15年の経験をもとに、特定社労士実務家の育成セミナーや、企業内ハラスメント研修、経営者向け研修など講師実績も多数。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
- 不満を聴けば、社内トラブルの8割は解消できる
- 不満を聞くときのNG行動5つ
- 「黙って辞める社員」... 不満が離職に直結する理由
- 不満を話してもらうために必要なこととは
- 部下の本音を引き出す「レッテルを貼らない」対話法とは
