● 来年の金融環境は近時稀にみるものになるだろう。日米欧の3地域で唯一現在の金融緩和をほぼ維持するとみられる。過去もこのような環境下では、90年代の金融危機時を除き、好景気が持続した。
● こうした環境に加え、折からの人手不足がデジタライゼーション投資や経営効率化に拍車をかける。賃金をじわじわと押し上げ、個人のセンチメントの改善や消費の拡大を促すだろう。
● 景気拡大を反映し、年後半から長期金利が上昇し始めるだろう。特に恩恵を受けるのは銀行株。国際規制強化の終息を受け、株主還元や投資も積極化へ。年後半の上昇が期待される。仮想通貨は、G20で初めて議論される可能性が高い。主要国の規制の動向がカギとなるだろう。
2018年の金融政策:稀にみる好環境
2018年はリーマンショックから10周年に当たる。というと不吉な感じもするが、まだ当面、金融環境は良好に推移するとみている。
とりわけ日本については、日米欧の主要3地域で唯一、金融緩和を続けざるを得ない。2018年は米国に続き欧州も金融政策の正常化に舵を取り、欧州も1月から資産購入を減少させ、段階的な金融政策の"出口"が模索される。これに対し日本は、インフレ率の低迷に加え、9月の自民党の総裁選や、18年中に決定する19年10月の消費増税の問題があり、好景気・株価維持のためにも超緩和策を続けざるを得ないだろう。
日本の金融政策は米国等に遅れる傾向があるが、これほど長期に亘り日本が引き締めに向かう米欧を尻目に緩和を継続したのは、87~90年代、90年代、04~07年に各数年間あっただけだ(図表1)。90年代の金融危機を除き、いずれの時期も緩和マネーが資産価格を上昇させた。
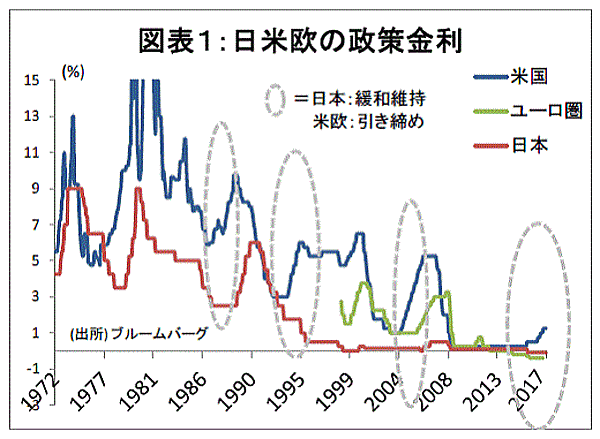
今回も、他国の方向と異なる、緩和的な金融政策の維持が、設備投資を刺激し、円安傾向を維持させることが、企業収益や資産価値にプラスに働くとみられる。
企業収益も一段の拡大へ:デジタライゼーションの本格化
企業収益の上昇も続くとみられる。企業の支払い金利は史上最低で、経常利益の押し上げに一役買っている。金利は少なくとも来年前半までは低位で推移すると予想され、かつ、徐々に金利先高感が出てくることから、設備投資が積極化されるだろう。
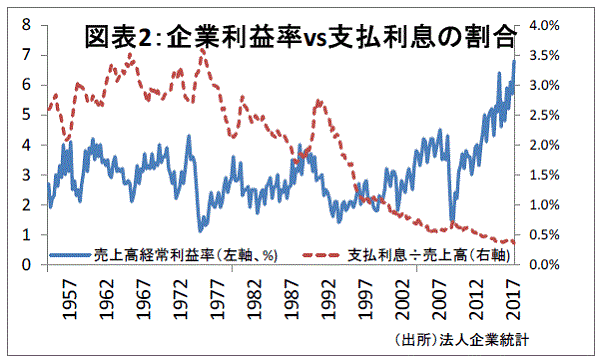
また、デジタライゼーションが企業の利益率を一層押し上げるだろう。これまでも、短期的なITブームは経験したが、今回の流れは、過去と2つの点で大きく異なる。まず、センサー、音声認識、AI、ビッグデータ解析など、様々な技術の進化により、格段に実用化されやすくなった点だ。もう一つのポイントは、深刻化を増す人手不足である。これまで日本では、従業員を解雇するのは難しいことから、たとえ非効率でも人員数を維持し、機械化が遅れてきた面がある。しかし有効求人倍率は上昇し続けており、これまではさほどでもなかった事務系の分野までもが人手不足に陥りつつある。来年は企業はこれまで以上にデジタライゼーションに取り組まざるを得なくなるだろう。
なお、バブル末期の80年代末から90年代初頭にかけて、人手不足による企業倒産が年々倍増し、その後の景気後退の一因となった。"人手不足倒産"という言葉が生まれたのもその頃である。しかし、今回は、むしろ人手を補うデジタライゼーション推進の原動力となり、中長期的な企業の生産性向上に繋がるだろう。
消費者センチメントの改善が続く
これらの企業収益の拡大で、賃金もじわじわと上昇してくるだろう。これに加えて、株価や地価などの資産価格の上昇などの効果で、一層の回復が見込めるだろう。
また、個人消費も緩やかな改善が続くとみられる。現在、消費者信頼感指数は日米欧揃って改善している(図表3-1)。しかも、欧米が過去最高を記録する中、日本ではまだ2004~07年のピークに到達しておらず、環境面を考えても一層の改善が期待できる。また、弊社の個人投資家サーベイでも、家計を引き締めている人の比率が、まだ低水準ではあるものの、徐々に増加している(図表3-2)。
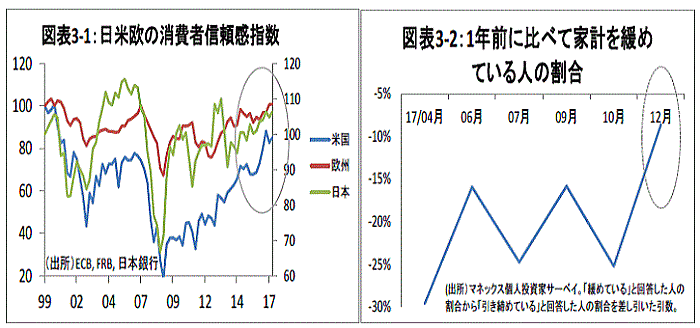
消費者信頼感指数の改善が続けば、2018年は個人消費も拡大が見込めるだろう。特に、近時の女性のいわゆるM字カーブの緩和(=女性の産後の離職率の減少)で、時間がない分、短時間で豊かな気持ちになれるような、新たなコト消費(たとえば外食、旅行、趣味等)等が拡大するとみられる。
長期金利:前半は低位推移、年後半に上昇へ
2017年中の日本の長期金利は、日銀のイールドカーブ・コントロールもあり、想定通り低位0~0.1%のレンジで推移した (図表4)。一方米国の長期金利は想定よりは低位に留まった。景気への見通しに対する慎重な見方が早めに意識された印象である。
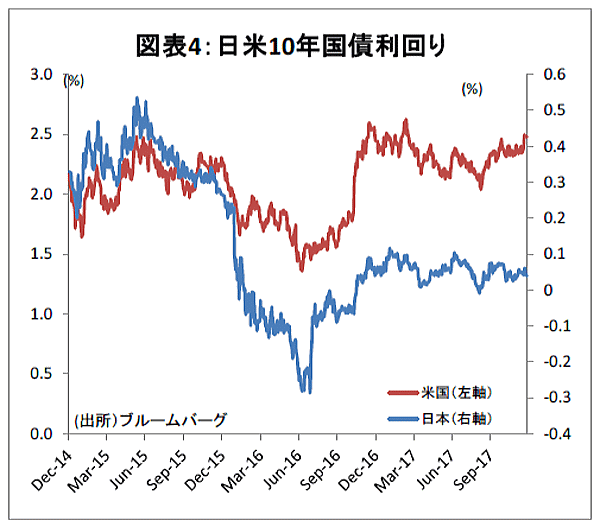
結果として米国のイールドカーブのフラット化が進み、長短金利が逆転する「逆イールドカーブ」が懸念されるようになってきた。しかし、2018年の政策金利の引き上げは、現在想定されている「3回」に対し、やや下振れする可能性がある。パウエル新FRB議長以下の新メンバーの下、金融政策運営は、景気動向をみながら極めて慎重に行うとみられる。このため、逆イールドの発生は2018年内ではなく、早くとも2019年以降となると考える(図表5)。
なお、通常、逆イールドが発生してからも、その後1年~2年間はダウ平均は堅調に推移する。米国で検討されている金融市場規制の緩和で、ピークの半分に落ち込んでいる米国の上場企業数の復活が期待される。これらのシナリオを前提とすれば、米国の株価は、今年に比べて勢いは落ちると思われるものの、引き続き底堅い動きを続けると予想される。
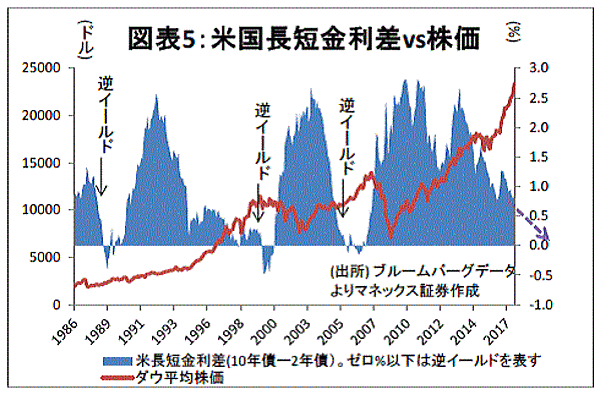
日本の政策金利は、黒田総裁の後任が誰になろうとも、現在のマイナス金利政策は維持されるだろう。物価上昇率はまだ低く、米国ほど資産価格の上昇も問題になっていないためだ。一方長期金利については、来年後半頃には、イールドカーブ・コントロールの操作対象を10年から5年に短縮し、若干引き上げる動きが出る可能性がある。金融機関の国内の預貸収益は低下の一途を辿っており、日銀に対する業界や政府からの批判が強まる可能性があるためである。
従って、年後半からは、じわじわと長期金利は上昇に向かい、銀行株は本格的な上昇局面を迎えるだろう。
世界の住宅価格上昇は減速へ
2017年も前年に続いて世界の住宅価格は上昇を続けた(図表6)。米国や欧州の主要国では、借家人の権力が強い日本とは異なり、物件価格とともに賃料も上昇しており、実需を伴う値上がりであり、不動産価格バブルとはいえない。
しかし、低金利を続けている北欧、カナダ、豪州等で価格の上昇が著しいことから、やはり緩和マネーの恩恵を受けていることも事実である。このため、2018年以降、金融政策正常化の効果の現れとともに住宅価格の上昇は徐々に沈静化していくだろう。
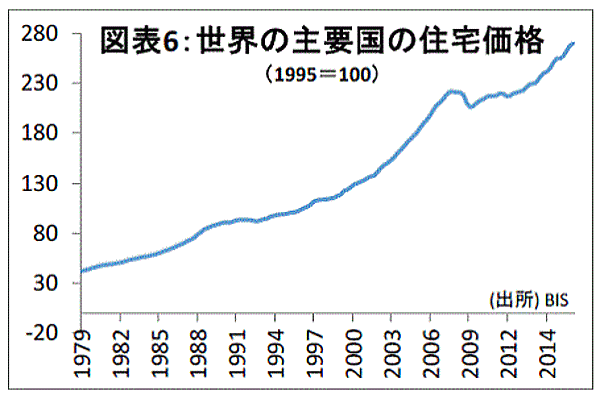
仮想通貨:ICOによる利用拡大。G20で方向性を議論へ
今月16日以降、仮想通貨の価格は下落し始めた。しかし、依然として年初からの価格上昇率は高く、ビットコインで14倍、その他のオルトコインでは450倍となっているものもある(図表7)。
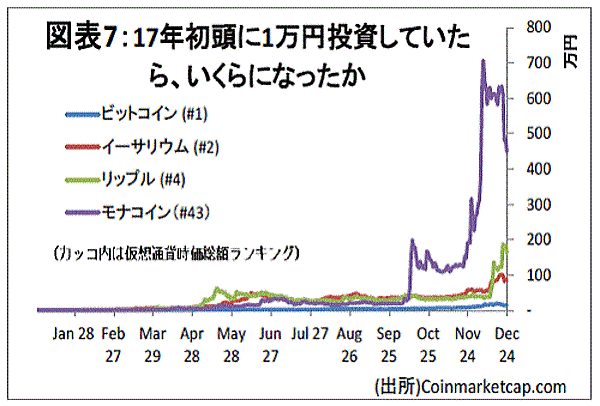
現在、仮想通貨は1380種類が発行されており、その種類は日々1~3程度増加している。2018年もこの傾向が続くだろう。
この背景にあるのは、ICOの活発化である。2017年11月までに世界で4,000億円がICOで調達され、引き続き発行を計画中の企業も多い。また、エストニア、トルコなどでは、政府が独自の仮想通貨を発行する計画を発表している。
ICOの発行は、既存の株式を希薄化することなく資金調達できる。また、発行体からみると「売上」と扱われるとみられ、一時的な業績の上ブレ要因になる可能性がある。日本でも既にフィンテック企業で発行が相次いでいるが、それ以外でも、12月12日にはシノケングループ(8909)が「シノケンコイン」の発行を発表した。将来的に入居者が家賃等の支払いに使えるようにするという。
一方、仮想通貨の価格動向については、主要国の規制の方向性がカギとなる。ロシアや欧州主要国が年末年始に新たな規制案を提示する見込みである。更に、2018年のG20(日程は未定)で議題の一つとなる可能性が高い。先進主要国では、まだ中国のように仮想通貨取引を禁止した国はない半面、欧州の小国のように自国の通貨発行検討などの支援を表明した国もない。2018年の仮想通貨価格は、こうした主要国の規制の出方次第とみられる。
しかし、いずれにしても、現在の金融システムは極めて非効率である。例えば、世界各国には合計300万台ものATMが設置され、年間数兆円規模の運営費がかかっているとみられる。外貨送金も1件当り1万円近くの手数料がかかり、かつ一回当りの送金額にも上限が設けられている。
このような非効率性は長期的には何らかの技術で刷新されるだろう。その手段として、現時点で最も近い場所にあるのが、仮想通貨の基盤であるブロックチェーンの技術である。代替技術の開発には相当の時間がかかると見られるため、当面は、現存の技術の中でハッキング対策や処理速度等に優れており、使い勝手が良いものが選別され、実用化に向けての試作が進められるだろう。これらが政府の支援を受け、人々の信任を得られれば、再び投資家の人気を集めることになるだろう。
大槻 奈那(おおつき・なな)
マネックス証券 チーフ・アナリスト
【関連リンク マネックス証券より】
・2018年の投資環境 世界経済の拡大続く 死角はないが「もしもは起こる」と考える 市場の変動性自体がリスク
・日経平均が2万3000円の大台に乗せて今年を終えることができるか
・2018年は「3」がキーワード...来年の日本経済に注目
・年末年始の日米株価の動きはどうなる?
・日経平均反発 来週の掉尾の一振を期待させる終わり方