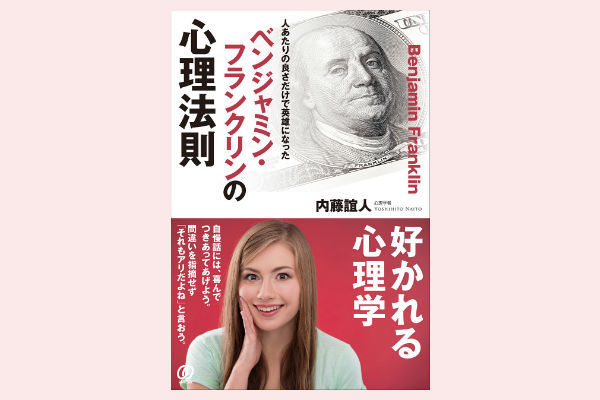(本記事は、内藤誼人氏の著書『ベンジャミン・フランクリンの心理法則』ぱる出版、2018年6月18日刊の中から一部を抜粋・編集しています)
【『ベンジャミン・フランクリンの心理法則』シリーズ】
(1)人たらしがやっているカンタンなテクニックとは?
(2)なぜお金持ちほど自分にお金をかけないのか
(3)「議論しろ」はあまり良くない風潮?フランクリン流「人たらし術」
(4)資産2兆6千億を築いた大富豪が特に気をつけていたこと
常に腰を低くして対応する。
ウォルマートの創業者にして、大富豪のサム・ウォルトン。
1992年に亡くなったとき、彼は2兆6千億円もの個人資産を残したという。
彼は、従業員をとても大切にし、店員を「アソシエーツ」(仲間たち)と呼んでいた。
サムは、もともとお金持ちになりたかったわけではない。
人あたりがよくて、気づいたらお金持ちになっていた、というのが事実に近い。
もともとスーパーマーケットチェーンのウォルマートも、サムが、都会に買い物に行くついでに友人の頼みごとを聞いてあげることからスタートした。
都会でほしいものをまとめて買ってきてあげて、並べているだけのお店だったのだ。
「都会に行くんなら、こんなのもついでに買ってきてくれ」という友人のお願いを、ホイホイと聞いているうちにお金持ちになってしまったのである。
サムは、とても腰が低かった。
そんなサムのことを嫌う従業員は一人もいなかった。みなサムが大好きだった。
そんなサムが気をつけていたのは、とにかく常に腰を低くすること。
キングズ・デパートの社長であるウィリアム・F・ケネディはサムについてこう語る。
自己紹介に際してサムは自分を、アーカンソーから来た田舎者ですといってたね(『サム・ウォルトン』NTT出版)。
サムは、全米一の資産家となってからも見栄を張ったり、偉そうに振る舞ったりはしなかった。常に質素でありつづけることを選んだ。
それは自家用車がオンボロのトラックだったことでもわかる。
これほどの財産を手にしていれば、ヨットでモンテカルロの輝く陽光を浴び、ランボルギーニのスポーツカーを乗り廻し、王様のような暮らしを送ることもできたはずだ。
ウォルトンは、ひとつとしてそんなことはしなかった。ピック・アップ・トラックが一台と、ガレージに埃をかぶったシヴォレーのセダンがあるだけだ(『サム・ウォルトン』NTT出版)。
好かれるコツは、とにかく腰を低くすることである。
謙虚な人を嫌う人はいない。
カリフォルニア州立大学のマイケル・ロビンソンは、「自慢する人」のプロフィールと「謙虚な人」のプロフィールを作って人に与える印象を調べて、謙虚な人のほうが「正直者」で「好感」を与えることを明らかにしている。
いつでも低い心を持とう。そうしていれば、周りに人がどんどん寄ってくる。
他の人と違うことをしない。

サムは、航空会社の飛行機で旅をするときには、エコノミークラスにしか乗らなかった。
なぜかというと、社員がみなエコノミークラスを使っているからである。
サムには、「社長なんだから」という理由は通らない。他の人がやっていることには、自分も合わせるのが当然だと思っていた。
サムには、次のようなエピソードもある。
サムは、こと仕事のこととなると、どんなときも贅沢をしようとしない。
バートン・ステイシーといっしょに出張に出かけたとき、ステイシーがレンタカーを借りに行った。サムはその車をキャンセルさせた。
「サブコンパクト(小型車より小さい)以上の車をサムは借りようとしないのです」とステイシーは語っている。
「サムは、社員ではとても行けないような場所には行こうとしません。社員より良いホテルに泊まろうとしません。社員の行くレストランより高級な場所で食事をしようとしません。
社員より良い車に乗ろうとしないんです」(『サム・ウォルトン』NTT出版)。
日本の少し大きな企業にでもなれば、重役は平社員が行けないようなお店ばかりでお酒を飲んだりするのが普通である。
「自分は重役なんだから、これくらいの待遇は当然」と考えてしまうのであろう。
まったくサムの考えとは反対だ。
サムは、アソシエーツ(仲間たち)と同じことをする。だから、アソシエーツもサムのために頑張って働く。
もしサムが、自分は社長なんだぞと偉ぶってみせたりしたら、社員たちも働くのがバカバカしいと思ったであろう。
社長も重役も、他の社員と同じことをしていれば、社員たちは「自分は公平に扱われている」と感じる。これが仕事へのモチベーションになる。
社長や重役だけがおいしい思いをしていて、自分たちは不当に扱われていると感じたら、社員は「手抜き」によって復讐しようとする。
スイスにあるバーン大学のノーベルト・セマーによると、私たちは自分が不当な扱いを受けていると感じると、会社の備品を盗んだり、意図的に仕事をサボったりすることなどによって、「公平感」を取り戻そうとするらしい。
この気持ちは、人情としてよく理解できる。
人たらしは、他の人と違うことをしない。
職場の人たちが2万円くらいのスーツを着ていれば、自分もそれくらいのスーツを着るのであって、1人だけ100万円もするスーツを着ることはない。
職場の人たちが安いランチですませているのなら、自分もそうする。
人と違うことをしてもいいことは何もない。
職場の人たちがどんなことをしているのかをよく観察し、そこからなるべく外れないようにするのがポイントだ。
相手を「家族」だと思え。
私たちは、自分とは無関係な人に対してはいくらでも冷たくなれる。
私たちが、思いやりや愛情を注げるのは家族や親切など、身内に対してだけである。
ドイツにあるフンボルト大学のフランツ・ネイヤーは、「血は水よりも濃い」というのは正しく、私たちは身内に対して一番のつながりを感じると指摘している。
人に親切に振る舞いたいのなら、「他人」という意識を持つのではなく、「家族」や「身内」という意識を持つといいだろう。
この人は、私のお兄ちゃんなんだと思えば、素直に言うことも聞けるだろうし、この人は私の妹なんだと思えば、口汚くののしったりできなくなるであろう。
血がつながっていなくとも、家族のようなものだと思えば、失礼なこともしなくなるのだ。
ウォルマートは、トップから底辺までみな”家族”なのだ。本社では家族という集団のなかでだれもが平等だ。みな、互いにファースト・ネームで呼び合う。
とりわけサムはそうしていた(『サム・ウォルトン』NTT出版)。
サムが、職場のスタッフから好かれたのは、「家族」という意識を持って接していたからであろう。家族だと思っていたから、サムは思いやりにあふれた接し方が自然にできたのである。
考えてみると、業績のいい日本企業は、たいてい「家族的な雰囲気」があるものだ。組織というよりは、むしろ家族である。
お父さんがいて、お母さんがいて、お兄さん、お姉さんがいる、というように家族的な雰囲気の会社のほうが、業績がいいのである。
お互いに名前も呼び合わず、重苦しい雰囲気の会社では、社員がお互いに「他人」だと思っている。どうせそのうちに転職してしまうのだから、そんなに深くつきあう必要もないだろう、とお互いに思っている。
こういう会社が業績を上げるのは難しい。
心理的に、身近な人を自分の家族だと思い込むのはいい方法である。
私も、自分の大学の教え子たちは、本当に自分の息子であり、娘であると思って指導しているから、自然にやさしくなれる。
「この子たちが社会に出てから、立派に巣立てるように」と思えば、手抜きもできず、頑張って指導する気持ちになれる。
部下や後輩の指導がうまい人は、たいていそうだと思うのだが、意識としては「家族」に近いものを相手に感じて接することができる人である。
家族なのだと思えば、「他人」に接するときのような冷たい態度はとれなくなるものだ。
内藤誼人(ないとう・よしひと)
心理学者。立正大学客員教授。慶應義塾大学社会学研究科博士課程修了。アンギルド代表取締役。社会心理学の知見をベースに、ビジネスを中心とした実践的分野への応用に力を注ぐ心理学系アクティビスト。近著に、『アドラー心理学あなたが愛される5つの理由』『羨んだり、妬んだりしなくてよくなるアドラー心理の言葉』『人は「心理9割」で動く』(以上弊社刊)、『ヤバすぎる心理学』(廣済堂出版)、『人前で緊張しない人はウラで「ズルいこと」やっていた』(大和書房)、『図解身近にあふれる「心理学」が3時間でわかる本』(明日香出版社)などがある。