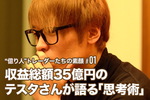投資信託とは「投資を信じて託す」ものであり、あくまでも主人公は投資家自身だからこそ、これまで数回にわたり「信じる」をキーワードに話を進めてきた。いうまでもなく「信じる」とは誰かに強制されるものではなく、能動的な判断であるべきだ。従って、その結果責任についても「自己責任」と考える必要がある。そこで、前回のコラムでは、まずは「信頼できる相談相手」を見つけてほしいとお伝えしたが、今回からは適切な投資信託選びの具体的な議論として「どんな投信会社を選ぶか?」について論じてみたい。
もし本当の意味で投資家が「信じて託している」のなら…
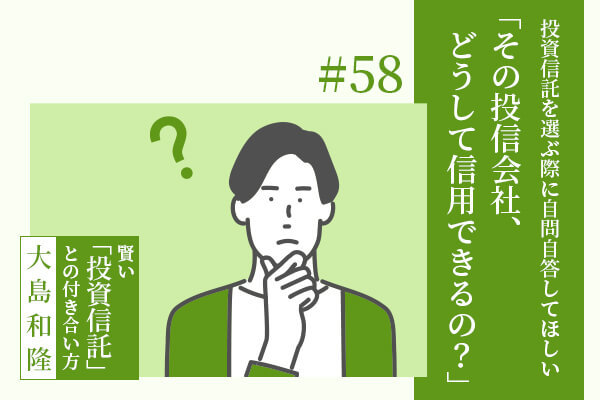
投信会社は自社の投資信託の基準価額が前日比で5%以上下落した場合、当該投資信託の「臨時レポート」を発行しなくてはならないことは以前にもお伝えした。そして販売会社も当該投資信託を保有するお客様に連絡し、「臨時レポート」が発行されていること、そしてその内容を説明しなければならないことをお伝えした。ただ、もし本当の意味で投資家が自分自身にとって適切な投資信託を選んで「投資を信じて託している」のならば、いちいちそんな連絡をする必要はなかったはずだ。通り一遍の運用コメントでしかなく、定型的な結文として「(略)しかしながら、○○○○なことから市場は早晩回復してくると思われます。引き続き基準価額の向上に最善を尽くして参る所存ですので、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます」と締め括られる「臨時レポート」などを読まされても、投資家側は寧ろ不安が加速するだけだろう。ましてやそんな連絡を受けても通常投資家としては「もう解約してください」と言うか、「保有し続けます」と言うかの選択肢しかない。
だが、そもそもそんな状態からのリカバリーなども含めて「投資を信じて託している」のだから「小さな親切、大きなお世話!」と思えるような世の中ならば問題なかった。しかし、現実には基準価額が前日比5%以上下落した場合、投信会社は「臨時レポート」を作成するのが義務となった。その真意は「基準価額がいつの間にかこんなに下落していたなんて知らなかった。一切販売会社から連絡もなかった。もし連絡があれば、途中で解約しており、ここまで損失は膨らまずに済んだ」という主旨の投資家からのクレーム、最悪のケースは損害賠償請求を回避するための金融機関側の証拠づくりに他ならない。
ただ投信会社は臨時レポートだからと言って「本ファンドの投資の基本方針に沿った最良最善の運用を尽くしても当面は基準価額の大幅な回復・向上は望めず、お客様の大切なご資産の損失が更に膨らむ可能性のほうが高いと思われます。従いまして極めて遺憾ながら可及的速やかに本ファンドは解約して頂くことをお勧めしたいと思います」とは決して言わない。仮に運用サイドが当面は厳しいという見通しを立てた場合でも、それをストレートにコメントすることは投信会社の経営陣も、販売会社も許容しない。世の中は既にかなり拗れていると思う。