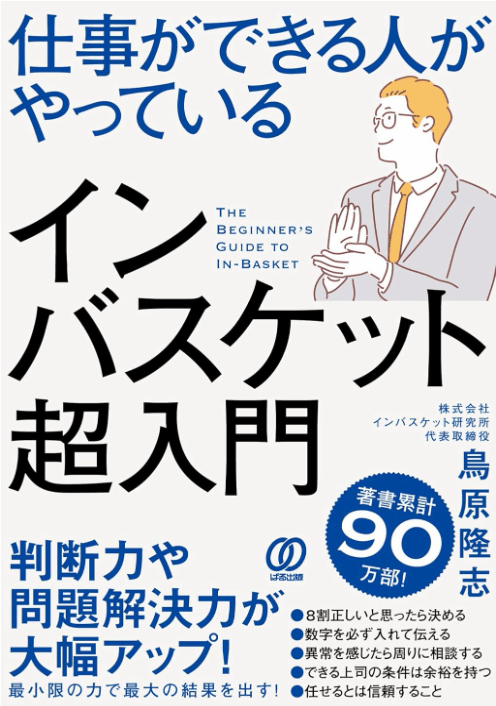本記事は、鳥原 隆志氏の著書『仕事ができる人がやっているインバスケット超入門』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

意思決定のコツ
判断の順番は大きいものから小さいもの
インバスケット問題では、大小さまざまな判断を迫られます。
オフィスの備品発注のような、些細なものから、部署全体の戦略に関わる重要なものまで、多岐にわたります。
時間に余裕があれば、すべての判断を完璧に行いたいところですが、実際にはそうはいきません。
小さな判断に時間をかけすぎると、大きな判断をする時間がなくなってしまい、結果的に、組織全体の目標達成を阻害してしまう可能性があります。
判断は、ストレスのかかるものです。
そのため、すぐにできる小さな判断から片づけたくなる気持ちはよくわかります。
しかし、リーダーに求められるのは、小さな判断よりも大きな判断です。
なぜなら、組織の方向性や業績は、リーダーの大きな判断によって大きく左右されるからです。
インバスケット問題の回答を見ていると、細かな判断は完璧なのに、大きな判断は先送りされているケースがよくあります。
あるいは、時間が足りなくなって、十分な検討ができないまま、判断を下してしまうケースもあります。
このような事態を防ぐためには、判断にも優先順位をつけ、大きな判断から行うことが重要です。
例えば、部署の方向性や戦略といった、中長期的な視点で判断すべきことを、最初に決めてしまいましょう。
そうすることで、後の小さな判断も、大きな方向性に沿って行うことができるので、矛盾や迷いが生じにくくなります。
これは、家を建てるときに、まず基礎工事を行うようなものです。
基礎がしっかりしていれば、家は安定し、長く住み続けることができます。
逆に、基礎工事をおろそかにしてしまうと、家は傾き、倒壊してしまうかもしれません。
インバスケット問題では、大きな方向性を決める意思決定能力も評価の対象となります。
最初に大きな方向性を決めることで、後の判断がスムーズになり、高得点につながるだけでなく、一貫性のある行動計画を立てることができます。
ぜひ、大局を見据え、重要な判断から取り組むように心がけましょう。
- すぐにできる判断は後に回し、難しい判断に取り組もう。
費用対効果で賢く判断!
マネジメント職として、的確な判断を下すことは、組織の成功に欠かせません。
さまざまな判断基準がある中で、今回は「費用対効果」という視点でお話します。
費用対効果とは、かけた費用に対して、どれだけの効果が得られるのかを測る指標です。
例えば、部下から新しい装置の購入申請があったとします。
このとき、承認するかどうかを判断する際に、費用対効果を意識することが重要です。
「その装置は、いくらなのか?」
「導入することで、どのような効果が期待できるのか?」
「効果を金額で表すと、どれくらいになるのか?」
といったことを、具体的に検討します。
もちろん、すべての効果を金額で表すことは難しいかもしれません。
しかし、可能な限り定量化することで、より客観的な判断ができます。
例えば、「作業が楽になる」という効果であれば、「作業時間がどれくらい削減できるのか?」「人件費に換算すると、どれくらいのコスト削減になるのか?」といったように、具体的な数字で表すようにしましょう。
費用対効果を考える際に、注意しなければならないことがあります。
それは、「埋没コスト」です。
埋没コストとは、過去に投資した費用のことです。
例えば、新しいシステムを導入したものの、うまく機能せず、多額の費用を無駄にしてしまったとします。
このとき、「せっかく多額の費用をかけたから…」と、使い続けるのは得策ではありません。
過去の投資は、あくまで過去のものであり、未来の判断には影響しません。
埋没コストにとらわれず、将来を見据えて判断することが重要です。
「費用対効果」は、投資判断を行う上で、非常に重要な指標です。
限られた資源を有効活用し、最大の効果を得るために、費用対効果を意識した判断を心がけましょう。
- 会議や打ち合わせをする際に、どのくらいのコストがかかっているのかを計算してみる。
選択肢は4つに決める
良い判断をしたいと願う人は多いでしょう。
では、良い判断とは、どのようにすればできるのでしょうか?
それは、ずばり、選択肢の数で決まります。逆に、判断ができない人や、判断ミスが多い人は、そもそも選択肢が少ない傾向があります。
例えば、あなたが通販サイトで、ある商品を「買おうかどうしようか」迷っているとします。このときの選択肢は、「買う」か「買わない」かの2つだけです。
これでは、判断に迷ってしまうのも無理はありません。
そこで、「他に選択肢はないか?」と考えてみましょう。
「1日待ってから決める」
「他のサイトで価格を比較してから決める」
「似たような商品を探してみる」
「ポイントが貯まるまで待つ」
このように、選択肢を増やすことで、より良い判断をしやすくなります。
インバスケット問題でも、「A案とB案、どちらが良いですか?」のように、2択で迫られるケースがあります。
しかし、そこで立ち止まって、「他に選択肢はないか?」と考えてみましょう。
「C案」を作ることはできないか?
「A案とB案を組み合わせる」ことはできないか?
「そもそも、この問題は解決する必要があるのか?」
このように、視点を変えることで、新たな選択肢が生まれてきます。
選択肢を増やす際は、「多ければ多いほど良い」というわけではありません。
選択肢が多すぎると、かえって判断が難しくなってしまうことがあります。
これは、「ジャム理論」として知られています。
3種類のジャムを並べた方が、24種類のジャムを並べるよりも、売れるという実験結果があります。選択肢は、4〜5個程度に絞り込むのが良いでしょう。
もし、どうしても選択肢が浮かばない場合は、他者に相談するのも有効な手段です。
自分一人で考えていると、どうしても視野が狭くなり、偏った選択肢しか出てこないことがあります。
「あなただったら、どうしますか?」と、同僚や上司に意見を求めることで、新たな視点を得ることができます。選択肢を増やすことは、判断力を磨くための第一歩です。ぜひ、さまざまな角度から問題を見つめ、最適な選択肢を見つけるように心がけましょう。
- いつもあなたがとる判断と逆の選択肢を作って比較してみる。