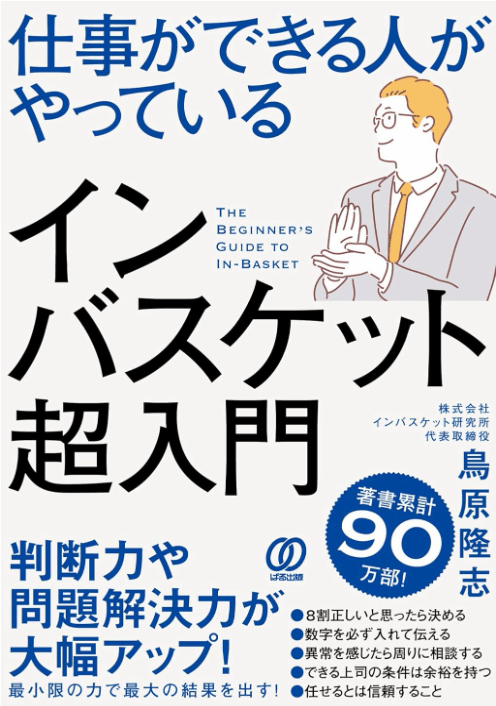本記事は、鳥原 隆志氏の著書『仕事ができる人がやっているインバスケット超入門』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

早く読み理解するコツ
8割ノイズ法を習得する
「どうすれば短時間で多くの情報を理解できるのでしょうか?」インバスケット問題を解くうえで、よく寄せられる質問です。
皆さんは、私がインバスケット問題に取り組む際に、すべての問題を読んでいると思いますか?答えはNOです。そもそも、すべて読もうとする考え方は捨ててください。「すべて読んでいないのに、どうやってインバスケットの回答を書けるのか?」と疑問に思うかもしれません。
実は、私自身もインバスケットを始めた頃は、すべてを読もうとしていました。そのために、速読教室に通ったほどです。
しかし、今は、そもそもすべてを読もうとしていません。なぜなら、情報の8割はノイズだと考えているからです。
インバスケットのコツは、「すべてが大事だと思わないこと」です。渡された情報も、すべてが大事だと思わないでください。
そもそも、インバスケット問題の情報量を全部読んで理解しようとしても、制限時間内にできません。なぜなら、文字数が1万字ほどあるからです。これは、ちょっとしたビジネス書の2割ほどの量です。しかも、インバスケット問題は、他の案件同士が関連したり、数値データなども多く含まれていたりするため、読んで理解しようとすると、数時間かかるでしょう。
だから、すべてを読んで理解しようとする考えは、現実的ではありません。仮に時間内に読んで理解できたとしても、インバスケットは回答を書かないと評価されません。だからこそ、すべてを読んで理解してはいけないのです。
私がおすすめする、早く読み理解するコツは、「すべてを読まなくてよい。2割の文章を読めば、8割は理解できる」というものです。
ビジネス書の多くも、ページの太文字部分や目次を読むだけで、大枠で何が書かれているか理解できるはずです。限られた時間の中で早く読み理解するためには、2割で8割を押さえる読み方が必要です。
実際に、あなた自身も経営者や経営層などの上層部の方が、上の空で報告や会議の発表を聞いているのを見たことがありませんか?これは、彼らがあなたの話の一言一句に聞き入っていないのではなく、ほとんどがノイズだと理解しているからです。彼らは、「8割ノイズ法」を実践しているのです。そして、彼らが結論を聞きたがるのも、理解できるでしょう。
あなた自身も、これから溢れる情報をすべてを把握しようとせず、8割のノイズを省くために、現場での情報処理の方法を変えてみてください。
- 長いメールはすべて見ない。重要な行だけを見つけるようにする。
マーキングをする
インバスケット問題で、状況を素早く理解できる人は、問題用紙を見るとすぐにわかります。
それは、マーキングをしているからです。
マーキングとは、重要だと思う文章やキーワードに印をつける作業のことです。
紙であれば、マーカーやペン、付箋などを使います。
電子書籍リーダーなどでも、マーキング機能があるものがあります。
マーキングをすることで、情報の理解が速くなります。
なぜ、マーキングをすると理解が速くなるのでしょうか?
理由は3つあります。
1つ目は手を使うことで、記憶に残りやすくなるからです。
子どもの頃、漢字を覚えるのに、ただ読むだけでなく、手で書く練習をしましたよね?
手で書くことで、脳に刺激が与えられ、記憶に残りやすくなるのです。
インバスケット問題では、時間がないので、すべて書き写すことはできません。
しかし、マーキングをするだけでも、記憶に残りやすくなるので、理解しやすくなります。
2つ目は、重要な情報を見つける訓練になるからです。
どこが重要なのかを探す癖をつけることで、情報処理能力が向上します。
3つ目は、読み返すときに、すぐに目的の箇所に戻れるからです。
マーキングをしておけば、重要な情報にすぐにアクセスすることができます。
マーキングをしていないと、最初から読み直さなければならず、時間の無駄になってしまいます。
では、どのようにマーキングをすればよいのでしょうか?
まず、1ページに1ヶ所程度にしましょう。
あまりに多くの場所にマーキングをすると、効果が薄れてしまいます。
マーキングは絞る技術です。多くの箇所にマーキングをつけてしまうのであれば、本当にそのマークは必要なのかと自問自答してみてください。
1ページに1か所つけるという自分ルールをつくることもおすすめです。
また、下線などを引く際にも基本は一行にしましょう。
2〜3行もマーキングしてしまうと、どこが重要なのかわからなくなってしまいます。
長い下線を使う方の傾向は文章としてマーキングする方が多いようです。
しかし、文章は前後とつながっていることが多いので、ついつい長い下線を引きがちです。
私は、単語単位でマーキングするようにしています。
具体的には
固有名詞(場所、人名、会社名など)
カタカナ言葉(ステークホルダー、グローバル、アカウントなど)
数字(20%、6月12日など)
は、重要な情報である可能性が高いので、マーキングするようにしています。
これらの情報は、他の案件との関連性に気づくきっかけになることもあります。
最初は、マーキングしても、あまり役に立たないと思うかもしれません。
しかし、マーキングも技術です。
練習を重ねることで、重要なキーワードを見つける力が養われます。
マーキングは、インバスケット問題だけでなく、ビジネスにも役立つスキルです。