本記事は、岡田 祐子氏の著書『ポイントサービス3.0 エンゲージメント時代のポイント戦略』(中央経済社)の中から一部を抜粋・編集しています。

ポイントサービスのコンプライアンス事項
〜法的・会計的留意事項
今まで、ポイントサービスの効果や魅力、今後の企業、社会に与える影響などを述べてきました。いわゆる「攻め」のポイント戦略といえます。
一方、サービス展開にあたっては、法律面や会計面でのコンプライアンス事項における「守り」の対応も不可欠です。特に景品表示法などは、サービス内容に直結する、知っておかなければならない事項といえます。また、会計処理基準に関しては、2021年4月、「収益認識に関する会計基準」に、初めてポイントサービスも視野に入れた新ルールが登場し従前のように一律引当金処理で済ますことができなくなりました。この新会計基準も、どのような場合に適用され、どのような処理になるのかなど、ビジネスの基本として押さえておく必要があります。
ここでは、そのような「守り」のポイント戦略について、わかりやすく説明していきたいと思います。
「ポイント」と呼ばれるものの分類整理と法的・会計的な留意点
一言で「ポイント」や「ポイントサービス」といっても、語っている人が何を指してそう呼んでいるのかは、見極めて整理しておく必要があります。企業や団体が、どのようなサービスを展開するのも自由ですが、法的あるいは会計的な遵守事項やルールは、同じ「ポイント」と呼ばれていても、内容やケースによって全く違っていたりするためです。
ここでは、その「ポイント」の分類と、各々が該当する法律や会計処理の整理を行っていきます。
まず、最初に必ず押さえておきたい分類は、その「ポイント」が通貨扱いなのか、そうでない扱いなのかということです。
(1)分類A:通貨か否か
① 企業がサービスとして提供しているもの⇒通貨とはみなさない
<適用される法律>
・景品表示法
※「ポイント」の交換(利用)先が100%値引きの場合を除く提供できる金額相当の上限値などが定められている
② お金で購入できるもの=通貨とみなされる
<適用される法律>
・資金決済法
※「ポイント」の有効期限が半年以内の場合、基準日未使用残高が1,000万円以下の場合を除くいわゆる「前払式支払手段」とみなされた場合に適用される法律で、未使用残高の2分の1の供託金の預け入れなどの規則がある。一般的には、商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード(いわゆる「電子マネー」)などがこれに該当する。
ここで取り扱っている「ポイント」、すなわち一般的に流布し語られるポイントサービスのポイントは、基本、①であることを前提としています。
②の「ポイント」は、①と区別するため、「コイン」など別の名称を付けられている場合が多いのですが、これもサービス提供者の気の向くままに名付けられているようで、コインと呼ばれていても景品扱いの①、ポイントと呼ばれていても通貨扱いの②の場合があるため、要注意です。ちなみに、②は課金ゲームなどでよく見かけますし、ネット通販などにおいても、チャージなどで購入できる「ポイント」などは、これに該当することになります。
なお、②の場合でも、あたかも通常の①のポイントサービスのように、購入金額のn%付与されたり、アクションでmポイントが付与されたりする場合もありますが、分類の分かれ目は、あくまでお金で(も)購入できるか否かにあります。お金で買える時点で②と判断されるので、注意してください。
ただし、一見お金で買える②に見えても、有効期限を半年以内に設定するなどして、供託金などのハードルの高い資金決済法の適用を逃れている場合も多く、どのような建てつけになっているかで、法律の適用が異なってきますので、そのあたりにも留意してください。
次に、分類A①の「ポイント」について、さらにその「ポイント」が使える(交換(利用)できる)か否かで分類しましょう。
(2)分類B:交換(利用)できるポイントか否か
① 交換(利用)できるポイント
通常の貯めて使えるポイントサービスが該当する。
<法的・会計的に留意すべき点>
100%値引き利用のケース以外は、景品表示法が適用される。また、会計処理においては、購入金額に付随する付与の場合は、「収益認識に関する会計基準」(新会計基準:2021年より上場企業強制適用)が、購入金額に付随しない場合は、一般的に引当金処理が適用される。
② 交換(利用)できないポイント⇒指標値としてのポイント
ポイントは貯まっていくが、単なるスコアのような指標値として用いられるだけで、使う(交換(利用)する)ことができないポイント。具体的にはステージ(ランク)制の指標値として用いられる場合が多い。1年間など一定期間内でポイントが累積され貯まっていき、累積ポイント数でステージの昇降が決まる。ステージごとに特典が設定されている。
<法的・会計的に留意すべき点>
ステージ制の特典類において、景品表示法が適用される。ただしクーポン券など自社商品・サービスの値引きに関する特典は、そこから除外される。会計処理は、一般的に引当金処理が適用される。
②は、銀行のポイントサービスなどでよく見かけます。ゴールドステージになるとATM手数料が何回か無料になるなどは、よくある特典といえます。また、それ以外の業界でもちょくちょく見かけますが、①の通常のポイントサービスと区別するため、「マイル」とか「マイレージサービス」などとポイントとは別の呼称で展開している事例もあります。たとえば、アパレル業界のユナイテッドアローズ「UAマイル」などはその典型といえましょう。
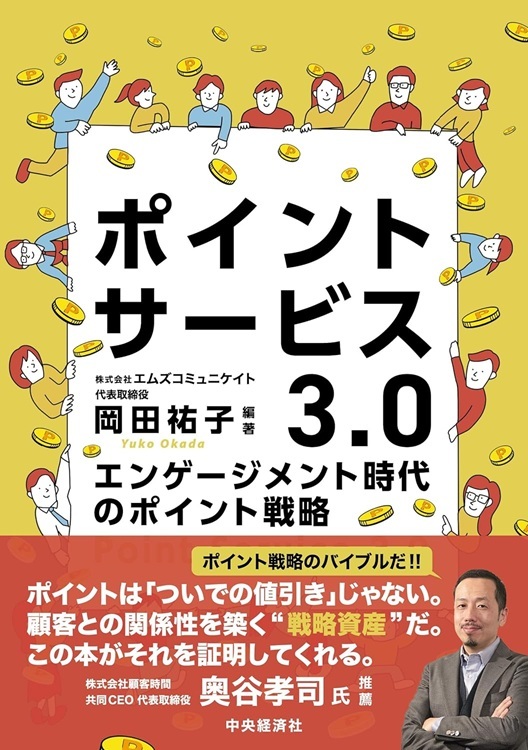
ポイントサービスコンサルタント。
慶應義塾大学卒業後、大日本印刷入社。社内ベンチャー制度にて2003年、国内唯一のポイントサービスおよび会員組織構築・運用支援の専門コンサルティング会社株式会社エムズコミュニケイトを設立。大手企業、自治体のポイントサービスやCRM・顧客戦略に関するコンサルティングのほか、セミナーや講演、執筆活動を行う。著書『成功するポイントサービス』(2010年 WAVE出版)、一般社団法人日本カスタマーエンゲージメント協会理事、総務省ポイントサービスアドバイザー、三鷹市地域ポイントの検討委員ほか。テレビ東京「ガイアの夜明け」ほか出演。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
