本記事は、岡田 祐子氏の著書『ポイントサービス3.0 エンゲージメント時代のポイント戦略』(中央経済社)の中から一部を抜粋・編集しています。

「ポイント=へそくり理論」について
へそくりの考え方について、より詳しく触れてみましょう。「ポイント=へそくり理論」は、私たちエムズコミュニケイトが当初から提唱している考え方です。ポイントとは、企業が顧客に提供する「おまけ=ご褒美」であり、金銭とは異なる「へそくり」のような存在として捉えると、いろいろな現象がわかりやすく説明できます。
- 罪悪感の軽減:へそくりを使う時のように、ポイントを使用する際は現金を使うよりも心理的な負担が少なく、罪悪感が軽減されます。
- 特別感:へそくりは「特別な出費」のために取っておくものという意識があるように、ポイントも特別な商品やサービスのために使いたいという心理が働きます。
- 計画外の喜び:思わぬ出費や贅沢品の購入に使われやすく、予期せぬ喜びや満足感をもたらします。
- 自己報酬:へそくりを使うことで自分へのご褒美を感じるように、ポイントの利用も自己報酬として機能します。
- 管理の楽しみ:へそくりを管理する楽しみがあるように、ポイントの貯蓄や管理自体が一種の楽しみとなります。
何よりも、へそくりは少しずつ貯めることにより、将来の期待感、満足度を高めます。たとえば、毎日3千円もへそくりをして、10日で3万円貯まってもおもしろくないでしょう。それより、小銭を中身が見えない貯金箱に入れ、満杯になっただろうころに開けてみると、思った以上の金額になっていることのほうが楽しく、同じお金でも、買いたかったあれこれを買ってしまおう、という気持ちにもなるのです。
ポイントサービスも全く同じで、導入の責任者や担当者は、付与率が高くないと受け入れられないのではないかと考えている方も多いのですが、ポイントプレッシャー効果でも触れたように、1人当たり年間1,000ポイントの付与原資があった場合、1回1,000ポイント付与するのと、100ポイントを10回付与するのとでは、効果において後者のほうに歩があるのです。一度に多く付与するよりも、ポイント数は少なくてもよいので、付与する機会を多くしてあげるほうが、お客さまには喜ばれます。つまり、やり方によっては、コストの総量を抑えてロイヤルティを上げることが可能なのです。
「ポイントは日本の文化」
~なぜ日本人はポイントサービスに心惹かれるのか
1. 日本人とポイントサービスの親和性
ポイントサービスは、一種のロイヤルティプログラムとみなせますが、他国での事例もあるとはいえ、その浸透度と影響力において、日本は群を抜いています。なぜ日本人はこれほどまでにポイントに惹かれるのでしょうか。その答えは、日本の文化と国民性の中に隠されているのではないかと思います。たとえば、子ども時代にラジオ体操のスタンプカードでご褒美をもらえる体験は、いまだ続く、日本人のポイントサービスにおける記憶の原風景ともいえるものではないかと思っています。
(1)「もったいない」精神と倹約美徳:1ポイントも見逃さない
「もったいない」。この言葉は、日本文化を象徴する1つの心情です。資源を無駄にせず、あらゆるものを大切に使い切る。この精神は、ポイントサービスと見事に調和します。日本人は一般的に倹約を美徳とし、「お得」な買い物を好む傾向があります。日常、頻度高く買い物をするスーパーマーケットにおいて、ポイント交換(利用)率は100%に近いのです。たとえ1ポイントであっても、それを無駄にすることは「もったいない」。この感覚が、日本人をポイントを貯めるという行為に駆り立てるのではないでしょうか。
(2)「コツコツ」貯めるということ:塵も積もれば山となる
日本には、「塵も積もれば山となる」という諺があります。小さな努力を積み重ねることで、大きな成果が得られるという考え方です。この「コツコツ」貯める文化も、ポイントサービスの本質と合致します。日本人は貯蓄率が高いことで知られていますが、この傾向はポイントの「へそくり」貯蓄にも表れます。毎日の小さな買い物で少しずつポイントを貯め、いつか大きな特典と交換する。このプロセスは、日本人の心に深く響くといえるのではないかと思います。エムズコミュニケイトの調査でも、日本の消費者の65%が「ポイントを貯めること自体に満足を感じる」と回答しています。また、過去の定点調査から、日本人の約7割がポイントサービス自体に好意的であるという結果が得られています。
(3)「ご縁」の文化:ポイントが紡ぐ中長期的な関係
日本には「ご縁」を大切にする文化があります。人と人、人とモノとの関わりを重視し、その関係性を長く保つことを尊ぶのです。筆者自身、ご縁によるありがたいつながりで今があると思っています。ポイントサービスは、まさにこの「ご縁」の現代版といえるでしょう。日本のビジネスカルチャーでは、中長期的な関係性の維持が重要視されます。ポイントを介して企業と顧客が中長期的な関係を築く。そして、その関係が新たな価値を生み出す。これは、日本的な「ご縁」の概念に見事に当てはまります。実際、先ほどの調査でも、日本の消費者の7割以上が「ポイントがあるから、その店舗やブランドを継続して利用する」と回答しています。
(4)「おもてなし」と「おまけ」:細やかなサービスへの期待
日本の「おもてなし」文化は、きめ細やかなサービスへの期待につながっています。同時に、日本には「おまけ」を喜ぶ文化があります。商品本体とは別に、小さな付加価値がつくことを好むのです。お菓子のおまけ、雑誌の付録、他にも、商店街の顔なじみの魚屋さんで、「今日はこれもおまけで持ってっていいよ」と追加で
(5)日本人の所属意識と上昇志向:ステージ制の魅力
日本人は集団への所属意識が強いとされます。同時に、その中で切磋琢磨して、少しでも認められたいという「上昇志向」も存在します。多くのポイントサービス導入企業が採用している「会員ステージ制度」は、この日本的な所属意識と上昇志向を巧みに刺激します。ポイントサービスへの参加は、ある種の「会員」としての所属感を満たします。さらに、ゴールド会員、プラチナ会員といったステータスは、上昇志向を刺激します。
実際、航空会社のマイレージサービスでは、上位会員になるための「マイル修行」と呼ばれる行動が、一種の社会現象となっています。これらの文化的要因が複雑に絡み合い、日本におけるポイントサービスの驚異的な浸透を生み出しているのです。
2.まとめ
ポイントサービスは、単なるマーケティングツールを超えて、日本文化の中に深く根づいた社会現象、もっといえば、「ポイントサービスは日本の文化」の1つであるとも思っています。日本人とポイントサービスの関係は、単なるインセンティブを超えた、文化的・社会的な現象といえます。企業がこの特別な関係を理解し、活用することで、より効果的なポイントサービスの設計と運用が可能になるのです。
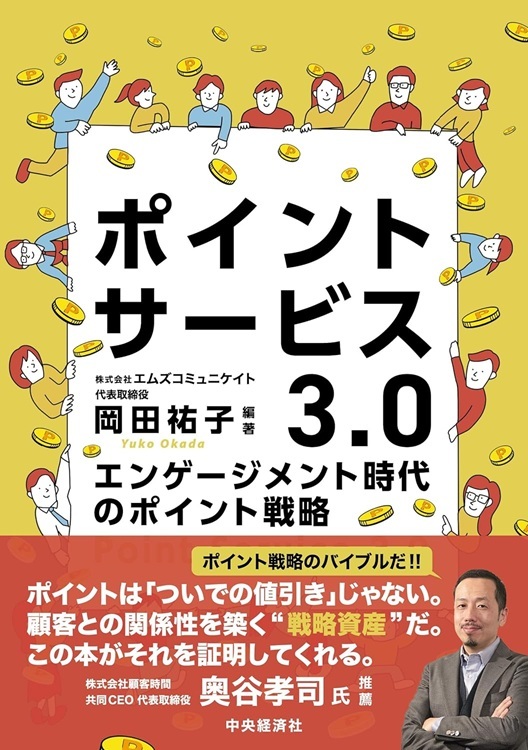
ポイントサービスコンサルタント。
慶應義塾大学卒業後、大日本印刷入社。社内ベンチャー制度にて2003年、国内唯一のポイントサービスおよび会員組織構築・運用支援の専門コンサルティング会社株式会社エムズコミュニケイトを設立。大手企業、自治体のポイントサービスやCRM・顧客戦略に関するコンサルティングのほか、セミナーや講演、執筆活動を行う。著書『成功するポイントサービス』(2010年 WAVE出版)、一般社団法人日本カスタマーエンゲージメント協会理事、総務省ポイントサービスアドバイザー、三鷹市地域ポイントの検討委員ほか。テレビ東京「ガイアの夜明け」ほか出演。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
