分散投資で資産形成をしていくプロセスにおいて、当初に決めたバランスが崩れることはしばしば起こるでしょう。このとき、元のバランスに戻すために資産配分を再調整することを「リバランス」と呼びます。
通常の証券口座などでは、価格が上昇したカテゴリの資産を売却すると、所得税として約20%を徴収されます。しかしiDeCo(個人型確定拠出年金)であれば売却益が非課税なので、税金がかからない状態でリバランスをすることができるのです。今回は、iDeCoを使ったリバランスの運用テクニックを紹介します。

「リバランス」とは何か?
「リバランス」は、資産運用を続ける間に当初に資産配分した運用商品のバランスが崩れたときに、元の状態に戻すことを言います。
例えば、100万円の資産を「株・債券・コモディティ・貯金」のカテゴリへ25万円ずつ配分して投資した(図1:左)とします。1年後、資産全体は120万円に増えたとしても各カテゴリの運用実績にはばらつきがあるため、内訳は当初の通りとは限らない(図1:右)ことがほとんどです。
【図1】
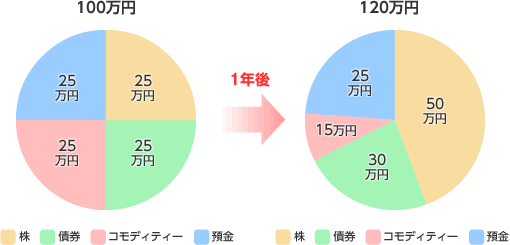
【図2】
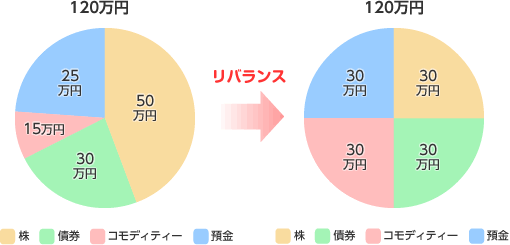
資産運用の結果、このように全体の金額は増えても運用当初のバランスのとれた資産配分ではなく(図2:左)、比率が増加した株に影響を受ける度合が大きくなります。このままではリスクコントロールに不安が残る状態になるため、価格が上昇した分の株を売却し、反対に価格が下降した分を買い増しして再び当初の比率へ戻します。これがリバランスです。
リバランスで利益課税されないiDeCoの運用テクニック
通常、株などの売却益には約20%の所得税がかかります。当然ながら、証券口座で上述のリバランスを行った場合も約20%の税金がかかります。しかし、iDeCoで運用すれば資産配分のリバランスをおトクに行うことができます。
iDeCoは税制面でとても優遇された年金プランで、運用して出た利益は非課税となり、同じように運用商品の買い替え(スイッチング)を行っても課税されません。
iDeCoを使ったリバランスの注意点
余計な税コストをかけずにリバランスを取ることができるiDeCoを使った運用テクニックですが、スイッチングはリアルタイムで行われるものではない点に注意しましょう。これが意味するのは、指示をしてから反映されるまでに資産配分が変わる可能性もゼロではないということです。せっかく熟考してスイッチングを行っても、想定していた資産配分にならないこともあります。
また、iDeCoは、年金として運用するのが本来の目的で、掛け金の上限が最大で年間81万6,000円(自営業者など)とそれほど高くなく、今すぐ資産全体のリバランスに使うには十分な額が確保できないことも覚えておきましょう。
ただし、iDeCoはそもそも年金制度として設計され長期的な資産運用に適している制度ですから、一時的な変動で一喜一憂することなく、長い目で非課税枠を十分に活用していくことをおすすめします。非課税でリバランスをとる手段としてiDeCoに加入しておくという方法もあるのです。
(提供: IFAオンライン )
【人気記事 IFAオンライン】
・
地方に富裕層が多い理由とは?
・
年代別にみる投資信託のメリット
・
ポートフォリオとアセットアロケーションの考え方
・
帰省の時に話しておきたい! 「実家の遺産・相続」の話
・
IFAに資産運用の相談をするといい3つの理由