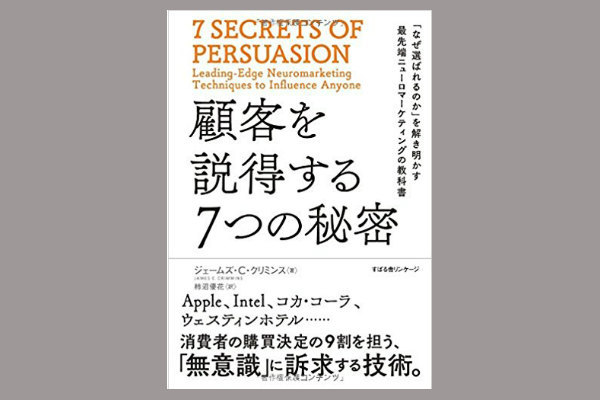誰かを説得しようと思うなら、トカゲの言葉独自のスタイルも習得する必要があります。相手の行動や感情、そしてその周囲の人間について話をするのです。これらは思い付きや連想を通じ、人の無意識に働きかけるのです。選択肢の思いつきやすさを向上させることで、そこから連想されるものに変化を与えます。
(本記事は、ジェームズ・C・クリミンス氏の著書『顧客を説得する7つの秘密』=すばる舎、2017年10月18日=の中から一部を抜粋・編集しています)
【関連記事『顧客を説得する7つの秘密』より】
・ビジネスで相手をその気にさせる手法 「トカゲの正体を見極めろ」
・ビジネスにおける基本文法とは何か?ロジックはトカゲには無力同然
トカゲの言葉を話せ:スタイル
誰かを説得しようと思うなら、トカゲの言葉独自のスタイルも習得するとよいだろう。
相手の行動、感情、そしてその周囲の人間について話をするのである。これらは思いつきやすさと連想を通じて人の無意識に働きかける。
行動、感情、そして他人の好みは、選択肢の思いつきやすさを向上させ、そこから連想されるものに変化を与える。
行動 AppleはMacBookの広告で、74種類の異なるデコレーションシートを用いた
行動は言葉よりも雄弁に語る、とは昔から言われてきたことだ。それはトカゲの場合特にあてはまる。
社会研究者達は人の動機ではなく実際の行動に注目する。
研究によると、人はどんな状況だろうと相手の行動を基にしてその性格を判断するものなのだという。
相手がその行動を取らざるをえなかったような状況においても、人は他人を、その人が実際に取った行動で判断する。
例えばもし法学生が人種主義者を弁護しなければならなかったとしたら、人はそれがその学生の本意ではなかったと知っていてもなお、彼に対して人種主義者的なイメージを抱いてしまう。この現象を、心理学者は「根本的な帰属の誤り」と呼んでいる。
マーケター達はよくこの根本的な帰属の誤りを用いる。もっとも、彼らはそのような呼び方はしないが。
Abecrombie&Fitchは長年、スポーツ関連商品とアパレルの分野、特に狩猟と釣り専門ウェアのハイエンドブランドだった。
1980年代後半、TheLimited社がAbecrombie&Fitchを買収した。
TheLimitedは、このブランドを若者向けの衣料品販売に用いることに決め、Abecrombie&Fitchをより洗練されたファッションブランドにしようとした。
どうすれば、高級だが時代遅れのスポーツブランドをファッショナブルにできるものだろうか?
TheLimitedはAbecrombie&Fitchに対する人々の認識を、ブランドの振る舞いを変化させることによって変えた。
当時のブランドイメージに沿って広告や宣伝を行うのをやめたのだ。
ブランドは自らがどうあるかではなく、どうありたいかによって、その魅せ方を決めた。どのようなブランドでありたいかと問われれば、それは当然、利益を生み出すブランドだ。
ブランドは自社のカタログやメディア、そして店舗でお洒落っぽさを大々的にアピールし、それを見ていた人々は、Abecrombie&Fitchがもともとファッショナブルなブランドだったかのように思うようになった。
たとえその方針転換が、金儲けのためになされたものだというのが明らかであったとしても。
トカゲからしてみれば、行動こそが全てなのだ。
言い換えれば、トカゲにとっては、人はなぜそれをしたのかではなく、何をしたかで判断されるものなのである。
潜在的な消費者に向かって「お洒落なブランドです」と訴えるだけでは駄目だ。
お洒落ですと主張するだけで本当にお洒落っぽさをアピールできるわけがない。
同じように、楽しさだとか、ドキドキ感だとか、男らしさなんてイメージも、口で言うだけでは伝わらない。
ブランドが自分はこうだと言葉で主張したって、受け手の感性には響かない。
お洒落だとか、楽しそうだとか、ドキドキするとか男らしいといったふうに受け取られるためには、ブランドは実際にお洒落で、楽しそうで、ドキドキするように、あるいは男らしく振舞わなくてはならない。
人々はマーケティング戦略や利益のことは頭の片隅に置いておいて、実際にどう見えるかによってそのブランドを判断する。
AppleはMacBookの広告で、74種類の異なるデコレーションシートを用いた。
ブランドが楽しいだとか信頼の置けるものだとか創造的だとか格好いいといったことを言葉では言わなかった。
広告は単にそれっぽく見せるだけで、そのメッセージを伝えられるものなのだ。
見る側は、ブランドメッセージ自体よりも、それがどのような形で示されたかによってブランドを理解する。
石油会社は見せ方次第で自社が環境に優しいようなイメージを作り出すことができる。
実際は環境意識を全く持っていなかったとしても、人々に自社は環境に優しいと思い込ませることができるのだ。
石油会社は野鳥保護を行う全米オーディボン協会へ寄付を行うことができる。
燃費のいい車を買いましょうと呼びかけることができる。
ガソリンスタンドを緑色にするのでもいい。こうすることによって、人々はその石油会社が環境に配慮していると思うようになるだろう。
たとえその行動が実際には国外での採掘権を得るための政治経済的判断からなされたものだとしても。
動機がどうであれ、実際に目に見える振る舞いによって人は物事を判断してしまうのだ。
思いやりがあり、したたかで、正直で、心が広い人はどのように振る舞うだろう。
もしあなたの支持する選挙候補がそれと同じように振る舞えば、有権者達は彼の人格をそうしたものとしてとらえ、それが票を獲得するためではないかなどといちいち疑問を挟んだりはしないだろう。
弱そうなイメージのあったブランドだって、もし男らしい広告を打てば、そういうブランドなのだと思われるようになる。
ブランドと、それを愛用する人々の組み合わせは、彼らが実際どうしてそれを選んだかではなく、ただそれを選んだという事実によって真実味を持つ。
ベルヴェデール・ウォッカは、広告の見せ方がどれだけ相手の認識に影響を与えるかについて、ある不幸な体験をしている。
当時のベルヴェデールのキャッチコピーは、「いつもゆったり味わえる」だった。これだけなら何も問題はない。
しかし同社はフェイスブックとツイッターの広告で、このキャッチフレーズを、薄ら笑いを浮かべた男が逃げようとする女性を後ろから無理やり捕らえている写真に添えてしまったのだ。
その写真の上には、別の色で小さく「一部の(せっかちな)人と違って(ベルヴェデールはいつもゆったり味わえる)」と書いてあった。
普通こんなものを見せられたら、この広告によって、ベルヴェデールはレイプの場面とブランドを関連づけようとしているのだと思い込んでしまう。
どんな理由があってブランドがその写真を選んだのかなど、ここでは関係ない。
写真に写っている人間がレイプをしようとしているように見える、それが全てだ。トカゲにとっては、なぜよりも、何をしたかが重要なのである。
もちろん、ベルヴェデール・ウォッカは謝罪した。しかし謝罪の言葉では、実際にやってしまっことがトカゲに与えた印象を拭い去ることはできなかった。
親は自分の赤ん坊に、何を食べると身体にいいかを振舞いを通じて自然に教える。
内なるトカゲとやりとりするのは、赤ん坊を相手にするのと似ている。
親は赤ん坊に、その食べ物がいかに美味しいかを言葉で説明したりはしないだろう。
そんなことを赤ちゃんに対して言っても無駄だと分かっているからだ。
親は大袈裟な喜びの表情で食べ物を口に運んで見せ、自分達がその食べ物を美味しく味わっているのだと赤ん坊に示す。
それで赤ん坊が本当に信じるとは思っていないが、説明するよりは効果的だと分かっているからだ。
マーク・トウェインはこのことをよく理解していた。
うんざりしたように、トム・ソーヤは「長々と続くフェンスの列を見て座り込んだ。」ポリーおばさんにはそのフェンスを白く塗って欲しいと頼まれていたが、トムにはそれは不可能なことに思えた。
友達に代わって欲しいと思ったが、ポケットの中にオモチャか何かがないかと探ってみても、「彼らの自由時間を30分貰うお礼にすら足りない分しかなかった」。しかしトムは想像力を働かせた。
彼は物々交換ではなく、自分の振る舞い方によって友達をその気にさせることにしようと思ったのだ。
トムはまるで自分がフェンスを塗るのを楽しんでいるかのように、そして自分が塗ったものに対して非常な誇りを抱いているかのように振る舞い始めた。
しばらくすると、トムの友達たちは彼の不遇を笑う代わりに、自分がフェンスを白く塗る番を待って列を作るようになった。
「行動に勝るものはない」。
赤ん坊は、親がご飯を楽しんで食べているように振る舞う本当の理由を尋ねたりはしない。
トムの小説に出てくる友達は、なぜトムがフェンスを白く塗るのを楽しんでいるのかを質問したりはしない。
トカゲは行動のみに注目し、その背後にある動機を無視する。
互恵関係、というものに着目すると、人の振る舞いが相手の判断に与える影響をまた違った側面から見ることができる。
アリゾナ州立大学のロバート・チャルディーニは、30年前、有能なコンプライアンス・プラクティショナー達を観察した。
その結果チャルディーニは、そうした人々が互恵関係を戦略の一つとして用いていることに気づいた。
相手が自分に優しいと、たとえそれが愛ゆえではなく利益目当てのものだと分かっていても、人は相手に対して親切にしたくなるものだ。
人は動機ではなく実際に為された行いに対して注意を払い、さらにその行為に対してお返しをしなければならないと思うようになる。
互恵関係というのは実に面白い。
人間関係は社会的交換によって築かれ、互恵関係はそうした社会的交換の基礎である。
社会的交換は経済的交換と比較すると理解しやすい。
経済的交換、例えば八百屋で何かを購入したりすることは、正確で即時的だ。
レジ係はペニー単位で私達が支払わなければならない額を計算する。私達はその場で直ちに支払いを済ませ、貸し借りなしの状態でその場を離れる。
もちろんそうした場面では、私達は店やストアマネージャーやそこで働く従業員に対して何の恩義も感じない。経済的交換は、その後の関係には繋がらない。
実際、経済的交換とは、関係を築くのを防ぐようにできているのだ。
しかし、社会的交換は、例えば誰かを夕食に招待すると今度は相手からお誘いが来るといったように、正確ではなく、時間的な遅れを伴うものだ。
社会的交換は、相互関係を築くようにできている。お返しをしなければという義務感が、関係を作り上げるのだ。
人はこの、お返しをしなければという義務感を感じるようにできている。それは人間の無意識に組み込まれている。
意識の上では相手が打算的にそうした行いをしているのだと分かっていても、何かお返しをしなくてはとの思いを抱えてしまう。
だからこそイスタンブールの絨毯売りは商品を見せる前に客に無料でお茶を振るまうのだ。
彼らがお茶を振る舞うのは接客商売の一環だと分かってはいても、私達はお茶をもらったからには何かお返ししなければならない、少なくとも彼の話くらいは静かに聴いてやらなければと思ってしまう。
感情 パンパースは感情ヒューリスティックをうまく利用した
人の無意識は感情に反応する。なぜなら無意識自体が、自分の望みを伝えるために好き嫌いや恐怖、喜びなどの感情を利用しているからである。
好き嫌いが人の認識に与える影響、すなわち心理学者達が言うところの「感情ヒューリスティック」というものが、これまで様々に研究されてきた。
ある概念や物事、人物を好ましく思っていると、人は特に証拠もないのに、その対象には好ましい要素がたくさんあり、一方でネガティブな要素はあまりないと思い込んでしまうのだ。
結果として、私達はこの世界を現実よりもシンプルに、より整合性のあるものとして捉えている。
現実世界では、どんな概念や物事、人物にも、良い面と悪い面が両方あるものだが、私達の好き嫌いはそこに偏見を加えてしまう。
別の立場に立つ者同士が議論するのは、この感情ヒューリスティックゆえに困難だ。
全ての証拠を客観的に見る代わりに、人は自分が元から持っている考えを補強するような証拠ばかりに注目してしまうのだ。
もし、ある政治家を好ましいと思っていたら、その人を良く見せるような情報に注意を払うようになる。
もしその政治家を好ましく思っていなければ、相手の悪い一面についての情報ばかりに目がいってしまう。
ダニエル・カーネマンが言ったように、「自分が無視しているという事実を無視できるからこそ、現実は一貫性を持って見えるのだ」。
パンパースは感情ヒューリスティックをうまく利用した。
このブランドは、美しく、心に訴えかけるような子守唄のビデオを作った。
母親が赤ん坊に向かって穏やかに歌を口ずさむ中、様々な国の人々が、子供にとってより良い暮らしを生み出そうとする場面が歌詞に合わせて流れる。
なぜパンパースはこのようなビデオを作ったのだろうか?パンパースは、本当に、温かくて優しくて、子供のより良い暮らしのためならなんだってするブランドなのだろうか?その可能性もゼロではないだろう。
パンパースは昨年800億円の売り上げを記録した巨大な多国籍消費財企業が出す商品の一つだ。
P&Gの他のブランドと同じように利益を追求している。
パンパースはおそらく純粋に子供達の幸福について考えてはいるだろう。それは善いことである。
だが、このビデオが作られたのは、純粋に彼らが子供達の幸福を願っているからというわけではない。
感情に訴えかけるビデオは、視聴者のパンパースに対するイメージに影響を与えた。
このビデオが打算に基づいて、収益アップのために作られたものだという事実はこの際問題ではない。
人々がお店の育児用品売り場に行った時、感動的なビデオを思い出して、ちょっとパンパースを買ってみようかと思うようにするために作られたビデオであったとしても、構わないのだ。
ビデオは意図的すぎると感じる人も中にはいるだろう、実際そうなのだから。
ビデオで使われている音楽とイメージは、視聴者の感情に訴えかけるように慎重に選び抜かれたものだ。でもそれでいいのである。
このビデオは、ブランディングと利益向上のために企業が創造性と感情を上手く利用した好例である。
ホールマーク(アメリカのグリーティングカード会社)も、視聴者の感情をうまく広告に利用した。
人はカードを送ること自体には慣れ親しんでいる。夫が妻にメッセージカードを送るのでも、子供が親に送るのでも、孫が祖父母に送るのでも、それ自体は普通のことだ。
ホールマークはトカゲ(=無意識)に働きかけるために感情を利用し、人々の涙を誘った。
トカゲにとっては、そういう気持ちになった、という事実こそが一番重要で、どうして、そしてどうやって、ホールマークがそんな気持ちにさせようとしたのかはあまり重要ではない。
ホールマークは広告キャンペーンとしてお試しプログラムを提供した。すなわち人々に、実際に誰かにカードを渡すというちょっとした経験をしてもらったのだ。
人はその時に経験した気持ちをホールマークカードと結びつけるようになる。この会社は、トカゲに働きかけるために感情をうまく利用し、結果としてカードとインクの販売、そしてクリエイティブな人材の獲得において大きな利益を得た。
このようにお試しプログラムを使って相手を説得するのはなかなかに有効だ。
誰かに喫煙をやめて欲しいと思ったり、デートして欲しいと考えている時には、そうしたらこんな思いができますよ、というちょっとした感情的経験を与えてあげるとよい。
父親が禁煙すると決めたら子供達がお祝いをする。
そうやって、実際に禁煙したら子供達に好きになってもらえて、ありがとうと感謝の言葉をもらえるかもしれないと思わせる。
女性をデートに誘う時には、実際にそのデートでどんな事をするのかのプランの一部を話して、その誘い自体を面白く魅力的なものにする。
連想は感情に絡めると、より記憶に残りやすい。
あなたが推している選択肢をある性質や人物と関連づけする時には、同時にターゲットに温かさや喜び、怒り、あるいは楽しさを感じさせるようにすること。そうすることで、二つの繋がりはより強固になる。
だが時折、感情を通じてトカゲに働きかけようとして逆効果となってしまうこともある。
「シュリッツを飲め、さもなくば殺す」で有名なシュリッツのキャンペーンは、まさにその例だ。
このキャンペーンはシュリッツがまだ人気のビールブランドだった頃のもので、広告には屈強な男、例えばボクサーやモーターサイクルギャング、ヘルズ・エンジェルスの一員のような男が起用された。
シュリッツから別のビールの銘柄に乗り換えるように迫られた男が、激昂しながらそれを拒否し、自分からシュリッツを取り上げようとする人間全員を脅しつけるというのが広告の内容だ。
この広告はあまりに強烈で、言葉通りに受け取られるべきものではないことは明らかだった。
しかしブランドのあては外れた。この広告キャンペーンを見た人々は、ブランドは「雄々しい人間はシュリッツを好む」というメッセージを伝えたかったのだろうとロジカルな判断を下すことはなく、また「そこまでするほどシュリッツのビールは美味いんだ」という感慨を抱いたわけでもなかった。
人々がこの広告から受け取ったのは、恐怖の感情だった。この広告は、シュリッツというビールと、その愛飲者は怖い、というイメージを人々に植え付けてしまったのだ。
このキャンペーンと他のいくつかのマーケティングの誤りによって、シュリッツの売り上げは急激に低迷していった。
他人の好み
選択に対する他人の影響というのは人の進化の過程に深く根ざしているようだ。
人間は他の多くの動物同様、真似をする生き物なのである。
真似をするという本能は、配偶行動において最も顕著に見られる。
科学者達によると、ある雌につがいとして選ばれた雄は、それ以外の雌にとっても、つがい候補としてより魅力的になるものなのだそうだ。
レック(雄が交尾するために雌を誘う場所)について考えてみてほしい。
レックはある種の動物の繁殖期に見られる、雄達が集まって自分がいかに魅力的かを競い合うように雌に見せるための場所である。
繁殖期には雄達は一箇所に集い、それぞれの小さな縄張り内で、訪れる雌達に自分をアピールする。
雌達はこの展示場の中を歩き回り、やがてその中の一匹とつがいとなる。たいてい、ここで雌達を惹きつける雄はほんの数匹に限られる。
科学者達はこのつがい形成の過程をよりよく理解するためにレックについて研究を進めてきた。
雄がつがいを設ける事ができるかどうかは、彼の外見やパフォーマンスだけでなく、雌達の互いを模倣し合うという習性にも依存しているらしいということが分かってきた。
雌は他の雌が近くにいる雄により惹きつけられる傾向がある。キジオライチョウの雌は、他の雌とすでにつがいとなった雄をより好んで選ぶ。
ジェームズ・C・クリミンス JAMES C.CRIMMINS
27年間にわたり、主にDDBシカゴのチーフ・ストラテジック・オフィサーを務める。また、世界的なブランドとして知られる、バドワイザー、マクドナルド、ステートファーム、ベティ・クロッカーなどのブランド企画ディレクターとしても活躍。
社会学の博士号と統計学の修士号を持ち、米国ノースウェスタン大学medillスクールで、統合マーケティングコミュニケーションを教えた。誰もが、説得力と影響力を手にする方法を、科学的、専門的、学問的な観点を背景に伝えている。