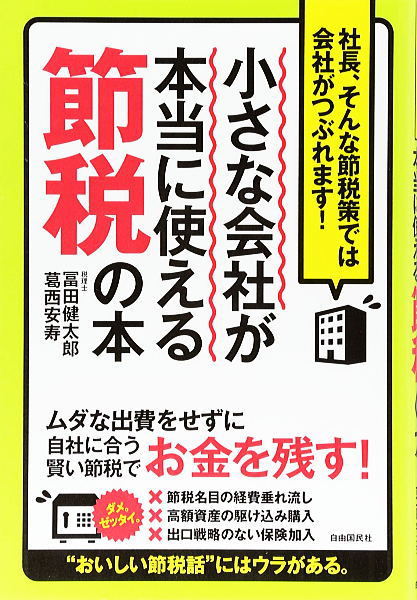(本記事は、冨田健太郎氏・葛西安寿の共著『小さな会社が本当に使える節税の本』自由国民社、2018年6月15日刊の中から一部を抜粋・編集しています)
積極的にやりたい節税策、期ズレでも効果大な手法

これからご紹介する節税策は、今すぐにできる節税策ではないものもありますが、該当した場合は積極的にやっていきたい節税策です。
基本的には期ズレなのですが、金額が多額になり、かつ、期ズレの期間が長くなるものがあります。
こういった場合、取り戻されるまで時間がかかるので、期ズレであっても積極的にとっていきたい手法です。
●期ズレでも効果的な節税策
簡単に分類すると、次のようになります。
(1)保険関係
(2)資産取得関係
(3)その他
保険関係については、数百万円から数千万円を損金にする手法を紹介します。
もちろん期ズレなのでどこかで取り戻されるのですが、取り戻される場合の戦略についても紹介します。
ただし、保険については勘違いしている方も多いので、注意したい点についても詳細を説明していきます。
資産取得関係については、建物や構築物のように償却期間が長いものについて、その期間を短くするような手法を紹介します。
10年、20年かけて経費にするのは気が遠くなるでしょうが、この手法を使うことで、ある程度まとまった金額を、短期間で経費にすることが可能になります。
設備が古くなってくると収益性も悪化するので、収益性が高い初期に多額の経費を計上することで、課税所得をコントロールすることが可能になります。
設備投資をした場合などは、必ず実施するようにしてください。
その他については、あまり該当することはないでしょうが、給与を減らしたり、所得をコントロールしたりして、あえて当期の税金を増やすことで節税するというトリッキーな方法になります。
いずれの方法についても、細かい注意点があるので各項をよく読んで理解を深めてから実施するようにしてください。
また、顧問税理士がいる場合は、必ず顧問税理士の判断も仰ぐようにしましょう。
そうすることで、リスク回避することができるでしょう。
退職金の3つのメリット
保険の出口戦略として、退職金で相殺するだけだと、「ただ単に、経費を入れただけじゃないか」と、あまり魅力を感じない方もいるでしょう。
しかし、この退職金という経費は税制上、非常に優遇されています。退職金のメリットは「退職所得控除」「1/2課税」「分離課税」の3点です。
●退職金にかかる税金は抑えられる
退職所得控除は「給与所得控除」のように、無条件で所得を控除することができる制度です。
退職所得控除は勤続年数により算定され、勤続年数20年以下の場合は「40万円×年数」、20年超の場合は、「800万円(40万円×20年)+70万円×20年超の年数」となります(1年未満の端数は切り上げて1年とします)。
たとえば、勤続30年の場合、「800万円+70万円×10年=1500万円」も控除することができます。
この場合、退職金が1500万円以下であれば、全額控除となり、税金は1円もかかりません。
退職所得控除だけでも結構な金額になりますが、さらに控除後の金額に1/2を乗じた金額が課税対象額となります。
したがって、先の事例で退職金が2000万円とした場合、「2000万円-1500万円=500万円」の1/2である250万円が課税対象額となります。
最後に分離課税です。
分離課税の場合は分離課税単独で税計算を行うので、給与所得等に加算されません。
所得税は超過累進税率が適用されるので、所得が高くなると税率も高くなるのですが、退職所得は別に計算をするので悪戯に税率が高くなることがありません。
少し難しい部分もあるので、簡単な事例で検証してみましょう。
例)連続30年6ヶ月、退職金3000万円の場合
【退職所得控除額】
800万円+70万円×11年=1570万円
【課税対象額】
(3000万円-1570万円)×1/2=715万円
【所得税額】
715万円×23%※-63万6000円※=100万8500円
※所得金額「695万円超900万円以下」の場合の税率と控除額
上を参照すると、3000万円の収入に対し、税額は約100万円となります。
実効税率はわずか3.3%です。
ここまで低い税率が適用されるのは退職所得以外にありません。
なお、仮に3000万円を給与所得で受け取った場合の所得税額は約830万円となり、700万円以上の節税効果があります。
退職所得にかかる税額は相当少なくなるので、毎月の役員報酬を少し下げて退職金で受け取るようにすれば、個人の手取り金額を最大化することが可能になります。
内部留保が溜まっている場合には、役員報酬を下げずに役員退職金を支払えばよいでしょう。
●役員退職金には一定の制限がある
退職金は税制の優遇がかなりあり、役員報酬で取るよりも退職金で取ったほうが得なので、退職所得の恩恵を受けるための調整をすることが考えられます。
その対策として、課税当局では役員退職金に対して一定の制限を設けています。
ひとつめは、短い勤続年数の場合の制限です。
H25年以降、役員としての勤続年数が5年以下の場合は、退職所得の金額の計算において、1/2を乗じることができなくなりました。
短期間の勤続年数でも1/2とすることを許してしまうと、会社を作って短期間で清算し退職金を得、また会社を作って……というスキームがまかり通ってしまうためです。
2つめは不相当に高額な金額の場合、税務否認される制度です。
たとえば、退職直前の役員報酬が10万円、退職金が1億円といったように、月額報酬と退職金とに著しい乖離があるような場合は注意が必要です。
仮に税務否認された場合、その否認金額は役員賞与として全額損金不算入となってしまうので、全く意味のないものとなってしまいます。
税務否認されないためには、次の算式で計算した金額の範囲内としておくのがよいでしょう。
もちろん、実態によって否認されるケースもありますが、ひとつの指標にはなるので、頭に入れておいてください。
【役員退職金=最終役員報酬月額×役員在任期間×功績倍率】
このなかの功績倍率には、何か決まった倍率があるというわけではなく、退職する役員の在籍中の貢献度を考慮し何倍にするかを決めることになります。
たとえば、代表取締役は3倍、専務取締役は2.5倍、常務取締役は2倍といったように決定していきます。
もちろん、あまりに高率ですと税務否認される可能性が高くなりますが、この例で表示した程度の倍率であれば、税務否認される可能性は低いでしょう。
また、この記算式で計算した結果が、同業他社の役員退職金と同程度であればよいのですが、突出して高いような場合は、高いことについての理由付けが必要となります。
最後に、役員退職金の算式や功績倍率を決定したら、役員退職金規程を作成しておくと、より客観性が増してよいでしょう。
当期の税額を減らす税額控除を取りきる
税額控除は当期の税額を直接減らすことができ、かつ、取り戻されないものなので非常に有用な制度です。
ただし、無制限に税額控除できるわけではなく、当期の法人税額に制度ごとに定められた一定割合を乗じた金額までと制限されています。
また、税額控除を取りきれなかった場合、翌期に繰越できるものとできないものとがあり、繰越ができないものについては、取りきれなかった時点で権利放棄することになってしまいます。
せっかくの税額控除なので、できれば全部取りきりたいものですが、どうしていけばよいのでしょうか。
簡単な事例で確認していきましょう。
(例)
所得拡大促進税制を適用、雇用者給与等支給額の増加額……200万円
当期の所得金額……600万円、当期の法人税額……90万円、
期ズレ前払費用……70万円
●あえて益出しをして税金を増やす
所得拡大促進税制の場合、雇用者給与等支給額の増加額の10%が税額控除の対象となります。
また、法人税額の20%が限度額であり、取りきれなかった場合の繰越は認められません。
現状では「200万円×10%=20万円」の控除枠があるのですが、法人税額の20%が「90万円×20%=18万円」しかないため、2万円は切り捨てられてしまいます。
そこで、あえて所得を増やして法人税額を増加させ、限度額を増やしています。
期ズレが70万円あるのでこれを取らなければ当期の所得は670万円となり、法人税額は100万5000円になります。
「100万5000円×20%=20万1000円」なので、控除対象額以上となり、税額控除がすべて取りきれることになりました。
結果として、当期の法人税を8万円多く支払うことになりますが、当期に入れなかった期ズレ分を翌期に取れば、翌期の法人税が10万円少なくなるので、2年間トータルでみると、税額控除が取れた分の2万円が納税減となります。
これに住民税、事業税が加わるので、もう少し節税メリットが増えます。
しくみさえ理解していれば簡単なので、税額控除が取りきれないような状況があれば、あえて「益出し」をして税金を増やし、税額控除を取る方法を検討してみてください。
社宅や福利厚生を充実させて給与を減らす
これまで、社宅制度や食費補助、新年会や忘年会などの福利厚生制度について紹介しましたが、これらの節税メリットは、同額の給与を支給するよりも大きいのです。
●福利厚生を充実させる節税メリット
法人が負担した福利厚生費は会社の損金になり、その分会社の税金が安くなりますが、その恩恵を受ける個人には課税がされません。
これは非常に大きな節税メリットです。
福利厚生費ではなく同額の給与を支給したとすると、その給与は法人の損金にはなりますが、個人の給与所得が増えて税負担が増加します。
さらに、給与が増えると法人と個人の社会保険料の負担も増えるので、福利厚生費は給与と比べるとはるかにお得なのです。
また、福利厚生費の大半は、飲食費など消費税のかかる取引なので、福利厚生費が法人の損金になると同時に、消費税の負担を抑えることができます。
これに対して、給与は消費税のかからない取引のため、給与をいくら増額しても消費税節税のメリットはありません。
このように、福利厚生制度は、法人税、消費税、所得税など、複数の税金において節税効果が期待できるので、福利厚生制度を充実させ、その分給与を下げることができれば、法人・個人両方の税金を安くできる可能性があります。
これらの節税メリットのほかにも、福利厚生制度には次のようなメリットもあります。
●節税効果以外にも嬉しいメリット
経営が厳しいときでも役員報酬は毎月同額でなければなりませんし、社員の給与を減らすことも容易ではありません。
しかし、社員旅行や新年会などは、経営状況によって中止したり、規模を小さくしたりすることが可能です。
また、福利厚生制度が充実していると、役員や社員が気持ちよく働くことができ、会社のイメージアップも図れ、支出額以上の副次的な効果も期待できるかもしれません。
福利厚生制度は、紹介した以外にもさまざまなものがあるので、どのような福利厚生制度が会社にとって有用か、役員や社員にとってうれしい制度か、そして給与課税されないものなのかどうかなどを調べ、検討してみるとよいでしょう。