(本記事は、生島 あゆみ氏の著書『一流と日本庭園』CCCメディアハウスの中から一部を抜粋・編集しています)

豊臣秀吉と醍醐寺三宝院
豊臣秀吉(1537〜1598年) 醍醐寺三宝院(だいごじさんぼういん)【京都】
土木マニアの豊臣秀吉が造らせた三宝院の庭は、醍醐、桜の名所だった。天下人のみが所有できる藤戸石を中心に展開された豪快な庭。
土木マニア秀吉の原点
最近、「土木マニアの秀吉」の一面が注目されはじめました。大坂城、京都の聚楽第以外にも、伏見の地に、指月(しげつ)伏見城、木幡(こはた)伏見城、淀城などを築城しています。秀吉は、ここ伏見を首都にしたかったようです。ですから、斜面に作った城下町は、等高線を無視して道を一直線に作り上げました。また、巨椋池(おぐらいけ)を水陸の交通の要所にするため、池の上に 太閤堤という道を作り、巨椋池で宇治川と淀川を無理矢理直結させます。とにかく、大規模な土木工事を、短期間で完成させる能力に長けていたのです。そのルーツは、秀吉がまだ木下藤吉郎と言われていた頃に培った人間関係にありました。
江戸時代に纏められた『太閤素生記』によれば、秀吉は尾張国愛知郡中村(名古屋市)の木下弥右衛門の子で、幼名は猿、日吉丸と伝えられています。『建築家秀吉』(宮元健次著)の中で、秀吉の出自は「ワタリ」と呼ばれる定住地を持たない技術者集団と関係していたと書かれています。秀吉の母・なかはワタリの鍛治師・関兼貞(せきかねさだ)の娘であり、秀吉自身も近江、浅井郡の鍛治師に弟子入りしていたという説もあるそうです。
近江で、秀吉は優秀な大工・阿部家や甲良家と繋がり、また穴太(あのう)の石工という、石垣を作る集団とも関係を持っていました。この土木技術者達との交流が、「土木マニア秀吉」「普請狂」と言われるぐらい、城造りのノウハウを熟知した秀吉を作り上げていったのではないでしょうか。
16歳のとき、流浪の旅に出て、遠江(とおとうみ)久能の城主・松下加兵衛に拾われ仕えました。しかし、出奔し織田信長に仕えます。草履取から出世していく秀吉の姿は、あまりにも有名です。
穴太の領主・杉原家次は、秀吉の正室・北政所の叔父にあたります。豊臣秀次の右筆駒井中務少輔重勝による『駒井日記』に、穴太駿河、穴太三河、穴太出雲と名乗るものが秀吉の配下にいたと記されています。穴太は、石工をたくさん抱えていたので、この杉原家次の家臣達を、各地の築城に派遣したのだと言われています。秀吉が若いときに培った経験、侍ではなく職業集団だったということが、優れた職人を見抜く目を持っていた一つの要因だと思われます。
およそ100年間続いた戦国時代から、織田信長・豊臣秀吉が政権を担った安土桃山時代まで、武士の出世に必要な条件は、まず戦に勝つこと、そして城を建てることでした。下剋上と言われる時代なので、能力のあるものが上の立場にとって代わる、その際たるものが秀吉だったと思います。
秀吉が信長から賜った「御普請奉行」として采配を振った清洲城に始まり、大坂城、伏見城でも、秀吉は城を建てるための生産能率性を高める工夫を取りました。前出『建築家秀吉』では、日本で初めてのジョイントベンチャーと位置づけています。清洲城の塀の修理時は、「割普請」という仕組みで、約182メートルの塀を10に分割し、いくつかの大工集団を競わせて修理させました。「これは、一足軽が雑兵と呼ばれる荒々しい技術者集団を集めて統率したものであり、技術者集団について熟知していなければ、到底成功には至らなかったに違いない」と説明しています。
続いて、同書では墨俣一夜城(すのまたいちやじょう)に関して、現代的に言えば、秀吉はべルトコンベアーシステムと、プレハブ工法を採用したとしています。これを成し遂げた背景に、木曽川の上流の山林技術者や大工ら建築集団、そして彼らを護衛する野武士達の働きがありました。
大坂城、聚楽第、そして伏見城
1583年、信長の後継者となった秀吉は、大徳寺で信長一周忌を済ませると、大坂に城を構えるため入ります。城建築の構想を2ヶ月間練り、石山本願寺跡に城を建てることを決めました。秀吉の重臣だった近江瀬田城主・浅野長政配下の穴太の石工や近江大工や職人を呼び寄せ、大坂城築城に着手しました。また、河内千塚、生駒山、御影、八幡の石に目をつけ、その石を運ぶための道を作りました。諸国の協力を仰ぎ、5万人ほどが集まり築城に邁進していったそうです。
1563年に来日したポルトガル人宣教師のフロイスが『日本史』を執筆し、前出『建築家秀吉』のなかでも、フロイスが著した大坂城について記しています。
- ―天守は八層であり、最上階は展望台となっていたという。また、各階には、金銀の織物やヨーロッパ風のカッパ、西欧風のベッド、黄金の茶室などが所狭しと並べられ、外部の屋根瓦にも金箔が用いられ、絢爛豪華であったという。―
ここに建てられた「黄金の茶室」もプレハブ工法で、取り外してどこにでも移築できるよう作られていたそうです。
フロイスは、大坂城内の庭園についても言及しています。山里曲輪(やまざとくるわ)と名付けられており、藤原家隆の歌「花をのみ まつらん人に 山里の 雪間の草の 春をみせばや」からとられているそうです。茶室に桜に、まさに秀吉の憩いの場所であったのでしょう。大変美しい庭園だったらしいのですが、皮肉なことに豊臣家滅亡のとき、この庭が秀頼と淀君が自害した場所となりました。二の丸に続く極楽橋は、三途の川の橋を意味し、かつてあった石山本願寺の阿弥陀堂への通路だったそうです。
1585年、秀吉は関白となり、その2年後、京都市上京区に、城郭風の大邸宅・聚楽第を完成させます。聚楽第では、後陽成天皇の行幸も叶い、秀吉の権勢は絶頂期に達します。後陽成天皇の弟で八条宮智仁親王が、秀吉の養子になっていました。そして、江戸時代に入ると、智仁親王が桂離宮を建てることになるのです。聚楽第は秀次に継がれますが、秀次自害とともに取り壊しとなり、大半は伏見城に移築されました。
1592年〜1594年にかけて、秀吉は隠居の城として伏見城を建てます。最初に選んだ場所は指月という場所でした。ここは現在の京都市伏見区豊後橋(現在は観月橋)あたりとなります。その頃はまだ、巨椋池が見渡せ、月を愛でるのに最高の場所とされていました。平安時代、平等院鳳凰堂を建てた藤原頼通の息子で、日本最古の造園書『作庭記』を書いた橘俊綱(たちばなのとしつな)が、この指月の丘に「伏見山荘」を構えていました。「都人暮るれば帰る今よりは伏見の里の名をも頼まじ」と、夕方、帰るぐらいなら、泊まっていけばいいのにと俊綱が詠んだぐらい、去りがたい光景が月夜に見られるのでしょう。
秀吉は、伏見山荘に憧れ、また伏見が不死身に聞こえるのでこの地を選んだのではないでしょうか。残念ながら、1596年に推定マグニチュード7.5以上の慶長伏見地震が起こり、城は崩壊します。指月伏見城は幻と化してしまったのです。
しかし、あきらめずに、秀吉はその隣に木幡伏見城を建てます。聚楽第からも多くのものを解体して、伏見城に運ばせました。天守閣は、望楼型五層で、その姿は「洛中洛外図屛風」にも描かれています。天守からの眺めは、都である京都、そして大坂、奈良と全てが見渡せる絶景でした。
秀吉はここに茶亭学問所を設け、茶会を催しました。また、御舟入から屋形のついた御座舟に乗り、巨椋池に繰り出し舟遊びや観月の宴を楽しみました。桂や宇治、大坂城へも舟で行ったとされています。隠遁の身ではありましたが、天下人秀吉のユートピアをここに築きあげたのではないでしょうか。
明治維新後も、『太閤記』(1625年、小瀬甫庵著)は大変人気でした。新政府の徳川アレルギーがそうさせたのか、明治天皇も『太閤記』が好きでした。だから、この小幡伏見城の跡地に自分の御陵を作らせたのです。今、明治天皇が眠る場所に伏見城があったのは、全くの偶然ではなかったのです。
キリスト教と西洋文化
秀吉が好んで取り入れた建築法の特徴には時代背景と信長にかなり影響されていることがうかがえます。1549年、フランスシコ・ザビエルによるキリスト教伝来、またその少し前、1543年にはポルトガル商人を乗せた中国人倭寇により、日本に鉄砲が伝わります。
ポルトガル人宣教師・フロイスは、自著『日本史』に信長や秀吉と対面したことなどを詳しく書き残しています。キリスト教布教のため持ってきた献上品が、椅子やベッド、絨毯やワインでした。
このときに、西洋の建築法の基本となるものもありました。黄金比、ヴィスタ、そしてパースペクティブ(遠近法)です。この技法を秀吉は、街づくりや庭造りに取り入れたのです。
特に、ヴィスタというルネッサンス・バロック期に誕生し発達した手法を、城下町の町計画に利用したのです。ヴィスタというのは、視界が遠くまでスッキリ見渡せる仕組みです。西洋庭園でよく、中央に配置された噴水や記念碑を中心にした左右対称の景観が見られますよね、あの手法です。
秀吉は、大坂城や聚楽第の城下町の真ん中に、大きな道を走らせ、その両側を左右対称にしました。城からの見通しを良くしたわけです。聚楽第建設時には、「二階建町屋建築令」を発令して、二階建ての町屋が並ぶ城下町を演出しています。その中心に、大手筋という道が一直線に通っていました。直線好きな秀吉にとって、このヴィスタが、整然として好ましく思えたのかもしれません。
また、西洋文化の影響を受け日本庭園に好んで取り入れられていたのが、蘇鉄(そてつ)です。1577年に、京都でキリスト教宣教師によって建てられた教会に初めて蘇鉄が植えられました。これを見たか聞いたかした秀吉が、聚楽第、そして醍醐寺三宝院に植えたのが、日本庭園の蘇鉄の始まりでした。これ以降、多くの日本庭園で蘇鉄が見られるようになりました。他に当時取り入れられた西洋文化が、花壇です。秀吉は、三宝院に初めて花壇を造りました。
秀吉は、信長同様、最初はキリスト教にも寛容でした。しかし、徐々に信者が増えていくキリスト教に脅威を持ち、キリスト教禁止令を出します。
秀吉の建築や美意識にもう一つ大いに影響したのが、茶の湯の千利休です。これに関しては、後ほど千利休と大徳寺黄梅院の項で書かせていただきます。ただ、千利休の周囲の人々(弟子や家族)の多くが、クリスチャンかそれに関係した人々でした。千利休が大成した茶道には、キリスト教の意味合いも深く入り込んでいたのです。

醍醐寺三宝院と伝説の庭師・賢庭
醍醐寺三宝院は、伏見区にあります。室町時代には金剛輪院と呼ばれ、寝殿造の庭園でした。秀吉は1597年、亡くなる前年にここ醍醐で花見をしています。多分、秀吉は自分の死期が近づいていると感じていたのでしょう、「死への恐怖」というものを持っていたのではと思われます。1598年3月に自ら再び花見を企画しますが、準備のために三回も醍醐寺を訪れ、縄張りから着手し、庭造りに没頭していたそうです。秀吉は庭園の完成を待たず亡くなり、その後、住職であった義演准后(ぎえんじゅんごう)が庭師・賢庭(けんてい)を重用して、25年以上の月日をかけて完成させました。
賢庭は、初めは与四郎と呼ばれていました(別人説もあります)が、1615年に後陽成天皇からその名を受けて、江戸期には、作事奉行の小堀遠州のもとで数多くの庭を手がけたと言われています。実はこの賢庭こそが、後陽成天皇の要請で、当時宮廷付工人(きゅうていつきこうじん)であった小堀遠州とともに宣教師から西欧技術や西欧整形式庭園を学び、日本の庭園史に新たな風を吹き込んだ伝説の庭師だったと前出の『建築家秀吉』に記されています。
では、三宝院の庭というのはどういう造りなのでしょうか。醍醐寺三宝院表書院の南側に位置し、中に池があります。もともとは、表書院から眺める座観式でしたが、後に義演准后が回遊、舟遊式に改修していきました。池の西端には現在、出島になっている蓬萊山の石組があります。建物内の泉殿から表書院に進むにつれ、池の中の鶴島・亀島が正面に見えてきます。鶴島には蓬萊山の出島から、木材を苔むした土で固め造られた土橋が架かっています。鶴島と亀島の間に架かる石橋のように、当時は石橋が普通だったのですが、同じような立派な土橋が池の東側にもあり、三宝院の庭のアクセントとなっています。
建物から庭を観たときに、池向こうの中央には、立派な岩組があり、須弥山を表しています。この中央の石がとても個性的です。これが藤戸石で、別名、天下の名石とも言われています。藤戸石は織田信長が好んだ石でしたが、それ以前には八代将軍で銀閣寺を建てた足利義政が所有していたという説もあります。秀吉は、藤戸石を聚楽第に飾っていましたが、最後はここに持って来ました。横に小さな二石を置き、三尊石として、阿弥陀三尊を表しているとも言われます。遠目にも存在感を感じる、表面に模様のある素晴らしい石です。私はこの庭が大好きで何度も来ていますが、やはり庭の重心をこの藤戸石に感じま す。
表書院の東には純浄観(じゅんじょうかん)という一段上がった建物があります。普通は入れませんが、たまたま特別拝観をしていたので、中に入ることができました。建物内を西から東に歩くと、美しい庭は視点の変化とともに、さらにその姿を変えてくれることがよくわかりました。
藤戸石を過ぎてさらに東に向かうと、三段の滝が見えてきます。見事に方向を変えて、三段に水が落ちており、その滝の前に水分石があります。この三段の滝は、明治維新に作られた無鄰菴(むりんあん)の滝のお手本になりました。三宝院の庭は、石のセレクションが素晴らしく、水は深くて紅葉など周りの木々が映ります。石組、植栽、水の流れ、全てにバランスのとれた名庭だと思います。
花見と死生観
有名な醍醐の桜は、実はまだ海外の観光客にはあまり知られていません。お客様を連れて行くと、皆様その素晴らしさに息をのまれます。秀吉が催した花見もさぞ豪華絢爛だったと思います。「醍醐花見図屛風」に豪勢な花見を楽しむ秀吉の絵が描かれていますが、かなり老いており、足元もおぼつかない様子が見受けられます。老いてもなお美しいものを追い求める、秀吉の貪欲な美意識への追求が感じられます。花の命は短く儚く美しい、だからこそ、桜をこよなく愛していたのかもしれません。
花見の後、5月、秀吉は病の床に就き、8月18日に伏見城で62歳の生涯を閉じました。『建築家秀吉』の中に、足利義政や八条宮智仁親王も、現実逃避のために無心で庭造りに打ち込み、その完成を見ないまま死んで行くと記されていました。秀吉も晩年、庭造りに着手し、その完成を見ずに亡くなっています。
庭園を観想することによって静かに現世や来世のことを考え、「死生観」を持つという考え方もあります。私には、豊臣秀吉と足利義満が重なって見えます。自力で富と名声を得て全てを手中に収めても、死の恐怖からは逃れられませんでした。だからこそ、浄土のような庭を造り、そこに自分の死を重ね合わせて、永遠の繁栄を願う。それが、権威を示す豪華な庭に、一抹の悲しみを感じさせる無常観が生まれるのではないかと思います。庭には死生観が存在する、だから人間を魅了するのではないでしょうか。
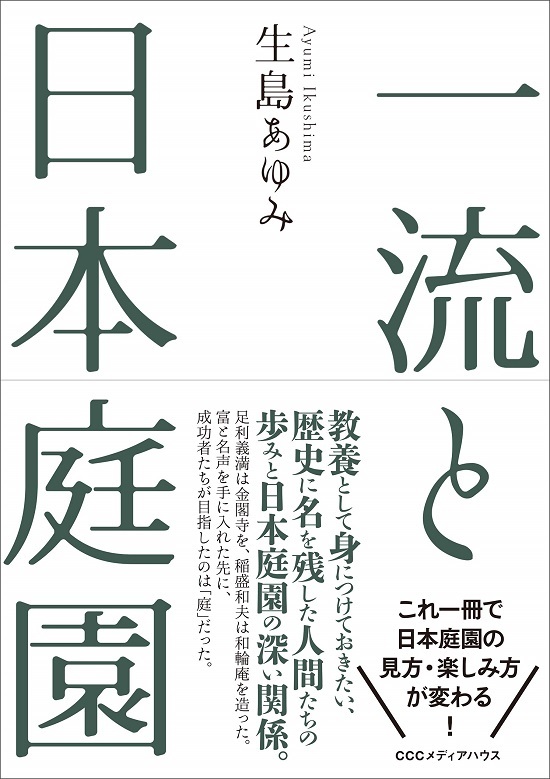
※画像をクリックするとAmazonに飛びます