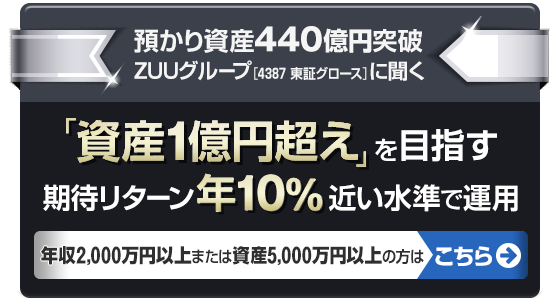多くの富裕層が投資している外国債券だが、1つや2つの銘柄だけに投資するわけではない。基本的には10銘柄以上に分散投資してポートフォリオを設計する。今回は富裕層向けに資産運用コンサルティングを行っている株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口氏に最新の「外国債券ポートフォリオ戦略のポイント」を解説してもらう。

富裕層は外国債券に分散投資する
富裕層の多くは資産を2倍、3倍にすることより、減らさないことを重視するため、株式ではなく債券への投資を選ぶことが多い。とりわけ国内債券にほとんど金利がつかないことから、外貨建ての外国債券に投資する。
なぜ分散投資するかというと、1つの債券が倒産したときの損失を軽減することができるためだ。1つの債券だけに投資していた場合は、その会社が倒産したら投資元本の100%(すべて)を失うが、10社に分散投資すれば1社倒産しても損失は10%にとどまる。
債券投資でどれだけ高い利回りを得ることができても、倒産して大きな損失が出てしまっては意味がない。ポートフォリオを設計することは、安定した利回りを長期的に得るためリスク管理上必要な戦略といえるだろう。
最新の外国債券ポートフォリオ構築事例
百聞は一見にしかず。まずは世古口氏が2022年11月に手がけた実際の外国債券ポートフォリオを見てみよう。
外国債券ポートフォリオ〔運用総額6億円〕

20銘柄に分散した運用総額6億円の外国債券ポートフォリオである。1つずつポイントを解説してもらった。
株式の期待リターンより高い利回り
まずは債券に投資する主な経済効果となる「利回り」についてだ。
今回の例だとポートフォリオ全体の平均の年利回りは8.5%となる。基準となる同時期のアメリカ10年国債の利回りは3%後半なので、かなり高い利回り水準といえるだろう。年間リターン+8.5%は株式の期待リターンよりも高い水準である。
「高い希望利回りを望む方だったので、このように高利回りを享受できるポートフォリオを設計した。運用総額6億円だと年利回りベースの年間予想利益は5,100万円となる。これほどの不労収入が毎年債券から生まれれば、多くの富裕層は満足するだろう」と世古口氏は語る。
為替変動がなく、発行会社が倒産しないという前提だが、債券は償還まで持ち切れば約束された利回りで運用できるので、それなりに高い可能性で8.5%の年利回りは達成されるわけだ。
通貨は米ドル建てが基本
外国債券は「外国債券=米ドル建て債券」と理解していいほど、米ドルが中心だ。
その理由は2つある。1つは日本で取り扱い可能な外国債券の大半が米ドル建て債券という現実だ。ユーロや豪ドル、英ポンド、その他の新興国通貨での投資も可能だが、ラインナップが少なく、十分に選べるほどの債券が存在する通貨は米ドル建てだけになる。
2つ目は利回りの高さである。特にここ1年はアメリカが先行して金利を上げているため、米ドルと比べると他の通貨は債券の利回りが見劣りしてしまう。高い利回りを得たい富裕層なら米ドルを選ぶことになる。
高利回りの劣後債中心
劣後債を中心にポートフォリオを構成していることも、平均利回りが高い理由の1つである。表の債券種類を見ると3銘柄の普通社債を除いて、すべてが劣後債となっている。
劣後債とは、簡単にいうと、発行会社が倒産したときに債券(債権)保有者に資金が返ってくる順番が普通社債よりも遅い代わりに、高利回りを享受できる債券の一種だ。
現在は、高水準の利回りを得たい多くの富裕層が劣後債をポートフォリオに組み入れている。「今回の例の富裕層も希望利回りが高かったため、大部分を劣後債で運用する必要があった」(世古口氏)という。
本記事の主題はポートフォリオなので詳しい解説は割愛するが、劣後債のことを詳しく知りたい方は「富裕層がこぞって投資する『CoCo債』の魅力」をご覧いただきたい。
格付けでリスク管理
リスク管理の観点からは、格付け会社の格付けが重要になる。基本的には、アメリカの三大格付け会社S&P、Moody’s、Fitchが「BBB」以上の格付けを付与している債券を選ぶことが好ましい。
格付けBBB以上の債券は、BBB未満の債券と比較して、倒産する確率が段違いに低くなるからだ。また格付けBBB以上の債券は、多くの年金やファンドなどの機関投資家の投資対象となる。BBB未満の債券と比較すると取引量が多く、流動性も高いためだ。
今回のポートフォリオだと20銘柄中14銘柄(全体の7割)が債券格付けBBB以上である。
残りの6銘柄はBBB未満の債券ということだが、劣後債は発行会社自体の格付けよりも債券の格付けが低くなっており、発行会社そのものの格付けだと20銘柄中18銘柄(全体の9割)がBBB以上、2銘柄がBBB未満となる。
「格付けが低い債券をさらにポートフォリオに組み込むことで、全体の利回りを高めるという選択肢もあったが、リスク管理の観点からこの程度にとどめている」(世古口氏)という。
3つの分散でリスクを低減
外国債券のポートフォリオ設計においては、以下の「3つの分散」もリスク管理において重要だ。
1つ目の分散は「一債券あたりへの投資金額の分散」である。今回は20銘柄に均等に投資しているので、一債券あたりの保有比率は5%だ。万が一いずれかの債券が倒産しても5%の損失であれば、8.5%の年利回りでカバーすることが可能というわけである。
2つ目の分散は「債券を発行する会社の所属国や業種の分散」である。企業は所属する国や業界全体のリスクにある程度依存するので、発行会社の国や業種も分散した方がよい。今回のポートフォリオだと7カ国、7業種に分散投資をしている。
3つ目の分散は「残存年数の分散」である。債券の償還で資金が返ってくるタイミングを1年後、3年後、5年後、7年後と分散することで、償還資金を再投資するときの利回りを平均化できる。3年後に返ってくる債券だけだと本来8.5%の利回りが、再投資したときには低金利で利回り4%(仮定の数字)になってしまうリスクがある。
債券は減点法の投資
外国債券ポートフォリオ戦略のポイントについてご理解いただけただろうか。
債券は確定利回りである代わりに、その利回りを超える利益はほとんどの場合、発生しない。つまり債券投資においては数%の利回りなら、それをいかに減らさないかという戦いになるわけである。一発逆転で2倍、3倍を狙える株式とは異なり、債券は減点法の投資といえるだろう。
それゆえ今回のテーマの「ポートフォリオ設計によるリスク管理」が特に重要になるわけだ。いかに持ち点(利回り)を減らさないように投資先を分散して、倒産しない会社を選ぶかが勝負となる。
IFAやPBなど専門家に相談
それなりにバランスのよいポートフォリオを設計したい場合は、IFAやプライベートバンクなど金融資産の専門家に相談することをお勧めする。本記事をご覧いただいてわかるように、少数の銘柄に投資することと違って、全体のバランスを考える必要があり、難易度が高い投資となるからだ。
特に高い利回りを希望する場合は、格付けが低い債券に投資しなければならないので、詳細な財務分析や緻密なリスク管理が必要になるだろう。
さらに情報を知りたい方へ
キャッシュフローの最大化を図るには、節税はもちろん、さらに効果的な資産運用サービスを知っておく必要がある。
詳しい情報をご希望の方は、株式会社ZUU 富裕層向け金融サービス専用フォームからのお問い合わせをおすすめしたい。
資金調達の方法に始まり、運用から、償却に至るまでのキャッシュフロー全般の情報を、 金融機関65社との接点を持つZUUグループなら「中立的」な立場で紹介可能だ。
ZUUグループでは、これまでに保有資産額10億円〜100億円超の方々に至るまで、 不動産、外国債権、ブリッジローンといった幅広い金融サービスをご提案している。
まずは以下のフォームで回答してみよう(所要時間1分)。