
製造業のDXに対する取り組みについて、コアコンセプト・テクノロジー(CCT)CTOでKoto Online編集長の田口紀成氏が対談する本企画。第19回のお相手は、オーエスジー株式会社のIT戦略部で部長を務める原田剛氏です。
金属加工において、穴の内側にねじを刻むタップを柱に、エンドミル、ドリル、転造工具などを製造・販売する総合切削工具メーカーとして知られる、オーエスジー。同社の製品は自動車や金型、航空宇宙、エネルギー、重工・機械などありとあらゆる製造業で使用されています。また、1968年に最初の現地法人をアメリカに設立して以降、企業理念「地球会社」のもと、世界33ヵ国に製造・販売・技術サポート体制を整備するなど、グローバル企業として著しく発展を遂げているのも特徴です。
オーエスジーでは業務基幹システムの刷新を中心に、近年は社内におけるDXを加速させています。これにより業務効率を上げるだけでなく、固定費の削減によって投資に回すIT予算を確保するのが狙いです。今回の対談では、同社におけるDXの進展や具体的な取り組みについてお聞きしました。

1999年東京都立大学理学部物理学科卒業後、日本ユニシス株式会社に入社。プロジェクトマネージャとして大手企業の基幹システム導入プロジェクトに従事。2012年にオーエスジー入社。オーエスジー入社後はシンガポールに赴任し、東南アジア圏の情報システム責任者として域内のIT推進を担う。各国のERP、WMS、生産管理システムの導入を主導。2017年に帰国し、2019年から現職。

2002年、明治大学大学院理工学研究科修了後、株式会社インクス入社。自動車部品製造、金属加工業向けの3D CAD/CAMシステム、自律型エージェントシステムの開発などに従事。2009年にコアコンセプト・テクノロジーの設立メンバーとして参画し、3D CAD/CAM/CAEシステム開発、IoT/AIプラットフォーム「Orizuru(オリヅル)」の企画・開発などDXに関する幅広い開発業務を牽引。2014年より理化学研究所客員研究員を兼務し、有機ELデバイスの製造システムの開発及び金属加工のIoTを研究。2015年に取締役CTOに就任後はモノづくり系ITエンジニアとして先端システムの企画・開発に従事しながら、データでマーケティング&営業活動する組織・環境構築を推進。
目次
高齢化や人口減、属人的な業務がビジネス上の課題
田口氏(以下、敬称略) 原田さんは、どういったキャリアを歩まれてこられたのでしょうか。
原田氏(以下、敬称略) オーエスジーに入社したのは、2012年のことです。入社と同時にシンガポールに赴任し、情報システムの責任者として各国のERPやWMS、生産管理システムの導入を主導するなど、東南アジア圏におけるITの推進業務を担いました。その後、2017年に帰国し、2019年から現職であるIT戦略部の部長を務めています。
田口 前職もIT関連だったのですか。
原田 IT企業に12年間勤め、プロジェクトマネージャーとして、大手企業の基幹システム導入などに携わっていました。
田口 長きにわたり組織におけるITの推進に携われていますが、オーエスジーがDXを意識するようになったきっかけについて教えてください。
原田 やらざるを得ない状況になったというのが大きいと思います。当社はとりわけDXが進んでいるわけではなく、むしろ昔ながらのアナログなものづくりの会社です。時代に取り残されないようにしなければ、というのが赤裸々な理由です。従業員の高齢化や労働人口の減少など産業界共通の課題は当社にも影響を与え、属人的な個別プロセスも看過できない状況になっています。
田口 属人的なプロセスとは、具体的にどういったことでしょうか。
原田 対応力の高さは当社の強みですが、これは言い換えると「現場の努力で個別要件に応える」ということです。納期要望や製品仕様の要求に柔軟に対応することでマーケットを獲得してきました。柔軟に対応するということは、一方でイレギュラーな業務フローをたくさん生むことになります。85年も会社が続いていると、そういうものの蓄積が生産性の低下を招いていることも事実です。
現場の頑張りで吸収するには限界があり、今後も対応力を差別化要因にしていくのであれば、テクノロジーの力でバックアップする仕組みが必要だと感じています。
田口 短納期だと、残業なども大変ではないでしょうか。
原田 アウトプットは時間に大きく依存します。現場の残業時間は受注量に左右されます。そういった労働集約的な働き方を変えていくこともDXの目的の1つだと考えています。
田口 その波に応え安定的に製品を供給するとなると、属人化するのではなく、DXを活用しなければなりませんね。
原田 機械はあっても段取り工が足りず生産高が上がらないといった問題もあり、人に依存する領域を減らしていく必要があります。
田口 段取り部分がネックというのは、製品の数が多いからですね。
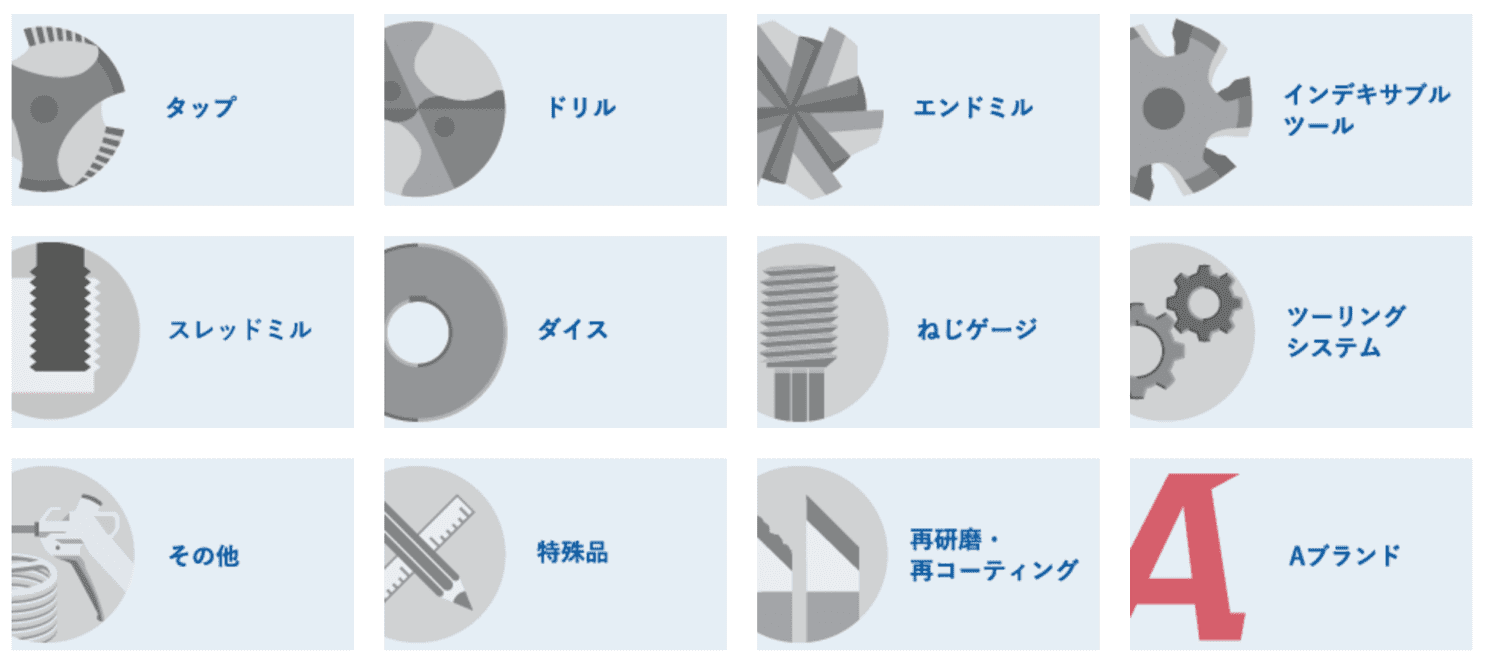
原田 工具はカタログ品だけで約6万アイテムあり、標準品に加えてお客様固有のカスタマイズ品もあります。そうすると機械の種類も多種多様で同じ型番でもクセが異なる、このアイテムはこの人でないと段取りできない、現場の班長しか知らないという世界になるのです。
田口 しかしながら、ロボットに置き換えるというような一足飛びは難しいでしょうから、少なくとも属人的でないようにするのが、最初のステップのようですね。おそらく、納期を含め仕事の取り方も営業担当者次第のところがあり、製販の連動をスムーズにするのも目下の課題なのだと受け取りました。
原田 かつて営業のトップから「うちは”ビジネス”ではない、”商い”だ」と言われたときは、「あるべきプロセス」を振りかざしがちなITの仕事はやりにくいなと感じました。
田口 杓子定規にいかないという意味なのでしょうが、非常に分かります。ですが、その人間関係の機微をある程度柔らかくするためにも、デジタル技術の適用は効果的だと思います。
現場のストレス軽減がDXの目的
田口 そういった中、DXに取り組み始めたのは、いつからですか。
原田 4~5年前からです。ただし、当時は世の中が言い出したから歩調を合わせただけで、目的と手段がリンクしておらず、こういう世界を目指すからDXが必要だという文脈にまで落とし込めていませんでした。「生産性が改善するのでは?」といった漠然とした期待でDXという言葉を上層部は使っていたと思います。ですから、当社におけるDXは何かを定義することも重要です。
田口 さきほどの「商い」の言葉に象徴されるように、人が主体であることは変わりないと思います。人間関係を主軸としながらも、そのやり取りを効率化し人依存にしないといったアプローチが考えられるかと思いますが、いかがですか。
原田 デジタルやマシーンが人に取って代わるアプローチではなく、現場のストレスが軽減することが、当社における正しいDXの姿だと私は捉えています。こういった考えについては、経営層と話す機会を増やさなければなりません。
田口 経営層にとって、DXにより自分たちのビジネスが効率よく進む姿が想像できないというのは、なんとなくわかります。人間関係で成り立っていると感じるからこそ、意識改革からスタートする必要がありそうです。
原田 多品種を手がけ個別要件にも対応しているので無人化が正しいとは限りませんが、全アイテム中のいくつかは無人で加工できるようにすることを入り口にする気はします。
田口 商品点数が多いと、自動化のラインを作るだけでも随分なコストがかかり、技術力も求められます。やり遂げたときの価値は高いのでしょうが。
原田 社内には商品点数を整理しないと、生産性の向上が見込めないと主張する従業員もいます。ただし、厚い製品ポートフォリオが他社との差別化要因であることも事実です。こういったジレンマがあることも、忘れてはなりません。
ERPパッケージからの解放を目指す
田口 原田さんはDXの一環として、基幹業務システムの刷新に取り組んでいるとお聞きしています。
原田 現在使っているERPパッケージが導入から13年目を迎え、老朽化したことが理由の1つです。また、これまで使いづらいものを皆が無理して使っていたのではないかという反省も背景にあります。次の10年を支える基幹業務システムは、外資系ベンダーのパッケージに合わせるのではなく、自分たちは何者なのか、どういう考えでものづくりをしているのか、といった点を大切にしたうえで、フィットするアーキテクチャを選ぶ必要があると考えています。その役割を担うのが私と私のチームであり、会社が提起するものづくりのコンセプトに沿ったシステムを選定・導入する計画です。

田口 多くの企業を見ていると、基幹業務システムは競争領域のものではなく、こだわる意味もないという理屈から、外資系のパッケージに乗っかるように業務を変えるケースは少なくありません。御社はその真逆を行くわけですが、それは業務の中にある自分たちの強みを理解しているからですか。
原田 自分たちの強みをしっかり認識することから始めるのが、今回のプロジェクトでは重要だと思っています。ERPは記録のためのシステム、と割り切るのは日本企業には難しいでしょう。自分たちが作ってきた仕事のやり方こそが競争優位を生むもので、システムは忠実に人を支援すべきもの、という考えが根強いです。結果、ERPをフルカスタマイズするようなことが起こります。譲れる・譲れない領域をしっかり分別できるような進め方の工夫をしないといけません。それをできる人材が13年前はいませんでした。結局はすべてをやろうとして、すべてが中途半端になったのが、13年前のプロジェクトだったのです。
田口 基幹業務システムについて、改めて考える時期に差し掛かっているわけですね。私が知るある会社はERPの導入に3度失敗していますが、その原因は膨大な商品点数を扱うためのデータベースを取り込み切れなかったことでした。これを使い商品の価格決定や開発を進めているので、失うと営業上の強みを失うわけです。たくさんある商品をどのお客様にも届けられるようにしておくことを考えると、ERPがフィットしないこともあります。
原田 なかなか世の中に答えはなく、特に受注フロントなど顧客接点になるところは商品点数が多い課題もあり、お客様ごとに個別プロセスもあります。何かパッケージを持ってくるチャレンジではなく、腹をくくりスクラッチで進めようと判断しています。
田口 まずは運用し、そこで改めてERPを活用するなら導入する流れが良いと思います。今はノーコード・ローコードのクラウド環境もあり、コストを抑えて実装できる環境が整っています。
原田 受注フロントなどは、どうしても個別で作り込む部分をゼロにできません。ERPをベースにしてカスタマイズで作りこむという選択肢も考えましたが、そういう使い方をするには、ERPはあまりに高額です。ならば、スクラッチ開発の方がコストを抑えられるという発想です。
田口 確かに、そういった臨み方もあるでしょう。
原田 一方で生産管理の領域は、なんらかのパッケージソフトをベースにしたいと思っています。当社はメーカーなので生産がコアであり、世の中でこなれた生産管理のエンジンは、可能な範囲で使うべきです。ノーカスタマイズで導入はできないでしょうが、生産管理パッケージの中から当社にマッチするものを選定します。13年前は全業務領域をワンパッケージで、というERPのコンセプトに従いましたが、領域毎に分解していくのが今回の作戦です。
田口 業務そのものをデジタルに移行する中、どのように業務を定義するのか押さえておかないと、失敗を招きかねません。大きなチャレンジに映りますが、リスクを負ってまで進める理由は何でしょう。
原田 実現可能な唯一の選択肢と思われるのが、この業務領域毎に分割したシステム切替です。全業務をERPで一気に入れ替えるという13年前のようなプロジェクトは実行が難しいでしょう。私が取ろうとしているアプローチは個別最適に陥るリスクは否めません。しかし、実行可能で、広く現場の共感を得られるシステムを作り上げるために、この方針で取り組みたいと考えています。
田口 我々はクライアントに対してERPの導入を支援したことはありますが、社内はほぼスクラッチで対応しています。当社の業務はIT人材を大量に扱い、毎月異なる契約が発生するので、通常の基幹業務システムで回すと、とてつもない工数がかかるからです。今はノーコード・ローコードの環境もあるので、資金がありデザインする人材がいるなら、スクラッチは最も効率が良いと思います。掛け値なしにおすすめできることではありませんが、原田さんのように業務を定義して運用できる方がいるなら、有効な手段でしょう。今後はどういったスケジュールで進める方針ですか。
原田 現在開発している受注管理システムが構築できたタイミングでERPから入れ替え、その次は生産管理領域、のように既存ERPからの部分的な切り出しを続けていきます。最終的には会計帳簿だけがERPに残り、それも2029年までに他のソフトに置き換える予定です。
ERPの保守サービスを第三者方式に移行しコストを半減
田口 ERPの保守を第三者方式に移行したこともお聞きしています。
原田 当社はIT予算を、維持運営のための固定費と、変革に寄与する投資に分けて把握していますが、デジタル化に伴い固定費の増大に悩まされていました。固定費とは、IT資産の保守やリプレイスに伴う費用、クラウドサービスの使用料など、ビジネスの景況感に関わらず一定の額で発生する費用です。もちろん必要な支出ですが、固定費はなるべく抑え、限られたIT予算をできるだけ多く変革のための投資に回したいと思っています。。特に、ERPの保守サポート料は非常に負担が重く、この削減のために第三者保守を選びました。これにより、ライセンス保守料は半減しました。
また、データベースサーバーは、そのERPベンダーが提供するアプライアンス製品を使用していたので、保守サポートを解約した後も使い続けることでさまざまな課題が挙がっていました。そのため、ハードの保守切れのタイミングで、独立系ハードウェアベンダーの製品に切り替えています。
田口 価値に直接貢献する部分ではないので、コストの理由を説明するのも難しいと思います。
原田 ERPの保守サポート料は毎年億単位の支出になりますが、それに見合うリターンが不明確です。ですので、解約を決断しました。メガベンダーの囲い込み戦略は、ユーザー側からすれば選択肢を失い、健全とは言えません。あらゆる事に対し自社で選択肢を持つ、というのが私のIT選定の重要な方針です。ERPから離れるのもコスト面だけではなく、すべてを預けると身動きが取りづらくなるからです。
田口 削減した分の費用は投資に回せていますか。
原田 以前はIT予算の8割を固定費が占めており、さらなる上昇が危惧される中、歯止めをかけた格好です。削減した分で現場主体の工場DXを後押ししたいと考えています。会社がDXを進める上で私がすべきことは、限りあるIT予算の中から投資に使える部分を確保することでした。固定費の削減にメスを入れ、保守費の削減などにつなげるなど、一定の成果を収めることはできたと思います。
田口 同じような課題を抱えているIT部長はたくさんいるでしょうから、原田さんの姿勢や実践は非常に参考になるでしょうね。
原田 トップはDXのキーワードを出しますが、我々のミッションは実現に向けた具体策に落とし込むことです。経営層が思うことを自分なりに解釈し、行動に移すことが何よりも重要だと痛感しています。
田口 普段の情報収集やパートナー選びに工夫はありますか。
原田 一般的なメディアや雑誌には目を通しますが、特別なことはしていないと思います。自社に合う有効なデジタル戦略の答えは、自分で考えるしかありません。パートナーに関しても、自分から声をかけた相手としか付き合わないですね。自社がしたいことを明確に決めたうえで、みずから探しに行かないと、うまくいかないからです。
例えばセキュリティだと、エンドポイント、ネットワークなど、メーカーによって売りは異なります。優先順位を決めてから社外パートナーに声をかけないと反対に振り回されるので、チーム内でもこのプロセスを守っています。
全社的なデジタルリテラシーの底上げに着手
田口 これまでの取り組みの手ごたえはいかがですか。
原田 デジタルを使ってみる土壌は育ち始めました。また、経営層から意見を求められるなど、IT部門の社内での地位は上がった気がします。DXの良し悪しで業績が左右されるようなデジタル依存度の高い会社体質が作れれば私のミッションも達成であり、そういった状態で次の世代にバトンタッチできれば幸いです。
田口 さらなるDX推進に向けて、デジタル人材の育成はどのようにお考えですか。
原田 特定の部署だけでなく、全社的なデジタルリテラシーの底上げが必要です。この部分は今まで活動が足りていなかったと自覚しています。経産省が「DXリテラシー標準」を発表していますが、経営層を含めた全社員が身につけるべきだと思います。今後は目標値や必要なスキルを定義し、DXの推進人材とリテラシー人材を育成する教育カリキュラムや認定制度を構築する方針です。

一部の社員でトライアル的に特定のDX施策を進めるのは、初期の刺激としては有効です。しかし、本当の成果に繋げるには、DXが会社全体の大きなうねりにならないといけませんし、風土として根付かせるには誰も置き去りにせず、全社員にデジタルの知識を身につけてもらう必要があります。現場力に優れた社員たちが、さらにデジタル脳も兼ね備えた時、オーエスジーの次の成長が始まります。それを考えるとワクワクします。
田口 全体を考えたとき、どの部分は外部に頼り、どの部分は内部で持たないといけないか、基準を設けていますか。
原田 新しいテクノロジーを導入する時は外部でも良いですが、仕事をわかっている者が主導しないとDXは実現しません。現場の人たちにプラスアルファの武器としてデジタルの知識を身につけてほしいと考えています。
田口 今のお話から思うに、DXの成否を握るのは「人」であるわけですね。
原田 現場力あってこその当社には、人不在のデジタル改革は成立しません。データを蓄積するための入力業務で作業者のストレスが増えた、などということでは本末転倒です。難しいのは「現場主体」だとカイゼンの域を出られないことです。アナログ脳のままで「どこかにデジタルを使えないか」というアプローチだとこれに陥ります。「デジタル脳で仕事を再構築する」という発想が必要ですが、これがとても難しく、会社全体にデジタル思想を植え付ける地道な努力が不可欠で、それ以外の近道はないかもしれません。
田口 DXを通じて目指すべき姿について、どのようにお考えでしょうか。
原田 デジタルで人を置き換える発想は成り立たず、現場主体、人中心であることは、これからも変わりません。一方、その人たちが疲弊しているのが実情なので、DXによりストレスがなくなり、一層ワクワクする、創造的な仕事に目を向けられるようになってもらいたいと思います。作業員が代わってもプロセスとシステムが出来上がっているので一定水準の成果が上がるというのが、当社の目指す姿です。
田口 最後に、Koto Onlineの読者にメッセージをお願いします。
原田 日本の製造業が再び輝きを放つことを夢見ています。我々日本人が本来備えている強みをDXで加速させるには、人間の意思をどこまで介在させるか、デジタルとの最適な均衡点を探ることが重要だと思っています。
田口 本日は御社の課題や解決に向けた方向性、基幹業務システムに関する具体的な施策について、お聞きすることができました。ありがとうございました。

【関連リンク】
オーエスジー株式会社 https://www.osg.co.jp
株式会社コアコンセプト・テクノロジー https://www.cct-inc.co.jp/
(提供:Koto Online)