本記事は、午堂登紀雄氏の著書『教養としてのお金の使い方』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

情報を制する者がお金を制す
情報に振り回されると財布を開かされる
かねてより、情弱つまり情報弱者とは「知らない」「最新情報にアクセスできない」人を指し、ゆえにチャンスを逃したり不利になったりするという文脈で使われてきました。
確かにインターネットがなかった時代、知っているか知らないかで差がつくことは多かったですし、いまでもその側面はあります。
しかしネットで誰もが気軽に世界中の情報にアクセスできる時代になっても、いやだからこそ、情弱があぶり出される傾向が強くなっています。
ここでいう情報弱者とは、他人の情報を
どんな最新情報や有益な情報があったとしても、それをうまく活用できなければもともとなかったのと同じです。もしそれによって誤った判断につながったとしたら、そんな情報はむしろマイナスでしょう。
たとえば昨今「闇バイト」という事件がニュースになっていますが、SNSでこれらの高収入バイト情報を見て疑わない人などはわかりやすい例だと思います。
そもそも真偽のほどが確かでないSNS上に、信頼できる求人情報があるでしょうか。誰でもできる・短時間で済む仕事に、なぜそんな破格の賃金が支払われるのか疑問に思わないでしょうか。秘匿性の高いメッセージアプリに誘導されたとき、仕事なのになぜそんなコソコソするような連絡手段を使うのか、おかしいと思わないでしょうか。
そして、案件の内容が犯罪だとわかっても、警察など然るべき機関に相談しようと思わない(相談できない)わけですから、「情報」を鵜呑みにし、振り回され、そのおかげで自分が不利になってしまう典型例ではないでしょうか。
わかりやすい例として闇バイトを引き合いに出しましたが、情報弱者はこの例に限らず生活の全方位で情報に振り回されます。
たとえば「リボ払いは毎月一定額の返済だからオトク」とか「この食品を食べると
あるいは「投資」と「出費」の区別がついておらず、たとえば「奨学金は借金だ」などと騒いだり、「自分へのごほうび」「映えるから」などと根拠のない支出を重ねます。また、詳細は後述しますが「SNSの詐欺広告」に騙だまされる人も後を絶ちません。
このように、情報処理能力が低いままでは「お金は出ていくけれど入ってこない」という状況に容易に陥ってしまうでしょう。
情報処理能力を高めればお金は「万能の道具」になる
もし「がんばっているのに一向に収入が増えない」「節約しているつもりなのにお金が貯まらない」「便利な世の中になっているはずなのに、生活に余裕がない」と感じているとすれば、まずは情報処理能力を高める必要があるといえます。
それはたとえば自分に必要な情報を取捨選択する能力、その情報をさらに掘り下げてウラを取ったり比較したりする検証能力、情報の裏に隠されている意図や本質を読み解く洞察力、自分や生活への影響を考察する想像力のことです。
これらの力を高い水準で獲得できれば、収入を増やしたり、無駄な支出をなくしたり、銀行からお金を借りて投資したりなど、自分のお金だけでなく他人のお金すらも自由自在に扱い、生活を豊かにすることができます。
まさにお金を「万能の道具」としてフル活用できるわけです。
- POINT
- 「情報処理能力」を磨いて生活を豊かにする
スマホ料金があなたのマネーリテラシーである
「よく考える人」と「考えない人」の差が出る
過去5年間で、自分のスマホや携帯電話の料金プランを何度見直したでしょうか。
「見直したことがない」と言う人でも、「自分のライフスタイルに最もフィットし、最もコスパのよい料金プランを選んでいる」と自信を持って言える人はどのくらいいるでしょうか。
各社から毎年のように新プランが発売されているうえ、通話時間にパケットの量、パケットの繰り越しやシェア、家族割から各種付帯サービスとの併用割引など、複数の要素を組み合わせることになりますから、選択肢は膨大です。
そのため、「複雑だ」「よくわからない」という印象を持つ人も少なくない。ゆえに「よく考える人」と「考えない人」の差が出やすいのです。
ここで思考を放棄する人の典型例が「大手キャリアのセットプランを選ぶ」か、「店頭で店員に(もしくは家族や友人などに)おすすめされたプランを選ぶ」かのいずれかではないでしょうか。
さらにスマホ・携帯は今後生涯にかけて加入し続けるものですから、累積すると金額的にも大きな差を生みます。たとえば月5000円だとしても、1年で6万円、40年で240万円にもなりますから。
つまり誤解を恐れずに言えば、毎月のスマホ料金が自分のマネーリテラシーを反映している可能性があるのです。
自分にとっての優先順位を考える
どのキャリアで契約するかの前に、自分にとっての優先順位を考える必要があります。たとえば、
- 通話品質(つながりやすさや音質)は重要か
- 通話頻度・通話時間はどのくらいか
- パケットはどのくらい消費するか
- 留守電機能は必要か
などです。
これらに加えて、ほかの要素、たとえばパケットシェアや繰り越し、家族割、2年縛りの有無などさまざまな項目を加味して、最適なプランを選び、それを提供するキャリアのなかから最も有利なサービスを契約することになります。
しかも毎年のように新サービスが出てくるので、それらとも比較を続ければより有利なプランを利用できます。
もちろんお金があり余っていて「そんなのどうでもいい」とか、忙しくて「ほかにもっと考えるべき重要なことがある」と言う人には関係のない話ですが、5,000円のスマホ料金が半額になっただけでも40年で120万円の差になりますから、一般の人には見直す価値はあるのではないでしょうか。
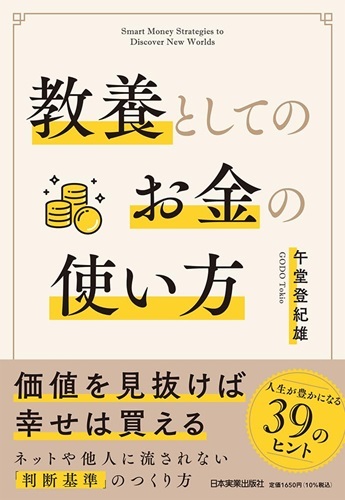
現在は不動産投資コンサルティングを手がけるかたわら、資産運用やビジネススキルに関するセミナー、講演で活躍。著書に、『捨てるべき40の「悪い」習慣』『「いい人」をやめれば人生はうまくいく』『孤独をたのしむ力』(以上、日本実業出版社)、『33歳で資産3億つくった僕が43歳であえて貯金ゼロにした理由』(日本経済新聞出版社)などがある。※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
