本記事は、午堂登紀雄氏の著書『教養としてのお金の使い方』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。
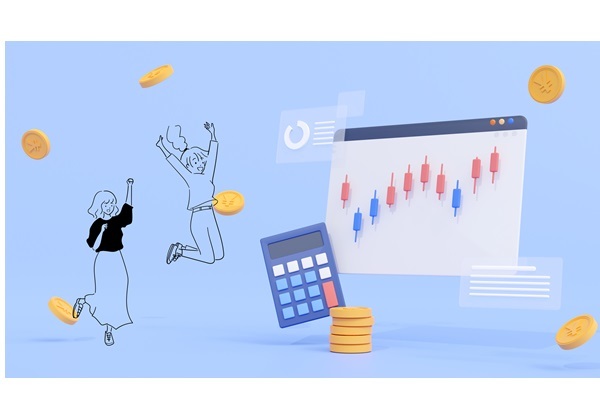
iDeCoをやらない理由が見当たらない
老後のための資産形成で有力な方法のひとつが「iDeCo(個人型確定拠出年金)」です。
iDeCoは収入の低い人でも年利15%、平均的な年収500万〜800万円の人なら年利20%、年収1,000万円を超えるような人なら、年利33%もの高利回り商品となりえます(独身者の場合。家族構成や所得によって異なります)。
超低金利時代の現在、資産運用で年利10%という数字を上げ続けるのは至難の業ですが、それがiDeCoを活用すれば、本人の努力や才能とはまったく関係なく、15%や30%超といった年利を稼げるのです。
実はこの利回りは、減税効果によるものです。
iDeCoの掛け金は全額所得控除されるため、所得税と住民税が安くなります(会社員の場合は、毎年の年末調整による所得税の還付、翌年の住民税が減り毎月の手取り額のアップとなります)。
「増やす」というより「(税金という)支出を減らす」ことで実質的な経済的メリットが得られるのです。
節税は景気に左右されることもありませんから、〝株価や為替とはほぼ無関係に、さらに本人の能力とも無関係に、メリットを享受できる〞制度なのです。
では、弱点はないのでしょうか?
iDeCoは金融商品を自分で選んで自分で運用する制度なので、うまくやれば資産の増加が期待できます。しかし反面、相場の変動によって元本が減る可能性があります。
もちろん定期預金や保険商品を使えば、途中解約しなければ基本的に元本が減ることはありませんが、インフレ時には実質的に目減りすることになります。
とはいえ、仮に運用で利益が出なくても、インフレで若干目減りしたとしても、何もしないよりは節税分だけ確実にメリットが得られます。
また、iDeCoはいったん始めたら60歳までは引き出せない制度なので、使いたいときに使えない、という点を指摘する人もいます。しかし逆に、老後資金を強制的に貯められるという点においては、むしろ長所と言えるでしょう。
加入期間中に得られた運用益(金融商品の売却益、分配金、利息など)は全額非課税で、対象となっている投資信託にかかる手数料も非常に安い。
60歳を迎えてiDeCoの年金を受け取るときは、一括で受け取る「一時金方式」か、毎年少しずつ受け取る「年金方式」、あるいはその併用から選べます。
そして、所得税の計算では、一時金方式なら「退職所得控除」、年金方式なら「公的年金等控除」の適用を受けることができます。
これは、民間の保険の満期返戻金や年金が一時所得や公的年金等控除の適用されない雑所得扱いで、総合課税となるのと比べても、非常に優遇されています。
つまりどんなに「iDeCoをやらない理由」を探しても、私には見つからないのです。
なので投資信託での運用の最優先はiDeCoです。ただし後述しますが掛金上限は小さいので、余裕がある人はプラスしてNISAでの運用がよいと思います。
iDeCoと通常の年金との違い
ここからは少し詳細にiDeCoの制度について解説していきます。
iDeCoを単純化して言うと、「加入者が毎月掛け金を払って、定期預金や保険、投資信託などで運用し、60歳以降に年金として受け取る制度」です。
これは、サラリーマンが加入している厚生年金、自営業者が加入している国民年金とは別の年金制度です。
通常の年金と大きく異なるのは、年金が「賦課方式」(現役世代から広く保険料を徴収し、受給者にそのままスライドして分配する)なのに対し、iDeCoは「積立方式」である点です。
賦課方式の年金は、「将来いくらもらえそうか」というシミュレーションはできても、徴収された年金保険料は全員の分がごちゃまぜにされるため、自分が預けたお金がいまいったいいくらになっているのかはわかりません。逆にこれが不公平感の元にもなっています。
一方、積立方式のiDeCoは、自分がもらう年金は自分で積み立てる方法で、自分で積み立てたお金はすべて自分で受け取ることができます。
iDeCoは自己責任型の年金形成法
また、iDeCoは「見える化」と「持ち運び」もできます。
積立をしている金融機関の専用ウェブサイトにログインすれば、自分のお金がいまいくらになっているかがすぐにわかります。
転職・離職する場合でも、自分のiDeCoを持ち運ぶことができます。
また、iDeCoは運用方法を自分で決める制度なので、払い込みの窓口となる民間の金融機関(銀行や証券会社など)を決め、そこが用意している金融商品のなかから自ら選びます。
商品の種類は、大きく「元本確保型」のものと、「元本変動型」のものに分けられます。
前者には定期積立預金や確定給付型の生命保険が、後者には投資信託があります。
掛け金は通常の年金などと同じく「全額所得控除」ですが、民間の保険と同様に、会社員なら年末調整(会社に控除証明書を提出)、自営業者なら控除証明書を添付して確定申告をします。
加入期間は最低10年で、10年以上加入すれば60歳から受け取れます。仮に52歳で加入した場合、受け取りは62歳からと後ろにずれる形になります。
このように、自分で積み立て、運用方法も自分で選ぶという、完全な自己責任の年金です。
iDeCoの加入条件と掛け金
iDeCoを含む確定拠出年金は大きく分けて、「企業型」と「個人型」の2種類があります。
企業型(企業型DCといいます)の場合、会社が制度を導入し、社員のために掛け金を拠出します。会社が負担する金額に加えて、個人が追加で拠出できる「マッチング拠出」も可能です。
個人型(iDeCo)の場合は、各人が自分で掛け金の金額を決め、自分のお金で積み立てていきます。
毎月の掛け金は最低月5,000円からですが、1,000円単位で指定できます。途中で金額の変更も可能で、届け出を提出すれば年1回まで可能です。
家計が苦しいときは、会社や金融機関に届け出をして一時的にストップすることもできます(その間は退職所得控除の加入期間にカウントされません)。
拠出できる掛け金の金額は、会社員か自営業か、あるいは会社の制度の有無によって上限が決まっています。
自営業者の場合は個人型iDeCoで、掛け金は国民年金基金と合わせて月6万8,000円までです。
たとえば国民年金基金に毎月2万円払っていれば、確定拠出年金の掛け金は月4万8,000円までということになります。
会社員の場合は、勤務先の年金制度によって変わります。
会社が企業型DCを導入していれば、掛け金は合計で月額5万5,000万円まで(ただし、マッチング拠出を利用している場合はiDeCoの利用はできません)。
企業型DCではない確定給付型の企業年金制度(厚生年金基金など)を導入している企業の場合、掛け金の上限は月額2万円(企業年金によって異なる)。
会社が企業型DCも企業年金制度も導入していなければ、自営業者と同じく個人型iDeCoの扱いとなり、掛け金の上限は月額2万3,000円(自分の預金口座からの引き落とし)。つまり普通の企業に勤めている会社員は、少なくとも月額2万3,000円までは払い込むことができるということです。なお、掛金上限については現在見直しの検討が行われており、増額される見込みです。
- POINT
- 完全に自己責任の年金「iDeCo」を使いこなす
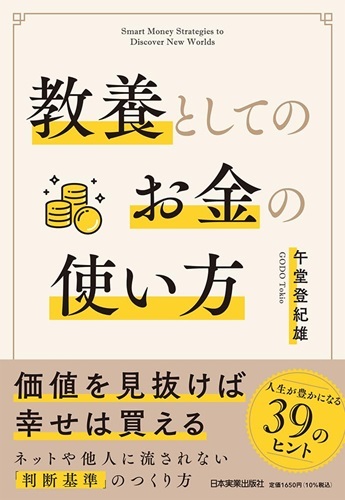
現在は不動産投資コンサルティングを手がけるかたわら、資産運用やビジネススキルに関するセミナー、講演で活躍。著書に、『捨てるべき40の「悪い」習慣』『「いい人」をやめれば人生はうまくいく』『孤独をたのしむ力』(以上、日本実業出版社)、『33歳で資産3億つくった僕が43歳であえて貯金ゼロにした理由』(日本経済新聞出版社)などがある。※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
