本記事は、午堂登紀雄氏の著書『教養としてのお金の使い方』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。
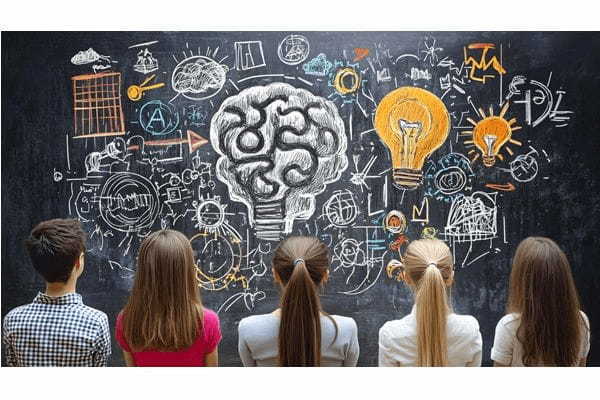
「自分」こそ最強の投資先である
「知能」とは何か。ここで言う「知能」とは、いわゆる知能テストで計るようなものではありません。認知・記憶・予測・判断をはじめ、仮説を組み立てる力、人生設計やリスクへの備えなどを含む、人間の知的活動を営む土台となる能力のことです。
そして有効なお金の使い方のひとつとして、知能が高い人間が選ぶものこそが自己投資ではないでしょうか。
とくに20代は資産運用などは不要で、自分の能力と信用力の向上にフルベットするほうが、生涯リターンが最も大きいと私は思います(例外はiDeCoで、これはメリットしかないため、20代から自分の最大枠を使って投資信託の積立をやるのはいいと思います)。
これには3つの理由があります。
自分への投資が数億円のリターンを生む
1つめは、自分への投資が最も利回りが高くなる可能性が高いからです。
たとえば一般的な大卒会社員の生涯年収は2.5億〜3億円と言われており、自己投資によって生涯年収が5億円になったとすれば、その投資は2億円以上のリターンをもたらしてくれたことになります。
たとえば私の場合、大学や公認会計士の勉強にかけた学費はたいしたリターンを生まなかったものの、読書は確実にリターンとなっていると感じています。
私が20代〜30代のころは、毎月20冊以上の本(ビジネス書、実務書、経済誌や専門誌など)を読んでいて、仮に月30,000円の出費を20年間続けたとして投資額は720万円くらいでしょうか。
ほかにも起業の前後では有料セミナーや勉強会などへの参加もありましたから、総投資額は1,000万円ぐらいかかっているかもしれません。
私が大学を卒業したときは、どこにも就職できずフリーターで年収は200万円ほどだったと思いますが、就職して年収400万円、転職して600万円、さらに転職して1,200万円となり、起業してからは手取りで年3,000万円前後を推移しています(自営業の場合は経費や節税対策があり年収という言い方は正確ではないため)。
もちろん新規事業などへの投資(による経験の蓄積)や、人との出会いなどへの投資も一種の自己投資とも言えるので、読書のおかげだけではありません。
しかし、就業時間の前後や休日など、仕事以外の自分の自由な時間を費やして自己投資した、と私が自信を持って言えるのは、やはり読書です。
だからというと生存者バイアスかもしれないなという多少の自覚はあるものの、ゆえに私は読書の効能には絶対的な信頼を置いています。
私の場合は自営業で生涯現役なので、生涯年収と言うにはまだ途中ですが、すでに実質的な累計収入では5億円を超えています。
そう考えると1冊1,500円程度の書籍への投資が、平均的な社会人の生涯年収を2億円以上上回るリターンを生んでいるとするなら、これほど確実かつ有益な投資はほかにないでしょう。
「仕事の実力」がつくと自信が強くなる
2つめは、自己投資によって仕事の実力がつくことは自分への自信となり、それは自己有能感や人生の満足感につながるからです。
たとえば先ほどの読書をすれば生涯年収が上がるという話も、「そんなにうまくいかないよ」という反応をする人がいると思いますが、そういう思考パターンであるがゆえにうまくいかないわけです。
「現実はそううまくいかない」とやらずしてあきらめる思考パターンを脱却し、「ではどうすればうまくいくか」という思考パターンに変えていくのが、ここでいう「仕事の実力がつく」ということです。
仕事の実力がつく過程で、どのような困難な状況に直面しても打開策を模索し挑戦する姿勢が培われます。すると「人生は自分次第でなんとでもなる」という楽観的な発想になる。
こうなるともう「人生楽勝」となり、「政治が悪い」「会社が悪い」などという他責の発想とも無縁になるのです。
投資に回す余力を拡大できる
3つめは、投資に回す余力を拡大できるからです。
そもそも、投資をするには元手が必要であり、自分の実力を高めなければ収入が上がらないですから、投資に回すお金も限られます。
たとえば毎月3万円を投資できる人が、40年間積立投資を続けると元本の累計は1,440万円になるのに対し、毎月20万円の投資余力がある人なら、40年続けると約1億円になりますから、どちらが有利かは明白でしょう。
また、仕事ができて周囲からの信用を得ていれば、定年退職後もかつての取引先や同僚などから「手伝ってくれない?」などと誘われる可能性もあり、働き続けられる期間も長くなる期待があります。
さらに、高年収であれば給与から天引きされる社会保険料の金額も上がりますが、その反面、老後に受け取れる厚生年金も手厚くなり、二段構えで安心です。
つまり、現役時代の高年収は、投資にも老後の生活にも有利に働くのです(ただし子育て・教育に関する補助金や助成金の多くは所得制限があり、高所得だと引っかかるという不公平が生じていたのですが、これも早晩解消される見込みです)。
ゆえに20代から30代前半は収入のすべてを自分の成長のために使い切るぐらいでちょうどよい、というのが私の考えです。
そうやって自分の実力を高め仕事に自信が持てるようになったころ、結婚・出産を通じて家族構成が変化すれば、「老後のため」「家族のため」という判断軸が浮上してきます。それから投資を始めても十分キャッチアップできるでしょう。
- POINT
- 若いうちは資産運用よりも自分にフルベットする
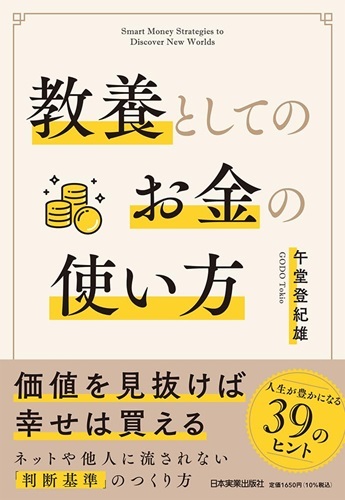
現在は不動産投資コンサルティングを手がけるかたわら、資産運用やビジネススキルに関するセミナー、講演で活躍。著書に、『捨てるべき40の「悪い」習慣』『「いい人」をやめれば人生はうまくいく』『孤独をたのしむ力』(以上、日本実業出版社)、『33歳で資産3億つくった僕が43歳であえて貯金ゼロにした理由』(日本経済新聞出版社)などがある。※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
