本記事は、午堂登紀雄氏の著書『教養としてのお金の使い方』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

「時間の価値」と「お金の価値」を理解する
お金の価値は一定ではない
「家族全員分の新幹線代を払って行くより、渋滞につかまってもクルマのほうが断然安上がり」と考える人もいれば、「新幹線だと小さな子どもたちが騒いだり走り回ったりして大変だし荷物も多いので、クルマのほうがラク」と考える人もいます。
あるいは、「旅費が高くついても新幹線で行くことで、道中は本を読んだり仕事をしたりなど時間を有意義に使える」「新幹線ならクルマよりも移動の疲労が小さくて済むし、事故の心配もないから安心」と考える人もいるでしょう。
そこに自分なりの合理性、つまり自分の時間とお金の価値を理解したうえでの判断を積み重ねていけば、納得性の高い生き方につながります。
しかし、ただ「お金がもったいないから」という理由だけで自分の時間を投入するのはもったいない。なぜなら、その時間を使えばできたはずのほかのことができなくなるからです。
逆に、ただ「面倒くさいから」という理由だけでお金を払うとしたら、それももったいない。なぜなら、そのお金があればできたであろうほかのことができなくなるからです。
「お金」を優先すべきか、「時間」を優先すべきか?
また、自分の時間の価値、お金の価値は状況によっても変わるものです。
「1万円は1万円であり、それ以上でも以下でもない」という意見もあるかもしれませんが、たとえば砂漠ではお金より水のほうが価値があると言えばわかりやすいと思います。
たとえば数億円の取引につながる可能性のある商談に遅れそうという場合、タクシーを使ってでも時間を買ったほうがよい。逆に、仕事帰りでとくに急ぎの予定もないという場合、電車代節約と健康維持を兼ねて、最寄り駅から1駅手前で降りて歩いて帰る、など。
家に書棚が必要だというとき、家具店で買って業者に設置してもらうか、ホームセンターで材料を買ってきて自分でつくるか。
ほかにもっと重要なやるべきことがあれば既成品を買ってでも時間を捻ねん出しゅつしたほうがよいし、急ぎで重要性の高いタスクがなければ自分でつくって安く上げようという判断になる。
あるいは、仕事を多く抱えている状況での出張であれば、「集中できる環境」を買うため新幹線ではグリーン席に乗ることが合理的になる。
しかし出張からの帰り道、疲れて仕事をする気力もなく、ビールを飲みながら弁当でも食べよう、という場合は普通席で十分だし、「のぞみ」ではなく値段の安い「こだま」でもいい。
このように、時間のほうが重要な局面もあれば、お金のほうが重要な局面もある。つまり「いまの自分の時間の価値・お金の価値」は一定ではなく、状況に応じて変わるということです。
にもかかわらず、「お金がもったいないからタクシーは使わない」とか「新幹線はつねにグリーン車」という硬直的な発想では、時に大切な時間を失い、時に大切なお金を失ってしまうということになりかねません。
「いまの自分の状況を考えたとき、お金を優先すべきか、それとも時間を優先すべきか」という2つの軸で冷静に考える必要があると思っています。
自分の時間を使ってお金を節約するのか、お金を使って時間を買うのか、そのどちらの判断が合理的なのかを考えることは、生活の全方位に影響し、自分の人生を決定づけることになるでしょう。
- POINT
- 「お金か? 時間か?」は柔軟かつ冷静に考える
自分の可能性を広げることにお金を使う
「スマホ料金があなたのマネーリテラシーである」という話をしましたが、だからといっていますぐ買い換えればいいということではありません。
たとえば新しいスマホに買い換えたとして、ではそれを買うことによって、自分はどういう進化・変革を遂げられるかを考えてみるのです。
スマホに限らず、ただ便利になるから、ただおしゃれだからという理由だけではなく、自分の可能性を広げる出費かどうかを振り返ってみましょう。
最新スマホを買うと何が変わるか?
たとえば私の妻は、仕事のほとんどをスマホで完結させます。電話やメールはもちろん、スケジュール共有、写真を撮ってブログやSNSにアップするといったマーケティング活動まで、すべてスマホ1台。
だから彼女にとっては、生産性を左右するスマホの性能は重要であり、処理速度が速く写真画像もきれいな最新型に買い換える意味は大きいと言えます。
あるいは、スマホの使い方の解説や商品レビューを商材として売っている人にとっても、新型スマホに買い換えることは、仕入行為であり必要経費です。それがのちに収益をもたらしてくれるからです。
一方、私は仕事もプライベートもほぼパソコンで完結しますから、新しいスマホに買い換えても、それで仕事や生活が何かバージョンアップするわけではありません。
新たな収益機会が得られるとか、コスト削減につながるとか、人脈が増えるとか、最新スマホでは何も起こらない。たとえば速度が上がり画面がキレイで電池の持ちがよくなるといった、使い勝手が快適になって自分が満足するだけです。だからそういったものには極力お金をかけないようにしています。
反対に、たとえば本を読むこと、旅をすることは、自分に新しい発見をもたらしてくれるから、そういうものには惜しまずお金を使う。家族の健康に貢献することや、子どもの成長につながることにもお金を惜しまない。
あるいは、のちに収入をもたらしてくれるもの、たとえば不動産や太陽光発電システムなどの資産運用にも資金を投下する。
もちろん、こういうお金の使い方を「味気ない」「そのほうがつまらない」と感じる人もいると思います。それはそれでよいのです。なぜならこれはあくまで私の場合であり、自分が本当に満足するお金の使い方は人それぞれだからです。
いずれにせよ、「その出費は自分の何を変革してくれるか、人生を前向きに切り開く力になるのかどうか?」をつねに問うことで、よりリターンの高いお金の使い方になると考えています。
- POINT
- 「どんなリターンを得られるか?」を想像する
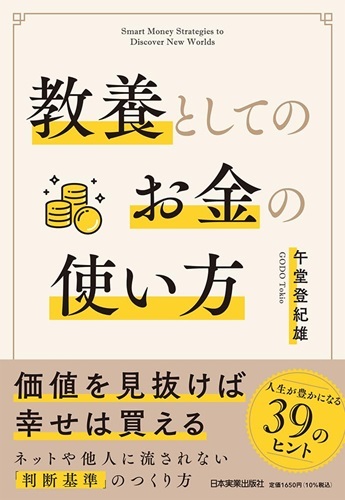
現在は不動産投資コンサルティングを手がけるかたわら、資産運用やビジネススキルに関するセミナー、講演で活躍。著書に、『捨てるべき40の「悪い」習慣』『「いい人」をやめれば人生はうまくいく』『孤独をたのしむ力』(以上、日本実業出版社)、『33歳で資産3億つくった僕が43歳であえて貯金ゼロにした理由』(日本経済新聞出版社)などがある。※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
