本記事は、午堂登紀雄氏の著書『教養としてのお金の使い方』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

FIREを「FI」と「RE」に分けて考える
流行のアルファベットには要注意
昨今、アメリカを中心にして「FIRE」というコンセプトが人気です。これは缶コーヒーのことではなく、Financial Independence Retire Early、つまり「経済的に自立し(FI)、早期リタイヤする(RE)」という意味です。
こういうアルファベットの頭文字を使ったキーワードが出てくるときは要注意です。必ずそれを商売にしようという人・企業が出てくるからです。
ビジネスの世界でもたとえばCRMとかSFAなどと、内容はごく当たり前のシステム投資のことですが、それを導入すればあたかもあらゆる問題が解決する魔法の道具のような響きがあり、IT会社(ベンダー)のカモになってしまうというアレです。
また、そういう短縮キーワードを使うとなんとなく最新で賢そうなイメージもあるためか、中身を深く考えずつい口にしてしまいがちです。
ここでは、表面的な新規性(に思えること)よりも、内実に目を向けてみましょう。
「経済的自立」は言うまでもなく重要で、誰もがうなずくところだと思います。
そのうえで、経済的自立には2つの意味があると私は考えています。1つは一般的な「自分の労働力に依存しない不労所得がある」ということ、2つめは「誰にも頼らず自分の腕一本で食べていける」という意味です。
前者の不労所得にもいくつかのパターンがあります。
たとえば若いころは猛烈に働いて節約貯金し、あるいは起業してその会社を売却するなどして多額のお金を手にし、あとはそのお金を取り崩しながら生活するというタイプ。アメリカに多いと聞いたことがあります。
つぎは、貯蓄額はそれほどではないものの、高配当株や高利回り債券などによる配当収入や金利収入で生活する人、賃貸用不動産を所有し家賃収入で生活する人です。
とくに日本では、賃貸用不動産を複数所有し会社員を卒業する人が多い印象です。
というのは、株にしても債券にしても、配当や金利だけで生活するレベルにするにはやはりそれなりの元手が必要ですが、不動産は手元資金が潤沢ではなくても、金融機関からお金を借りることで大規模な運用が可能だからでしょう。
後者の「誰にも頼らず自分の腕一本で食べていける」とは、ひと言で言うと「プロ」のことです。需要の高い技術(スキル)、希少性の高い技術、誰よりもうまくできる技術、余人を持って代えがたい技術を持っていれば、仕事の依頼が途切れることはない。
これは職人などに限らず、会社員でも同じことが言えると思います。たとえば生産管理のプロ、AI活用のプロ、あるいは組織マネジメントのプロなどは、引く手あまたではないでしょうか。
早期リタイヤするかどうかは「仕事観」
「FI」しても「RE」するかどうかの分かれ目となるのは本人の仕事観です。「働きたくない」「仕事が楽しくない」という人が「RE」つまり早期リタイヤを望みます。
私の知人でもリタイヤしている人を知っていますが、若いころからずっとリタイヤを目標としてお金を貯めて実現し、現在はおいしいものを食べたり、気ままに旅行に行ったり、日がなのんびり過ごしているようです。
一方、「仕事は楽しい。でも会社員だと自由にならない」という人は、自分で会社を立ち上げるなどして働き続けます。経済的自立も早期リタイヤも手段でしかなく、「自分がやりたいことを仕事にする」ためのリタイヤです。
私の周囲の富裕層はこのタイプが圧倒的多数派で、彼らは仕事が楽しくて仕方がない。そもそも好きなことをやって、顧客から感謝されて、お金までもらえるので当然と言えば当然かもしれません。
実際、一生かけても使い切れないほどの巨額の財産を持つ孫正義氏、柳井正氏、三木谷浩史氏が、なお現役を続けるのは、おそらくそういうことなのでしょう。
50歳を超えてなおプレーする、Jリーグ史上最高齢プロサッカー選手の三浦知良氏も「サッカーが好きだ」と公言します。
つまり、イヤイヤ働いてきた(あるいはストレスに耐え忍んで働いてきた)人は早期リタイヤを選び、充実して働いてきた人は独立起業を選ぶと言えそうです。
これはどちらが正しいかではなく、本人がどういう生き方を志向するかという問題ですし、もちろんいろいろな人がいますから人によって考えも異なります。
たとえば私の周囲の不動産投資家のなかには、会社がイヤで不動産投資を始め、それで成功して会社を辞めたものの、ヒマに耐えきれず不動産売買ビジネスに進出する人、講演ビジネスやオンラインサロンなどを始める人は少なくありません。
早期リタイヤの「リスク」をどこまで織り込んでいるか?
なお、早期リタイヤを選ぶ人の多くは、その後も節約をする生活で日々を送る傾向があります。
たとえば数千万円のお金を貯めて、あとはそれを切り崩すだけとか、年間の配当収入や家賃収入が手取りで300万円から500万円ほどの小ぶりなスケールの人に多い印象です。
仕事から解放され自由になったのはいいのですが、興味関心のほぼすべてが「いかにローコストで生活するか」で占められているという、そういう生き方が幸福なのかどうか。
また、リスクについても分析・把握し、対策を打っておく必要があります。
まず1億円も投資元本を貯められるような人は
それが株式や投信だけで構成されているなら、将来の減配や株価・基準価額下落のリスクをどこまで織り込んで生活設計を考えているのか。
現預金であれば、円安や資源価格高騰などでインフレが進んだときの資産価値の減少を想定しているのか。
会社を辞めれば厚生年金から外れますから、将来の年金受給額も減ります。それを補う方法を考えているのか、あるいはなくても問題ない計画をしているのか。当然ながら国民年金・国民健康保険に自前で加入し、住民税も自分で納めることになります。
旅行やレジャーや外食がどのくらいのレベルでどのくらいの頻度でできると思っているのか。あるいはなくても問題ないのか。自分の趣味嗜好が変わることも想定しているのか。
独身者や共働き世帯は別として、子どもがいれば学費や教育関連費なども想定済みなのか。
そしてもしお金が足りないという事態になったら、バイトでもするのでしょうか。社会から長く離れたうえに60歳や70歳を超えてできる仕事は限られていて、あまり選り好みできないような気もしますが……。
将来、親に介護が必要になったとき、支えられるのか。生涯医療費の半分以上は70歳以降にかかってくると言われており、病気や医療費への備えも考えているのか。
そして自分自身(あるいは配偶者)が介護を受けなければならなくなったとき、設備や体制の整った施設に入居できるのか。
若い人はまだ元気だし親も健在な人が多いでしょうからピンとこないかもしれませんが、確実に見えている未来です。
- POINT
- 自分の「仕事観」「リスク許容度」を考える
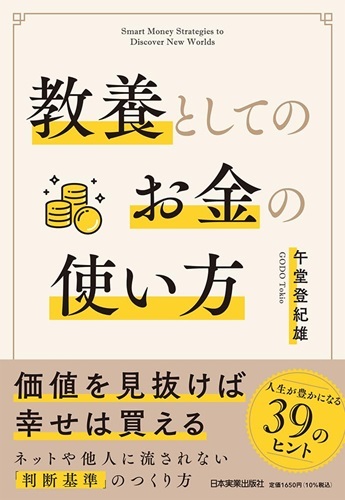
現在は不動産投資コンサルティングを手がけるかたわら、資産運用やビジネススキルに関するセミナー、講演で活躍。著書に、『捨てるべき40の「悪い」習慣』『「いい人」をやめれば人生はうまくいく』『孤独をたのしむ力』(以上、日本実業出版社)、『33歳で資産3億つくった僕が43歳であえて貯金ゼロにした理由』(日本経済新聞出版社)などがある。※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
