本記事は、午堂登紀雄氏の著書『教養としてのお金の使い方』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

家計簿をつけてもお金が貯まらない理由
「家計簿は貧乏になるツール」と言われて、信じられるでしょうか。しかし現実には、家計簿をつけている人ほどお金がなく、貯めている人ほど無頓着な傾向があります。
それは、「お金がたっぷりあるから家計簿をつける必要がないだけ」という単純な理由ではありません。家計簿をつけてもお金が貯まらない人に欠けているのは、つぎの3つの力です。
①欲求をコントロールする力
自分が何にお金を使っているかすべて洗い出し、いったん「家計の見える化」をするのは、一定の効果はあるでしょう。
しかし、毎月家計簿をつけているにもかかわらず、毎月のように「今月は使いすぎた」「無駄な出費をしていた」と気がつく人は、欲求をコントロールできていないということです。
家計簿を見なければその出費が必要か不要かが判断できないのだとしたら、よく考えずに買い物をしているということ。
そこで、買い物をするときは、いったん立ち止まって、「この出費は、本当に必要か?」「もっと安くて同じ効用を得られるものはないか?」「値段以上に使いこなせるか?」「自分の将来に有効に作用するか?」を考える習慣をつけることです。
②収支を俯瞰・把握する力
たとえば結婚して間もない家庭など、月間・年間でどのような出費項目があるか、その金額はどのくらいかなどの全体像を把握していない人にとっては家計簿をつける意味があるでしょう。
しかし、同じ環境でしばらく暮らしていれば、毎月どういう経費がかかっているか、いくらまで使って大丈夫か、どのあたりで危険信号か、などといったことはわかってくるものです。
たとえば、今月はかなりエアコンを使ったから、来月の電気代はこのくらいの金額になりそうだ、という体感イメージを持っている人も多いでしょう。
このイメージがあると「予測力」「全体を見る力」として、家計簿をつけなくても家計の収支全体が把握できるようになります。
もし家計簿をつけなければ収支が把握できない、貯金できないとしたら、仕事でも予測力や俯瞰力が乏しい可能性があり、結果として本業での収入に跳ね返ってくるかもしれません。
③タイムマネジメント力
日々家計簿をつけたところで、当たり前ですが、使えるお金が増えるわけではありません。「家計簿を1年間つけたら100万円もらえる」のであれば、喜んでつけるでしょう。
しかし、手取りが月30万円と決まっているなら、その管理にいくら時間と労力をつぎ込んだとしても、使えるお金は30万円です。
家計簿をつけると、それだけ自分の時間が奪われます。でも、お金は増えない。むしろ市販の家計簿を買った分、お金が減るだけです。
もちろん、家計簿が自分が納得できる方法であるとか、支出が見えて安心感が得られるという人もいるでしょう。
ですから、「家計簿をつけることは無意味」ということではなく、「自分はいったい何に時間を使うことが、もっともパフォーマンスが高くなるのか?」を考えましょうということです。
- POINT
- 「家計の見える化」以外にも大切なことがある
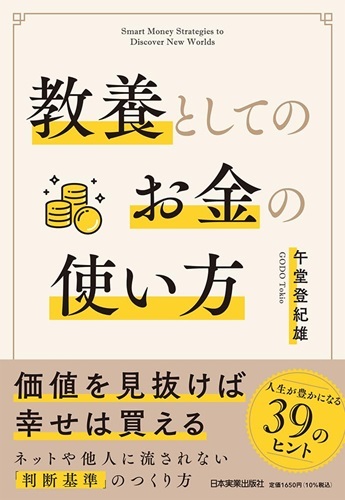
現在は不動産投資コンサルティングを手がけるかたわら、資産運用やビジネススキルに関するセミナー、講演で活躍。著書に、『捨てるべき40の「悪い」習慣』『「いい人」をやめれば人生はうまくいく』『孤独をたのしむ力』(以上、日本実業出版社)、『33歳で資産3億つくった僕が43歳であえて貯金ゼロにした理由』(日本経済新聞出版社)などがある。※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
