本記事は、午堂登紀雄氏の著書『教養としてのお金の使い方』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

「自分の才能」に投資して人生をつくる
自分と他者を差別化された人生をつくる
テーマでもある「教養としてのお金の使い方」とは、自分の人生を有利にしてくれる、結果として幸福感を得られる人生に導くお金の使い方です。
たとえば朝起きて満員電車に揺られて通勤し、会社の近くのコンビニでコーヒーを買い、ランチタイムには行列のできるラーメン店で食事、仕事が終わったら家の近くのコンビニで夕食を買って帰り、スマホでSNSをやって動画を見て寝る、という生活は、独身者であれば珍しくないかもしれません。
そして週末は昼ごろ起きて都心に出かけてウインドーショッピング、というのもよくある光景でしょう。
しかしここで立ち止まって考える。自分の人生を有利にしてくれるお金の使い方をしているだろうか、と。5年後、10年後の発展的な未来につながるお金の使い方をしているだろうか、と。
意識したことはあるでしょうか。「私たちはお金を使うことで、他者と差別化された人生をつくってきた」ということを。
ビジネススクールや英会話教室、スポーツクラブなどに行けば、当然ながらお金がかかります。しかしその出費と引き換えに、他人より優れたスキルや運動能力を手に入れることができる。あるいはその能力を他者よりも強化することができる。
たとえば私の妻はピアニストですが、学生時代、高い月謝を払って著名な先生についたからこそ、競争率の高い音楽大学に進学でき、国際的なピアノコンクールで入賞できたと言っていました。
私自身、米国公認会計士の資格を取得するために専門学校に通いましたし、論理的思考力を身につけるためビジネススクールにも通いました。英語力向上のため、夫婦そろってフィリピンの英語学校にも通いました。
資本主義社会において効率よく自分のスキルや能力を高めようとすると、多少なりともお金はかかるものです。逆の言い方をすると、お金を払ったからこそ一般に流通していない貴重な専門知識やスキルを教えてもらえるし、それが短期間で習得できるわけです。
「もったいない」では新しい世界を体験できない
私はこれまでも「節約貯金は貧乏への最短コース」と主張してきました。その理由は「経験の格差」につながるからです。
お金を貯めようと節約貯金をすることは、いま使えるお金を少なくする行為です。
つまりそれは、結果として自分ができることの幅や深さをわざわざスケールダウンさせることと同じです。
もちろんお金をかけなくても人生を楽しむ方法はたくさんありますが、やはり限界があります。
「お金がもったいないから本を買わない」「お金がもったいないから勉強会に行かない」「お金がもったいないから旅行にも出かけない」という生活を続ければ、確かにお金は貯まるでしょう。
もちろん、そんな生き方を否定するつもりはありませんし、「節約貯金が重要」「老後対策が最大の関心事」「自己満足で何が悪い」という価値観の人もいると思います。
それはそれで本人の自由であり、他人がどうこう言うことでもない。
しかし、ではその先に、いったいどれほど魅力的な人物となるか。自分が生きた証を後世に残せる人材となれるのか。数十年後に死の床を迎えたとき、「なかなかいい人生だった」と納得してこの世を去ることができるのか。
節約貯金に励むだけでは、お金を使わなければ得られない人生の広がりを捨ててしまうリスクがあります。
1,500円がもったいないからと本を買わなければ、それを読んだら得られたはずの、新しい情報や知恵や考え方がもたらされない。
10万円がもったいないからと海外旅行に出かけなければ、それで得られたはずの、新しい経験や見聞や発見がもたらされない。
お金を使わない生活とは、いまの自分の生活圏の外側へ踏み出さないということです。
狭い自分の世界のなかだけでこじんまり生きるのは、確かに安心で心地いいかもしれない。しかし、いまの自分が見たことのない世界を体験しないとか、いまの自分が持っていない発想や価値観に触れないという生活は、自分が進化しないということを意味します。
- POINT
- お金を使ってスキル・能力を進化させる
自分の頭脳を「負債」ではなく「資産」にしていく
『アリとキリギリス』には第2幕がある!?
『アリとキリギリス』というイソップ寓話は、多くの人が一度は聞いたり読んだりしたことがあると思います。
要約すると、夏の間、アリたちは冬の食料を蓄えるために働き続け、キリギリスはバイオリンを弾き、歌を歌って過ごした。やがて冬が来て、キリギリスは食べ物を探すが見つからず、最後にアリたちに乞い、食べ物を分けてもらおうとするが、アリは「夏には歌っていたんだから、冬には踊ったらどうだい?」と食べ物を分けることを拒否し、キリギリスは飢え死んでしまった、という話です。
そして一般的には「コツコツ働くことが大事」「いざというときに備えて貯蓄しよう」という教訓が語られます。
しかしこの話には第2幕があります(イソップ自身が書いたわけではないそうですが)。それは、「お金がなくなったキリギリスは、コンサートを開いて歌やバイオリンを披露した。するとアリたちが食べ物を持ってコンサートに集まってきた」という話。
キリギリスは夏の間は歌とバイオリンの練習をしていて、それは商品価値を持っていたということで、自分の才能を磨いて付加価値を高めれば、困難が訪れても乗り越えられると言えるのではないでしょうか。
このような話を聞いて「自分にはムリ」「そんなにうまくいくはずはない」「やってもムダ」などという発想をするとしたら、自ら自分の人生の足を引っ張ることになりかねません。それは自分の頭脳が「負債」となるだけです。
しかし自己投資の本質は、自分の頭脳そのものを強力な「資産」にしていくことです。
資産としての頭脳が進化すれば、つねに自己を成長させ、毎年最高益を更新し続ける自分になることができます。そしてそれを実感できる人生となる。
この感覚は、私たちの「幸福」を構成するひとつの要素を手に入れたと同じくらい大きな価値があると考えています。
- POINT
- 「自分の頭脳」が最高最強の資産である
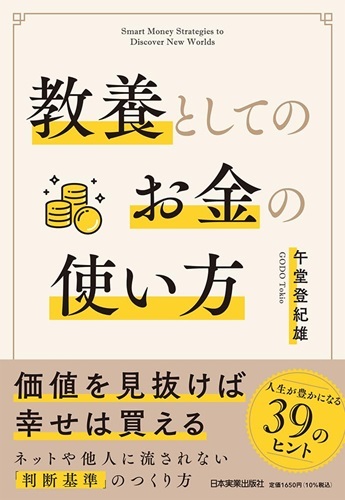
現在は不動産投資コンサルティングを手がけるかたわら、資産運用やビジネススキルに関するセミナー、講演で活躍。著書に、『捨てるべき40の「悪い」習慣』『「いい人」をやめれば人生はうまくいく』『孤独をたのしむ力』(以上、日本実業出版社)、『33歳で資産3億つくった僕が43歳であえて貯金ゼロにした理由』(日本経済新聞出版社)などがある。※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
