AI(人工知能)・5G(第5世代移動通信システム)・IoT(モノのインターネット)・自動運転車などの進化に伴い、これらの技術を支える半導体チップの性能向上が求められています。
本記事では、より効率的でエネルギー消費の少ない次世代半導体チップ技術として開発が加速している「3D(3次元)半導体チップの高積層化技術」に期待されているメリット、課題、最新開発動向についてレポートします。
3D半導体チップの高積層化技術とは?
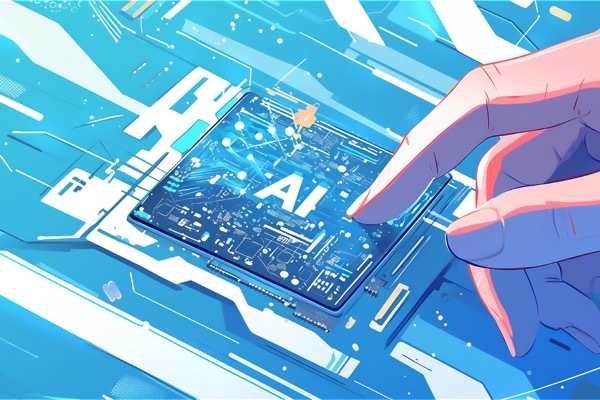
従来の2D(二次元)半導体チップは回路が平面的に配置されているため、高密度化や性能向上面に限界があります。信号伝送の遅延や電力消費の増加、熱管理などの課題に直面しており、近年はこのような課題解決に向け、複数の半導体チップを垂直方向に積み重ね、単一の高機能チップとして機能させる「3D集積化技術」への移行が加速しています。
3D半導体チップの高積層化技術のメリット
その中でも特に注目されているのが、チップを積み重ね、より高密度な半導体を実現するための「積層化技術」です。これのメリットは、
・回路間の配線を短縮することによりデータ送信をさらに高速化
・電力消費を抑えつつ
・限られたスペース内でより多くの機能を集約できる
そのため、多くのデータを高速で処理する必要があるデータセンターやストレージデバイス、高性能なAIチップやGPU(※)、モバイルデバイスなど、さまざまな分野で役立つと期待されています。
(※)Graphic Processing Unit:画像や映像処理を高速で行うための専用プロセッサ
従来の3D集積化技術との違い
従来の3D集積化技術は、チップを繋ぐために「シリコン貫通ビア(※1)」というものを使用しています。しかし、高コストであり、位置がずれるなどの問題があります。
一方、3D半導体チップ高積層化技術は「モノシリック3D積層(※2)」や「フリップチップ積層(※3)」といったより精密な積層方法が採用されており、従来の手法では実現が難しかった高密度・高性能なチップを作ることができます。
(※1) TSV(Through silicon via):シリコンウェーハ内部に金属を埋め込んで電極を作り、チップを電気的・機械的に接続する技術のこと。
(※2)基板上に複数の半導体層を直接形成し、各層に回路を構成する技術のこと。
(※3)チップを裏返して積層・接続する技術のこと。
モノリシック3D高積層化技術
マサチューセッツ工科大学(MIT)とサムスン高等技術院(SAIT)が共同開発した「モノリシック3D高積層化技術」は、先述した「シリコン貫通ビア」を使わずに、半導体層を直接積み重ねる技術です。チップ上のトランジスタ数を飛躍的に増加させ、層間通信や計算をより高速で行うことに成功しました。
同技術が将来AIハードウェアに応用された場合、スーパーコンピューター並みの処理速度と性能を有し、データセンター級のデータ容量を備えたノートパソコンやスマートフォンが誕生する可能性があります。
広範囲な実用化に向けた課題もまだ多い
一方で、広範囲な実用化に向けたさまざまな課題も存在します。
・構造上、熱がこもりやすい
・層数が増えることにより信号延滞が発生しやすくなる
・電力密度が高くなることにより消費電力が高くなる
・製造過程が複雑なため高コスト
これらの問題を解決するために、より効率的な放熱技術や接続技術、低消費電力化技術などの開発が進められています。
多様なテクノロジーの進化に欠かせない技術
3D半導体チップの高積層化技術は、より速くて、コンパクトで、省エネなチップを実現するための重要な技術であり、テクノロジーが進化し続ける上で欠かせない要素として期待されています。ですので、投資対象としても注視したい領域です。Wealth Roadでは今後も3D半導体の高積層化技術を含む半導体市場動向をレポートします。
※本記事は投資に関わる半導体技術を解説することを目的としており、個別企業への投資や半導体銘柄への投資を推奨するものではありません。
(提供:Wealth Road)
